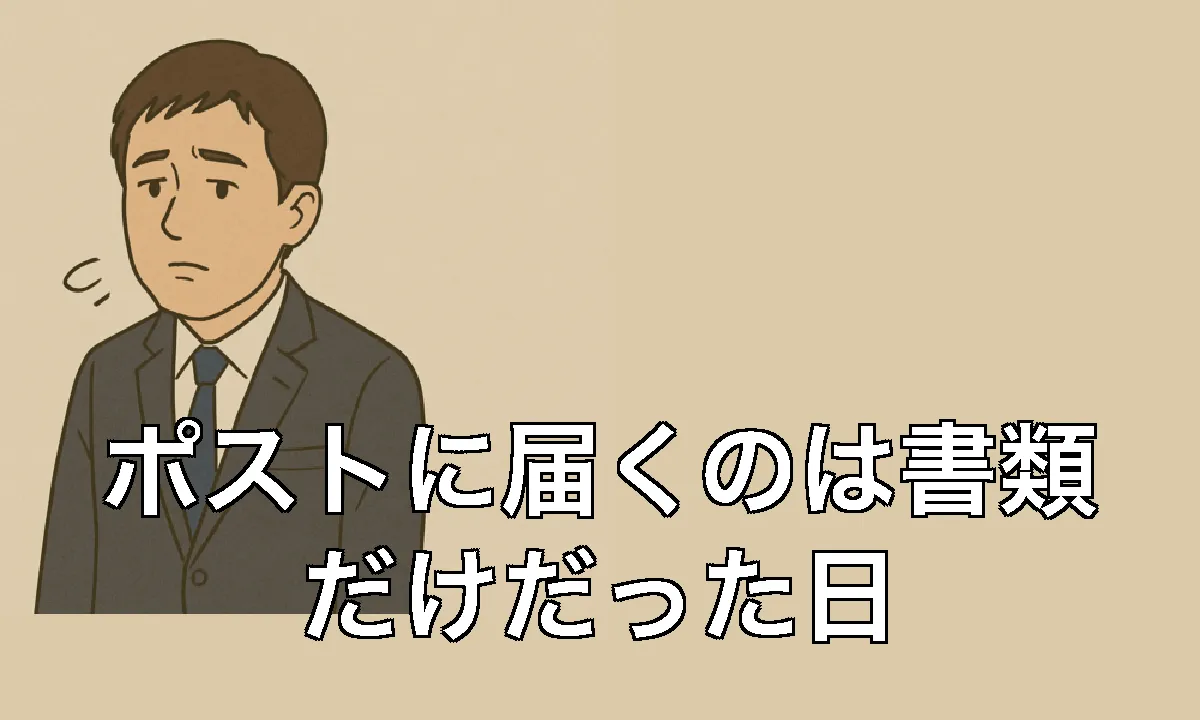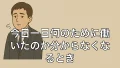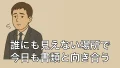ポストを開けた瞬間に感じるやるせなさ
郵便受けを開ける、そのたった数秒に、ささやかな期待を込めてしまう自分がいる。もしかしたら何か嬉しい知らせが届いているかもしれない、誰かからの手紙が混じっているかもしれない。そんな淡い希望を抱いてポストを開けるのだけれど、現実は冷たかった。中身はすべて仕事関係の封筒。登記識別情報通知、法務局からの照会、依頼者の資料の束。色も形も見慣れた封筒ばかりで、心が少しずつ萎んでいく。
心のどこかで期待してしまう自分がいる
この歳になっても、どこかで「誰かが自分を思ってくれている」という証拠が欲しいのかもしれない。実際には誰からも手紙なんて来ないし、DMさえも仕事絡み。それでもつい、昔好きだった人からの年賀状や、疎遠になった友人からの突然の便りみたいなものを想像してしまう。まるで高校時代、合宿帰りに自宅ポストに置いてあったラブレターを開けるような、あの甘酸っぱい期待感を、今もなお引きずっている。
チラシでもいい 誰かからの何かを待っていた
正直、内容がどうでもいい。ただ誰かから、自分宛に何かが届くという事実が欲しいのだ。飲食店の割引チラシでも、町内会のお知らせでも構わない。無意識に「自分は孤独ではない」と思いたいのだと思う。そういう小さな“つながり”に飢えているのかもしれない。逆に言えば、それほどまでに日常が事務的になってしまっているという証拠だ。
全部が業務書類だったときのあの沈黙
結局、ポストの中身を全部確認して、封筒の山を小脇に抱えて事務所に戻る。足取りはいつもより少し重い。誰にも見られていないのをいいことに、ふっとため息が漏れる。自分の感情が仕事に消費されていると気づいてしまう瞬間。ああ、今日も俺は、ただ“処理するだけ”の人間で終わっていくのかという無力感に襲われる。
ひとり暮らしのポストに私信は届かない
独身生活も長くなると、自宅のポストが完全に“事務用”の受け皿になってくる。生活感のあるものが減り、管理会社や役所、金融機関からの通知ばかりが並ぶ。特に司法書士をしていると、日中は事務所にいて、プライベートなやり取りをする相手もいない。家に帰ってポストを開けても、そこに「人間関係」はない。
同級生は家族写真を送ってくる季節
年末が近づくと、ポストには唯一“私信”らしきものが届く。それが年賀状。でも、内容はだいたい家族写真。子どもが生まれました、マイホーム建てました、そんな報告が並ぶ。かつて一緒に汗を流した野球部仲間たちは、もう違う世界に行ってしまったのだと痛感する。自分はというと、家と事務所を往復する毎日で、家族写真の送りようもない。
自分宛の年賀状が減っていく現実
ここ数年は、年賀状の枚数もめっきり減った。LINEで済む、SNSで事足りる、そんな世の中になったからかもしれない。でもそれ以上に、自分が誰かの“近況を知りたい相手”になれていないのだと思う。司法書士という職業柄、近況報告をするような関係性が作りづらい。日々の忙しさにかまけて、自分も誰かに便りを出すことを忘れてしまった。
それでも仕事の書類は律儀に届く
皮肉なことに、業務書類は遅れることなく毎日届く。法務局からの書類、クライアントからの返信、登記に必要な原本類。こっちは一方的に忙しいのに、相手は義務としてきっちり送ってくる。その律儀さが時に憎らしく感じる。でも仕事だから受け取るしかないし、処理するしかない。人としての感情よりも、職業人としてのルーティンが勝ってしまう。
事務員の手が開かないから郵便も全部自分
うちの事務所は、小さな個人事務所だ。事務員さんがひとりいてくれるだけでも本当にありがたい。でも当然ながら、郵便のチェックや仕分けまで手が回らないことも多い。だからポストを開けて、中身を確認して、緊急性のあるものを選別するのは、結局いつも自分の仕事になる。郵便物ひとつでも気を抜けないのが、今の現実だ。
小さな事務所ゆえの限界
スタッフが少ないということは、何でも自分でやるということ。忙しさのなかで、本来なら誰かに任せたい仕事も手放せない。郵便の内容一つが案件の行方を左右することもある。だから自分の目で確認しないと不安になる。それでも、毎日この量を処理し続けるのは、心にも体にも堪える。自分が壊れたら終わりだというプレッシャーが常につきまとう。
誰かと分担できることのありがたさを知る
以前、事務員さんが体調不良で数日休んだことがあった。たった数日で、仕事の流れがガタガタになった。郵便を開ける暇もなく、机の上が封筒の山に埋もれた。そんなときに改めて気づいた。分担できるというのは、物理的な話だけじゃなく、精神的な負担の共有でもあるのだと。誰かがいるという安心感。それを得るために、もっと人を雇いたいけれど、それも簡単じゃない。