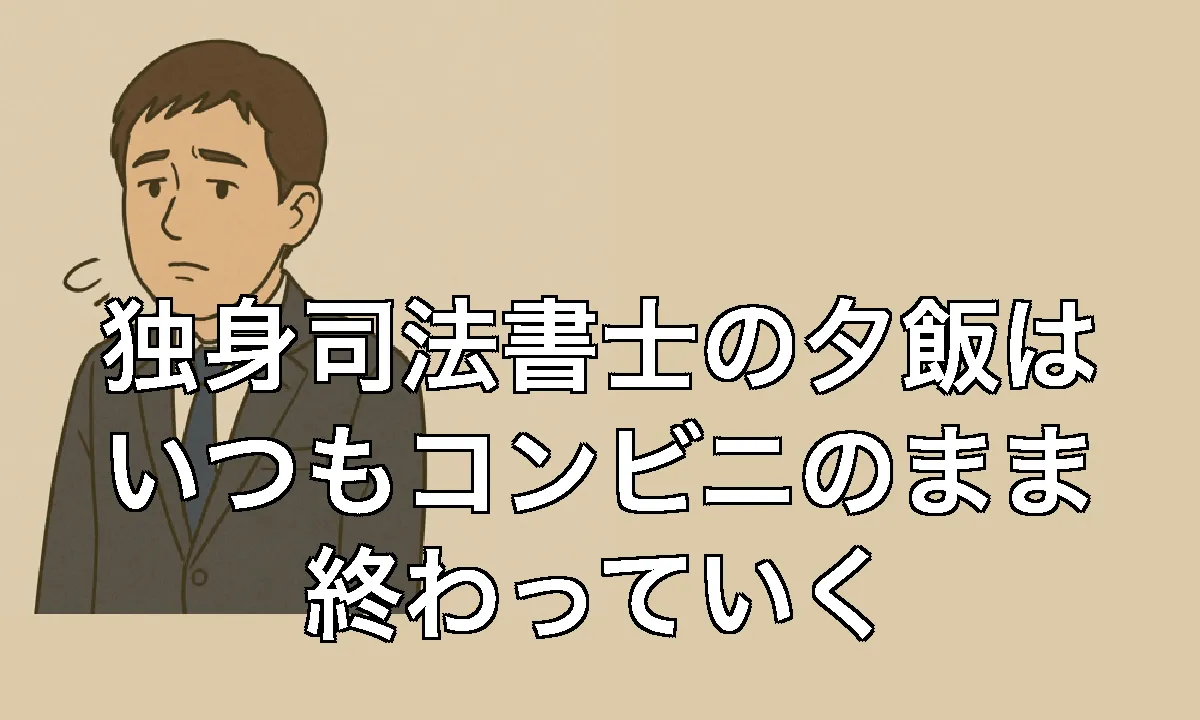独身司法書士の夕飯はいつもコンビニのまま終わっていく
今日もまたコンビニに吸い込まれる夜
「ただいま」と言っても誰もいない玄関。そんな夜がもう何年も続いている。仕事終わり、事務所の電気を消し、歩いてすぐのコンビニへ。選択肢はあれど、手に取るのは決まっていつものサラダチキンとカップ味噌汁。それを買って、レジの「温めますか?」という機械的なやりとりに軽くうなずく。それが夕飯の始まりであり、終わりでもある。なぜだか店内の冷気が、帰り際の自分の背中を押しているように感じるのは気のせいか。誰かと食卓を囲むことのない日々に、慣れたつもりでいても、ふとした瞬間にぽっかりとした空洞が心に顔を出す。
選ばれないお惣菜と独身の背中
コンビニのお惣菜棚の前に立つ時間が、最近少し長くなった。唐揚げ弁当、幕の内、パスタ、炒飯。どれを選んでも、別に誰にも文句は言われない。でもそれと同時に、「これ美味しかったよ」と共有する相手もいない。結局、味よりも消化しやすさで選んでしまう。そんな姿を、コンビニの防犯カメラが毎晩見ているのだろうと思うと、少し恥ずかしくなる。背中には元野球部の面影もなく、ただの疲れた中年司法書士の輪郭が映っている。
レジ袋の音だけが帰宅の合図になる
コンビニのレジ袋をカシャカシャと鳴らしながら歩く。住宅街の中、すれ違うのは犬を連れた夫婦や、手をつないだ親子。自分だけが袋一つを頼りに帰る。ふと、実家で母が「晩ごはんよ」と呼んでくれた声が耳の奥でよみがえる。温もりのある声と、今の袋の音。何が違うのかは明らかだ。生活の全てが「自分ひとりで完結してしまう」ことに慣れてきてしまっている。そのことに、どこか居心地の悪さを感じている。
湯気が出ない夕飯に慣れた自分が少し怖い
コンビニで買ってきたお弁当は、食べる前には湯気がある。でも、食卓に運び、箸をつける頃にはすっかり冷めていることが多い。テレビも点けない。スマホでYouTubeを流しながら、無言でかき込む夕飯。誰かと話すわけでもない。何かを味わうでもない。ただ、空腹を埋めるための作業。そんな夕飯に慣れてきてしまった自分を、ふと「このままでいいのか?」と問い詰めたくなる夜もある。でも、それを言葉にする相手がいないのが、いちばん堪えるのだ。
炊飯器を使わなくなってからどれくらい経つか
独り暮らしを始めたころは、ちゃんと炊飯器も買ったし、週末には煮物にも挑戦した。カレーを鍋いっぱいに作っては、冷凍保存していた時期もある。でも気づけば炊飯器の蓋は開けなくなり、鍋は物置の奥へ。あの頃は、もしかしたら誰かを家に招く未来を想像していたのかもしれない。でも今は「誰かのために」なんて気持ち自体が、遠くに行ってしまった。夕飯が温かい必要すら感じなくなっている。
自炊に挑んだ日の敗北記録
数ヶ月前、ふと思い立って野菜炒めを作った。久々に包丁を持ち、野菜を刻んでフライパンに放り込んだ。しかし、油の量を間違え、焦げ付き、味はイマイチ。後片付けも面倒くさくなり、結局コンビニで買い直した。その時の敗北感たるや、なかなかのものだった。努力が報われないのではなく、「やらなければよかった」とさえ思ってしまった。自炊は、誰かが喜ぶ食卓にこそ報われるものなのだと、その時気づいた。
仕事が終わるころには冷凍庫に手が伸びる
仕事が長引くと、夕飯に対する意欲がゼロになる。冷凍庫の中にある餃子やチャーハン、パスタ。それらは便利だけど、温かさや香りで癒してくれる存在ではない。ただの燃料補給だ。心を満たすどころか、さらに虚無を広げていく。仕事のストレスを食で発散するという選択肢が、自分にはもう残っていないのかもしれない。食事という行為が、ただの生活の維持になっていることが寂しい。
コンビニ飯に栄養以上の役割を求めるなと言われても
「コンビニ飯は便利だけど、栄養偏るよ」とよく言われる。もちろんわかってる。でも、今の自分にとっては、栄養だけじゃなく「一日の区切り」や「孤独の埋め草」としての役割も担っている。だから、そこに温かさや心の癒しを求めるのは、間違っているとわかっていても、どこかで期待してしまう。レジの店員の「ポイントカードお持ちですか?」という一言に、わずかでも人との接点を感じてしまう自分が、なんとも哀しい。
司法書士という仕事は誰かと食べる時間を奪う
この仕事をしていると、夕方から夜にかけての相談が当たり前になる。お客さんは仕事終わりに来るから、こちらの仕事終わりはどんどん後ろ倒しに。事務員さんには早めに帰ってもらっても、自分だけ残っている日が多い。そんな日々が積み重なり、気づけば夕飯は「仕事のあとのご褒美」ではなく「終業の証明書」になってしまった。誰かと囲む時間ではなく、自分が何とか一日を乗り切ったことへの確認作業になっている。
顧客の相談が夕飯時に食い込んでくる現実
予約は17時だけど、終わるのは19時。そんなパターンが日常茶飯事だ。とくに高齢のお客さんは、世間話も含めてじっくり時間をかけたいタイプが多い。こちらとしてもないがしろにはできない。結果として、自分の夕飯時間はどんどん後ろに押され、22時を過ぎることもある。そういう日には、さすがに胃が重くなる。でも、それがこの仕事の宿命だと受け入れてしまっている自分が、少し情けない。
事務員さんのまかないがうらやましいと感じる時
たまに事務員さんが手作りのお弁当を持ってきていて、「いいですね」と声をかけると、少し照れたように「昨晩の残りです」と返される。何気ないやりとりだけど、その「昨晩の残り」に家庭の存在が透けて見える。誰かのために作ったものを、翌日自分のために持ってくる。そんな当たり前が、どこか眩しい。自分にはない風景に、ほんのり羨望を抱く瞬間だ。
登記よりも大事なものを後回しにしていないか
登記は期限があるし、間違えれば大事になる。だからこそ慎重になるし、責任も重い。でも、そればかりを優先しているうちに、自分の生活や健康、人とのつながりはどこかに置き去りになっている気がする。お金を稼ぐことは大事だけど、それで満たされるのは通帳の数字だけ。人としてのあたたかさや、心の潤いは、数字じゃ測れない。分かっていても、忙しさの中ではその「分かってること」を、つい忘れてしまう。
野球部だったあの頃はまさかこんな未来とは
高校時代は野球部だった。グラウンドで汗を流し、みんなで笑って、バカな話をしながら帰った日々。まさか将来、コンビニで一人弁当を選ぶ男になるとは思ってもみなかった。あの頃は、チームで戦い、チームで飯を食っていた。負け試合のあとでも、仲間と食う飯は美味かった。今は勝ちも負けもなく、ただ終わる日々。そのギャップに気づいてしまった時、なんとも言えない寂しさがこみ上げてくる。
ベンチでもみんなと飯を食った日々
控えだった時期もある。でも、仲間がいた。ベンチで声を出して、試合後はみんなで同じ食堂に向かった。別に豪華なメシじゃない。カレーか、ラーメンか。でも誰かと食べるそれは、格別だった。味というより空気が美味かった。あの空気を、今の自分はどこで吸っているだろうか。食事とは、栄養補給ではなく、心の充電でもあったはずだ。
孤独のスコアボードは誰がつけているのか
今の自分のスコアは何点だろう。仕事はこなしている。ミスも少ない。でも、それだけじゃ合格じゃない気がする。人生のスコアボードは、誰が採点してくれるわけでもない。だからこそ、自分でつけるしかない。でも正直、最近は白紙のままだ。試合に出ている実感がない。日々をただこなしているだけ。そんな自分を客観的に見たとき、少しだけ、立ち止まりたくなった。
モテない男の夜はこうして静かに更けていく
モテないのは慣れている。でも、誰にも求められない夜が続くと、心の奥が冷たくなるのを感じる。恋人がいた時期もあったが、仕事優先の生活に耐えられなかったのか、去っていった。自分の優しさは、誰かを癒すには不器用すぎたのかもしれない。今はただ、静かな夜に、あの人の声すら思い出せなくなってきたことに、なんとなくの怖さを感じている。
婚活アプリより帰り道のファミマがリアル
一時期、婚活アプリを試した。けれど、メッセージのやりとりすら億劫になり、続かない。プロフィールに「司法書士」と書いても、反応が良くなるわけでもない。現実は厳しい。結局、今日も帰り道のファミマに寄って、レジの店員さんの方がよほど会話している。恋愛市場より、近所の店舗のほうが今の自分にはずっとリアルで、皮肉だけどそれが現実だ。
寂しいという感情すら希釈されていく日々
最初は孤独が寂しかった。でも、今はその寂しさすら感じにくくなっている。感情が薄まっていくような、じわじわと冷めていく鍋のように。これはある意味で、老化なのか、心の防衛反応なのか。とにかく、何かに感動したり、傷ついたりする回数が減ってきた気がする。それを「大人になった」と言うのかもしれないけれど、自分にはただ、心が鈍くなっているように思えてならない。