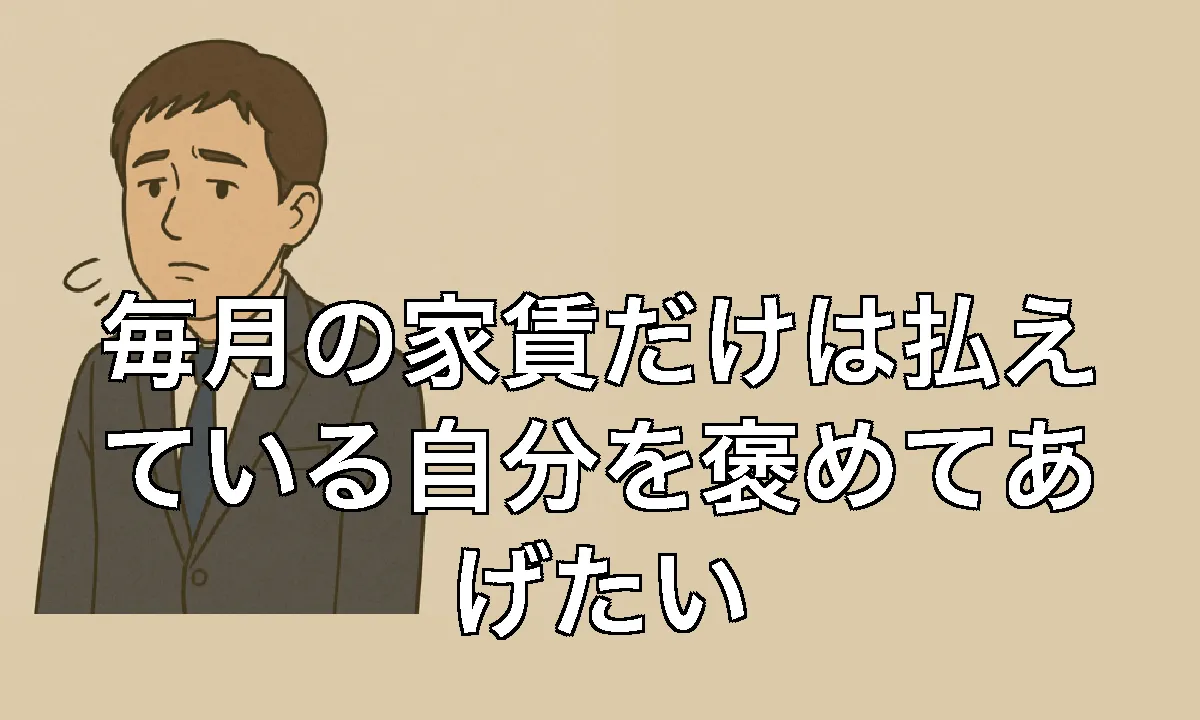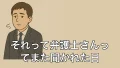家賃が払えることが自信の最後の砦
「ちゃんとしてる」と言われることはない。だけど、毎月の家賃だけはしっかり払っている。これだけは自分に課した最低限の責任だと思っている。司法書士という肩書きがあっても、現実の生活は楽じゃない。時には仕事が重なりすぎて何もかもが手につかなくなる日もあるけれど、それでも口座から家賃が引き落とされたことを確認するたび、「まだ俺は生きてる」と思える。それが、自分を保っていられる小さな誇りであり、世間とつながっているかすかな実感でもある。
支払いが済むたびに感じる安堵と虚しさ
家賃の支払いは、喜びよりも「なんとか間に合ったか…」という安堵の方が大きい。けれど、その安堵も束の間、次の月の不安がすぐに顔を出す。たとえば、以前依頼者からの入金が遅れ、通帳を何度も確認するような日々が続いた。ギリギリで間に合った月は、達成感ではなく、むしろ情けなさの方が胸に残った。「司法書士なのに…」という言葉が自分の中で反芻される。
預金残高を見て深呼吸する朝
毎月1日の朝は、ATMで残高を見ることから始まる。小銭のような数字が並ぶ通帳を見ては、目を閉じて深呼吸。その数字が減っていくのは分かってる。でも、ゼロじゃないだけで、妙な安心感を覚えてしまう。高校時代、試合前に深呼吸してた癖が、こんな場面で活きるとは思わなかった。
毎月の決済通知が「俺もまだ大丈夫」と教えてくれる
ネットバンキングの通知が鳴ると、心臓が跳ねる。「入ってるかな?」「引き落とし済んだかな?」。その通知で「決済完了」と出ると、少しだけホッとする。決して大きな成功ではない。でも、あの小さなメッセージが「まだ大丈夫」と背中を押してくれるようで、今の自分には十分すぎる支えになっている。
他のことはボロボロでも家賃だけは守ってきた
スケジュールはぐちゃぐちゃ、書類の山も放置気味、電話も折り返しが追いつかない。でも、なぜか家賃だけは守り続けている。逆に言えば、それ以外はもう崩れてしまってるのかもしれない。だけど、全部落ちても、ひとつ守り続けるものがあるって、どこか人としての線引きになるんじゃないかと思ってる。
書類の山 溜まった未処理 でも家賃だけは滞らない
机の上には未処理の登記書類が山のように積まれている。見たくない、でも見なきゃいけない。それでも、家賃の支払いだけは忘れないようカレンダーに赤字で印をつけている。皮肉な話だけど、「事務所を維持すること」だけが、仕事と生活の最低ラインになっている。
生活の崩壊と家賃の支払いは比例しない不思議
不思議と、生活が荒れても家賃の支払いは止まらない。夜中にカップラーメンしか食べてなくても、家賃だけは支払われる。それが、自分でもよく分からないこだわりだ。もはや意地だと思っている。誰に見せるでもなく、誰に褒められるでもなく、ただ「俺は払ってる」と思いたいだけかもしれない。
司法書士という肩書きと現実の乖離
世間から見れば「先生」と呼ばれる仕事。でも、実際の生活は想像とは違う。特に地方では、名ばかりの信用と、収入の不安定さが常に隣り合わせ。大きな事件があるわけでもなく、細かな業務に追われて日々が過ぎていく。そんな中で、「司法書士なのに…」というプレッシャーは、家賃の引き落としにも染みついてくる。
先生と呼ばれながらコンビニで割引弁当を選ぶ日々
名前で呼ばれることなんて、もうずっとない。みんな「先生」と呼ぶ。でもその「先生」、夕方のコンビニで半額シールを探してる。レジの若い店員さんが気を遣ってシールを貼ってくれたこともある。「がんばってください」と言われて、泣きそうになったこともある。肩書きと現実のギャップは、こんなときに特に突き刺さる。
地域の顔なのに 財布の中身はギリギリ
地元では「頼れる司法書士」と言われても、現実の財布はいつも薄っぺらい。飲み会に誘われても断る理由を考えるのが先。自分だけ時間が止まっているような錯覚に陥る。だけど誰にも言えない。誰にも知られたくない。ただ、家賃を払っていることで、少しだけ社会との接点を守れている気がする。
誰かに助けてほしいと言えない立場の重さ
「助けて」と言えたら、どれだけ楽かと思うこともある。でも、司法書士という仕事柄、弱さを見せることがはばかられる。昔、同業の先輩が事務所を畳んだとき、「誰にも言えなかった」とこぼしていた。その言葉が、ずっと心に残っている。だからこそ、せめて家賃だけは払って、自分を保っていたい。