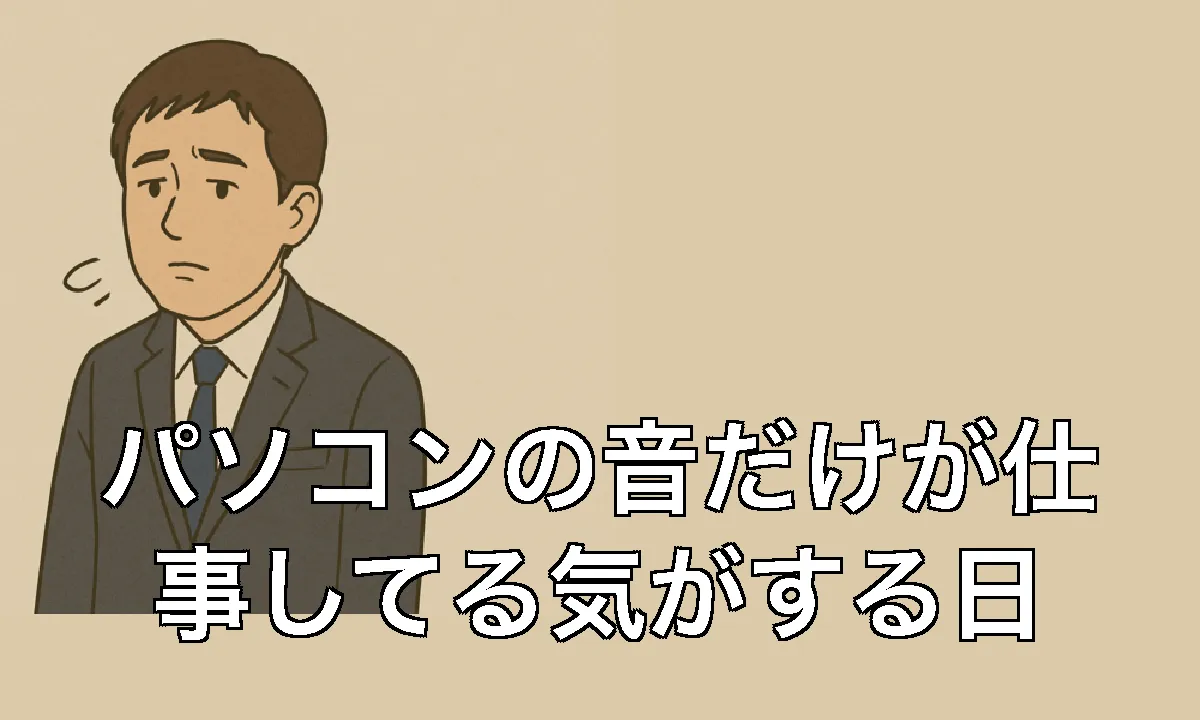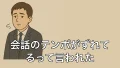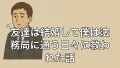パソコンの音が響く静かな昼下がり
司法書士の仕事場というのは、にぎやかとは無縁だ。特にうちのような地方の事務所で、職員が一人しかいないとなると、基本的にはとても静かだ。今日はその事務員も外出中。書類の山とにらめっこしながら、唯一鳴り続けているのが、カタカタと響くパソコンのキーボードの音だけだ。まるで事務所で仕事してるのはパソコンだけなんじゃないかと錯覚するような、そんな昼下がり。誰とも話さずに終わる日があることに慣れてしまっている自分にも、少し寂しさを感じる。
誰とも話さない日があるという現実
「今日は一言も声出してないな」と気づくことがある。特に登記関係のオンライン申請が中心の日などは、電話すら鳴らない。以前、久しぶりに人と話した瞬間に自分の声がカスれていたことがあった。笑い話のようだが、誰かと会話しないまま一日が終わるのは、案外心にくるものだ。独身だと家に帰っても話す相手はいない。テレビの音が妙にうるさく感じられて、結局消してしまう。静寂が心地よいときもあれば、重たくのしかかる日もある。
事務員も外回りの日は本当に無音
うちの事務員はとても優秀で助かっている。でも、彼女が役所や法務局に外出する日は、事務所が一気に無音になる。エアコンの送風音とパソコンのファンの音、そしてカタカタという自分のキーボード音だけが空間を支配する。音がないことは集中には向いているけれど、感情の逃げ場がないようにも感じる。ふとした時に、あれ俺、生きてるんだよな?と確認したくなる。この静けさに、自分の存在すら消えかけているような錯覚を起こすのだ。
音のない時間が思考を追い詰める
静けさはときに、思考を深めるための友になる。でも同時に、自分の不安や迷いを際立たせる敵にもなる。仕事の進みが悪いときや、ミスを引きずっているときには、静けさがその思考をエコーのように何度も反響させる。もっとできたはずだ、なんであんな説明しかできなかったんだ、と。誰にも相談できない、というのもまた静けさの中では顕著に感じる。司法書士という職業は、内省と向き合う時間がいやでも増えるのだ。
一人で仕事を回すという不安とプレッシャー
司法書士として独立して以来、基本はすべて自分で決めて自分で動く生活だ。事務員には支えられているが、それでも責任の最終的な矛先は自分にしかない。だからこそ、急ぎの登記が重なるときや、裁判書類がミスできないプレッシャーを伴うときは、胃がキリキリと痛くなる。誰にも頼れない、そんな思いが、静かな部屋の中でじわじわと広がっていく。
電話が鳴るだけで心拍数が上がる
電話のベルが鳴ると、一瞬ビクッとする。もしかして何かトラブルか、補正の連絡か、それともクレームか。昔は電話の受話器を取るのに何の感情もなかったのに、今ではちょっとした勇気が必要になっている。何か失敗していないか、送った書類に不備はなかったか。特に静かな日中に突然鳴る電話は、心臓に悪い。音がないぶん、音の衝撃が倍に感じられるのだ。
「すぐ対応します」が言えない状況
電話の相手に「今すぐ対応します」と答えられないことも増えた。一人で全部抱えていると、そもそも今やってる仕事も〆切が迫っていたり、登記の受付時間がギリギリだったりする。優先順位をつけるのが本当に難しい。結果として、どれも中途半端になりそうで、それがまたストレスになる。できることならもう一人、誰かいてくれたら。でも人件費の現実もあり、そこがジレンマだ。
誰にも代わってもらえない業務の重さ
一人親方の辛さはここにある。体調が悪くても、家族の用事があっても、結局は自分が対応しなきゃいけない。司法書士の仕事って、代行が効かないものも多い。代理人としての責任や立場がある以上、簡単に他人に任せられない。特にクライアントとの信頼関係が築かれている場合、対応が遅れるとそれだけで信用を失いかねない。だから、どんなにしんどくても、電話が鳴れば出る。パソコンが唸ってても、自分も唸るしかない。
かつての野球部仲間と自分の今を比べてしまう
高校時代の野球部仲間とは、今でも年に一度くらい会う。でもそのたびに、なんとも言えない気持ちになる。彼らは家庭を持ち、子どもがいて、マイホームがあり、奥さんの手料理の話なんかをしている。そんな話を聞きながら、自分は今日もカップラーメンか、とふと思う。仕事に打ち込んできたつもりだし、後悔してるわけじゃない。でも、たまに比較してしまう夜もある。
家庭もチームも持ってるやつらのSNS
最近はSNSもつらい。特に土日。子どもとキャッチボールしてる写真、家族で出かけた公園の写真、誕生日ケーキに囲まれた笑顔。スマホでそれをスクロールしている自分の指が、ふと止まる。「これが普通なんだろうな」と思いつつ、いいねも押せずに画面を閉じる。自分は何をしていたかというと、登記の準備を一人、静かな事務所で進めていたりする。
ユニフォームを脱いだあとの孤独なグラウンド
野球部時代は、常に誰かと一緒だった。声を出し合い、励まし合い、時にはケンカもした。でもいま、自分が立っているグラウンドは、自分しかいない。応援もなければ、監督もいない。打席に立っているのか、ベンチにいるのか、それすらわからないまま、毎日を過ごしている気がする。あの頃の一体感が懐かしい。そして、もう二度と戻らないことも知っている。
救いになったのは小さな音と習慣
それでも、完全に折れてしまわないのは、たぶん毎日の中にある小さな「音」や「習慣」のおかげだと思う。カタカタと一定のリズムで打ち込まれるキーボードの音、昼に飲む缶コーヒーのプシュッという音。誰にも気づかれない日常の中に、自分をつなぎとめるものがある。
キーボードの音にリズムを感じ始めた日
あるときふと、自分のタイピング音がメトロノームのように聞こえてきた。リズムに乗っているときは、仕事が不思議とスムーズに進む。まるで小さな音楽のようだ。ひとりでいることを逆手にとって、集中のための「音」を味方にする。それに気づいてから、音のない空間にも、少しだけ意味が生まれた気がした。
コンビニのコーヒーがくれる安心感
毎朝、同じコンビニで買う缶コーヒー。正直、味が特別美味しいわけじゃない。でも、「いつもの」があるということが、こんなにも安心感をくれるとは思わなかった。季節が変わっても、価格が変わっても、そのコーヒーだけは変わらずにそこにある。そんな小さなルーティンが、心を安定させてくれている。
誰かの一言が耳に残ることもある
この前、依頼者の一人から「先生って、すごく丁寧にやってくれるから安心です」と言われた。その一言だけで、一週間は頑張れた気がする。たった一言。でも、ずっとパソコンとだけ話していた自分にとっては、言葉以上の価値があった。人とのやり取りって、やっぱり必要だと思う。そして、それがあるから今日もまた、パソコンの前に座れているのかもしれない。