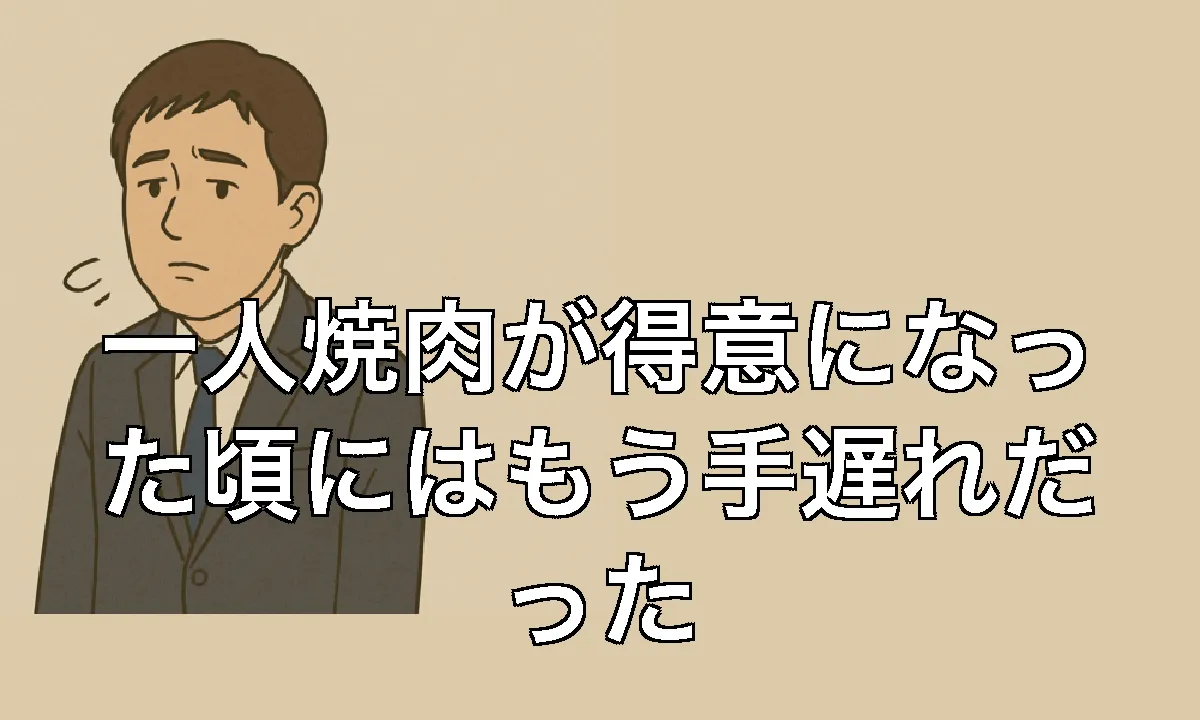静かに焼ける肉と静かに減る人間関係
一人焼肉を「得意」と言えるようになったのは、決してポジティブな意味ではない。気付けば、誰かと食事の約束をすることもなくなっていた。最初は忙しさが理由だったが、そのうち連絡をくれる人もいなくなり、自然と「一人」でいることが当たり前になった。焼肉店に入っても、最初は周囲の目が気になったが、今ではそれすら感じない。網の上の肉が静かに焼けていく音と、心の中の寂しさが重なる夜もある。けれど、それを誰かと共有する場面も、もうほとんどない。
誰にも邪魔されない焼き時間は心地いい
一人焼肉のいいところは、気を遣わなくていいこと。焼きすぎたって自分の責任、箸を止めたって誰にも気を使わなくていい。話題に困ることもなければ、愛想笑いもしない。自分のペースで焼いて食べて飲んで、店を出る。そんな自由な時間に、妙な安心感を覚えるようになったのは、司法書士という職業柄、人間関係に神経をすり減らしているせいかもしれない。事務員との会話ですら気を張ってしまう日もあるのに、誰かと「楽しく焼肉」なんて、もう重労働にすら思える。
会話しない安心感がもたらす癒し
焼肉といえば、かつては誰かとワイワイ盛り上がるイメージだった。けれど今は、無言で網に向かい合う時間こそが一番落ち着く。言葉がないことが、こんなにも気を楽にしてくれるとは思わなかった。忙しさの中で「ちゃんと喋る」ことが仕事になってしまった今、無言の時間は貴重だ。煙と共に疲れも流れていくような、そんな気すらしてくる。
「焼きすぎてないよ」って言ってくれる人がいない
どこかで寂しさもある。自分が焼いた肉が焦げてしまったとき、「大丈夫だよ」と笑ってくれる人がいれば、もっと楽しいのかもしれない。だけど、そんな誰かはもう現れない気がしている。年齢的なものもあるし、そもそも出会いなんてこの仕事をしている限り、ほとんどない。気付けば「焼き加減の失敗すら笑いにできない」場所に、自分は立っていた。
一人で食べるという選択肢が日常になった理由
一人焼肉が特別な行動ではなくなったのは、食事の誘いが来なくなったからだ。断るのが面倒で、最初はあえて誘いを遠ざけた。そのうち誘い自体が来なくなった。仕事が忙しいと言えば聞こえはいいが、本当は人と向き合う気力がなかった。だから、気軽に一人で行ける焼肉は、自分の逃げ場になっていた。
予定が合わないんじゃなくて、誘われない
「最近忙しいんですよね?」と、たまに顔を出してくれる知人がそう言う。違うんだよ、本当は暇でも誘われてないだけなんだよ。そう喉まで出かかるが、笑ってごまかす。こちらが疎遠になったのか、向こうが諦めたのか。どちらにしても、「久しぶりに食事でも」と言ってくれる人が減ったのは、こちらの態度が原因なんだろう。
「今度飲みましょう」が二度と来ない地方都市
地方では人間関係が濃密な分、壊れると修復も難しい。会わなければ自然と関係は薄れ、「今度飲みましょう」が社交辞令になるのも早い。そうして気づけば、気軽に連絡を取れる人は事務員ひとりだけになっていた。彼女とは仕事の話しかできない。つまり、本当にどうでもいい話をできる人間関係が、もうないのだ。
元野球部という肩書きはもう効力を失った
若い頃は「元野球部」という肩書きだけで、それなりに話のタネになったし、ちょっとはチヤホヤもされた。でも45歳にもなると、そんな過去は誰も聞いてこない。むしろ「今、何してるの?」のほうが問われる。そして「司法書士です」と答えると、会話が止まる。堅苦しいとか、難しそうとか、そう思われるらしい。だから焼肉の話くらいしか、自分を語れることがない。
昔は打席に立てばチヤホヤされた
高校時代、バッターボックスに立てば応援もあったし、多少モテもした。自分がチームの一員で、何かの役に立っていると実感できた。ところが社会に出たら、誰も拍手してくれないし、打っても褒めてはくれない。今の自分は、守るものもないし、応援もされない。そんなとき、一人焼肉の静かな時間が、唯一の逃げ場になっている。
バットを置いたら途端に空気のような存在に
引退してからというもの、野球というフィルターが取れた自分は、案外何もない人間だったと気づいた。司法書士として働き始めても、それは肩書きに過ぎず、自分自身を見てくれる人は少ない。だから一人焼肉の時間は、誰にも評価されず、干渉されない。空気のような存在でも、網の前ではちゃんと肉を焼けるのだ。
焼肉の煙だけは今も体にまとわりつく
野球部時代の汗の匂いと同じように、今は焼肉の煙の匂いがスーツに染みつく。でも、どこかその匂いが安心する。がむしゃらに走っていた昔と、煙に包まれて静かに肉を焼く今。その対比が、自分の変化を教えてくれる気がしている。
司法書士としての肩書きが焼肉の味を変える
「先生」と呼ばれることが増えた分、「さん」付けで呼ばれることが減った。人として見られていない、役割として見られている。焼肉を食べているときくらい、ただの「おっさん」として存在したい。網の上の肉は、そんな肩書きとは無関係に焼ける。焼肉だけが、役職や立場を持ち込まない空間なのかもしれない。
「先生」と呼ばれても家では箸を落とす
どんなに「先生」と言われても、帰宅してひとり食べるコンビニ弁当では箸を落とすし、タレもこぼす。そんな人間臭さが、表に出せないのがこの職業の辛さだ。だからこそ、焼肉屋の煙の中でひとり佇む時間が必要なのかもしれない。
事務所で感じる責任と焼肉屋で感じる自由
事務所では常に「責任」を背負っている。小さな登記ミスも大ごとになる世界で、気が抜けない。けれど焼肉屋では、焦がしたって笑って済ませられる。自分のペースで食べ、自分のタイミングで出る。そんな自由が、少しだけ心を解いてくれる。
「一人焼肉、得意なんです」が誇れる資格じゃない
「一人焼肉が得意です」と言ったところで、誰かに評価されるわけではない。でも、自分にとっては小さな誇りだ。誰かに頼らず、自分の分を焼いて、自分で食べる。それだけのことに救われている。そんな夜が、今の自分には必要だ。
それでも焼くことで自分を保っている
誰とも話さず、静かに肉を焼く時間。その中で、ようやく自分を取り戻せる気がする。司法書士という職業も、元野球部という過去も、一旦全部置いておける場所。そんな時間を持てるだけで、自分はまだ大丈夫だと思える。焼き網の上で、じりじりと音を立てる肉のように、少しずつでも前に進めていればいい。
一枚ずつ焼くことでしか前に進めない夜もある
人生も焼肉も、一気に焼くと失敗する。一枚ずつ、丁寧に焼いて、ゆっくり食べる。そんな風に、自分の人生をもう一度味わっているのかもしれない。ひとりの焼肉に、そんな深い意味を感じてしまうのは、きっと年を取ったからだろう。
誰かのために焼く日を夢見て
今は一人で焼いて食べているけど、いつかまた、誰かのために肉を焼ける日が来たらいいなと思う。焦げすぎたら笑ってくれる人、焼き加減を褒めてくれる人。そんな誰かが現れたら、「一人焼肉が得意だった頃」の話を、笑ってできたらいい。