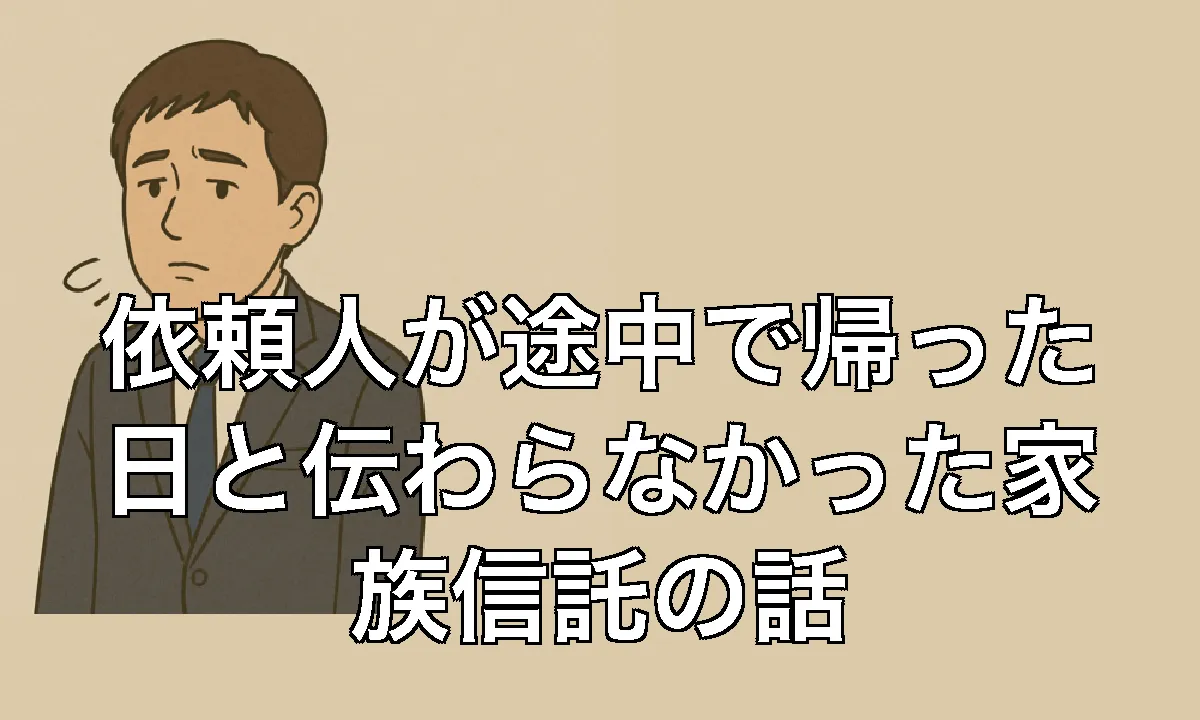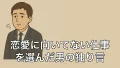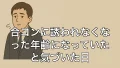忘れもしない あの日の相談室
司法書士としてやっていると、「あの日のことだけは忘れない」という瞬間がいくつかあります。たいていは登記でひやっとしたときや、裁判所の書類に不備があったときなど、胃がきりきりする経験なのですが、今回は違いました。相談に来られた依頼人が、こちらの説明の途中で席を立ち、そのまま戻ってこなかったのです。まるでドラマのワンシーンのように、ドアの音だけが耳に残っていて、いまだにその「間」の気まずさが記憶にこびりついています。
笑顔で始まった家族信託の説明
相談にいらしたのは60代後半の女性。明るいピンクのカーディガンに控えめな笑顔。「家族信託って、最近よく聞くけど…」とおっしゃるので、これはわかりやすく説明せねばと意気込みました。ところが私ときたら、いつものくせで冒頭から「受託者」「信託財産」「残余財産帰属権利者」などの専門用語をつらつらと並べ立ててしまい、依頼人の眉間にはあっという間にしわが寄ってしまいました。話がすべっていく感覚、ありますよね。相手の反応を読み取るどころか、私は完全にひとり舞台を演じていたのです。
「専門用語が多すぎるね」と言われて
説明の途中で、依頼人が小さく漏らしたひと言。「…なんだか、専門用語が多すぎて、よくわからないわ」。それでも私は焦って説明を継続してしまった。「すみません、ではもう少しかみ砕いて」と言いつつ、用意していた資料をめくり、例を挙げて喋り続けました。でもそれは本当の意味で“かみ砕いた”説明ではなかった。ただ話のスピードを落としただけで、根本的には自分の話しやすいスタイルを押し通していただけでした。
伝えたいことが伝わらない もどかしさ
家族信託のメリットもリスクも、一生懸命伝えていたつもりでした。けれどその「つもり」は独りよがりで、依頼人の心には何一つ届いていなかったのかもしれません。理解してほしいという思いが空回りし、焦れば焦るほど言葉が宙に浮く。伝えることと、伝わることは違う──その当たり前の事実に、あの日私は改めて突き付けられました。資料に目を落とす依頼人の無言に、私は何も返せなかったのです。
途中退席 机に残されたパンフレット
そしてその瞬間は、唐突に訪れました。ふと腕時計を見た依頼人が、急に椅子から立ち上がり、「すみません、今日はここまでで…また連絡します」とだけ言い残し、資料も持たずに帰ってしまったのです。引き止める声も空しく、ドアが閉まる音が無性に大きく感じられました。資料を整える手がしばらく止まらず、私は机の上に残されたパンフレットをただ眺めていました。
引き止める声も虚しく ドアが閉まる音
あの瞬間、私は自分の無力さを実感しました。法律の知識も経験も、相手に寄り添う気持ちがなければ無意味です。「信頼関係を築く」なんて口では簡単に言えるけれど、それがどれだけ難しいことか。依頼人の背中を見送ったあと、私はしばらく席から動けずにいました。ほんの数分の出来事なのに、心に残る影響は想像以上でした。
ひとり事務所に残された書類と私
その後、静まり返った事務所に一人。目の前には家族信託の資料、パンフレット、そしてお茶の残った紙コップ。「また連絡します」という言葉は、たいてい戻ってこないものだと、長年やっているとわかってきます。あの日の相談は、きっと依頼人にとって「よくわからないまま帰った」経験として残っているのでしょう。なぜ、もっと違う話し方ができなかったのか──反省と後悔が机に散らばるような午後でした。
なぜ伝わらなかったのか 自問自答の時間
私の説明は“正しかった”かもしれません。けれど、“わかりやすかった”とは言えなかった。法律家にとっての「説明」は、相手に合わせて変わるべきものです。それなのに、私はまるでセリフを読むように、自分の中で完結した話をしてしまった。あのあと一人事務所に残って考えたのは、自分の中の「安心」が相手の「不安」を無視していたことでした。
説明の順番か 雰囲気か それとも私か
帰られてしまった理由を、いまだに私は正確にはわかっていません。説明の順番だったのか、部屋の空気が冷たかったのか、それとも私自身が“壁”だったのか…。あの場面を何度も思い返しては、頭の中で別のシナリオを描いてしまいます。例えば、最初に「今、不安なことは何ですか?」と聞けていたら。私の声や表情がもっと柔らかければ。そんな“たられば”が今でも私の心に住み着いています。
士業の壁 専門職の独りよがり
士業という立場は、時として「わかってもらえない前提」に甘えてしまう危うさがあります。難しい話をしても「それが仕事」と思い込み、相手に委ねてしまう。でも本当に必要なのは、わかりやすさと対話です。独りよがりな説明が人を遠ざけるなら、それは本当の専門職ではありません。痛感するのはいつも、誰かが離れていった後です。
「難しいって言われちゃった」事務員の一言が刺さる
夕方、事務員が机を片付けながらぽつりとつぶやきました。「ちょっと難しかったのかもね、あの話」。その一言が、やけに心に刺さりました。私が長年積み重ねてきた知識が、相手にはただの“難解な話”でしかなかったこと。もっと噛み砕いた言葉を使うべきだった。もっと相手の表情を見て話すべきだった。ベテランぶっていた自分が、急にちっぽけに思えて仕方ありませんでした。
野球部だった頃はもっと伝えるのがうまかった気がする
高校時代、野球部でキャッチャーをしていた私。ピッチャーとのサインがうまく通じたときの快感、外野からの大声で指示が通ったときの一体感。あの頃は、言葉じゃない何かがちゃんと伝わっていた気がします。それが今はどうでしょう。声だけは張っていても、誰の心にも届いていない。士業の現場で「伝える」とは、声の大きさでも言葉の難しさでもなく、相手の理解に寄り添うことなのだと、しみじみ思います。
声だけは通る けど届かないこの言葉
「声が大きいだけじゃ意味がない」──元野球部としては耳が痛い言葉ですが、まさにその通りです。事務所での説明も、熱量だけで乗り切れるものではない。家族信託のような制度は特に、生活に直結するからこそ、相手の人生に寄り添った言葉選びが必要です。声を張るだけではなく、語尾の優しさ、相槌の温度。そういった細部に、想いは宿るのだと思います。
キャッチボールは相手がいて初めて成立する
キャッチボールと同じで、こちらがいくら投げても、相手が構えてくれなければ意味がありません。そして、それは相手のせいじゃなく、こちらが投げるタイミングやスピードを間違えているだけなのかもしれない。法律の話も同じです。早すぎたら届かないし、遅すぎたら見失われる。ちょうどよく、ちょうどいい言葉で──これからはそんな投げ方ができるようになりたいと、あの日以来思っています。
士業の説明も結局は相手への配球がすべて
伝え方は配球と同じで、相手の反応を見て変えるべきです。真っ直ぐばかり投げてもダメ、変化球を混ぜすぎても信頼を失う。大事なのは、相手が“取りやすい球”を投げること。それが結局、士業の「伝える力」なのだと実感しました。説明の技術は磨けるし、反省は次の一球に活かせる。そう思えるようになったのは、途中で帰られてしまったあの経験があったからです。