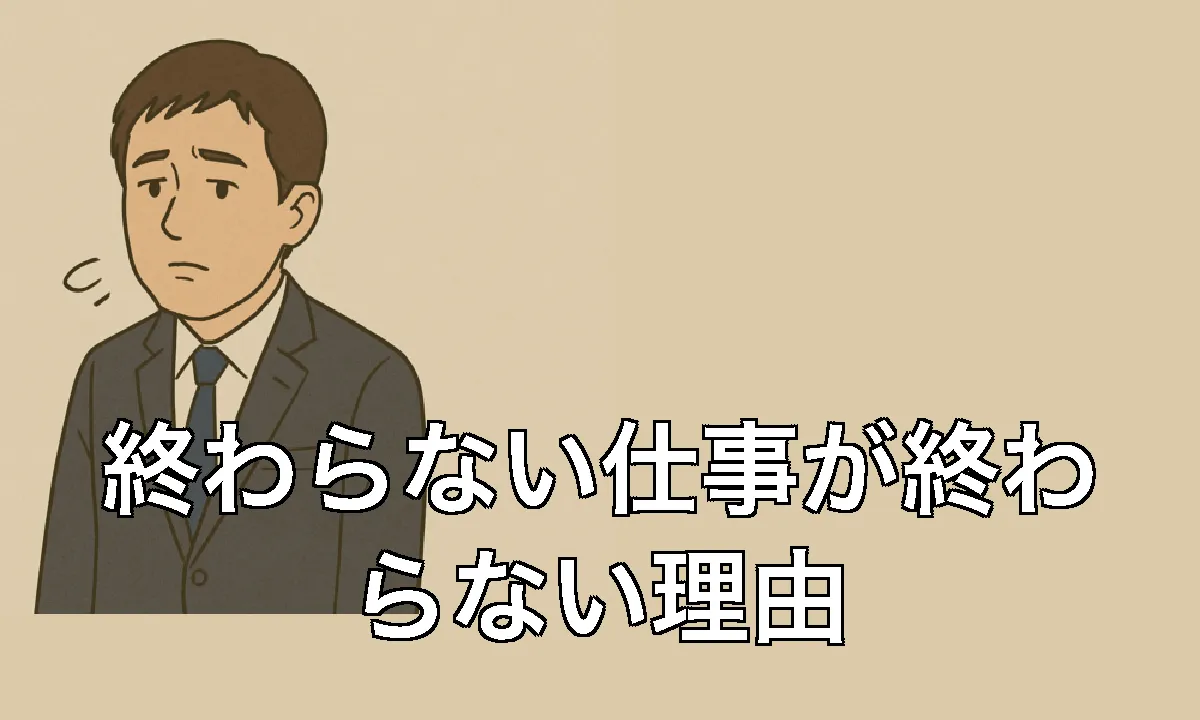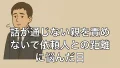毎朝始まる終わらない一日
司法書士としての朝は、決して「今日で終わる」と信じてはいけない。終わるわけがないのだ。開業して十数年、朝8時に事務所を開けるたび、前日にやり残した案件が「おはよう」と言わんばかりに机に鎮座している。書類は誰も片づけてくれないし、依頼は待ってくれない。書いたはずの報告書も、チェックすれば誤字脱字や訂正が出てきて、また書き直しだ。日が沈む頃には「今日は何をしたっけ?」と頭を抱える。そんな日々が繰り返されるうちに、「仕事が終わる」という概念自体が、まるで都市伝説のように思えてきた。
机の上に積まれた書類の山
気づけば机の左端には「至急」と赤で書かれた書類、右端には「要返信」と付箋が貼られた封筒。目の前には開きっぱなしの登記簿、背後の棚には「一応保管」の名のもとに放置された書類箱がずらり。片づけても片づけても、まるでどこかに増殖する魔法でもかけられているかのように、新しい書類が届く。以前、学生時代に寮の掃除を任された時のことを思い出す。誰かが片づけても、次の日にはまた誰かが散らかす。まるでその再現だ。「この事務所、実は誰か散らかしてるんじゃないか?」と本気で疑ったこともある。
終わりが見えない感覚に慣れてしまった
最初の数年は、「今日中に終わらせるぞ」と意気込んでいた。が、現実はそんなに甘くない。電話一本で流れが変わる。役所からの返答待ちでストップ、依頼者からの情報が不足して保留、あるいは急ぎの登記が入って予定が吹っ飛ぶ。そんな繰り返しの中で、私は自然と「すべてを終わらせる」という考えを捨てることにした。終わらないことに対してイライラするよりも、終わらないことを前提に動いた方が楽だと気づいた。諦めではなく、戦略的あきらめというやつだ。
片付けても片付けても次の案件
かつて「今日は早く帰れそうだ」と16時に思ったことがある。その直後、相続登記の電話が鳴り、別件の不動産会社から催促の連絡が入り、結局帰宅は21時すぎ。「片づけた」と思った瞬間に、次の波がやってくるのがこの仕事だ。まるで終わりのない波乗り。波を乗りこなす余裕もなく、気づけば溺れている。そうやって今日も、机の上に積まれた「終わらない案件たち」を眺めながら、「まあ、生きてるだけマシか」とつぶやいている。
事務員ひとり司法書士ひとりの戦場
ウチの事務所は、私と事務員の2人だけ。少数精鋭というにはおこがましい。限界ギリギリの布陣で、日々の業務をまわしている。私が依頼者とやりとりをし、事務員が書類作成と郵送手配を担う。でも、どちらの手が空いていても、案件の量が多ければ結局ボールはこぼれる。二人三脚で走っているようで、実際はお互い違う方向に引っ張られているようなもの。そんな日々の中で、「なぜスタッフを増やさないのか」と聞かれても、「増やせるわけない」としか答えようがないのが現実だ。
分担しているはずが結局自分の肩に
確かに仕事は分担している。が、どこまでいっても最終責任は私にある。事務員が処理した内容に間違いがあれば、修正するのは私だし、ミスが起これば謝るのも私。とくに法務局や依頼者からの問い合わせは、「責任者と話したい」となる。つまり、仕事の最終地点には必ず私がいる。だから分担していても、どこかで私の手に戻ってくるのだ。ふと気を抜くと「この人に頼みすぎてないか?」と自分に言い聞かせる。でも、頼らないと回らないというジレンマ。結局、私は私自身のキャパシティと毎日取引している。
感謝してるけど文句もある
事務員には助けられている。彼女がいなければ、今ごろ私は過労で倒れている。でも、たまには「これ、見ておいてくれたら助かったのに」という場面もある。人間だから仕方ないと思いつつ、「俺ばっかり気を回してるのかな」と感じることもある。忙しさのピークになると、そのモヤモヤが爆発しそうになる。そんな時は事務所の外に出て、深呼吸をしてから戻る。彼女に八つ当たりしても意味はないとわかっている。でも、愚痴くらいはこぼしたくなるのが本音だ。
二人三脚のようで足並みはバラバラ
体育祭でやった二人三脚を思い出す。足を紐でくくって「せーの」で走るのだが、息が合わなければ転ぶ。今の事務所運営も似たようなものだ。こちらが急ぎたい時に相手はマイペース、相手が手が空いた時はこちらがテンパっている。まるでタイミングが噛み合わない。でも、どこかで帳尻が合っているから続いているのかもしれない。完璧じゃない。でも、なんとか前には進んでいる。その絶妙なバランスの上で、今日も事務所の一日は転がっている。
人はなぜこの仕事を選ぶのかと問いたくなる夜
誰に頼まれたわけでもない。自分で選んだこの道。それでもふと、夜遅くに帰宅して冷蔵庫を開けて、コンビニ弁当を見つめながら思うのだ。「なんでこの仕事を選んだんだっけ?」と。誰かの人生を支える立場である誇りはある。でも、その誇りだけでは、やりきれない夜もある。特に、誰とも話さず一日が終わった時。人のために働いて、人と接して、人に感謝されるはずの職業なのに、なぜこんなに孤独なのか。そんな気持ちに飲み込まれそうになる夜も、確かにある。
誰にも聞かれないけど答えたくなる問い
飲みに行く相手もいないから、誰かにこの問いを投げかけることもない。でも、心のどこかでいつも問うている。「これは幸せなんだろうか?」と。もしかしたら、この問いに明確な答えはないのかもしれない。だけど、考えることで自分を保っている部分もある。昔、野球部でベンチに座っていた時、試合に出られない悔しさと向き合っていた感覚に少し似ている。出られなくてもチームのためにやる。その先に何があるのか、誰にもわからない。でも、続けるしかなかった。今も、それに近い。
それでも辞めないのは誰のためなのか
毎日「もうやめたい」と思っている。けれど、本当にやめる選択をしないのはなぜか。それは、たぶん私が「自分のため」ではなく「誰かのため」に働いていると信じたいからだと思う。依頼者の「ありがとう」が嬉しい。登記が無事に済んだときの安堵の顔を見ると、「もうちょっと続けよう」と思えてしまう。報われることなんて少ない。でもゼロじゃない。その一瞬が、この終わらない日々を続ける燃料になっているのだ。