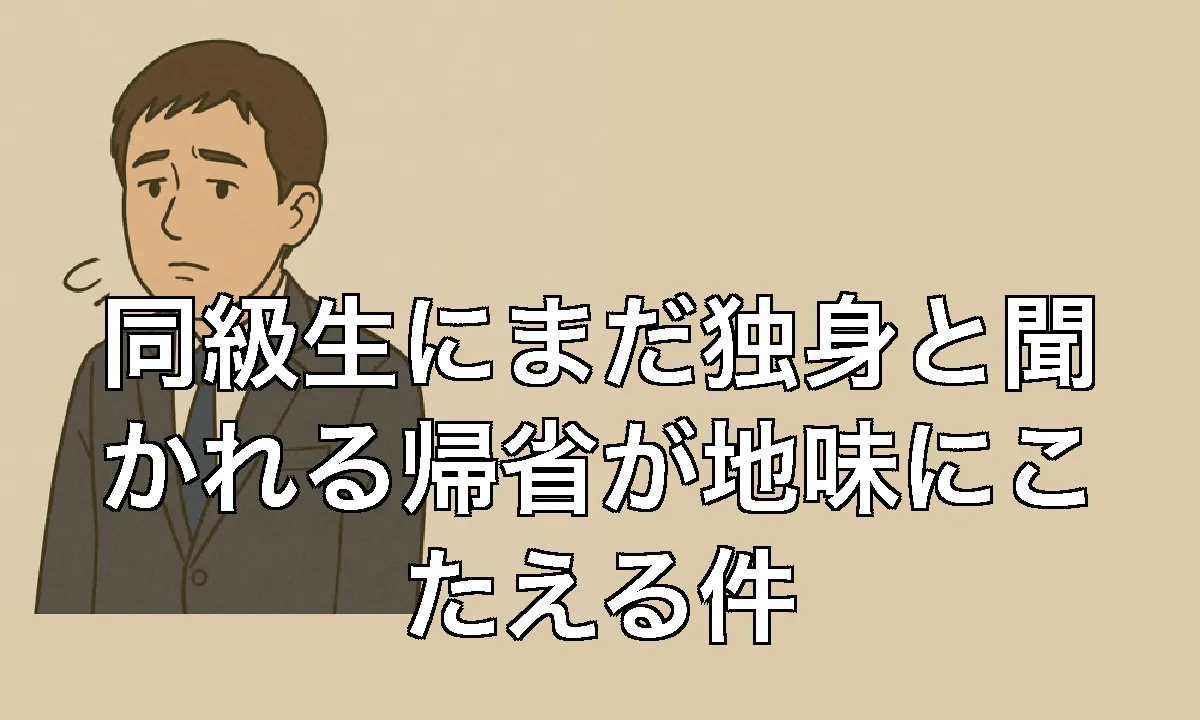帰省するたびに聞かれる質問がある
年末年始や盆の帰省。田舎に住んでいる身としては「帰る」というより「迎え撃つ」ような気持ちで実家に向かっている。駅を降りれば、空気が違う。空気だけならまだいいが、向こうからやってくる地元の誰かが、あっけらかんと「まだ独身なん?」と聞いてくる。こっちはただコンビニに寄っただけだ。なのにその一言で胃がキュッと縮こまる。まるで「人生、うまくいってないんやろ?」と刺されているようで、軽い言葉がズシンと心に乗る。別に悪気はないのはわかっている。でもこたえるのだ。
おかえりより先に飛んでくるその一言
高校時代の友人にばったり会った瞬間、笑顔でこう言われた。「元気そうやな、で、まだ独身なん?」。どうしても順番が逆なのが気になる。「おかえり」や「久しぶり」より先にくるのが“婚姻確認”とは、いったいどんな文化なのだろうか。彼らにとっては軽い近況報告なのかもしれないが、こっちはその問いに何度も傷ついてきた。冗談交じりの言い回しでも、独身でいることが欠落のように扱われるその空気に、居心地の悪さを感じずにはいられない。
同級生の笑顔と子どもの話題が刺さる
同級生たちのSNSには、笑顔で映る家族写真が並ぶ。子どもの運動会や、誕生日、七五三。みんな幸せそうだ。見せたい気持ちもわかる。だがそれを見るたび、自分の生活と比べてしまう。事務所で一人、年賀状を印刷する年末の夜。隣でキーボードを叩く事務員さんの指音だけが響く。こっちだって毎日真面目に生きているのに、なぜこうも「足りない人」扱いを受けるのか。笑顔の裏に苦労があるのもわかっている。でもやっぱり、うらやましい。
元野球部キャプテンだったあいつの現実
野球部時代、キャプテンだったあいつは、今や二児の父。実家の近くで家を建て、地元の企業で働いている。年に一度の飲み会では「いやー、子育て大変よ」と笑いながら語る。正直、羨望よりも少しの疎外感を覚えてしまう。あの頃はチームメイトだったのに、今や「家庭を持つ人」と「独身者」という分類で距離を感じる。グラウンドで一緒に汗を流した仲間が、遠くなっていくような気がして、ちょっと寂しい。
独身の何が悪いのかと開き直れない夜
「結婚してないんですか?」という問いに、心から「はい、独身です!」と笑って返せる日はまだ来ていない。どこかで引け目を感じている自分がいる。仕事で忙しい、時間がない、タイミングが合わない……。そうやって理由を並べているうちに、気づけば四十代半ばになっていた。選ばなかったのか、選ばれなかったのか。そんなことを考えては、また一人、焼酎のお湯割りを煽る。自分で選んできた人生のはずなのに、なぜこんなにも重いのだろう。
一人で食べる正月のすき焼きと気まずさ
正月に実家ですき焼きを囲む。両親と私、三人分の食卓。兄弟たちはそれぞれ家庭を持ち、家族でにぎやかに過ごしている。母が「〇〇ちゃんとこは来年小学校やて」と話すたび、会話の向こうにある「あなたは?」の気配を感じてしまう。もちろん誰も責めない。責められないからこそ、空気が重い。箸を動かす音だけがやけに響く正月の午後。たまらず早めに事務所に戻る準備をしてしまう。
親の無言の視線も地味に効いてくる
口に出して言われないほうが、逆にこたえる。「無理せんでええよ」と母が優しく言う時、逆にプレッシャーを感じてしまう自分がいる。父はテレビを見ながら黙っているけれど、たまに「○○くんとこは孫がな…」とポロリと漏らす。悪気がないのはわかっている。でも、この家族の中で「自分だけ」が空白のように感じる瞬間が、妙に冷たいのだ。
お前もそろそろの言葉が古傷をえぐる
親戚や近所の人にまで「お前もそろそろな」と言われる。年賀状で結婚報告を見ては、もうそんな時期かと焦る。でも、焦ってもうまくいかないのが人生というものだ。見合いの話もあった。合コンも行った。でも、結局「誰かの人生と重なる」ことができなかった。その理由は、自分にあるのだろう。
事務所に戻ればまた現実が待っている
実家を離れて事務所に戻ると、また日常が始まる。司法書士としての業務、書類、電話、依頼対応。忙しい毎日が、心のモヤモヤをいくらか紛らわせてくれる。ただ、ふとした瞬間に思う。果たしてこのまま一人で、死ぬまで仕事だけして生きていくのか?と。
独身のまま司法書士を続けるということ
誰にも頼らずに働き続ける生活は、ある意味で自由だ。だがその分、すべての責任が自分に降りかかってくる。体調を崩しても誰も気づかないし、休む間もなく仕事が山積みになる。事務員さんがいるとはいえ、経営者としての孤独は消えない。ふとカレンダーを見て、休日が埋まっていく様子に「このままでいいのか」と不安になる。
相談者に家庭の話を振られて固まる自分
依頼者との雑談で「先生もお子さんいらっしゃるんですか?」と聞かれた瞬間、言葉が詰まった。「いえ、独身なので…」と返すと、相手が「あ、そうなんですね」と少し気まずそうな顔になる。そんな場面が何度もある。無理もない。世の中の“普通”は、結婚して子どもがいて、という形なのだ。自分がそのレールから外れていることを、改めて思い知らされる。
事務員さんの優しさが逆につらい日もある
年末の片付けを一緒にしていた時、事務員さんがぽつりと「先生、一人で年越しですか?」と聞いてきた。悪気のない問いなのはわかる。むしろ気を遣ってくれているのだろう。でもその優しさが逆に沁みてくる。ありがたい。でも、どこか虚しい。そんな矛盾した気持ちに押し潰されそうになる日がある。
それでも生きていく理由くらいはある
独身であることに悩みは尽きない。それでも、仕事にやりがいはある。依頼者の困りごとを解決し、感謝の言葉をもらった時、この仕事を選んでよかったと思える瞬間がある。誰かと比べるのではなく、自分の人生として向き合っていくしかない。そう思えるようになったのは、ここ数年のことだ。
依頼者の感謝に救われる瞬間
先日、相続登記を終えたご高齢の依頼者が「先生、あなたにお願いして本当によかった」と涙ぐんで言ってくれた。独身だとか関係なく、人として信頼された気がして、胸が熱くなった。仕事を通して人とつながれることのありがたさを、改めて感じた瞬間だった。
誰かの人生の一部に関われる誇り
司法書士という職業は、地味だが人の人生に深く関わる仕事だ。登記、相続、会社設立、誰かの「節目」に立ち会うことができる。家庭を持つことが人生の全てではない。そう自分に言い聞かせながら、今日も誰かの力になれるよう机に向かう。
独身だって誰かの役に立っていい
結婚していなくても、家族がいなくても、自分にはできることがある。誰かの困りごとを解決し、支えになれるなら、それでいいじゃないか。ふとした拍子にまた「まだ独身なん?」と聞かれるだろう。でもそのたびに、「はい、それが何か?」と少しだけ強く言えるようになってきた自分が、今は少し誇らしい。