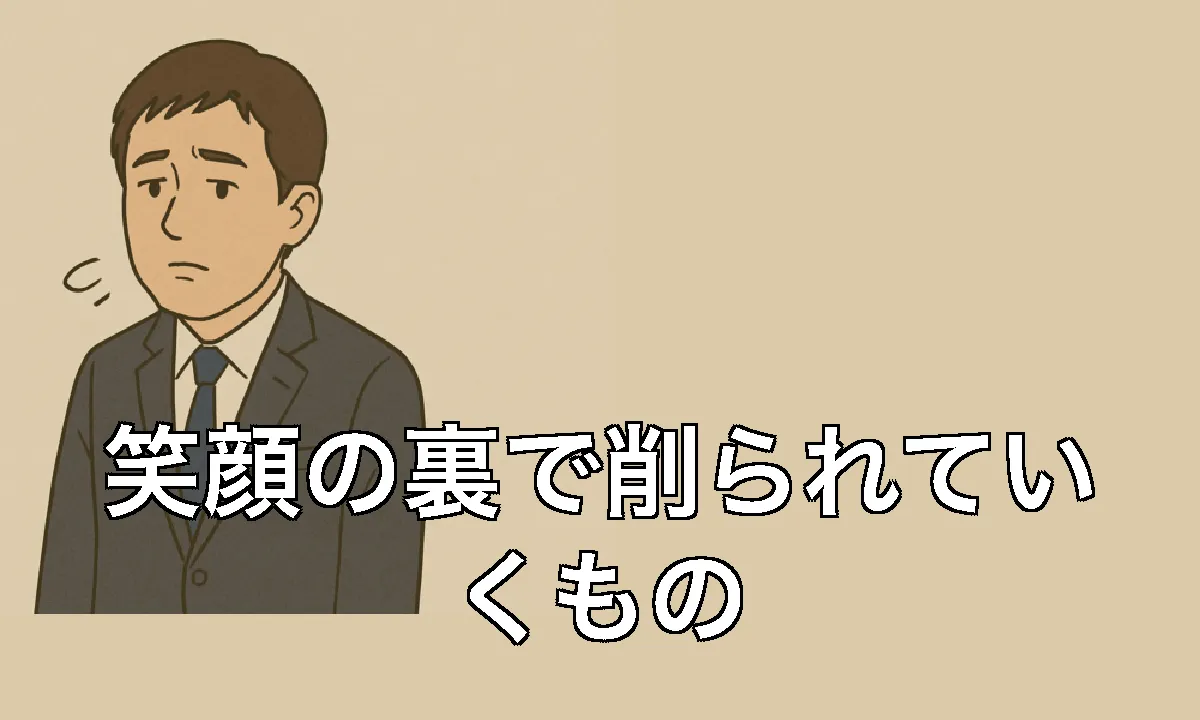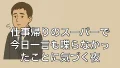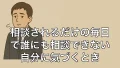笑顔の裏で削られていくもの
毎日の業務に潜む見えない疲労
司法書士として仕事をしていると、肩書きだけでは見えてこない「感情の負担」がどんどん蓄積されていきます。手続き自体は淡々と進めることが多く、書類を整える、登記申請をする、依頼人に説明する、といった作業が続くのですが、その一つひとつに「人」が関わっているという点が、想像以上に神経をすり減らします。特に、依頼者の不安や怒り、焦りといった感情を受け止めながらも、こちらは終始穏やかに対応する必要があります。それが当たり前と思われがちな職業だからこそ、余計に「笑顔の裏で何かが削られていく」ような感覚が、日々の中に忍び込んできます。
表情を作ることが仕事になる瞬間
たとえば相続の相談に来る依頼人。悲しみの中で手続きの説明を受ける彼らに対して、私は冷静でいながらも、どこかに寄り添った態度をとらなければなりません。目の前の人が泣き出しそうなとき、こちらも胸が痛みますが、それを表に出すわけにもいかない。だから、口調を優しくし、笑顔で「大丈夫ですよ」と伝える。でも本音を言えば、こっちもギリギリの心境で対応していることもあるのです。「表情を作ること」が求められるこの仕事、まさにそれが感情労働の正体なんだと思います。
怒りを飲み込む日常の積み重ね
中には理不尽なクレームを言ってくる人もいます。登記の完了日が思ったより遅い、説明が足りない、電話にすぐ出なかった……。正直言って、こちらに非がないことも多いんですが、感情をぶつけてくる人には「そうでしたか、」と謝るしかない。納得してもらうには、まず怒りを受け止めるしかないというのが現実で、こちらが感情的になるわけにはいきません。そういう日々を繰り返していると、自分の中に溜まった怒りやストレスの出口がなくなっていきます。
相手の機嫌に左右されるストレス
「今日は機嫌がよさそうだから、この話を切り出せるな」とか、「ちょっと今日は言いづらいな」とか、依頼人とのやりとりでも、常に相手の空気を読んで動く必要があります。これが地味にしんどい。たとえ自分の体調が悪かろうが、気分が落ちていようが、相手の感情を優先して振る舞わないといけない。この“空気を読む力”が必要とされる環境は、まさに感情労働の連続です。そして、気を遣えば遣うほど、夜になってどっと疲れが押し寄せてくるのです。
感情を消耗する案件対応のリアル
司法書士の仕事って、法律知識があればできると思われがちですが、実はそれ以上に「感情のマネジメント」が重要です。中でも、トラブルが絡む案件や、他士業との連携が必要な場面では、精神的な疲労が一気に増します。丁寧に話せば通じるとは限らない。むしろ「この人は自分のことを分かっていない」と思われたら、そこから信頼を回復するのは大変です。結果だけでなく、その過程の“感じのよさ”まで求められる。まさに感情が削れていく仕事です。
理不尽な要求と淡々とした受け答え
「至急でお願い」と言われて引き受けた案件が、結局本人の書類不備で進まず、そのくせ「まだですか?」と催促される……なんてことはしょっちゅうあります。こちらが怒りたい気持ちを抑え、「現在、こちらで可能な準備は整っております。〇〇の書類が揃い次第、すぐ対応しますね」と返す。この“淡々とした受け答え”の裏で、どれだけ感情を飲み込んでいるか。誰も見ていないし、誰も評価してくれません。でもそれをやらないと仕事が円滑に回らない。虚しいです。
声のトーンひとつで左右される印象
電話対応ひとつとっても、こちらが少しでも早口だったり、声が低めだったりすると「冷たい」「感じが悪い」と思われることがあります。逆に、明るすぎると「軽く見られた」とクレームになることもある。じゃあ、どんな声が正解なんだよ……と内心思いながら、毎回“ちょうどいいトーン”を探して話します。これがまた疲れる。声色や抑揚、ちょっとした「間」にまで気を配るなんて、もう漫才師の世界ですよ。
丁寧であればあるほど消耗するジレンマ
丁寧に、丁寧に、と心がけていると、どんどん自分の気力が削れていきます。特に「丁寧に対応しないと、信用を落とす」というプレッシャーがあるから、力を抜くわけにいかない。けれど、どこかで自分の中に限界が来る。最近は、無意識にため息が増えてきました。「ああ、また丁寧にやらなきゃいけないな」「今日も声を張って笑顔で迎えなきゃいけないな」って。自分をすり減らすことが、職業倫理のようになっている現実に、そろそろ疑問を感じます。
事務員との連携もまた感情労働
うちの事務員はひとりだけ。真面目で助かってるんですが、当然ながらこちらが気を遣う場面も多いです。ミスがあったとき、厳しく言えば空気が悪くなる。でも甘くすれば繰り返される可能性もある。この「ちょうどよい叱り方」もまた、感情を使います。しかもそれを、誰かに相談できるわけでもない。結局、自分の中でうまく調整しながら、黙々と日々をこなすしかない。人を雇うって、本当に大変なことですね。
気を遣いすぎて結局自分が疲れる
事務員が体調悪そうな日なんかは、「無理してないかな」「帰ってもらった方がいいかな」と気を回しつつも、業務は進めなきゃいけない。頼りにしてる分、遠慮もあるし、感謝もあるし……そういう感情がぐるぐる回って、最終的に自分が疲れる。決して嫌な子じゃないんです。でも、感情を使う場面が多すぎて、仕事の終わりには心がぐったりしていることが多いです。
小さなミスでも空気が重くなる
ちょっとした書類の打ち間違いがあって、「あ、ここ違うね」と言っただけなのに、急に空気がどよんとする。相手は悪気があるわけじゃないし、こちらも怒鳴ったわけじゃない。でも「注意した」という事実だけで、お互いに気まずくなる。こういう時、「もういっそ全部自分でやったほうが早い」と思ってしまうんですよね。だけどそれも違うし……。感情を管理しながら一緒に仕事する難しさを、改めて感じる場面です。
責任者としての孤独な気配り
私は所長ですから、最終的にはすべての責任を背負わなければいけません。仕事が回らなければ「自分の指導が悪いのか」と反省し、ミスがあれば「きちんと見ておくべきだった」と悔やむ。感情を乱さず、穏やかに、でもしっかりと指示する。そのバランスが、誰にも見えないところで私を削っていきます。笑顔を保つのが一番難しいのは、こういう孤独な時間かもしれません。
笑顔で乗り切ることに慣れてしまった自分
ふと気づくと、笑顔で対応するのが習慣になっていました。内心では落ち込んでいても、誰かが事務所に入ってくると「こんにちは〜」と明るく声を出す。この癖が染み付いてしまった自分を、時々他人のように感じます。「本当の自分は、こんなに元気じゃないのにな」と。笑顔が板についてしまったことが、いいことなのか、ちょっと分からなくなってきました。
「良い人」でい続けることの代償
依頼人から「先生って優しいですよね」と言われるたびに、少し嬉しく、でも同時に虚しさも感じます。良い人でいるって、しんどいんですよ。優しさの裏では、たくさんの感情を抑えているし、自分を後回しにしている。なのに、それが報われることはほとんどない。優しさの使い方を、間違っているのかもしれない。でも、そうしないとこの仕事は続けられない気もする。矛盾ですね。
誰にも見せない本音の行き場
夜、ひとりで事務所に残って仕事していると、ふと本音が漏れそうになります。「しんどい」「もうやめたい」「誰か助けてほしい」……でも、言えない。言ったところで状況は変わらないし、愚痴を聞いてくれる相手もいない。せめてここで書くことで、自分の中の感情を整理しているのかもしれません。本音って、本当にどこにも行き場がないんですよね。
それでもまた明日も笑う選択
それでも、明日になればまた事務所を開けて、依頼人を迎えて、笑顔で対応する自分がいます。なんだかんだで、私はこの仕事が嫌いじゃないのかもしれません。感情を削りながらも、それを誇りにしている部分もある。削られることに意味を持たせないと、やっていられないのかもしれません。でも、もう少し楽に笑える日が来たらいいなと、どこかで願っています。