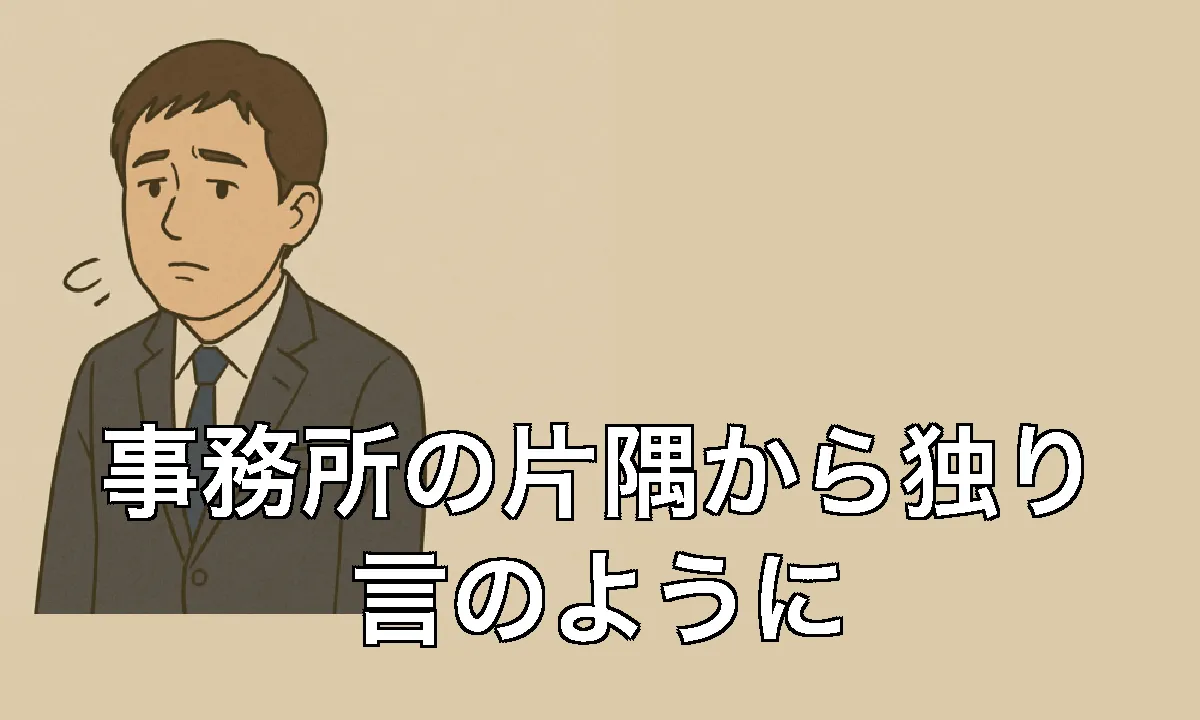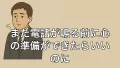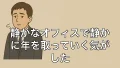朝の静けさに紛れて始まる一日
まだ薄暗い朝、電気ストーブのタイマーが作動して、冷えきった事務所が少しずつ温もっていく時間が好きだ。けれど好きだから早く来ているわけではない。ただ誰にも見られずに書類を開き、心の準備をしたいだけだ。今日はどんな電話が鳴るのか、どんな面倒が待っているのか、そんなことを考えていると、結局いつもより30分早く出勤してしまう。朝の静寂と書類の重さの対比に、今日もまた始まったのだと実感させられる。
机に広がる書類の山を前にして
どんなに前日に整理しても、翌朝にはまた机の上が埋まっている。登記簿、契約書、委任状、住民票……とにかく種類が多いし、期限もばらばら。まるで野球部時代の練習メニューのように、次から次へと片付けるべきことが降ってくる。だけどあの頃と違うのは、仲間がいないこと。球拾いをしてくれる後輩も、檄を飛ばしてくれる監督もいない。ただ一人、ペンを持って打席に立ち続ける毎日だ。
時間が足りないという現実
一日24時間というのは、誰にとっても平等なはずなのに、なぜこんなに足りないのだろう。タイムスケジュールを組んでも、予定どおり進んだ試しがない。来所予約がずれ込み、電話が割り込んできて、思わぬトラブルで役所まで出向くことになる。気がつけば昼ごはんも食べ損ねている。まるでエンドレス延長戦。バッターが打っても打っても、試合が終わらない感覚に近い。
それでも出勤してくれる事務員に感謝
そんな中でも、黙って出勤してきてくれる事務員の存在には本当に助けられている。無口だけど几帳面で、僕が言い忘れていた依頼にも気づいてくれる。年齢もだいぶ離れているけれど、どこかお母さんのような安心感がある。でも、あまり頼りすぎてはいけないと思う反面、頼らなきゃやっていけない現実もある。せめて給料だけは遅れないようにと、毎月祈るような気持ちで振り込んでいる。
電話が鳴るときの胸のざわつき
着信音が鳴るたび、心臓が軽く跳ねる。事務所の電話というのは、基本的に「いい話」では鳴らないことが多い。登記の遅れ、書類の不備、時にはクレーム。「また何か起きたか?」と条件反射のように警戒してしまう。そんなふうに構えてしまう自分も嫌だけど、そうでもしないと精神がもたないのだ。
トラブルの匂いはすぐにわかる
声のトーンや第一声の言い回しで、大体の展開が読めてしまうようになった。たとえば「ちょっとお聞きしたいんですけど…」から始まる電話は、たいてい簡単では終わらない案件だ。以前、そういう電話に「はい、大丈夫ですよ」と気軽に応じたら、丸三日寝られないトラブルに巻き込まれたことがある。慎重すぎるくらいでちょうどいい、そんな教訓をいくつも重ねてきた。
受任の重さと断ることの罪悪感
依頼を引き受けるとき、どうしても「この人の人生の一部を背負う」という感覚になる。司法書士の仕事は、法的な手続きを代行するだけのものではない。その人の希望や不安、家族との関係まで踏み込んでしまうこともある。だからこそ、依頼を断るのはとても苦しい。手が回らないとわかっていても、断るときは自分が冷たい人間のように感じてしまうのだ。
そしてまた自分を追い詰めてしまう
そんなこんなで、つい無理をしてでも引き受けてしまう。その結果、夜遅くまで事務所に残る日が続き、家に帰っても頭が冴えて眠れない。翌朝、また机の上に積まれた書類を見て、ため息をつく。この繰り返しだ。仕事をしているのか、仕事に追われているのか、自分でもよくわからなくなる。
一人の昼食と黙った空間
昼の時間になっても、食べに行く元気がない日は多い。コンビニおにぎりをかじりながら、静まり返った事務所の空気に包まれる。誰とも話さずに昼食をとるのが当たり前になって久しい。元野球部の頃は、いつも賑やかにワイワイやっていたはずなのに、今はその賑やかさすら、どこかまぶしすぎる。
ラジオだけが会話相手
そんな昼の時間を少しでも紛らわせてくれるのが、ラジオのパーソナリティの声だ。明るいテンションで日々のニュースを読み上げる声が、なんとなく救いになる。自分の生活とは違う世界が確かにあると実感させてくれるからだ。人間関係は希薄でも、声のぬくもりだけで少しだけ孤独が薄まることもある。
誰かと笑うことに飢えている
最近は、心から笑った記憶があまりない。テレビを見て、クスっと笑うことはあるけれど、誰かと一緒に笑うって、どれだけ豊かなことだったんだろう。友達も減り、合コンも縁遠くなり、そもそも誘われることもない。モテたいわけじゃないけど、「この人と話したい」と思われる存在になってみたい。そう思う自分がいる。
それでもやめない理由
仕事は苦しい。正直、何度も「辞めようか」と考えた。でも、それでも続けているのは、やっぱりどこかで救われているからだ。誰かが「助かりました」「本当にありがとう」と言ってくれる、その一言があるから。
依頼者の「助かった」が救いになる
ある日、登記の相談に来た年配の女性が「こんな複雑な話、どこにも頼めなくて困ってたの」と涙ながらに言ってくれた。手続きが完了したとき、「これでようやく眠れます」と笑ってくれた。その瞬間、自分のやってることも、まんざら無意味じゃないんだなと感じた。
誰かの人生に少し関われる幸せ
司法書士の仕事は、決して派手ではないし、脚光を浴びることもない。でも、その人の節目に立ち会える仕事だと思っている。人生の転機に、ちょっとだけ支えになる。そんな役目を果たせるなら、この狭い事務所の片隅で、もう少しだけ踏ん張ってみようか。そんな気持ちが、また次の日を迎える力になっている。
もうちょっとだけ頑張ってみるか
朝が来て、また書類に埋もれ、電話に追われる日々だけど、それでもこの場所が自分の居場所だと思えるようになった。モテなくても、愚痴っぽくても、誰かの力にはなれている。それなら、もうちょっとだけ頑張ってみても、悪くないかもしれない。