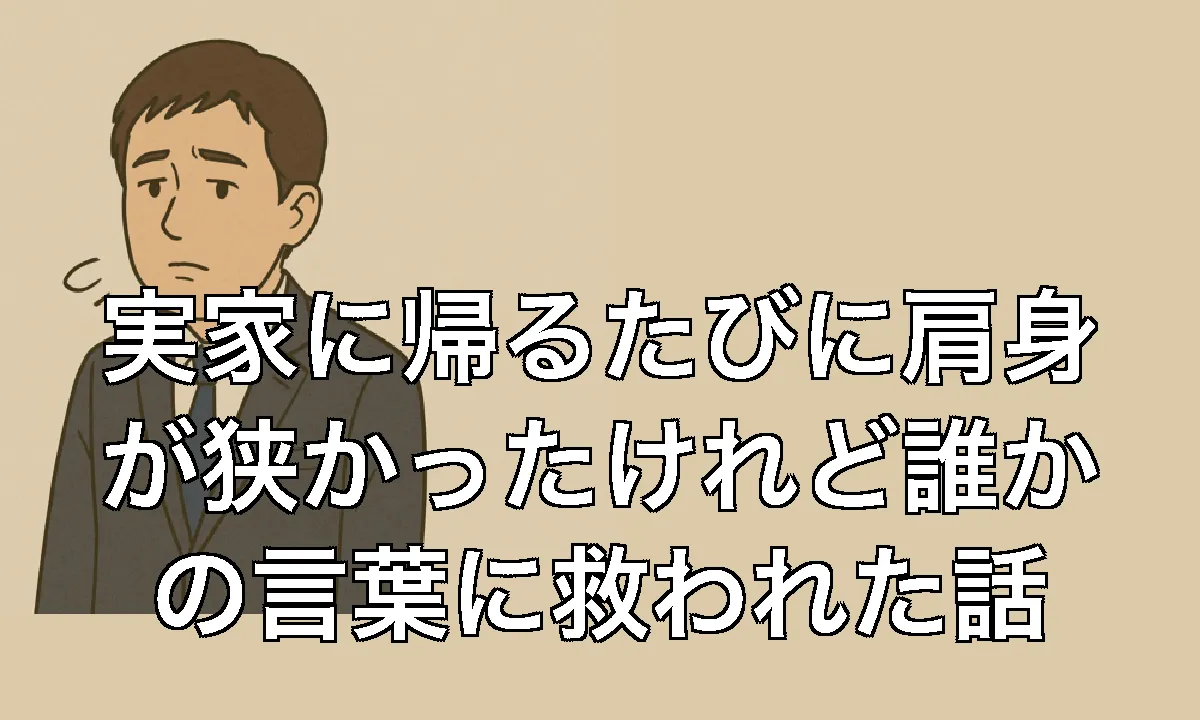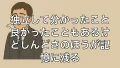実家に帰るたびに感じるあの空気の重さ
年末年始や盆暮れ、世間が「帰省ラッシュ」で賑わうニュースを見るたびに、私は憂鬱になる。たとえ仕事が順調であっても、独身で子どももいないという一点だけで、実家の空気が重く感じられる。田舎という土地柄もあるのか、「結婚して一人前」「家を持って一人前」みたいな空気がまだまだ残っている。司法書士という職業の説明をしても、それは親にとっては「安定してる仕事」ではあっても、「誇れる息子」にはなれないのだ。
玄関を開けた瞬間に漂う無言の圧
ドアを開けると、母が「おかえり」と言ってくれる。その言葉自体は優しいはずなのに、どこか探るような視線が混じっているような気がしてならない。お土産を渡しても、食卓につくまでの会話はぎこちなく、「仕事は順調?」という言葉に続いてくるのは、「で、結婚の話は?」と続きが読める。この数秒の沈黙が、もうなんとも言えず重い。あれが耐えがたいのだ。正月なのに胃が重くなる。
親の優しさがプレッシャーに変わる瞬間
「あんたが元気ならそれでいいよ」と母は言う。でもその直後に「〇〇ちゃんとこはもう二人目なんだって」と続く。その情報、今必要?と思ってしまう。でも、悪意があるわけじゃないのはわかる。心配しているだけ。でもその心配が、私にとってはプレッシャーになる。結婚しない=不安定という価値観が根強い中で、今の生き方を説明するのは本当に疲れる。
「そろそろ結婚は?」が毎回のルーティン
親戚が集まるとさらに事態は悪化する。「良い人いないの?」「紹介しようか?」という言葉の応酬。断ってもまた次回には同じ会話が繰り返される。もうスクリプトでも渡しておこうかと思うほどだ。司法書士として独立して働いていることなんて、話題にもならない。年齢と結婚だけが判断材料になる。実家にいる間中、自分の人生そのものが評価されているようで、ただただ肩身が狭くなる。
司法書士という肩書が通用しない場所
どれだけ仕事で成果を出しても、地元の空気はそれを評価しない。特に親戚の中では「会社員=安定」「公務員=安心」という風潮が根強い。司法書士といっても、士業に詳しくない人からすれば「なにそれ?」という反応も多い。説明するたびに、「へー、なんかすごそうだね」で終わる。それ以上話が広がらない。孤独感というか、自分の立場をいちいち弁明しなきゃいけないのが面倒なのだ。
親戚の集まりで味わう説明の虚しさ
「登記とか、相続の書類とかやってます」と言ってもピンとこない。中には「弁護士とどう違うの?」と毎回聞いてくる叔父さんもいる。いや、前も話したはずなんだけど…と内心では思うけど、表向きは笑顔で答えるしかない。せっかくの休みなのに、仕事の話ばかり。しかも説明するたびに、話している自分がどんどん虚しくなっていく。誰のための帰省なんだろう、と思ってしまう。
年収や安定を語っても響かない理由
一応、それなりに稼いでいるつもりだし、仕事も安定している。でもそれを口にしても、「でも一人なんでしょ?」の一言で一蹴される。実家の価値観では、収入よりも家庭があることが重視されるのだ。そんな中で、どれだけ「こっちはこっちで幸せなんだけどな」と思っていても、なかなかそれが伝わらない。理解してもらおうとするだけで、疲れてしまう。
それでも辞めなかった自分の意地
だからといって司法書士を辞めようと思ったことはない。むしろ、反発心で続けてきたところもある。「何があっても独立して食っていく」という気持ちは、ある意味、実家の圧力のおかげかもしれない。帰省のたびに肩身が狭くなるからこそ、「誰にも頼らずやってやる」という意地が芽生える。そうやって自分を鼓舞してきたのも事実だ。
そんな中で救ってくれた一言
何も変わらない実家の空気に、毎回落ち込むのが恒例行事になっていた。そんなある年、久々に連絡をくれた高校時代の友人がいた。何気なく、「仕事、頑張ってるんだってな」と言われた。それだけの一言だったけど、なぜか胸に残った。「見てる人はいるんだな」と思えて、妙に嬉しかった。救われたというのは、こういうことなんだと実感した。
古い友人からの何気ないLINE
その友人とは、野球部時代に一緒に汗を流した仲間だった。お互い別の道に進んだけど、たまたま彼の親族が相続で困っていて、ネットで調べていたら私の名前を見つけたらしい。「あ、あいつ頑張ってるじゃん」と思ったそうだ。それをそのままLINEで送ってくれた。その一言で、私の心はふっと軽くなった。「ああ、見てくれてる人がいるんだな」と。
「がんばってるの、知ってるよ」の破壊力
シンプルだけど、こんなにも心に響く言葉があるのかと思った。「がんばってるの、知ってるよ」って、今までどれだけ欲しかった一言だったか。実家では一度も聞いたことがなかった。司法書士という仕事に誇りを持てていたはずなのに、その一言でようやくそれが報われた気がした。見えないけれど、ちゃんと伝わっていたんだと安心できた。
あの言葉が胸に残って仕事に戻れた
帰省の数日後、また事務所に戻り、いつものように書類に囲まれた生活に戻った。でも心は違っていた。もう実家の空気に一喜一憂しなくていい。「自分をわかってくれる人がどこかにいる」という安心感が、仕事にも前向きな姿勢をくれた。あのLINEがなかったら、たぶん今ごろもっと荒んでいたかもしれない。
誰かの共感が肩の荷を軽くする
肩身の狭さは、結局のところ「誰にも理解されていない」と感じる孤独から来る。でも、それを打ち砕くのは、たった一言の共感だったりする。人にわかってもらえるって、すごく力になるんだなと身をもって感じた。だからこそ、今は誰かが同じように肩身の狭さを感じていたら、そっと背中を押してあげたいと思っている。
自分もいつか誰かの支えになれたら
司法書士として、依頼者から「助かりました」と言われることもある。それはもちろん嬉しい。でも、もっと人間として「いてくれてよかった」と思われる存在になれたら、それこそが本当の意味での「支える仕事」なんじゃないか。そう思えるようになったのは、あの友人の言葉のおかげだ。今度は自分が誰かに言ってあげたい。「がんばってるの、知ってるよ」と。
愚痴をこぼせる相手のありがたさ
結局、誰かに話せるだけで救われることって多い。私はいまだに、事務員さんにも全部は愚痴れないけど、心のなかで誰かとつながっているという感覚があるだけで、ずいぶん違う。もし今、帰省がつらいと感じている人がいたら、「自分だけじゃない」と思ってほしい。少なくともここにも一人、同じような気持ちの人間がいる。
肩身が狭いのは自分だけじゃないと気づく
実家に帰っても肩身が狭くて、自分だけが取り残されてるような気持ちになることはある。でも、そんな人は決して一人じゃない。むしろ多くの人が、表では笑っていても内心では同じような思いを抱えている。そう気づけたとき、少しだけ気持ちが軽くなった。だからこの文章も、誰かの心を少しでも軽くできたら、それで十分だ。