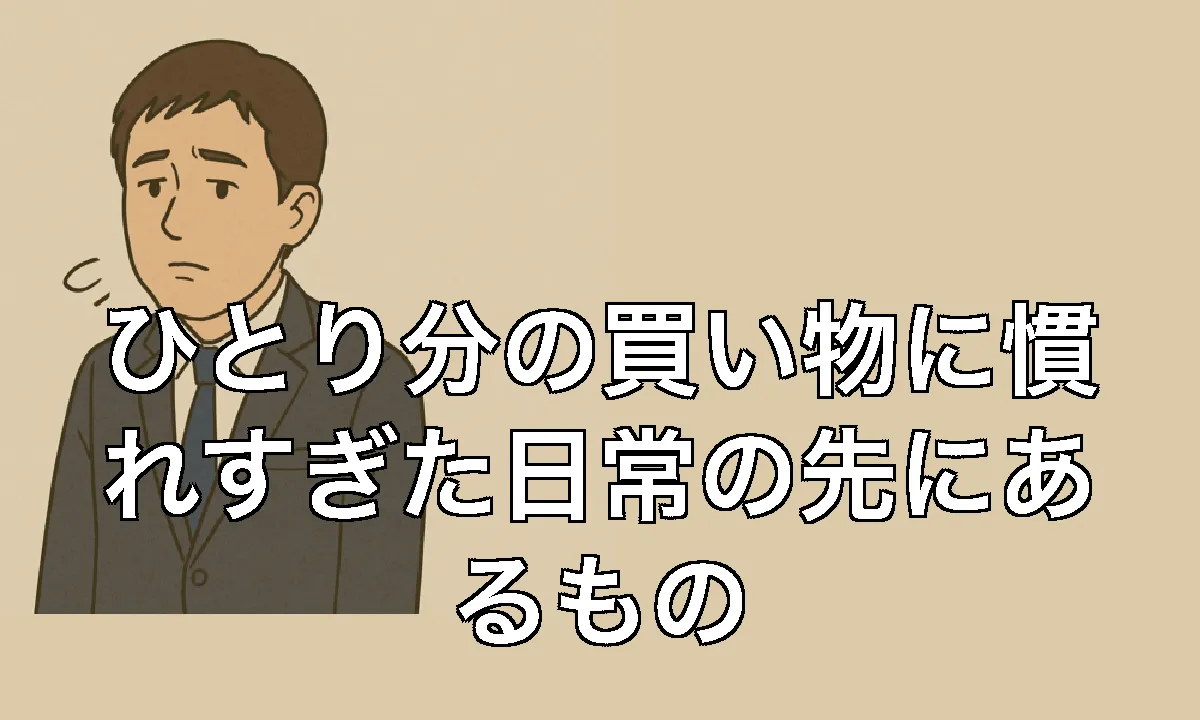ひとり暮らし歴が染みついた買い物習慣
気がつけば、ひとり暮らしももう10年以上になる。司法書士として仕事に追われる毎日、食事はもはや「必要だから仕方なくとるもの」という位置づけに落ち着いてしまった。誰かと一緒に食べるという感覚はとうの昔に薄れ、買い物の仕方にもそれが如実に現れている。「一人分」に最適化された思考と行動が、知らぬ間に自分の生活そのものを支配していた。
スーパーでの行動パターンはすでに固定
仕事帰りのスーパーでは、足取りも軽く、まるでルーティンワークの一部かのように売り場をめぐる。野菜売り場は基本スルー。向かうのは惣菜コーナーと冷凍食品棚。栄養バランスなんて気にしていられない。仕事で頭を使いすぎた分、せめて夕飯は思考停止して選びたい。そんな思いが根底にあるのだと思う。
カゴに入るのはいつもの食材だけ
冷凍うどん、レトルトカレー、豆腐、納豆、卵。いつも同じ顔ぶれの食品たちがカゴに入る。新しいレシピを試そうなんて気力は、朝から法務局とやり取りしてる時点でとっくに消えている。疲れた頭で冒険できるほど、日常に余白が残っていないのだ。
「半額シール」に反応する瞬発力の高さ
唯一、瞬発力を見せるのが「半額シール」への反応だ。背広姿のまま、他の客と同時に手を伸ばし、焼き魚のパックをゲットする瞬間には、まるでかつて野球部だった頃の闘志が蘇る。50円引きに本気を出す男、それが今の自分なのかと思うと少し哀しくなるが、それもまた現実だ。
ふと気づいた冷蔵庫の中の景色
ある夜、何の気なしに冷蔵庫を開けたとき、言いようのない虚しさに襲われた。中身はいつもの豆腐と納豆と卵。白と茶と黄の繰り返し。まるで色を失った風景のようだった。その瞬間、自分が「食事」ではなく「作業」としての買い物に慣れすぎていることに気づいた。
並んだパックの豆腐と納豆の安心感
豆腐と納豆は、賞味期限も長く、安価で、そして調理が不要。仕事に追われ、帰宅が遅くなっても「あると安心する」存在だ。だけど、その「安心」は「変化を拒む」ことの裏返しでもある。新しい食材を選ぶ余裕がない日々が、買い物の風景を単調なものにしていた。
色味のない食卓と仕事の疲れの相関関係
最近、食卓に色がない。茶色いおかずに白いごはん。サラダを添える発想すら忘れかけている。疲れているから、と言い訳して、結局は自分をないがしろにしているのかもしれない。食べることの楽しみを放棄することで、心の疲れをさらに深めていたようにも思う。
野菜の存在感の薄さが孤独を物語る
冷蔵庫に残る唯一の緑は、期限が近くなって変色したカットレタスの袋だった。「野菜を買っても食べきれない」という理由で買うのをためらい、結果的に栄養も気持ちもどんどん偏っていく。野菜を買うという行為すら、今の自分には「贅沢」になっていた。
誰かと分け合うという感覚の鈍化
2人前、3人前と書かれた食品が、今の自分には遠い存在になっている。昔は普通に作っていたカレーも、今はレトルト一択。誰かと一緒に食べることを前提とした量や味付けは、日常からどんどん消えていった。そしてそれに気づいてすらいなかった。
「2人前」という表示が遠く感じる理由
スーパーの棚に並ぶ「家族向け」のパッケージが、まるで別世界のもののように思える。一人用の冷凍食品がやけに目立つ今の時代、自分もそれに完全に順応してしまっている。「2人前なんて無理」「どうせ余る」そんな思考が先に立って、手を伸ばせなくなっていた。
「多すぎるからやめておこう」の連続
唐揚げの大パックや、4つ入りのコロッケ。食べきれないことを想定して手を引いてしまう。冷凍すればいいのに、それすら面倒に感じる自分がいる。結局、いつもと同じ一人前のパックに落ち着く。その選択が積み重なり、日常に変化がなくなっていく。
仕事に追われる日々と食の優先順位
司法書士の仕事は、地味ながらも責任が重い。ミスが許されない書類に神経を使い、日々の対応に追われると、食事なんてどうでもよくなってくる。「とりあえず腹を満たせばいい」が優先される。それが、いつしか習慣となっていた。
朝食抜きもはや日常 飲み物でごまかす
朝はギリギリまで寝ていたい。起きてコーヒーだけ飲んで出勤。そんな毎日が数年続いている。「朝ごはんくらい食べた方がいい」と頭ではわかっているのに、実行には移せない。空腹よりも眠気が勝ってしまうあたり、自分の生活バランスの悪さを物語っている。
昼はコンビニ 夜はスーパーの半額惣菜
昼は職場近くのコンビニでパンかおにぎり、カップ麺。夜はスーパーの惣菜が主力メニュー。調理する気力がないというより、「時間がもったいない」と思ってしまう。でもその時間を惜しんでまで働いたところで、報われるとは限らない。そう思っても、また翌日も同じ流れになるのだった。
ふと訪れる心の隙間の正体
ある晩、味噌汁をインスタントで済ませながら、ふと「これが本当に自分の望んでいた生活なんだろうか」と思った。誰かと食事をし、笑い合う時間。それが今は遠い夢のように思える。買い物も食事も、生活の根幹のはずなのに、いつしか「ただのルーチン」になっていた。
誰のために買い物をしているのか
「自分のために」と思って買い物をしていたつもりが、実際には「無難に済ませるための消費」だった。そこに楽しさも、選ぶ喜びもない。カゴの中身は、その日の気分ではなく「効率」と「疲労」で決まっていた。それに気づいた瞬間、胸の奥が少しだけ痛んだ。
カゴが軽くなるほど心が重たくなる
仕事が忙しい日ほど、買い物は最短コースで済ませる。カゴの中身は最低限。でも、家に着いてそれを冷蔵庫に入れたあと、なんとも言えない虚しさが残ることがある。誰とも共有しない食事、誰にも見せない買い物。それは、少しずつ心を蝕んでいたのかもしれない。