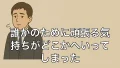一人きりの静かな事務所にて
地方で司法書士事務所を営んでいると、音のない時間がやたらと多くなる。朝、誰もいない事務所のドアを開けて電気をつけるとき、あの静けさに毎日慣れそうで慣れない。唯一の事務員さんは出勤時間が遅めだから、午前中はほぼ一人。書類の音、キーボードの打鍵音、コーヒーを注ぐ音、それ以外はない。40代になってから、この静寂が妙に重たく感じられるようになった。ふとした瞬間に、どうしようもなく胸が締めつけられるのだ。
今日も机に向かう音だけが鳴っている
依頼が殺到していた時期は、その音が「戦っている証」だった。でも最近は違う。静かすぎる日は、「今日、大丈夫か?」という不安の方が先に立つ。午前中に電話が鳴らないと、「なにか忘れてるんじゃないか」「急ぎの案件を落としてるんじゃないか」と落ち着かなくなる。特に月初や月末はその傾向が強く、業務量ではなく感情の消耗が大きい。静かであることがこんなにも不安につながるなんて、独立した当初は想像もしなかった。
電話の音にびくつくようになったのはいつからだろう
若い頃は電話のベルが鳴るたびに「仕事が来た」と嬉しく思った。けれど今は違う。電話の向こうに何があるのかを先に想像してしまう。「訴訟絡みか」「クレームか」「面倒な案件か」。そんな思考が先に走る。実際はただの問い合わせだったりもするのだが、気が抜けなくなっている自分がいる。気を張りすぎて、電話の後にどっと疲れることもある。情けないけれど、それが今の現実だ。
集中力を保つことすら、最近は難しくなってきた
朝9時に集中できていた自分が、今では10時になってもモヤモヤと雑念が晴れない。ひとつの書類を作るのに、以前より倍の時間がかかる日もある。昔は「どうしたら効率を上げられるか」を考えていたが、最近は「どうしたら感情を保てるか」を考えている。たとえば、いつも飲んでいた缶コーヒーを変えてみたり、小さな工夫で何とか自分をごまかしているのだ。
気を張り続ける毎日にふと訪れる空白
忙しい日々の中でも、ふと気が緩む瞬間がある。昼休みに窓の外を見ていたとき、夜にテレビを見ながらご飯を食べているとき。そんな何気ないタイミングで、涙が出そうになることがある。感情に理由があるわけじゃない。ただ、張り詰めていたものがふとゆるんで、「ああ、俺は疲れてたんだな」と気づくのだ。
緊張の糸が切れた瞬間に
数ヶ月前、遺言執行の仕事でようやく一段落した日があった。大きな案件だったから、それなりにプレッシャーもあり、終わった直後は「よし、やり切った」と思った。けれど、その日の夜、一人で食べたカレーの味がまったくしなかった。口に運んでいるのに、味覚がどこかへ行ってしまったようで、気づいたら目の端に涙が滲んでいた。感情の緊張が切れたとき、身体が勝手に反応してしまうことがあるらしい。
依頼人の言葉が胸に残って離れないことがある
「先生にお願いしてよかったです」——この一言が、ありがたくもあり、心に刺さることもある。なんでもっと優しくできなかったんだろう、もっと迅速に動けたかもしれない、そんな後悔がわいてきてしまう。特に、相続や家族のことで心が弱っている依頼人に接したあと、自分自身の孤独をいやでも感じることがある。感謝の言葉が、かえって自分の足りなさを浮き彫りにするのだ。
なんでもない風景に涙が滲む
ある日、帰り道の川沿いを歩いていたとき、小学生が友達と大声で笑いながら走っているのを見た。その瞬間、「ああ、こんなふうに誰かと無邪気に笑ったのはいつだっただろう」と思った。仕事で成果を出しても、社会的に認められても、満たされない感情がある。家族もいない、恋人もいない、誰にも心を許していない。そんな自分にふと気づいたとき、涙がこぼれそうになる。
強く見せようとする自分と本音との葛藤
「先生」と呼ばれる立場である以上、弱みは見せられない。誰かに頼ることも、愚痴をこぼすことも、なかなかできない。そんな「強くあらねば」の気持ちが、気づけば自分を縛りつけている。正直、もう少しラクになりたい。でも、それが許されないような空気を自分で作ってしまっている。
「先生」らしくあることの重圧
たとえば、依頼人の前では「わかりました」「ご安心ください」と堂々と答える。でも、心の中では「本当にこれで大丈夫か?」と不安に思っていることもある。司法書士という職業には「安心を与える責任」があると思っているけれど、それは同時に「不安を隠す努力」でもある。その重圧が積もると、いつの間にか自分の心がすり減ってしまう。
元野球部としての我慢癖が裏目に出るとき
高校時代、野球部で培った「我慢強さ」は今の仕事に大いに役立っている。でも、その「耐える癖」が逆に自分を追い詰めることもある。辛いときに「大丈夫」と言ってしまうし、体調が悪くても「動けるうちは休まない」が染みついている。それが積み重なって、ある日突然「限界」が来る。体育会系の美学が、今では自分の首を絞めている気がする。
弱さを出せる場所がなくなってしまった
友達とも疎遠になり、恋人もおらず、家族とは距離がある。そんな状況で弱音を吐ける相手がいない。唯一の事務員さんにも、迷惑はかけたくない。だからこそ、ひとりの時間に感情が溢れてしまう。「誰かに話したい」けど、「話せない」。このジレンマが、自分の中に溜まり続けている。
それでも誰かの役に立っていたいという願い
こんな自分でも、誰かの助けになれているのなら、それだけでまだやれる気がする。司法書士という職業は、目立たないけれど確実に人の生活に関わっている。だからこそ、自分の存在意義をそこで見出している部分がある。涙が出そうになっても、それが「意味のある涙」なら、耐えられるのかもしれない。
自分が誰かの安心につながっているなら
「困ったときに思い出してもらえる存在」であることが、僕にとって一番のやりがいだ。大きな感謝じゃなくてもいい。ちょっとした安心感を与えられたなら、それだけで十分だ。書類を渡すときのホッとした表情、説明を終えたあとの小さな「ありがとうございます」。その一瞬が、自分の中の空虚を少しだけ埋めてくれる。
事務員さんのひと言に救われることもある
「先生、今日少し顔が疲れてますよ」——そんな何気ない一言が、実はものすごくありがたい。見てくれている人がいる、気づいてくれる人がいる。その存在が、どれほどの支えになるか。小さな声かけに、何度も救われてきた。無口だけど、たまに差し入れてくれるお茶やお菓子にも、心がじんわり温まる。
それで今日も何とか乗り越えている
「気を抜くと涙が出そうになる」日々だけど、なんとか今日も仕事をしている。きっとこれからも同じような日が続くだろう。でもそれでいい。泣きそうになったって、泣いてもいい。自分の感情に正直になれる時間が少しでもあれば、また立ち上がれる。そんな繰り返しで生きていくのも、悪くないのかもしれない。