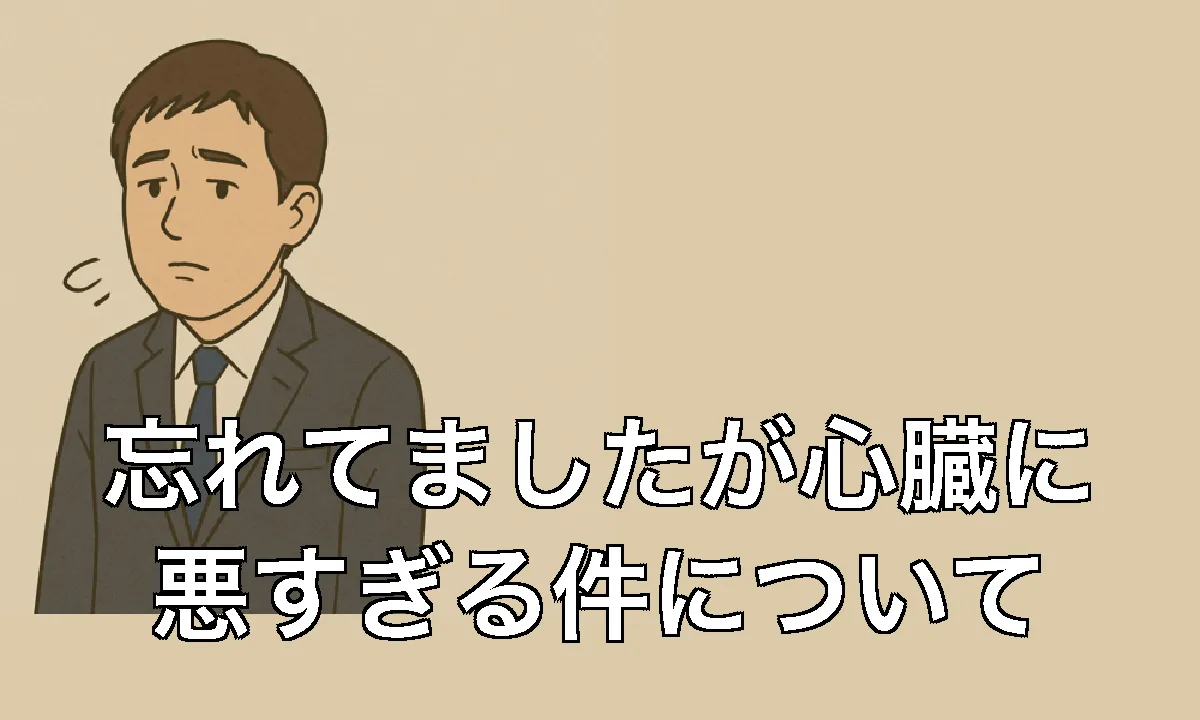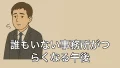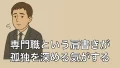日常に潜む恐怖ワード 忘れてました
司法書士として仕事をしていると、普段は聞き流せるような言葉が、時として鋭利な刃物のように胸に突き刺さってくることがあります。「忘れてました」というたった一言がその代表格です。日常会話の中では何気なく使われる言葉ですが、業務の中で耳にすると、その影響力は甚大です。ミスと違って悪意がない分、対応が難しい。しかもその一言が大きなトラブルの引き金になるのです。
あの一言がすべてをひっくり返す
「忘れてました」という言葉は、あまりにも軽く口から出てきますが、それによってこちらの1日がまるごと台無しになることすらあります。それどころか、クライアントとの信頼関係や、事務所の評価すら揺るがします。特に登記など期限が絡む案件では、その一言が命取りになるのです。
登記が終わったはずの案件での落とし穴
ある日、完了済みの登記案件について依頼者から電話がありました。「あの、先生、登記識別情報って…もらってましたっけ?」嫌な予感がして調べてみたら、郵送し忘れていたんです。というか、そもそも発送準備をしていなかった。「やってたつもりだったけど、忘れてました」。それに気づいた瞬間、心臓がバクバクし始めました。
「あ 先生 銀行への提出 忘れてました」
さらにトドメを刺すように、金融機関の担当者からの電話。「書類が届いてないんですけど…」と。事務員さんに聞いたら「すみません、封筒には入れたのにポスト投函を忘れてました」。もう何が怖いって、こういう時に限って相手が銀行なんですよね。融資実行が遅れたら全責任がこちらに来る。謝って済む話じゃない。胃がキリキリしました。
期日ギリギリの依頼人からの一言
「これ、今日中にどうしてもお願いできますか?」そんな無茶な依頼をこなしたことがあります。印鑑証明も全部揃えてもらって、こっちも全力で準備を進めたんです。ところが、最後の確認電話で本人がポツリ。「あ、印鑑持ってくるの忘れてました」って。心が折れそうでした。
「ハンコ押すの忘れてました ってこれ今日までですか」
午後3時、法務局の閉まる1時間前。依頼者から「印鑑証明は用意したけど、実印持ってきてない」と言われたときは本当に目の前が暗くなりました。「今日中じゃないと間に合わないんです」と説明しても、「すみません、忘れてました」。いや、こっちも忘れたいわ!って叫びたくなる瞬間でした。
事務所内でも容赦なく襲ってくる
「忘れてました」という言葉は外からだけじゃなく、事務所内からもやってきます。少人数で運営している以上、事務員さんに頼る部分が大きいのですが、ヒューマンエラーはどうしても避けられない。でも、それが期限付きの重要案件だと命取りになります。
頼みの綱の事務員さんの「うっかり」
うちの事務員さん、真面目で優しい人なんですが、月末の忙しいときに限って「ちょっと忘れてました」が出るんです。登記完了後の通知書の送付、相続人への書類案内、報酬の請求書…。細かい業務だからこそ、忘れると後々響いてくる。信頼関係を壊さないよう注意しつつ、再発防止策を考えるのが毎回つらい。
「今日の法務局の提出 忘れてました」からの冷や汗
締切日当日の朝、確認した書類を渡したはずなのに、帰ってきたらまだ机の上にある。事務員さんに「これ、出してくれました?」と聞いたら「あっ…出すの忘れてました」。その瞬間、頭が真っ白になって、血の気が引いたのを覚えています。なんとか走って提出に間に合いましたが、二度とこんな思いはしたくありません。
自分自身も例外じゃない
正直に言えば、私自身も「やったつもりで忘れてた」ことが何度もあります。特に繁忙期、電話と来客が重なると、1つメモを忘れるだけで地獄が始まる。忘れないようにとTODOリストに書いていても、そのリストを見るのを忘れてしまう。皮肉にも。
「こないだの相談予約 今日だった」背筋が凍る瞬間
とある日の午後、「○○さん、お約束の時間に来られました」と事務員さんから告げられて、何のことか分からず一瞬固まりました。スケジュールに記入してあったはずの相談予約、なぜかその日だけ見逃していたんです。慌てて対応しましたが、準備不足で信頼を損ねたことは否めません。自分に腹が立ちました。
なぜ 忘れてました がこんなにも恐ろしいのか
「忘れてました」は、意図的な過失ではないからこそ怖い言葉です。誰も責められない。でも結果として損害が発生し、信用が落ちる。そこに理不尽さと恐ろしさがあるのです。自分自身も含め、常に気を張っていても完璧には防げない。それでも何とかしないといけない。司法書士という仕事のプレッシャーの正体の一つが、まさにここにあります。
信用と信頼を一気に壊す破壊力
依頼者にとっては「間に合うかどうか」「ちゃんとやってくれるか」がすべて。そこで「忘れてました」なんて返ってきたら、二度と頼んでもらえない可能性すらあります。長年積み上げてきた信頼関係も、一度の失敗で音を立てて崩れ落ちます。
仕事の評価はミスよりも忘却で下がる
ミスならまだ説明できる余地がありますが、「忘れてました」には説明のしようがない。単純な忘却ほど致命的なものはありません。「この人、信頼していいのかな?」と一度思われたら、挽回には何倍もの努力が必要です。
「あの先生 ちょっと頼りないんだよね」の破壊力
一言のミスが噂になり、「あそこの事務所、大丈夫かな?」という不信感につながる。特に地方ではクチコミの影響力が大きく、ちょっとした失敗が地元に広まるのはあっという間。どんなに一生懸命やっても、最後に「忘れてました」で台無しになる恐怖が常にあるのです。
ひとつの「忘れ」が広がる被害の連鎖
「忘れた」こと自体よりも、それによって派生するトラブルの方が恐ろしい。登記が遅れる、契約が流れる、相手方に損害が出る。しかも、それが全部「こっちの責任」として戻ってくる可能性がある。だからこそ、司法書士の仕事は常に「忘れないこと」が前提になるのです。
登記の遅延が招く信用問題
例えば、相続登記の締切を過ぎたことで相続人間の揉め事が再燃し、こちらに責任を追及されたケースがありました。実際は依頼者側の書類の不備でしたが、「先生、確認してくれてたら…」というニュアンスで責められる。こういうのが一番しんどいんです。
金融機関や相続人からの苦情に耐える日々
ときには「なんでそんな大事なこと忘れるんですか」と怒鳴られることもあります。こっちはこっちで全力でやってるつもりなんですが、それが通じないのがこの仕事の難しさ。忘れたつもりはなくても、結果として「忘れてた」ことになると、本当にしんどいですね。
「忘れてました」にどう向き合うか
完璧に防ぐのは難しい。それでも、できる限りリスクを減らす方法を模索するしかありません。仕組み化、可視化、声かけ…地味な積み重ねこそが最善の対策なのだと思います。そして何より、「忘れる前提」で動くこと。それが今の私のやり方です。
自分を責めすぎずに仕組みで防ぐ
昔は「なんでこんなことも忘れたんだ」と自分を責めてばかりいました。でも最近は、仕組みで防ぐことを意識しています。リスト化、二重チェック、リマインダー。感情ではなく構造でミスを防ぐ。それが精神的にも一番穏やかです。
リマインダー頼みの仕事術
Googleカレンダーに加えて、紙の手帳、付箋、ホワイトボードと、あらゆる手段を使って「忘れない」を徹底しています。書いたことを忘れることもあるので、リマインダーはしつこいくらい鳴らすようにしています。音で知らせてくれるって、ありがたいですね。
アナログとデジタルのハイブリッド管理術
アナログ派の私ですが、スマホのリマインダーと手書きメモを併用しています。打ち合わせ直後は手帳に書き、帰ってからカレンダーに入力。事務員さんにも共有し、誰かが気づける体制をつくるようにしました。それでも100%じゃない。でも少しずつ、恐怖ワードを聞く頻度は減ってきた気がします。