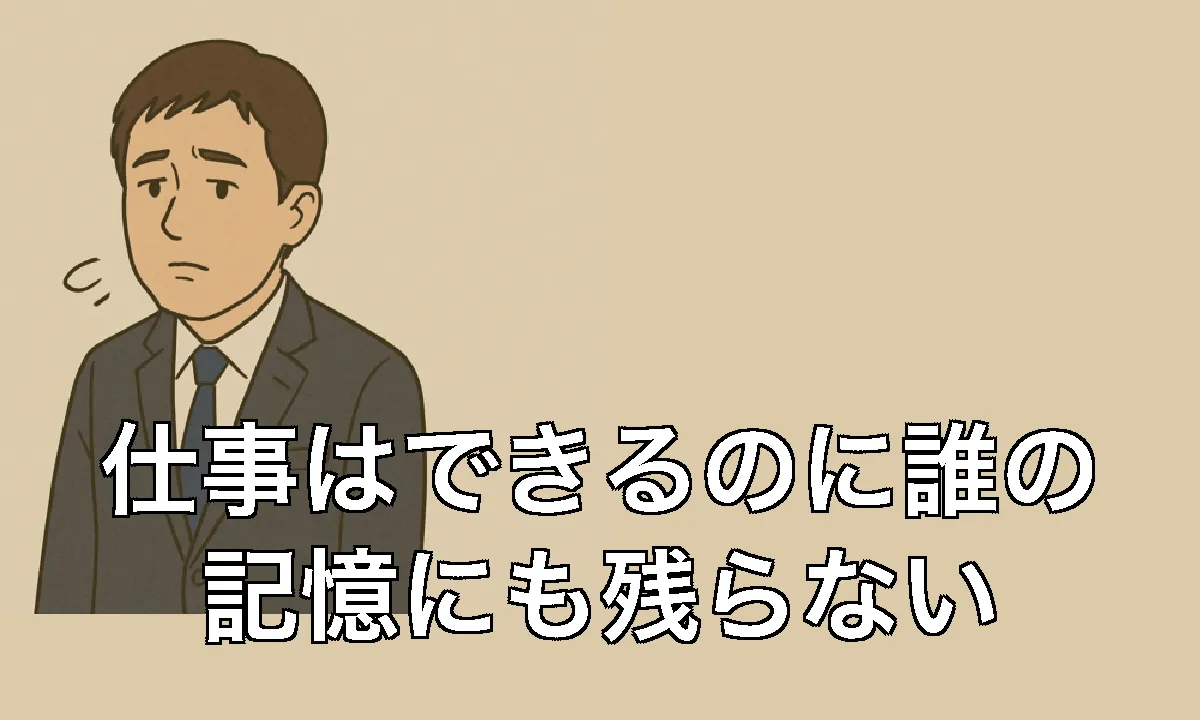誰にも気づかれない日々にふと立ち止まる
最近、自分の名前を口にしてもらった記憶がほとんどないことに気がついた。司法書士として、仕事は次から次へと舞い込んでくる。登記や書類作成、相談対応に追われる日々の中で、感謝の言葉はもらえても、それは「先生」とか「助かりました」といった定型句だ。誰かが私という人間そのものに興味を持ってくれたことが、いつ以来だろう。忙しさの中で、ふと足を止めると、静かすぎる自分の存在に気づいてしまう。評価はあっても、誰にも「覚えられていない」感覚。それは意外と堪える。
名前じゃなくて役割で呼ばれることが増えた
昔は「稲垣さん」と呼ばれることも多かったが、今はほぼ「先生」としか呼ばれない。もちろん職業上の敬称として理解しているし、悪気があるわけではない。でも、それが当たり前になってくると、自分が誰かの中で“役割”にしかなっていないような気がしてくる。「あの司法書士さん」というカテゴリの中に押し込められて、個人としての存在感が薄れていくのだ。思い返せば、高校の野球部時代は名前で呼ばれ、あだ名で笑い合った。今の自分には、それがない。
「先生、あの件なんですけど」から始まる会話
電話でも来客でも、最初の一言はたいてい「先生、あの件なんですけど」。それが本当に多い。私の名前は出てこないし、雑談もない。ただひたすら、業務の始まりと終わりが繰り返される。相手にとってはスムーズで効率的なやり取りかもしれないが、私は毎回「存在を消して役に徹している」ような虚無感を覚える。仕事が終わったあとも、余韻のようなものが残らず、ただ淡々と消費された気分になる。
自分の存在は仕事の外にないような気がしてくる
こういう日々が続くと、「自分という人間は、この仕事をしているときしか意味がないのでは」と思ってしまう。趣味も人付き合いも、気づけば削られていた。食事をする相手も、LINEをする相手もいない。ふと鏡を見て、「こんな顔してたっけ」と他人事のように感じるときがある。存在感が仕事の成果とリンクしていて、それ以外では空気のように扱われること。それは、自分でも気づかないうちに心を蝕んでいく。
仕事だけが取り柄だと思っていたけれど
司法書士としての誇りはある。資格を取り、独立し、事務所を構えて、事務員さんを雇い、地域で信頼を積み重ねてきた。それでも、仕事「だけ」が取り柄になっている気がすると、心のどこかがスースーするのだ。人としてのぬくもりや、くだらない会話や、誰かに頼られる感覚がないと、仕事の達成感すら空虚になることがある。大げさに言えば、「この仕事にしか存在価値がない」ような気がしてしまうのだ。
成果を出しても心は満たされない理由
先月も無事に数件の相続登記を終えた。お客様から「本当に助かりました」と言われたが、その言葉がなぜかスッと胸に入ってこなかった。かつては嬉しかったはずなのに、今はどこか空っぽになる。おそらくそれは、誰かとのつながりが仕事の中にしかないからだろう。評価はされても、そこに人間関係はない。「ありがとう」にも温度がある。それを感じなくなったとき、自分の仕事がただの機能になってしまった気がした。
感謝されることと理解されることは違う
「助かりました」「さすがですね」と言われても、それは私の行動やスキルへの評価であって、私自身への理解ではない。たとえば、どんな気持ちで日々を過ごしているか、どうやって乗り越えているか、そういった部分に目を向けてくれる人は少ない。人は意外と、他人のことを見ているようで見ていない。私もまた、誰かにそうしているのかもしれないけれど、自分がそれをされると妙に寂しくなる。
どこか虚しい「助かりました」の言葉
感謝の言葉が欲しくないわけではない。ただ、それが事務的な挨拶のように聞こえる瞬間がある。「助かりました」と言われて、「はい、こちらこそ」と答える自分の声が、他人のもののように聞こえるときがある。こんな感情、贅沢だろうか。誰かの役に立つことが大事な仕事だ。それでも、ほんの少しだけでもいい、自分自身のことを見てほしい。そんな気持ちになる日が、最近は増えてきた。
事務所に流れる静かな空気と自分の影
うちの事務所は静かだ。BGMもなければ、雑談も少ない。事務員さんは黙々と仕事をしてくれるし、私もそれに甘えてしまっている。忙しいのはありがたい。けれど、会話がなければ、空気は澱んでいく。私の影もまた、壁に溶け込むように薄くなっていく。朝から晩まで、誰にも必要以上に話しかけられず、無音のまま日が暮れていくと、「今日、自分は本当にいたのかな」と思ってしまうことすらある。
事務員さんと交わす会話も淡々と
「お疲れさまです」「これ、確認お願いします」「ありがとうございました」——そんなやりとりがほとんどで、感情のある会話は少ない。私にも原因はある。話しかけるタイミングを逃し、仕事以外の会話が気まずくなり、次第に言葉を減らしてしまった。でも、ふとした拍子に、以前勤めていた事務員さんとの何気ない雑談を思い出す。仕事の話ばかりじゃなく、帰省のこととか、お弁当の中身の話とか、そんな日常会話が恋しくなる。
雑談が生まれない職場はどこか冷たい
効率は上がるかもしれないけれど、雑談のない職場はどこか冷たい。事務所の空気がピンと張っていて、冗談一つ言えないまま一日が終わると、自分まで無表情になってしまう。昔の野球部では、試合前にバカなことを言い合って緊張を和らげていた。それができる空気は、仲間意識や安心感の表れでもあった。今はどうだろう。成果だけが重視され、笑いは置き去りにされている。
笑顔の理由が業務完了だけなのは寂しい
事務員さんの笑顔を見るのは、仕事が一区切りついたときだけだ。達成感のあるタイミングとはいえ、それ以外で笑うことがないというのは、やはり寂しい。たとえばお菓子の差し入れで笑ったり、天気の話で盛り上がったり、そういうゆるい空気がもっとあってもいいのにと思う。仕事が円滑に進むのは大事。でも、心が動かないまま進む仕事ばかりでは、人間としての潤いを失ってしまう。
人として見られないことの苦しさ
私は司法書士として、ある程度の成果は出してきたと思う。それでも、人としての存在が評価されないと感じることが多い。誰かの記憶に残るのは仕事の内容だけで、自分という人間はスルーされていく。そんな日々の積み重ねは、じわじわと心を削っていく。人として必要とされたい、ただその一言が欲しいだけなのに、それが一番遠いのかもしれない。
仕事以外の「自分」に誰も関心がない
たとえば「趣味はなんですか?」と聞かれることもないし、「休みの日はどうしてますか?」という雑談もない。相手は私を“司法書士”としてしか見ていない。私の中に“稲垣”がいることを、誰も見ようとしない。昔は音楽が好きだったし、ひとりでドライブするのも好きだった。でも、そんな自分の話をする機会がないうちに、忘れてしまいそうになっている。
独身の寂しさよりも存在感のなさが堪える
独身でいること自体にそこまで引け目は感じていなかった。でも、今感じるのは孤独よりも、「誰にも意識されていない」ことへの寂しさだ。誰かの記憶に残らないこと。誰の目にも映らないこと。それが続くと、自分という存在がこの社会の中で消えかけているような錯覚すら覚える。恋人が欲しいわけじゃない。ただ、誰かとちゃんと繋がっていたいだけなのに。
元野球部だった頃の自分と今のギャップ
野球部だった頃は、笑われても怒鳴られても、誰かに“見られていた”実感があった。自分が存在しているという手応えが毎日にあった。でも今は、自分がいてもいなくても、業務は進む。もしかしたら、AIがもう少し進化すれば、司法書士も必要とされなくなるんじゃないか——そんな不安さえ頭をよぎる。あの頃の活気ある自分と、今の静まり返った自分。ギャップは、心の奥に小さな穴を開ける。