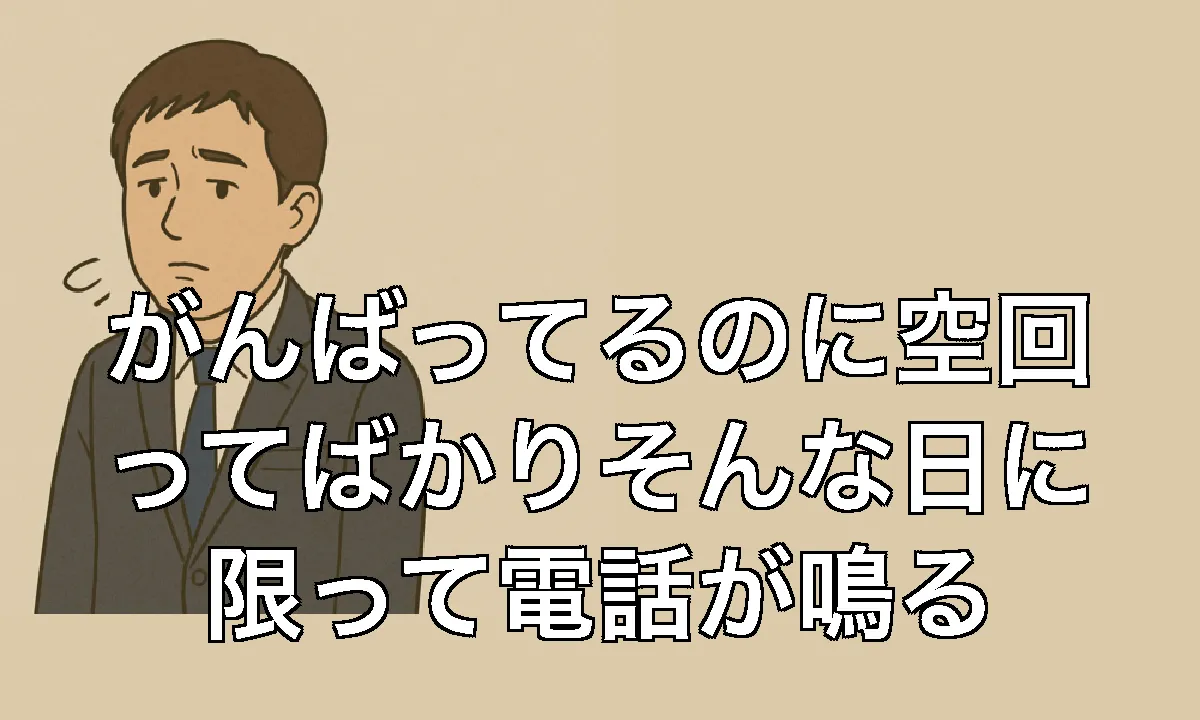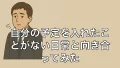がんばってるのに空回る日の正体とは
自分なりに頑張っているつもりでも、結果が伴わない日というのはある。むしろ、そういう日に限って無駄に力が入ってしまって、周りの反応もどこかちぐはぐになり、余計に落ち込む。先日も登記申請のために事務所で朝から黙々と準備していたが、肝心の委任状が差し替わっていたことに気づかず、法務局で「これは使えません」と言われてしまった。誰のせいでもないが、なぜか自分だけが責められているような気がしてならない。そういうとき、「努力してるのにどうして」と心の中で何度もつぶやいてしまうのだ。
「ちゃんとやってるつもり」が通じない瞬間
努力は目に見えにくいものだ。自分の中では綿密に段取りを考え、先回りして動いたつもりでも、相手にはそれがまったく伝わらないことがある。ある時、依頼者のために通常の倍以上の時間をかけて書類を整え、完璧だと思って提出した。ところが、依頼者から返ってきた言葉は「え、これだけ?」だった。そんなはずはないと説明を試みるも、相手の興味はすでに他のところに向いていた。誤解されることに慣れているとはいえ、徒労感が胸にのしかかる。やればやるほど空回っている気がしてならない瞬間だった。
心を込めた説明が伝わらないもどかしさ
専門用語を使わず、できるだけ噛み砕いて伝えようとしても、途中で「つまり何すればいいんですか?」と遮られる。決して馬鹿にされているわけではないと分かっていても、こちらの熱量と温度差がありすぎて、途中で喋るのが嫌になる。昔の野球部時代を思い出す。声を張っても誰も聞いていないベンチで叫んでいる気分。何が正解なのか、分からなくなるのだ。
書類を丁寧に仕上げてもやり直しになる日
何重にもチェックして、封筒の角度まで気にして送った書類が、「一部不足です」と返送されてくる日がある。しかも、その不足書類は、以前のメールで「不要」とされたもの。理不尽だと叫びたくなるが、相手もきっと悪気はない。問題は、こういう小さなミスが連鎖して、全体のリズムを崩してしまうことだ。自分のやってきた努力が、ただの「回り道」に見えてくる瞬間。地味に効いてくる。
空回りする日によく起きる出来事
一日がうまくいかない予感というのは、朝の段階でどこか察してしまう。靴下の左右を間違えたとか、コーヒーをこぼしたとか、些細なつまずきが地味に蓄積していく。そういう日に限って、依頼者の対応がなぜか雑で、電話は無駄に鳴るし、書類の誤字に後から気づいて愕然とする。落ち着こうと思っても焦りだけが先に立ち、空回りのスパイラルから抜け出せない。努力が報われないのではなく、努力がかえって状況を悪化させているような、そんな錯覚に襲われるのだ。
急ぎじゃない急ぎの電話
「すぐに!」と言われて折り返すと、「あ、すみません、今じゃなくてもいいんですけど…」というパターン。もうこれ、何度目だろう。しかも内容は「戸籍の写しって、どこで取るんでしたっけ?」。なんなら市役所に直接聞いてくれよと思うが、それを言えない自分が腹立たしい。気がつけば、電話を切ったあとため息が止まらない。時間を取られたのは事実だが、それよりも心が削られている気がする。
見積りだけで終わる相談
昼休みにようやく食べようとした弁当を前に電話が鳴る。「相談だけなんですけど…」から始まり、「いくらくらいかかりますか?」の一点張り。見積りを伝えると、「じゃあまた検討して連絡しますね」。たいてい、もう連絡は来ない。もちろんそれも仕事の一環なのは分かっている。でも、あまりにもタイミングが悪すぎる。心が「やられた」と感じるのは、弁当が冷めるせいだけではない。
司法書士という仕事と空回りの相性
司法書士という仕事は、結果がすぐに見える仕事ではない。書類を出しても、それが登記完了するまで数日〜数週間かかることもあるし、その間に別の案件でトラブルが起きることもある。やっていることが正しいのかどうか、すぐには答えが出ない。これは、自己肯定感の低い人間にとっては特につらい。頑張っているのに、何も起こらない。もしくは、何かが起きたとしても「当たり前」として処理される。それが日常なのだ。
制度が複雑すぎて伝わらない
登記制度や相続関連の法改正は、一般の人にとってはまさに「暗号」だ。こちらは分かりやすく説明しているつもりでも、説明中に眉をひそめられたり、途中で「それって必要なんですか?」と聞かれたりする。必要だから言ってるんだが、それをそのまま言えば角が立つ。そうして口調を柔らかくしていくうちに、自分が何を言っているのか分からなくなる。制度が複雑なぶん、自分も複雑になっていく。
専門用語に詰まってしまう依頼者の反応
たとえば「権利証」「登記識別情報」「法定相続情報一覧図」。これらを使うたびに依頼者の目が泳ぐ。それを見て、また説明を繰り返す。そうして話が二転三転していくうちに、「この先生、なんか話が長いな」と思われていそうな空気が流れる。自分が悪いわけではないが、場の空気は確実に冷えていく。話すのが嫌になる日もある。
同じことを何度も説明する疲労
一日に同じ説明を3回も4回もすると、だんだん自分の声が自動音声のように感じられてくる。しかも相手が違えば反応も違う。ある人には好感触でも、別の人には「もっと簡単に言えませんか?」と切り捨てられる。自分の中の引き出しがすり減っていく感じ。こうして空回りの地盤ができあがっていく。
それでもやっぱりやるしかない理由
辞めたいと思ったことは、一度や二度ではない。だけど、それでもやめられないのは、誰かがこの仕事を必要としてくれているからだ。たとえ言葉にならなくても、「ありがとう」の一言で救われる瞬間がある。そういう小さな報酬が、自分をなんとか持ち上げてくれるのだ。空回っても、ぐるぐるしながら前に進む。それがこの仕事の不思議なところだ。
誰にも頼れない仕事だからこそ
スタッフは一人。相談できる同業者も少ない。地方ではなおさら孤独が深い。だからこそ、「自分がやるしかない」と腹をくくるしかない。でもそれは、悪くない感覚でもある。孤独の中でしか育たない意地とか、信念とか。そんなものを、大事にしながらやっている。
「先生」という肩書の重さと孤独
「先生」と呼ばれることに、いまだに違和感がある。でもその違和感こそが、自分を律してくれているのかもしれない。期待されていると思うと逃げられないし、応えなければと身構える。孤独だけど、その孤独は自分で選んだものだ。そう思える日があるだけで、なんとか続けていける。
背中を押してくれるのは結局自分だけ
モテるわけでもなく、家に帰っても誰もいない。だけど、朝目覚めて仕事に向かうのは、自分の意志だ。他人の評価がどうあれ、自分で「よくやった」と思える日が少しでもあるなら、それは充分だ。空回りの日々に意味があったと、あとで思える日がくることを信じて。