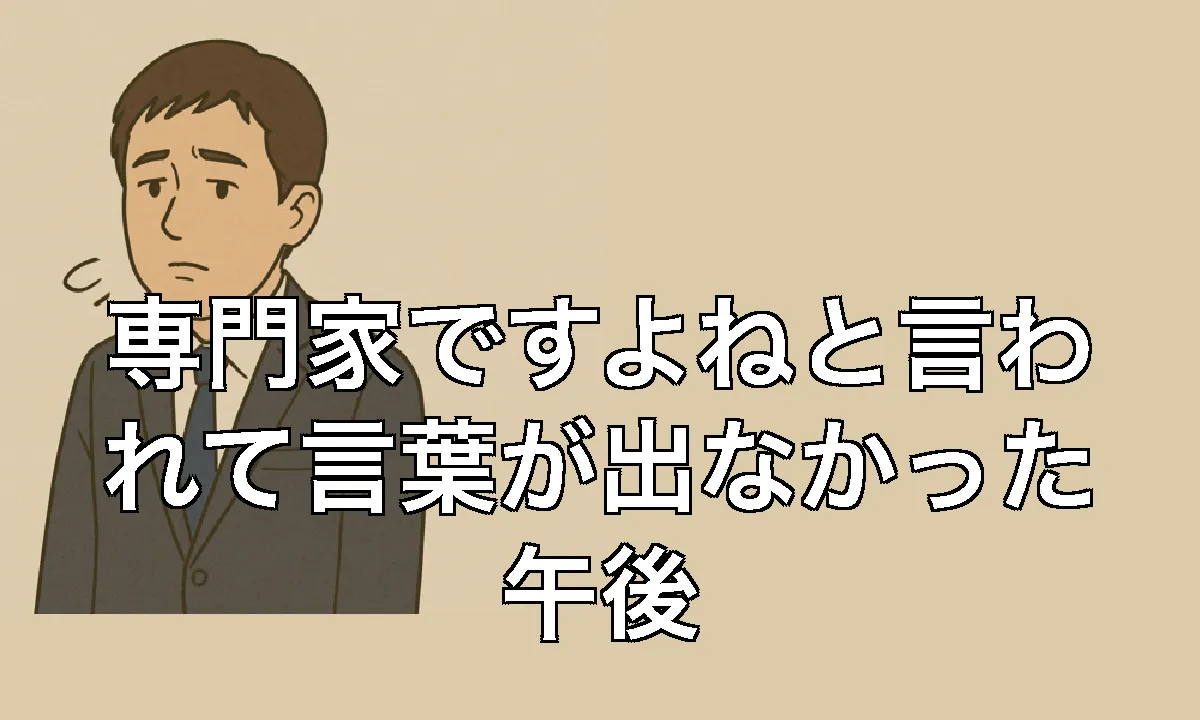専門家なのに黙ってしまった瞬間
「司法書士さんなら、これくらいわかりますよね?」と聞かれた瞬間、口がきけなくなった。あの午後のことは、今でもよく覚えている。正直に言えば、わからなかった。まったく知らない内容ではなかったが、断片的な知識しかなく、間違って答えたらどうしようという気持ちが先に立ってしまった。専門家としてのプライドと、間違えたくない気持ちと、現場の緊張感が一気に押し寄せて、声が詰まった。「……ちょっと調べますね」とだけ絞り出した自分が、情けなかった。
「専門家ですよね」と言われて思考が停止する
普段から「先生」と呼ばれることが多い仕事ではある。だからこそ、「この人はすべてを知っているはずだ」という目で見られることがある。でも、現実には全部を知っているなんて不可能だ。司法書士の業務範囲は広く、法改正も多い。わかっていることと、すぐに説明できることは違う。それでも、「え、それも知らないの?」という空気を出されると、正直しんどい。人としての自信まで揺らいでしまう。
知っていて当然の空気に飲まれる
相続関係の相談で、「この場合は配偶者の取り分が増えるんですよね?」と聞かれた。民法改正後の話で、頭では理解していたが、数字がうまく出てこなかった。それだけのことで、「あれ?」と不安そうにされると、自分の中で何かが崩れる。専門家として当然のことを、当然のように即答できない自分。周囲の空気が急に冷たくなったような気がして、目を逸らすしかなかった。
わかってるけど説明できない不安
言葉にできないって、こんなに苦しいのかと思った。頭では理解しているのに、それを簡潔に説明できないと、「この人、本当にわかってるのか?」と疑われてしまう。専門家としてやっていく以上、それは致命的とも言える。けれど、人間だってことを忘れちゃいけない。私は人前で話すのが得意じゃない。とっさに言葉が出てこないこともある。それだけのことが、時に大きな罪のように感じてしまうのだ。
「プロとしての自覚」と「現実」のギャップ
プロとしての自覚はある。もちろん。毎日、朝から晩まで書類に目を通し、登記の準備をし、依頼者の話に耳を傾けている。でも、それでも「完璧な専門家」であり続けるのは難しい。ミスをしないように必死で気を張り、細かい点まで確認する。それでも抜けが出ることがある。そんなとき、「それ、プロですよね?」と投げかけられると、返す言葉が見つからない。
正解よりも空気を読む難しさ
「この場では、はっきり断言したほうがいいのか、それとも正直にわからないと言うべきか」――そんな葛藤を、一瞬で判断しなければならない。依頼者の期待が膨らんでいる中で、「今は断定できません」と答えると、がっかりされたり、不信感を抱かれたりすることもある。専門家だからといって、なんでも断言できるわけじゃない。けれど、それを理解してもらうのは難しい。空気を読む力が、専門知識以上に求められている気さえする。
無言のプレッシャーが生む自己否定
「やっぱり他の先生に相談してみます」と言われたとき、心の奥底がギュッと締めつけられる感覚になった。自分が頼りないと言われたような気がして、その日一日は落ち込んだままだった。自己否定の沼にハマってしまうと、次の依頼者にも自信を持って接することができなくなる。悪循環だとわかっていても、一度沈んだ心は簡単には浮上しない。専門家という言葉の重さに、ただ押しつぶされそうになる。
肩書きが重たく感じる日
司法書士という肩書きは、世間的にはそれなりに信頼されるものだ。けれど、その信頼の裏には「なんでも知ってて当然」という期待がつきまとう。だからこそ、知らないことを「知らない」と言いづらくなる。専門家とは、常に完璧であるべきだという幻想が、自分の首を絞めてくる。そんな日々に、ふと「なんでこの仕事を選んだんだろう」と振り返ることがある。
司法書士という名札に隠されたプレッシャー
名刺を渡すと、たいてい「すごいですね」と言われる。でも、その言葉にはプレッシャーが含まれているようにも感じる。「あなたなら、何でも答えてくれるんですよね?」という無言の問いかけ。相談者の期待を裏切ってはいけないという想いが、自分自身を不自由にしている気がする。たまには「すみません、それは他の分野なんです」と気楽に言えたら、どんなに救われるかと思う。
相談者の期待とこちらの体力
仕事が立て込んでくると、正直なところ体力的にも精神的にも余裕がなくなる。そんなときに限って、重たい案件や難しい相談が入ってくる。ありがたいことだけれど、連日の睡眠不足と疲れで、頭が回らない日もある。けれど、相談者はそんな事情を知らない。見た目は元気そうに見えるのだろう。「先生なら頼りになります」と言われるたびに、ちゃんとしなきゃと背筋を伸ばす。でも、いつか倒れるんじゃないかという不安もある。
事務所の看板と中の人のズレ
うちの事務所の看板は、立派な筆文字で「〇〇司法書士事務所」と掲げてある。けれど、その中にいるのは、朝コンビニで買ったおにぎり片手に仕事をする、疲れたおっさんだ。見た目も華やかじゃないし、女性にもモテない。ひとりで事務所を回し、合間に事務員さんとたわいない話をする日々。外から見える「専門家」としての姿と、実際の自分の姿のギャップに、時々疲れてしまう。
元野球部のノリは通用しない
学生時代は野球一筋だった。多少の無茶も気合と根性で乗り越えてきた。でも、この仕事では、そうはいかない。知識がものを言い、冷静な判断が求められる。声を張ったり、勢いで押し切ったりする場面なんてない。むしろ、淡々と冷静に対応できる人が信頼される。昔の自分が「俺がなんとかする!」と突っ込んでいたのが、今では「ちょっと確認します」と下がるようになった。なんだか、寂しい。
自分で自分を許すことから始める
完璧じゃなくてもいい、全部答えられなくてもいい――そう思えるようになるまでに、10年以上かかった。誰かの期待に応えようとするあまり、自分自身を責めすぎていた。でも、あるときふと気づいた。「そんなに責めなくても、ちゃんとやってるじゃないか」と。間違えてしまった日も、言葉が出てこなかった午後も、全部ひっくるめて自分なのだ。
完璧じゃない司法書士でも生きていける
この仕事に就いてから、ずっと「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーに追われていた。でも、今は「ちゃんと悩む自分」も認めてやりたいと思う。専門家だからこそ、間違いを恐れる。でも、専門家だって人間だ。ときには疲れたり、迷ったり、言葉が出てこなかったりする。それを許せるかどうかで、人生の重さが変わる気がしている。
間違えた日の夕飯がやけにしみる
ある日、失敗してしまった案件があった。自分では丁寧に確認したつもりだったが、提出書類に不備があり、修正に追われた。帰り道、スーパーで買った惣菜の弁当を食べながら、一人で反省会をした。味は普通だったのに、なぜかしみた。「俺、ダメだな」とつぶやいて、少しだけ泣いた。でも、次の日も朝は来るし、仕事も来る。そんな毎日を繰り返しながら、少しずつ前に進んでいる。
事務員さんの一言に救われた
あの日、落ち込んでいた私に、事務員さんが何気なく言った。「知らなくても、ちゃんと調べて対応できる人が、一番信頼できるんですよ」。その言葉に、ふっと肩の力が抜けた。知ってるふりをして間違えるより、正直に「調べます」と言えるほうが、よっぽど誠実なのだと気づかされた。自分の未熟さに向き合う勇気をくれたその言葉に、今でも救われている。
「知らなくてもいいんですよ」ってすごい
専門家って、全部を即答できる人のことだと思っていた。でも、「知らなくてもいい」という視点を持てるようになってから、少しだけ気持ちが楽になった。知らないことは調べればいいし、わからないことは正直に言えばいい。それでも信頼してくれる人はいる。そのことを知ってから、自分を許せるようになった。完璧じゃない自分でも、ここにいていいのだと思えるようになった。