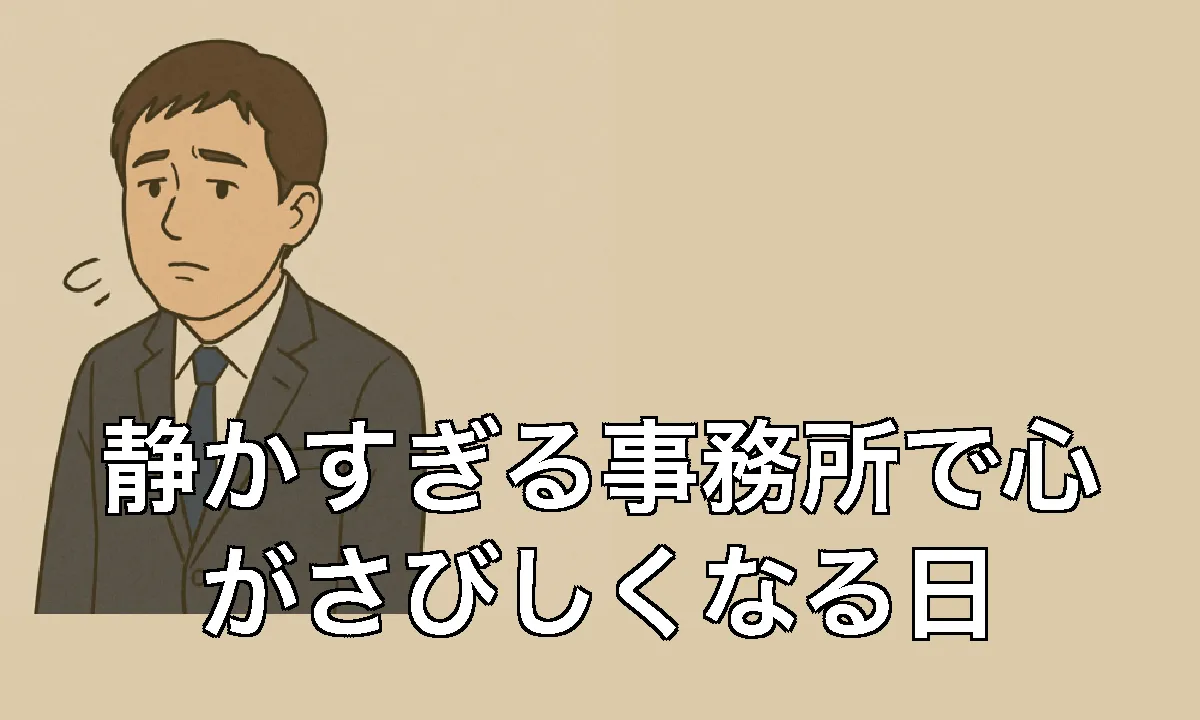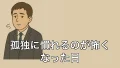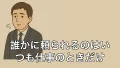静けさに包まれる日常がもたらすもの
一人事務所で仕事をしていると、思いがけず「静けさ」に押しつぶされそうになることがあります。もちろん最初は快適でした。誰にも邪魔されず、電話も鳴らず、淡々と業務に集中できる環境。だけど、それが数日、数週間と続くと、ただ静かなだけの空間が重くのしかかってくるのです。音がないことが、こんなに人の心を削るとは。かつて野球部で騒がしい日々を過ごしていた自分には、余計にこの「音のない職場」がこたえるのかもしれません。
朝の始まりから無音でスタートする
朝、事務所に鍵を差し込む音が響く。ガチャリと扉を開ける音、パソコンの電源を入れる音、それだけで始まる一日。おはようの声もなく、足音さえ吸い込まれるような静寂。最初のうちは、「集中できる」とプラスに捉えていました。でも、ある日ふと気づいたんです。朝、誰とも会話せずに始まる日は、なんとなく気分が重くなる。気分の切り替えができず、昨日の憂鬱を引きずったまま、なんとなく仕事を始めてしまう。誰かと一言でも交わすだけで、違うのに。
ドアを開けても誰もいない
一人事務所では、当たり前ですがドアを開けても「おはようございます」の声は聞こえません。このことに慣れたつもりでも、ふとした瞬間に寂しさが胸をつきます。たとえば、雨の日。びしょぬれで帰ってきてドアを開けた瞬間に、誰かが「大変でしたね」と言ってくれたら、どれほど救われるだろうと、想像してしまうのです。仕事のストレスというより、その“無反応”な空間に、気持ちがむなしくなることがあります。
タイピング音が一日のBGM
事務所でのBGMは、基本的に自分のキーボードを叩く音。カタカタという打鍵音、プリンタの印刷音、たまに鳴る電話の呼び出し音。それだけ。BGMとして音楽を流せばいいじゃないかと言われるかもしれません。でも、正直気が散るんですよね。司法書士の仕事って意外と繊細で、数字や表記の一つで全体が狂う。集中の邪魔になると思って音楽もかけずにやってきた結果、気づけば「音のない日々」にどっぷり浸かってしまっていたのです。
静かであることは本当に快適か
静かな環境が好き、という人は多いでしょう。確かに、他人の会話や雑音がないのは仕事に集中するには好条件。でも、静かすぎる環境は、逆に不安やストレスを膨らませる原因にもなり得ます。人の声がしないことで、外の世界から切り離されたような感覚になる。小さなミスでも、相談できる相手がいないことで必要以上に重くのしかかる。静けさには安心感と同時に、孤独や緊張を増幅させる二面性があるのです。
心が落ち着く一方で募る孤独
静かだと集中できる、心が落ち着く――それは確かにそうです。だけど、落ち着きすぎたその先には「孤独」が待っています。誰とも会話せず、相談もせず、ただひたすら書類と向き合う日々。ふとした瞬間に、「あれ、俺ってこのままでいいのかな」と思ってしまう。仕事の手は動いていても、心が空回りするような感覚。たまに事務員さんが話しかけてくれると、それだけで救われるんですよ。たった一言でも。
沈黙がミスへの不安を増幅させる
一人で作業していると、ちょっとした違和感やミスがあったときに「まあ大丈夫だろう」で流してしまいがちです。誰かに確認するわけでもなく、声に出すわけでもない。これが本当に良くない。ミスをしても、指摘してくれる人がいない。沈黙の中では「疑問」が「確信」にすり替わる。自分を疑う機会が減っていくんです。だからこそ、たまに「これ合ってます?」と聞かれるだけで、逆に自分の感覚が整うということもあります。
事務員さんがいてくれるありがたさ
一人での事務所運営に慣れているつもりでも、事務員さんの存在がどれだけありがたいかは、日常の小さな場面でふと気づかされます。忙しくてイライラしている時でも、ちょっとした気遣いや一言で、感情がリセットされる。自分のペースだけで回していると、心が硬くなるのかもしれません。誰かと一緒に働くことには、確実に意味があるんだと思い知らされます。
一言があるだけで救われる
「今日は暑いですね」――たったそれだけの会話が、どれだけ気持ちを楽にしてくれるか。一人で黙々と仕事をしていると、そういう当たり前のやり取りさえ、貴重なものに思えてきます。以前、仕事が立て込んでピリピリしていたとき、事務員さんが「お昼、これ食べませんか?」とコンビニのおにぎりを差し出してくれたことがありました。涙が出そうになるほど嬉しかった。沈黙の空間に生まれる“言葉”の力を、あのとき改めて感じました。
雑談のない職場はやっぱりきつい
雑談って、サボりのようで実は潤滑油なんですよね。話しかけることもなく、ただ淡々と目の前の作業だけをこなす毎日。それが続くと、まるで自分が機械になったかのような錯覚に陥るんです。誰かが「テレビ観ました?」とか「昨日の野球、惜しかったですね」と言ってくれるだけで、脳のスイッチが切り替わる。効率の話じゃなくて、人としての“呼吸”が整うんですよ。だからこそ、雑談のない職場は正直しんどい。
電話の音が会話代わりになることも
冗談じゃなく、電話の呼び出し音が「誰かが存在してる証拠」みたいに感じるときがあります。電話に出ることすら、ある意味で“会話の代替”。人の声を聞くと、妙に安心する。営業の電話でさえ、たまにはちょっと嬉しい。そういう感覚になってきたとき、「このままじゃいかん」と思いますね。沈黙が習慣になると、誰かと話すことが逆に怖くなる。電話でさえ、救いになる日があるという現実が、少し切ないです。
相手に気を遣いすぎて逆に疲れる日も
とはいえ、誰かがいればそれで全部がうまくいくわけじゃありません。事務員さんがいる日でも、話しかけていいのか、今は忙しいのか、そういう空気を読みすぎて逆に疲れることも。結局、一人でいる寂しさと、誰かといる緊張感の間で揺れている。それが地方の一人事務所という場所の、なんとも言えないリアルなのかもしれません。
沈黙が気まずくなる瞬間
事務所内でお互いに黙って作業をしていると、ふと「この沈黙、なんだか気まずいな」と感じる瞬間があります。相手が怒っているわけでもない、ただお互いが集中しているだけ。でも沈黙が続くと、「話さなきゃ」「何か言わなきゃ」という焦りが湧いてくる。それがまた変な空気を生んで、余計にしゃべれなくなる。この悪循環、たまにありますよね。きっとどの小さな事務所でも、似たようなことあるんじゃないでしょうか。
気にしないフリにも限界がある
気まずい空気に気づかないフリをする。会話がなくても平気なフリをする。そういう“フリ”を続けるのにも、限界があります。人間ってやっぱり、どこかで誰かに関わっていたい生き物なんだと感じます。自分の感情にフタをするのがうまくなってしまったけど、それは良いことではないなと、最近は思うようになりました。仕事の精度は大事。でも、心の精度も同じくらい大事なんですよね。