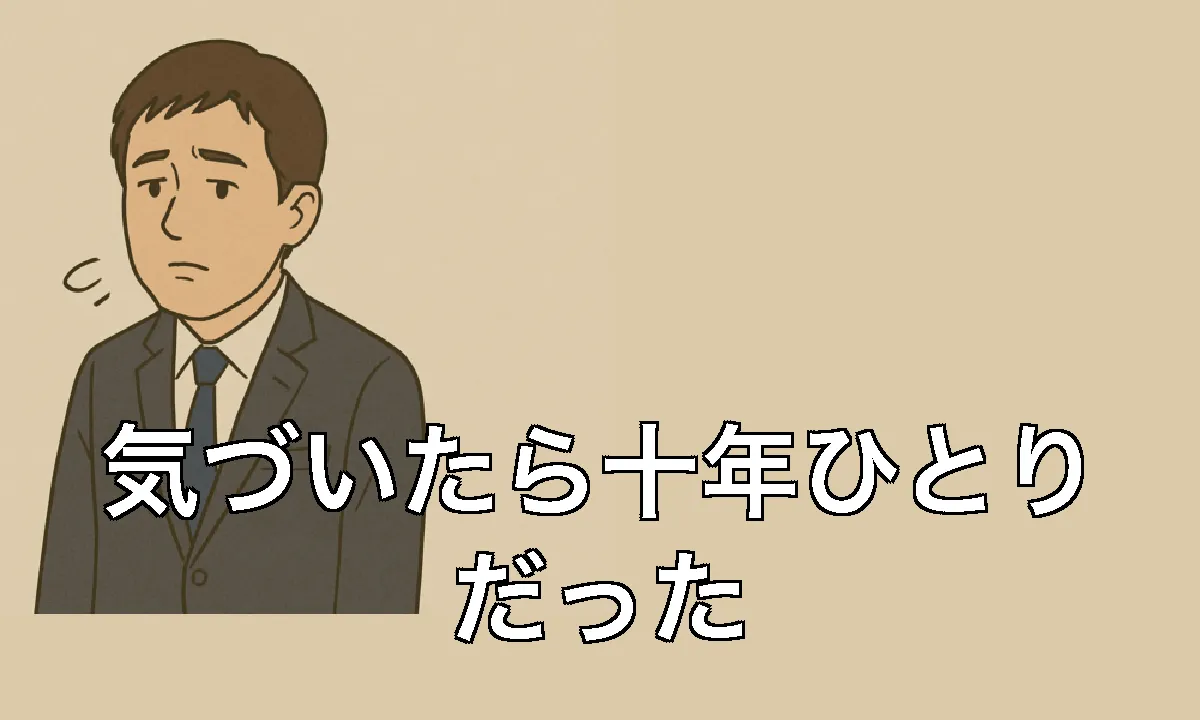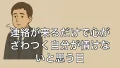十年前の自分に言いたいことがありすぎる
あっという間の十年だった。仕事に追われる毎日、目の前の案件に集中しているうちに、プライベートの時間はどこかへ消えた。最初の数年は「そのうち誰かと縁があるだろう」と楽観的だったが、気づけば誰かを思い浮かべることすらなくなっていた。ふと昔の写真を見返して、「この頃はまだ誰かと笑ってたな」と感じた瞬間、胸にぽっかり穴が開いたような気がした。
あの頃はまだ結婚できると思ってた
三十五歳の頃、年齢的にもそろそろ身を固めないとという焦りはあった。紹介も何度か受けたし、職業柄そこそこ信用はある。でも、それ以上に「今は仕事が忙しいから」と断る自分がいた。今思えば、仕事にかこつけて誰かと向き合うことを避けていたんだと思う。自分に向いてないと決めつけて、最初から関係を育てる努力を放棄していた。
紹介のたびに断る理由を探していた自分
紹介を受けた相手に対して、無意識に減点方式で見ていた。「ちょっと話し方が合わない」「趣味が違う」「家が遠い」…どれも後から考えればたいした理由じゃない。でも当時の私は、関係を築くということ自体に自信がなかった。誰かに踏み込まれるのが怖かった。だから、誰かを受け入れる前に、受け入れない理由を作っていたのだ。
今はその紹介すら来ない
今ではそんな紹介の声もかからない。まわりはみんな結婚し、子どもが生まれ、家を建てた。「いい人いないの?」と聞いてくれた友人たちも、もう私のことには触れなくなった。静かな時間が増えた分、孤独の音がやけに大きく聞こえる。人の声に飢えているのかもしれない。
仕事が忙しいと言い訳してきた代償
司法書士という仕事は、目立たずとも責任が重く、神経をすり減らすことも多い。登記の期日や書類の整合性、依頼人とのやりとり…すべてを一人でこなす日々は、確かに忙しい。でも、その忙しさに逃げてきたことも自覚している。「仕方ない、仕事だから」と自分を納得させることで、プライベートを見ないようにしていたのだ。
土日も夜も埋まる予定表のむなしさ
予定表は真っ黒なのに、心はどこか空っぽ。電話やメールが鳴り止まず、事務所に泊まることも珍しくなかった。でもその忙しさは、誰かのためではなく、ひとりを埋めるための作業だった気もする。働けば働くほど、ますます人との距離が広がっていくのが皮肉だった。
「充実してるね」と言われるほど虚しくなる
周囲からは「順調そうだね」「忙しそうで何より」と言われるたび、どこかで罪悪感を覚えるようになった。本当は、寂しいだけなのに。それを口にすると負けのような気がして、いつも笑ってごまかした。気づけば、自分の本音を話せる相手すらいなくなっていた。
ひとりでいることに慣れてしまった日
人は本当に、どんな環境にも慣れてしまう生き物だと思う。最初は寂しさに敏感だったはずなのに、今ではそれすら鈍ってきた。朝起きて、無言でコーヒーを淹れて、机に向かって、そのまま一日が終わる。そんなルーティンに何の違和感も持たなくなっていた。
家に帰っても声を出さない日が増えた
誰かと会話を交わすのは、ほとんど仕事の中だけ。自宅では一言も声を発しない日が増えてきた。昔はテレビにツッコミを入れたり、独り言が多いタイプだったのに、今ではそれすら面倒に感じる。喉が乾いたように、言葉が出てこない感覚がある。
冷蔵庫の中身も会話もスカスカ
食事はコンビニ、冷蔵庫には水とビールだけ。以前は誰かが来てもいいようにお菓子を置いていたこともあったが、今ではその必要もない。キッチンの棚も、会話のストックもすっかり空っぽ。あのころの「誰かと食べる食卓」がどれほど尊いものだったか、今になって痛感する。
依頼者の人生に寄り添うたびに思うこと
司法書士という仕事は、人の節目に立ち会うことが多い。相続や売買、結婚に離婚――他人の人生を静かに支えることが私たちの役割だ。でもそのたびに、胸の奥で「自分の物語はどこへ行ったのだろう」と、うっすらとした空虚感が湧き上がってくる。
登記完了の報告後に静かになる自分の部屋
手続きが終わり、感謝の言葉を受けて電話を切った後、静まり返る部屋に戻る。その瞬間が一番つらい。人の人生を前に進めることができたはずなのに、自分はその場に取り残されたような気がする。専門職の裏にある孤独を、誰かに理解してほしいと思う瞬間だ。
人の幸せを見送る専門職という孤独
人の幸せを見送る――それは誇らしいことでもあり、同時に強烈な孤独を伴う。友人の結婚、依頼者の新居、家族の再出発。どれも素晴らしいことだが、自分の人生は傍観者として過ぎていく。「自分の幸せって何だったっけ?」と、ふと立ち止まってしまう。
誰かの役に立ってると信じたい
それでも、私がこの仕事を続けているのは、誰かの役に立ちたいという思いが消えていないからだ。直接的な「ありがとう」がなくても、その人の人生に少しでも関わったという事実が、心の支えになっている。自分の存在意義を、他人の人生の中に見出している。
それでも毎朝、事務所の鍵を開ける理由
疲れていても、気持ちが沈んでいても、朝になると鍵を差し込み、ドアを開ける。その行為に救われている自分がいる。たとえ今日もひとりだとしても、依頼人が待っている限り、私はこの仕事を続ける理由がある。それが今の自分を支える唯一のリズムなのだ。
同じような誰かに伝えたいこと
この文章をここまで読んでくれたあなたが、もし少しでも似たような思いを抱えているなら、無理に前向きにならなくていいと言いたい。愚痴をこぼしながらでも、ひとりでも、私たちは生きていける。そして、時には誰かと心を交わせる瞬間がきっと来る。
ひとりでも、声を出して生きていこう
無理に誰かを求めなくてもいい。でも、誰かに届くように、自分の気持ちを言葉にしてみよう。声に出すことで、心が少しだけ軽くなる。そういう瞬間の積み重ねが、孤独と付き合う方法かもしれない。
心が折れない程度に愚痴をこぼしていい
真面目で責任感のある人ほど、自分のことを後回しにしがちだ。だけど、誰だって弱音を吐いていい。ときには誰かに聞いてもらって、笑ってもらって、それだけで救われることもある。完璧じゃなくていい、誰かとつながる糸が、きっとどこかにある。