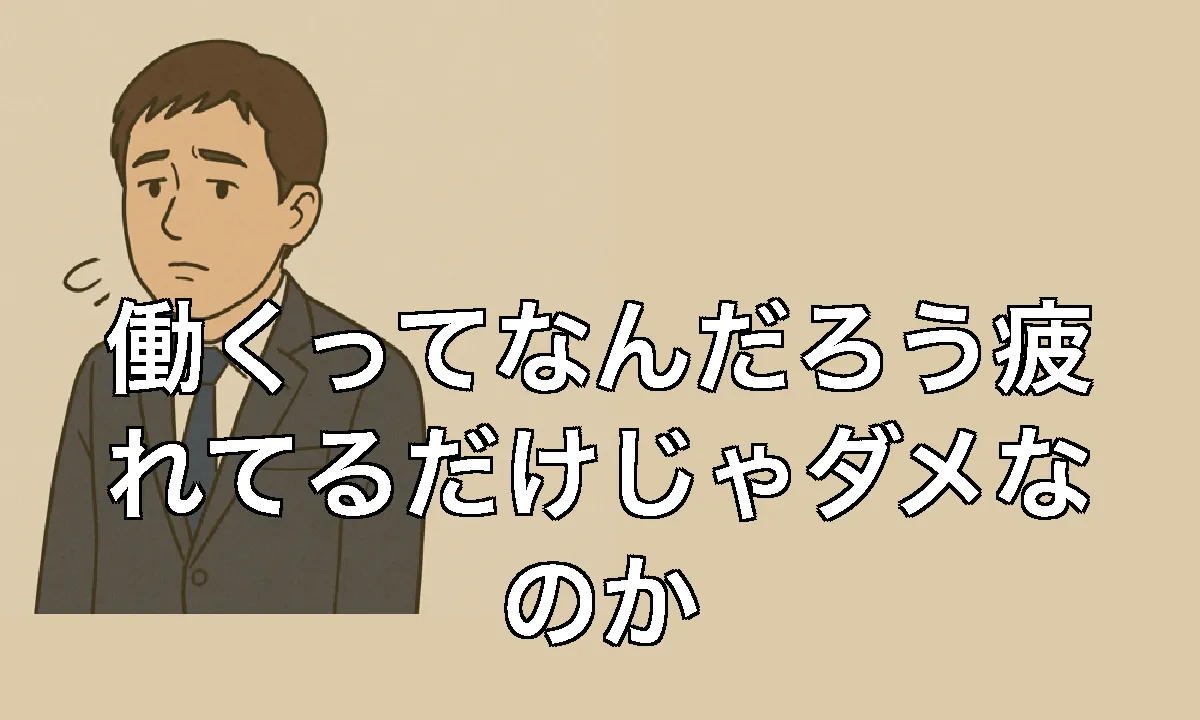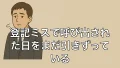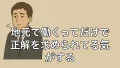朝がつらい理由を考える
朝、目覚ましの音で目が覚めても、すぐには体が動かない。心も重たいままだ。司法書士という仕事は、精神的な責任が大きい割に、世間からはあまり注目されない職業だと思っている。人の役には立っているはずなのに、なんだか報われない気がする。そんな気持ちが、朝の足取りをさらに重くする。誰かに「大変だよね」と言ってもらえれば、それだけで違うのかもしれないけれど。
目覚めた瞬間に押し寄せる重さ
昔、野球部で朝練があった頃は、目覚ましの音と同時に跳ね起きていた。あの頃は「キツいけど頑張る」ことに意味があったし、仲間もいた。今はどうだろう。ひとりで、事務所の鍵を開ける朝。今日も、またあの山積みの書類と向き合うのかと思うと、布団の中で現実逃避したくなる。疲れがたまっているというより、心が擦り減っていく感覚に近い。
期待されることがしんどい
依頼人から「先生なら大丈夫ですよね」と言われるたび、内心でため息をつく。信頼してもらえるのはありがたい。でもその言葉の裏にある「失敗しないでくださいね」という無言の圧力が、妙に重たいのだ。人を支える立場でありながら、自分を支えてくれる人はいない。そんな現実を噛み締める朝は、心がざらついて仕方がない。
支える人がいない孤独感
独身で、実家とも離れて暮らしている。家に帰っても誰かが待っているわけではない。休日に誰かと過ごすことも、最近は少なくなった。そうなると、ますます仕事に逃げるしかない。誰かの役に立っていないと、自分の存在価値を見失いそうになるから。けれど、その働き方は、孤独を深めるだけだったりもする。
司法書士の「忙しさ」は誰にも伝わらない
「司法書士って、普段どんなことしてるの?」と聞かれても、説明は難しい。登記のこと、相続のこと、成年後見のこと…一つひとつの案件が重たくて、しかも期限も厳しい。でもそれを伝えても、大半の人には「ふーん、大変そうですね」で終わってしまう。そういう「見えない苦労」に日々、飲み込まれていく。
依頼は切れず、電話も止まらない
ありがたいことに仕事はある。でも、忙しさは心の余裕を奪っていく。電話が鳴れば手を止めて対応し、またすぐに別の案件に取り掛かる。昼食もコンビニで済ませる日が増え、まともに咀嚼してる暇すらない。気づけば、何をしているのか分からなくなってくる。事務所にいる時間が長いほど、社会と隔絶されていく感覚もある。
感謝よりも文句が先にくる現実
丁寧に対応しても、「費用が高い」「遅い」といった声が先に返ってくることもある。もちろんこちらに落ち度があれば反省する。でも、目に見えない部分の努力は、まず伝わらない。何十年もこの業界にいて、報われたと思える瞬間は本当に数えるほどしかない。それでも、「もうやめた」と口に出す勇気は持てずにいる。
事務員ひとりで回すには限界がある
うちの事務所には、事務員がひとりだけいる。彼女もよく頑張ってくれているけれど、正直、回らない。結局、補正が来れば自分が夜中に処理し、書類の不備も最終的には自分で確認する。分業が理想なのはわかっていても、現実はそうはいかない。少人数の地方事務所には、余裕なんて存在しない。
それでも仕事を辞めない理由
愚痴ばかりこぼしていても、なぜか毎朝出勤している。理由は、たぶん意地と責任感と、ちょっとだけ残っているやりがい。司法書士をやめてしまえば、自分には何が残るんだろうと思うと、それが怖いのかもしれない。働く理由を見失っても、働かない理由は見つからない。そんな気持ちで日々を重ねている。
「やめたい」けど、やめない
何度も「もう無理だ」「続ける意味があるのか」と思ったことがある。でも、そのたびに「でも誰がこの仕事やるんだろう」と考えてしまう。小さな事務所の責任は、自分ひとりの肩にかかっている。逃げたら終わり、というプレッシャーとともに生きている。自由がないと感じながら、自由に辞めることもできない。
野球部で培った根性論が邪魔をする
昔から、「弱音を吐くな」「最後までやりきれ」と言われて育ってきた。元野球部の自分は、多少のことではギブアップできない性格になってしまったのだろう。痛みや苦しみを我慢して、結果を出すことが当たり前だと思い込んでいた。でも、社会人になってからは、それが逆に自分を追い詰める原因になっている。
辞めた後の自分を想像できない
もしも司法書士をやめたら、自分はどうなるんだろう。どんな仕事ができるのか、何がしたいのか、全く想像できない。この仕事が自分の人生そのもので、他に何も残っていない気がする。だからこそ、辞めることが選択肢に入らない。辛いけれど、続けるしかない。まるで出口の見えないトンネルの中にいるような感覚だ。