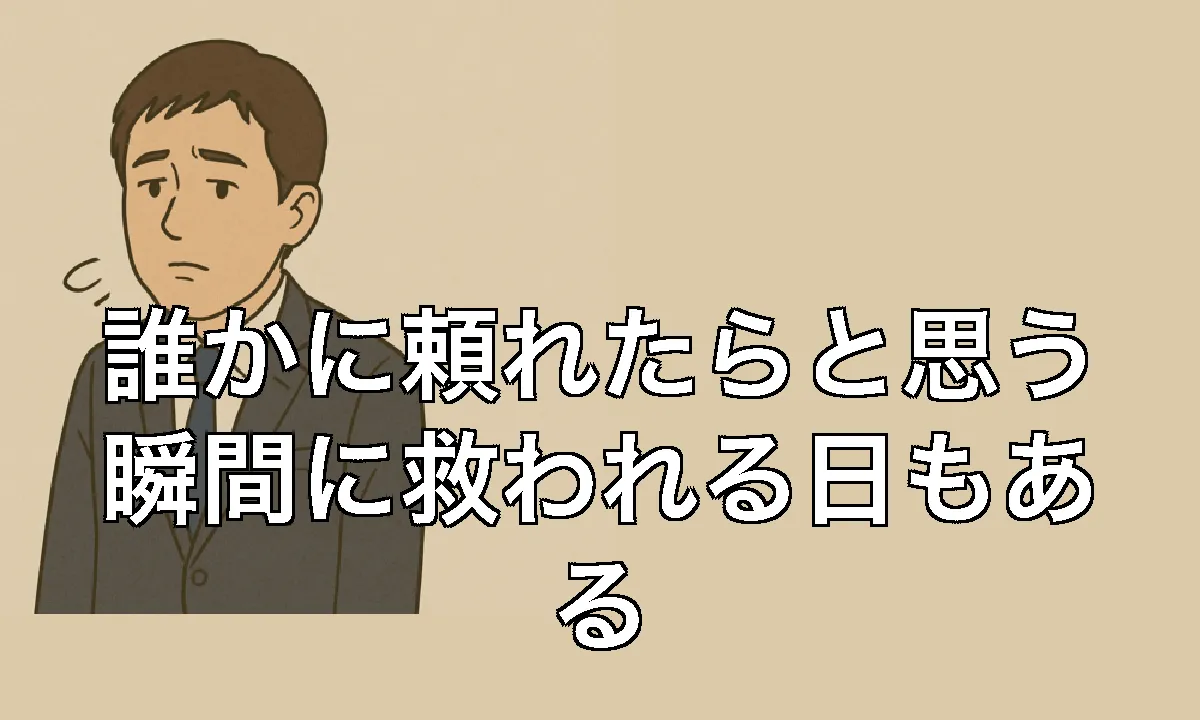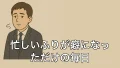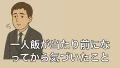一人で抱え込んでしまう司法書士の現実
司法書士という仕事は、基本的に「一人で完結させる」ことが前提にある職種です。ミスが許されない登記業務、期限が厳しい書類作成、そして依頼者の期待に応えなければという重圧。事務員さんが助けてくれることもありますが、最終責任は常に自分。だからつい、「自分がやらなきゃ」と全部を抱え込んでしまう。そんな日々の中で、自分のキャパを超えていることにすら気づけなくなるときがあります。
責任感が強いからこそ誰にも言えない
依頼者との信頼関係が命の仕事だからこそ、「自分が弱っている姿」は見せられないと思ってしまいます。特に私は、相談者に安心してもらうことが何より大切だと思っているので、たとえ体調が悪くても、心が折れそうでも、明るく振る舞ってしまう。けれど本音を言えば、ただ「疲れました」と一言言えたら、どんなに楽になるか。責任感が強いことは悪くない。でもそれが自分を追い込んでしまうこともあるんですよね。
「大丈夫」の裏にある本音
「大丈夫です」って、実は一番危ない言葉だと思います。以前、過労で倒れかけたときも、「大丈夫」と言いながら、内心は「もう無理だ」と思っていました。でも誰かに助けてと言えなかった。なぜかといえば、自分の中に「こんなことで弱音を吐いたらダメだ」という思い込みがあったから。けれど、それが結果的に自分を傷つける。誰かに頼ることは、恥じゃない。そう気づけるまで、随分と時間がかかりました。
小さなトラブルが引き金になるとき
一見すると些細なミス、例えば登記情報の入力ミスや、郵便の不達。それがきっかけで心が折れることがあります。普段なら「よくあること」で流せるのに、疲れや不安がたまっているときは、その一つで「もう全部ダメかも」と思ってしまう。実際、ある日、法務局への提出書類を事務所に忘れて外出してしまい、炎天下の中、慌てて戻ったことがありました。そのとき、自分の中でプツンと糸が切れたのを今でも覚えています。
ふと誰かに頼りたくなる瞬間
一人でやることに慣れすぎてしまっても、時折、誰かに「ちょっと手伝ってくれ」と言いたくなる瞬間があります。それは弱さではなく、ごく自然な感情なのだと思うようになりました。むしろ、誰かと支え合うことで初めてバランスがとれるのかもしれません。ふとしたタイミングでそんな思いに気づくことが増えてきました。
お客さんの感情を全部受け止めた日
ある日、相続で揉めていたご家族の相談を受けたときのことです。こちらは冷静に事務手続きを説明しているつもりでも、相談者の感情が爆発してしまい、まるで私が悪いかのような言われ方をしました。そのとき、「なんで俺がここまで抱えるんだろう」と思ってしまった。理不尽さを感じながらも、受け止めなければならない役割。その夜は、誰かに「今日、しんどかったよ」とただ話せたら…と心底思いました。
休みの日にも鳴り止まないスマホ
たまの休みに、スマホが鳴る。それが仕事関連だとわかった瞬間に、心がギュッと縮む。以前、キャンプに行っていた日曜、顧客から「緊急でお願いしたいことが」と連絡がありました。火を起こしてた手を止めて、慌てて山を下りる途中、ふと「この生活、いつまで続くんだろう」と虚しくなった。何もかも自分が背負うしかないという孤独感が、胸にじわじわと広がっていくのを感じました。
「自分がいないと回らない」幻想
独立してからずっと、「自分がいなきゃ」という意識が強すぎました。事務員さんにも任せられるはずの仕事を、つい自分でやってしまう。責任感というより、単なる癖。けれどある日、体調不良で寝込んだ際、事務員さんが何事もなく対応してくれて、「あれ、案外回るじゃん」と拍子抜けしました。それ以来、少しずつ任せるようになりました。「頼る」ことは、相手を信じることでもあるんだなと、あのとき初めて実感しました。
頼ることへの罪悪感とその背景
「助けを求める=負け」という考えが、知らず知らずに自分を縛っていた気がします。特に男社会で育った人間にはありがちかもしれませんが、「弱音を吐いたら終わり」という思い込みは、案外根強く残るものです。けれど、その価値観こそが、自分を一番苦しめていることに気づくのは、だいぶ後の話です。
弱音を吐くのが苦手な性格
私は昔から、「頑張っていれば報われる」と思って生きてきました。弱音を吐くことが許されない家庭で育ったこともあり、「つらい」と言うことにものすごく抵抗があるんです。だから、体調を崩しても「気のせい」、落ち込んでも「大丈夫」と自分に言い聞かせてきました。でもそれって、ただ心の声を無視してきただけなんですよね。ある日、鏡を見たら目の下にクマができていて、「これが限界かもな」とようやく自覚したこともありました。
元野球部の「我慢は美徳」精神
高校時代、私は野球部で副キャプテンをしていました。根性論が当たり前の時代で、熱があっても練習に出るのが美徳。そんな経験が染みついているせいか、いまだに「休む=怠け」と思ってしまう自分がいます。司法書士として独立した今も、「寝てる暇があったら仕事しろ」と自分を追い立ててしまう。でも、さすがに45歳にもなって、それが体にも心にも良くないってことくらい、薄々気づいてきました。
頼ること=負け、と思っていた
「人に頼るなんて、自分の力不足を認めるようなもんだ」。そんな思い込みを持っていた時期が長かったです。でも今思えば、それってただの意地ですよね。仕事が回らないのは、能力の問題じゃなく、仕組みの問題。だから、頼るべきときに頼ることは、むしろ仕事をうまく回すためのスキルなんだと、ようやく考えが変わってきました。誰かに助けを求めることを、「逃げ」ではなく「選択」と捉えるようになったのは、大きな一歩でした。
小さな助けが心を軽くする
本当にありがたいのは、派手なサポートではなく、ちょっとした気遣いだったりします。それが心の緊張をほぐしてくれる。仕事柄、誰かに支えられている実感はなかなか持ちづらいのですが、そんな一言や行動が、じわっと効いてくることがあります。
事務員さんの何気ない一言
ある日、繁忙期の書類山積みでイライラしていた私に、事務員さんが「先生、今日はもう上がってください」と言ってくれました。その言葉を聞いた瞬間、肩の力が抜けて、思わず「ありがとう」と返していました。自分では気づいていなかったけれど、きっと顔が限界だったのでしょう。たった一言。でもそれが救いになることもある。あの日は、久しぶりに自分の心が人に受け止められたような気がしました。
「今日は早く帰ってください」の重み
たぶん、あの一言がなければ、私はあの日も無理をして働いていたと思います。そしてまた、誰にも気づかれずに潰れていくところだった。けれど「帰ってください」と言われたとき、「あ、休んでもいいんだ」と、まるで許可をもらったような気持ちになったんです。自分に厳しすぎる人ほど、こういう“許可”が必要なのかもしれません。たったそれだけで、自分を少しだけ大切にしようという気持ちが生まれるのです。
司法書士という職業の孤独
専門職である司法書士は、他の人とチームを組んで進めるというより、一人で完結する業務が多いです。そのため、どうしても孤独を感じやすい。悩みを共有できる相手も少なく、仕事上の判断もすべて自己責任。だからこそ、「頼ること」を恐れてしまうのかもしれません。
専門職だからこその閉塞感
同じ資格者同士でも、横のつながりが薄い業界です。士業の勉強会に顔を出しても、皆どこか本音を隠していて、安心して話せる雰囲気じゃないことも多い。孤独を感じながら、同じことを繰り返す日々に閉塞感を覚えることもしばしばあります。だからこそ、本当に信頼できる人と出会えたときは、それだけで救われた気持ちになります。
相談できる人が近くにいない
何か困ったときに、「ちょっと聞いてもいいですか?」と話しかけられる相手がいない。これが想像以上に精神的に堪えます。孤独は音を立てずに心を蝕んでいくんですよね。そんな中、ふとしたきっかけで相談できる人が現れたとき、その存在がどれだけありがたいか痛感します。私は最近、近くの司法書士さんと少しずつ交流を深めています。まだ本音は言えていませんが、「話しても大丈夫かもしれない」と思えるだけで、少し楽になります。
誰かを頼る勇気を持つということ
頼ることは甘えではなく、生きるための知恵。そう考えられるようになってから、自分自身も少しだけ穏やかになれました。仕事の効率も上がった気がします。そして何より、他人の弱さにも優しくなれた気がしています。
肩の力を抜くことで見えるもの
昔の自分は、全身に力を入れて生きているような感じでした。仕事中も、家にいても、何かに追われるように時間を埋めていました。でも少しずつ、「そんなに頑張らなくてもいい」と思えるようになってから、不思議と仕事も人間関係もスムーズになってきた気がします。完璧を目指さない。助けを求めてもいい。それだけで、こんなにも心が軽くなるんだと知りました。
優しさは循環する
誰かに優しくされると、自分も誰かに優しくしたくなります。最近では、事務員さんや後輩の司法書士に、以前よりも余裕を持って接することができるようになりました。「しんどかったら言ってね」と声をかける。それだけで、相手もきっと少しは救われる。優しさは、循環するものなんですね。誰かに頼れたらと思う瞬間、それをちゃんと受け止めてもらえる社会であってほしいと思います。