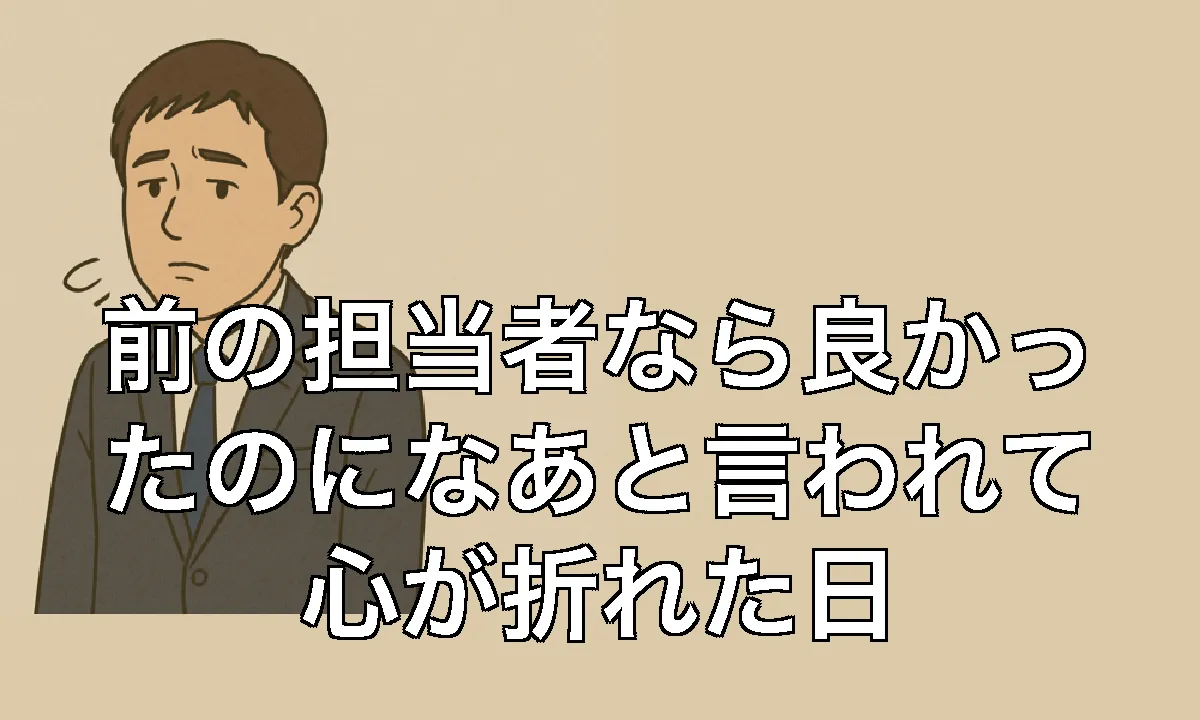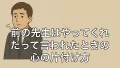その一言が頭から離れない朝のこと
「前の担当者ならもっと丁寧だったのにね」。そう言われたのは、登記の手続きのことで問い合わせをしてきた依頼者に対して、少しだけ急いだ対応をしたときだった。忙しさにかまけて、少し言葉が淡白になったかもしれない。だけど、まさかそんなふうに返されるとは思っていなかった。その一言がずっと頭の片隅にこびりついて、朝起きた瞬間から思い出してしまう。自分がやってきたこと、積み上げてきた信頼が、たった一言で崩れてしまうような虚しさに包まれる。
思い出してしまう依頼人の表情
その依頼人は、年配の女性で、話し方も穏やかだった。けれどそのときだけ、妙に冷たい視線だった気がする。何かが気に障ったのだろう、と思い返すが、決定的な原因は見えない。こちらが何をしても「前の担当者と比べて」見られるのだとしたら、努力は無意味なのか、とすら思えてくる。あのときの視線は、今もふとした瞬間に蘇る。そして、そのたびに胸が重くなる。
前の担当者を知らないからこその苦しさ
この地域に戻ってきてから、いくつかの業務を引き継いだ。その中に、長年信頼を得ていた司法書士が対応していた案件がある。引き継ぎ書類はあっても、人の信頼までは引き継げない。「前の人の方が安心できた」と言われても、どんな対応をしていたのか、想像するしかない。その人のやり方をなぞることもできない。知らないものに比べられるのは、なんとも不公平な気がする。
知らぬ過去と比べられる悲しさ
例えば、バッターボックスに立った瞬間に「前の4番はもっと打てた」と野次られているようなものだ。こちらは初回の一打席目だというのに、過去のホームランの記録と比べられても困る。それでも、依頼者にとっては「司法書士=誰でも同じ」なのだろう。そう考えると、悲しさと悔しさが同時にこみ上げてくる。自分は誰かの後釜でしかないのかと。
なぜ比べてくるのかという問い
依頼者が前任者と比べてくる理由は、決して悪意からとは限らない。むしろ、信頼していたからこその言葉であり、比較対象があるから不安になってしまうのだろう。とはいえ、当事者としては複雑だ。善意に見える言葉でも、受け取り手によっては鋭利な刃物のように刺さってしまうことがある。そして、その傷は思った以上に長引くのだ。
善意のつもりが刃になるとき
「悪気はないんですよ、ただちょっと前の先生がよかったってだけで」と言われたこともある。でも、それが一番キツい。悪気がない分、真正面から突き刺さる。むしろ、ちょっと気を遣ってほしかったと思ってしまう。優しい人ほど、無意識に無遠慮だ。それは、この仕事をしていると日常的に感じる感情のひとつだ。
期待の裏返しと捉えられるか
ポジティブに考えれば、それは「あなたにも同じくらい期待している」という裏返しなのかもしれない。でも、そんなふうに捉えられるほど、自分はできた人間ではない。疲れていたり、自信を失っていたりすればなおさらだ。ちょっとした言葉も、頭の中で反芻してしまって、自分を責める材料にしてしまうことのほうが多い。
それでも正面から受け止める意味
傷つかないように受け流すこともできる。でも、それでは仕事としての成長がないのかもしれない。あの言葉にいちいち反応してしまう自分を、情けないと思う日もあるけれど、反応することそのものは、まだ期待に応えたい気持ちがある証拠なのかもしれない。無関心よりはマシ。そう思うことで、なんとか気持ちの均衡を保っている。
心が削られる日々にできること
開業してからずっと、ひとりで受け止めてきたものは少なくない。なにせ、この町では司法書士が少ない。誰かに相談する機会も少ないし、同業者との距離感も遠い。何より、愚痴をこぼす場がない。溜まった気持ちは、夜遅く帰宅して、テレビの音に紛れて自分に向けて漏れる独り言になる。
愚痴を言える場所がない現実
昔は居酒屋で先輩や同僚にポロッと話せる場所があった。でも今はそんな機会もない。事務員に愚痴るのも気が引けるし、話しても仕事上の愚痴に付き合わせるのは申し訳ない。SNSに吐き出すような性格でもない。だからこそ、こんなふうに文章にして残しておきたくなるのかもしれない。
ひとり事務所の孤独と対峙する
静まり返った事務所で、カタカタとパソコンの音だけが響く。誰かに相談するでもなく、ただ淡々と仕事を進める。孤独ではあるけれど、逆にそれが自分にとっての「日常」になってしまった。慣れたら平気になるのかと思っていたが、慣れるほどに寂しさが深まる瞬間もある。
元野球部的メンタルでの乗り越え方
高校時代、野球部で怒鳴られても前を向いていた。あのときの「気にするな、次がある」という感覚は、今でも救いになる。ただ、あの頃は仲間がいた。今は、仲間もいないし、監督もいない。自分で立ち直るしかない。だけど、自分の中にいる「もう一人のキャプテン」がたまに声をかけてくれる。「お前はまだやれるぞ」って。
それでもこの仕事を続ける理由
つらい言葉に出会っても、仕事をやめたいとは思わない。むしろ、「こんな自分でも、できることがある」と思わせてくれる出来事がたまにある。そのたびに、辞められなくなっていくのだ。いい意味で、依存しているのかもしれない。
事務員さんの一言が救いになった話
ある日、何気なく「私だったら、先生の方が話しやすいですけどね」と言われた。その一言に救われた。誰か一人でも、自分を肯定してくれる人がいれば、それだけでまた数日は頑張れる。給与明細を渡すときの無表情なやりとりの裏に、そんな言葉があると知ると、日々の重みも少し変わる。
依頼者全員が敵じゃないと気づく瞬間
たった一人のクレームがあっても、実はその裏で感謝の手紙を書いてくれる依頼者もいたりする。だけど、どうしても印象に残るのはキツい一言のほうだ。人間って、そういう生き物だ。だけど、比べてくる人ばかりじゃない。静かに、でも確かに信頼を寄せてくれる人もいる。それに気づくとき、自分が少しだけ報われる。
比べられることより信頼されること
「前の担当者と違うね」と言われることに怯えていたけど、「今の先生にお願いしてよかった」と言われた瞬間に、その過去の比較が一気にどうでもよくなる。信頼は積み上げるものだとわかっていても、その事実を体感するまではやっぱりつらい。だけど、信頼は必ず自分のところにも戻ってくる。そんなふうに信じて、また明日も机に向かう。