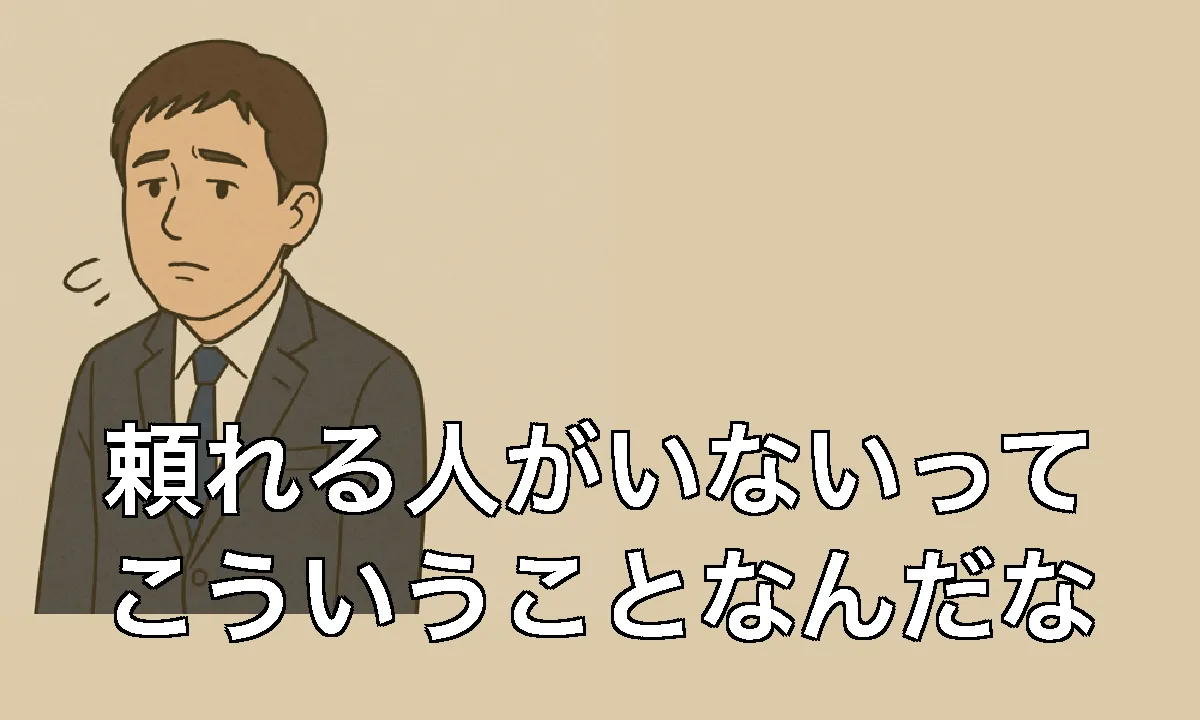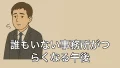朝から既に疲れているという感覚
目が覚めた瞬間から「今日も始まってしまったか」とため息が出る日が増えた。疲れているというより、心がどこか重く、エンジンがかからないまま事務所へ向かう。身体は動くが、気持ちがまるでついてこない。仕事は山積みで、ミスすればすぐにクレーム。誰にも代わってもらえず、全部が自分の責任になる。それを理解しているからこそ、気を抜くこともできない。けれども、そんな毎日が続けば、いつかどこかでポキッと折れてしまうのではないかという恐怖と隣り合わせだ。
今日も誰も代わってくれない現実
体調が悪かろうが、親の介護があろうが、司法書士という肩書には代役がいない。昨日、少し熱っぽかったが、「熱です」とは言えず、黙って案件を処理していた。顧客の都合に合わせて無理をするのは当然。電話が鳴れば取らねばならず、訪問があれば笑顔で対応する。だが、その裏で心はすり減っていく。「今日は誰か助けてくれるかもしれない」という淡い期待も、もう抱かなくなった。それが日常になってしまった。
電話が鳴るたびに心がすり減る
電話のコール音が、昔は仕事の証だった。ところが今は、音が鳴るたびにビクッとする。何か問題があったのか?クレームか?新しい依頼か?どれも即対応を求められ、重圧がのしかかる。たった一本の電話で、午前の予定が全部吹き飛ぶこともある。何が飛び出してくるかわからない電話が、もはや爆弾にしか見えなくなった。出るしかないのに、出たくない。この矛盾に疲れ果てる。
書類山積みでも「頼んだ」とは言えない
事務員さんが一人いるとはいえ、書類の内容は私の責任範囲。権限が必要な処理や、微妙なニュアンスが必要な案件は結局自分でやるしかない。「これお願い」と言いたくても、後で手戻りになるのが目に見えているし、何より彼女の手も空いていない。机の上に積まれたファイルを見て、頭の中で優先順位をつけながら、目の前の現実にため息をつく。分担とは名ばかり、責任を取るのはいつも一人だ。
心のどこかで助けを待っている自分
「一人で頑張ってるね」と言われると、胸が詰まる。そんなつもりはないけど、結果的にそうなっている。誰かに頼れたら、どれだけ楽だろう。けれど、「甘えるな」と言われたくないし、情けないと思われたくないという自尊心が邪魔をする。だから、黙って耐えることを選ぶ。だけど正直、そろそろ限界が近いんじゃないかと思っている自分もいる。それに気づきながらも、どうすることもできずにいる。
「頑張ってくださいね」と言われる辛さ
お客様や関係者から、よく「お忙しいでしょうけど、頑張ってくださいね」と言われる。悪気はない。でもその一言が、時にぐさっと刺さる。「これ以上何を頑張ればいいのか」と心の中で反射的に思ってしまう。頑張りすぎて空回りしていること、自分自身がわかっているだけに、その言葉が虚しく響く。労いのつもりが、プレッシャーになってしまう不思議な感情がある。
相談できる相手が思いつかない夜
仕事が終わって帰宅した夜、ふとした瞬間に「誰かに話したい」と思うことがある。だが、連絡先を開いても、すぐに思いつく相手はいない。友人はいる。でも、「最近どう?」と聞かれたときに、答えられない。愚痴ばかりになるのが分かっているから。恋人もいない。ましてや家族に弱音を吐くこともできない。テレビの音だけが響く部屋で、空虚さがじわじわと広がる。
たった一人の職場で見つめる現実
司法書士事務所というのは、基本的に小規模でまわしているところが多い。うちも例に漏れず、私と事務員さんの二人体制。効率がいいと思われがちだが、それは理想論。実際には、少人数ゆえにすべての工程をこなす必要があり、抜けや遅れはすべて直撃する。相談できる人も、頼れる人も少ないからこそ、心の余裕もすり減っていく。
事務員さんに全部は頼れない事情
事務員さんは本当にありがたい存在で、いなければ今ごろ潰れていただろう。ただ、全部は任せられない。司法書士業務は専門的で、細かい法的判断や説明責任が求められる。だから、結局自分で対応せざるを得ないことが多い。しかも、彼女に無理をさせすぎても辞められてしまう恐れがある。人手が少ない業界では、誰か一人でも抜けると即座に機能不全に陥るのだ。
優しさと遠慮のあいだで揺れる
「無理しないでね」と言いつつ、「でもこれお願いしてもいいかな」と言いかけて飲み込むことがある。彼女の様子をうかがいながら、少しでも負担を減らそうと努力する。でもそれは、結局自分への負担を増やしているだけ。優しさと遠慮が交差し、どこかで線を引けなくなっている。甘えることと、頼ることの違いが分からなくなってきた。
「自分でやった方が早い」の罠
この業界ではよく聞くフレーズだ。「自分でやった方が早い」。確かにそうなのだ。でも、それを続けていると、全部自分に戻ってくる。「頼む手間」「説明の手間」を惜しんだ結果、手が回らなくなってくる。わかってはいるのに、目の前のスピードを優先してしまう。そして、あとで後悔する。この罠から抜け出せる日は、まだ見えていない。
昼休みの沈黙が余計に心に刺さる
昼休み、本当は少し気持ちを緩めたいのに、机に向かったままコンビニおにぎりを片手にメールチェックしている。事務員さんも黙々と作業していて、会話はほとんどない。静かな空間が、逆に心を締め付ける。リラックスできる場所であるはずの職場が、気を抜けない場所になっている。それが習慣になってしまっている自分に気づいたとき、寂しさがどっと押し寄せてくる。
スマホを見ても誰にも連絡できない
昼休み、ふとスマホを手に取るが、開いても特に連絡をとりたい人がいない。SNSも眺めるだけで、自分から発信する気力はない。通知は仕事のメールばかりで、プライベートのメッセージはゼロ。元野球部の仲間のグループLINEも、気づけば自分は発言しなくなっていた。「誰かに会いたい」という気持ちと、「でも面倒だな」という気持ちがぶつかり合っている。
一人で食べる弁当の味気なさ
昔は弁当を食べる時間が楽しみだった。だが今は、ただ空腹を満たすための作業に過ぎない。誰かと笑いながら食べるご飯の味を忘れた気がする。事務所で一人、黙って食べる弁当は、味気ない。美味しいかどうかもよくわからない。口に運ぶたびに、何かが欠けているような気がしてならない。
期待されるけど誰も守ってくれない
司法書士という肩書は、信頼されると同時に、常に完璧を求められる。クライアントも、取引先も、役所も、みんなこちらに頼ってくる。それは光栄なことだ。でも、逆に言えば、失敗したときの責任もすべてこちらに降りかかる。そんな時、誰かが守ってくれるわけでもない。最後まで自分で処理しなければならないのが現実だ。
「先生」だから弱音を吐けない
周囲は「先生」と呼んでくれる。でも、「先生」という言葉には、常にしっかりしていなければならないという重圧がついてくる。ちょっとした疲れやミスも許されない空気がある。誰かに「しんどい」と漏らした瞬間、「あの人、頼りにならないかも」と思われてしまうのではという不安がよぎる。だから、黙って耐える。それが「先生」であることの現実だ。
プロでいることと孤独の比例関係
仕事を極めるほど、周囲と距離が生まれてくる。プロであることは、孤独であることと紙一重だと実感している。ミスを許されないからこそ、何でも自分で抱えるようになる。その積み重ねが、孤独を深くしていく。けれど、だからといって手を抜くわけにはいかない。自分の信頼と事務所の看板は、自分自身で守るしかないのだ。
どこまで頑張れば許されるのか
いつも思う。「どこまで頑張れば、認められるんだろう」。依頼を完了しても、感謝されることは少ない。逆に、少しでも遅れれば不満をぶつけられる。司法書士は、ミスをしないことが当たり前。だからこそ、頑張っても誰にも気づかれない。でも、だからといって手を抜けない。報われない努力を、ただ淡々と積み重ねるしかないのだ。
「相談される側」の苦しみ
相談を受けることは多い。法的なこと、人生のこと、相続や借金のこと。みんな悩みを抱えてやってくる。私の話を聞いて、ホッとしたような顔をして帰っていく。でも、私自身の話を聞いてくれる人は誰もいない。私は「聞く側」専門になってしまっている。誰かに話を聞いてもらいたい時、ふとそのことに気づいて、空しくなる。
「頼ること」ができない職業の宿命
司法書士は、頼られる側であることが宿命だ。だからこそ、自分から誰かに頼ることが難しい。弱音を吐いた時点で、「この人はプロとしてどうなんだろう」と見られる気がしてしまう。だから頼らない。けれど、心の奥底では誰かに甘えたい気持ちがある。人としては当たり前の感情なのに、それを抑え込まなければならないのがつらい。
一言「大丈夫?」がどれだけ救いになるか
ある日、事務員さんがふと「最近ちょっと疲れてます?」と声をかけてくれた。その一言で、涙が出そうになった。誰にも言えなかったことを、たった一言で見抜かれた気がした。大丈夫かと聞かれること、それだけで人は救われることがある。何も解決していなくても、「見てくれている」と思えるだけで、もう少しだけ頑張ろうと思えるのだ。