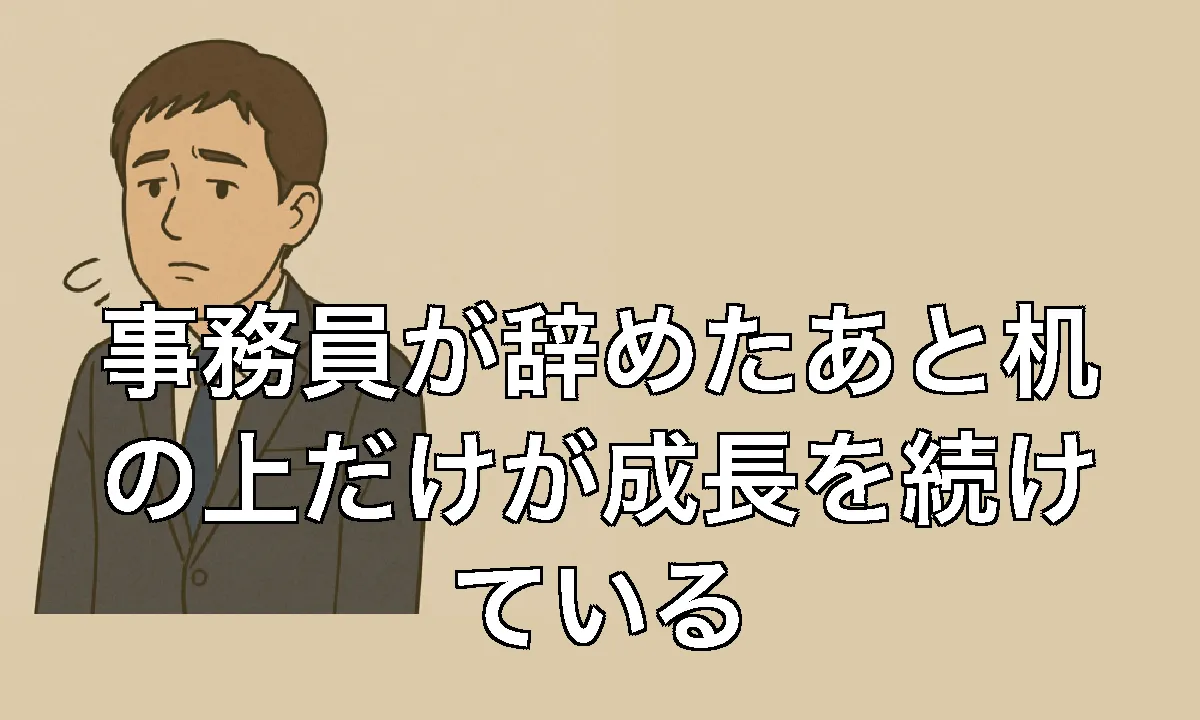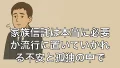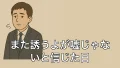あの日 突然やってきた別れの朝
「今日で最後です」と告げられたあの朝、私はただ「そうか」としか返せなかった。何度も予兆はあった。疲れた表情、深いため息、そして増えていく有休申請。覚悟していたはずなのに、現実として突きつけられると、驚きよりも無力感が押し寄せた。司法書士の仕事は細かくて煩雑だ。依頼者対応、登記書類の作成、スケジュール管理……事務員さんの支えがあってなんとか成り立っていた日常だった。その屋台骨が一気に崩れた瞬間だった。
引き止められなかった理由と心のざわめき
彼女は優秀だったし、辞めてほしくなんかなかった。でも、長時間労働や突発の対応、書類の山に追われる毎日は、彼女にとっても限界だったのだろう。私もそれに気づいていた。でも、どうしたら良いか分からなかったし、「せめてもう少しだけ…」と頼むこともできなかった。引き止めてしまえば、逆に彼女を責めるような気がしてしまった。事務員一人、雇えない自分の経営力のなさ、フォローできなかった気遣いの足りなさが心の中で暴れ回っていた。
言い出せなかった「ありがとう」と「ごめん」
最後の日、帰り際に「お世話になりました」と言われたとき、私は「こちらこそ」と笑って答えた。でも本当は「ありがとう」と「ごめん」を何度も言いたかった。もっとちゃんと労いの言葉をかけていれば、もっと早く疲れに気づいていれば――後悔は尽きない。机の引き出しに置かれたマニュアルメモや、細かく整理されたファイルを見るたび、胸が締めつけられる。無言の優しさが、どれだけ私を助けてくれていたのかを、辞められて初めて知った。
一人で抱えたくなかったのに 抱えるしかなかった
事務員がいなくなったからといって、業務が止まるわけではない。誰かに手伝ってほしいと何度思ったことか。でも田舎の司法書士事務所で、急に人を雇うのは現実的ではない。募集をかけても応募は来ず、知人に頼るにも限界がある。結果、すべてを自分で抱えるしかなかった。電話の対応から郵便の受け取り、書類の作成、法務局への申請まで、休む間もなく手を動かし続けた。夜になると背中が痛み、朝は目覚ましが恨めしくなる日々が続いた。
書類の波に飲み込まれる日々
司法書士という仕事は、とにかく「紙との戦い」だ。登記簿、印鑑証明、委任状、住民票……全てが正確でなければならず、期限もある。事務員さんがいたときは、目を通すだけで済んでいたものが、今や自分で一から作る羽目になった。そして処理しきれなかったものたちが、机の上でじわじわと積み上がっていく。目をそらすと崩れそうなその山が、私の心を圧迫してくる。まるで「お前が処理しないからこうなったんだ」と責められているようだ。
机の上が地層のように堆積していく
最初は「少しずつ片付ければいい」と思っていた。でも、次々に新しい案件が舞い込んできて、古い書類は後回しになる。やがてそれが1週間前のものか、3日前のものかも分からなくなっていく。気づけば、机の一角が“化石ゾーン”になっていた。昔の地層のように、上に重ねるだけで何も掘り返せない。探し物をするたびに全崩壊しそうになる恐怖。「このまま一人でやってたら、埋もれて発見されなくなるんじゃないか」とさえ思うほどだった。
誰にも頼れず声も出せずただ処理する
「助けて」と言えればどれだけ楽だったろう。けれど、司法書士として「ちゃんとしてる自分」を演じなければならないという思いが、口を閉ざしてしまう。「忙しいのは自分だけじゃない」「みんな頑張ってる」と頭では分かっていても、体は限界だった。昼は電話に追われ、夜はミスがないか何度もチェックし、気づけば終電ギリギリ。誰にも弱音を吐けず、ただ目の前の仕事を処理するだけの機械のようになっていた。
どこまでやっても「終わり」が見えない
作業を終えて机を見ても、まったく減っている気がしない。それどころか、ファックスやメールでどんどん依頼が増えていく。まるでバケツで水をかき出しても、底から水が湧いてくるボートのようだ。しかもそれが「いつ終わるか分からない仕事」だからなおさらキツい。毎日がゴールのないマラソン。何のためにやっているのか、自分が何者なのかさえ分からなくなっていく。気づけば、「もう辞めたい」が口癖になっていた。
誰かに会いたくて会いたくなくて
人に会いたい、でも人と話すのが怖い。そんな矛盾を抱えたまま、日々を過ごしていた。依頼者の来所があるたびに心の準備をして、笑顔をつくる。「大丈夫ですか?」と聞かれるたびに、「大丈夫です」と嘘をつく。その繰り返し。人と接するのが仕事なのに、自分の心はどんどん閉じていく。忙しさに加えて孤独が心を削っていった。
電話の音にビクッとするようになった
一番つらかったのは、電話が鳴る音にすら怯えるようになったことだ。以前は何でもなかった呼び出し音が、今は「また新しい問題が来た」という合図のように感じる。手が止まって、思わず耳を塞ぎたくなることもあった。実際、出られずに着信履歴だけが残っていることもあった。そんな自分に自己嫌悪する。プロとして、それはあるまじきことなのに。疲労と責任が、私の心をじわじわと蝕んでいた。
相談されるのが仕事なのに自分が一番迷っている
司法書士として相談に乗るときは、相手にとっての“道しるべ”でなければならない。でも、その頃の私は、自分の足元さえ見失っていた。「このまま一人で続けて意味あるのか?」「事務所をたたんだ方が楽じゃないか?」といった不安が、夜になると頭をよぎる。それでも翌朝にはスーツを着て、机に向かっていた。どこかで「踏ん張らなきゃいけない」と思っていた。でも、誰かに「もう頑張らなくていいよ」と言ってほしかった。
誰かの「大変ですね」に涙が出そうになった
ある日、久しぶりに顔を出した法務局の職員に「最近忙しそうですね」と言われた。その一言に、危うく泣きそうになった。誰かが気づいてくれた、それだけで心が救われた気がした。自分では気丈にふるまっていても、やっぱり限界だったんだと思う。優しい言葉って、すごい力を持っている。その日から、私も他人に対してちゃんと「気づける人間でいたい」と思うようになった。
それでも一人でやっていくしかないという現実
誰かが手伝ってくれるわけでもない。業務は待ってくれない。私は、一人でやるしかなかった。仕事を選ぶことも、休むこともできない。そんな状況に置かれて初めて、今までどれだけ周囲に支えられていたかが身に染みた。そして、それでも自分の名前で続けていかなければならないというプレッシャーは、私の背中に重くのしかかっていた。
募集をかけても応募が来ない
人手が足りないのだから、事務員を募集すればいい――そう簡単にはいかない。田舎の小さな司法書士事務所に、求人の応募はほとんど来ない。来てもすぐに辞退されるか、面接で「思ったのと違いました」と言われてしまう。業務内容が特殊で、責任も重い。待遇も都会のようにはいかない。そんな中で人を探すのは、まるで砂漠で水を探すようなものだ。
教える体力も気力もないのが本音
仮に誰かが来てくれたとしても、今の私に教える余裕があるかといえば、正直ない。ミスは許されない世界で、慎重に慎重を重ねている今、他人のミスをフォローする自信すら持てない。新人に丁寧に教えてあげたいという気持ちはある。でも、体がついていかない。優しく接する余裕すらない自分に、また自己嫌悪する。こんなループが続くくらいなら、一人でやっていた方がまだマシだとさえ思ってしまう。
新人に期待しては裏切られるループ
過去に何人か雇ったこともある。最初は「今度こそ」と期待する。でも、教える時間も余裕もない中で、どんどん気まずくなっていく。そして、ある日突然の退職。結局、自分の責任なのだと分かっているけど、何が悪かったのかも分からない。期待しては裏切られ、また期待しなくなっていく。こうして私は、「どうせ無理だ」と思い込むようになっていった。
少しだけ気が楽になった瞬間
そんな毎日の中でも、ふと気が楽になる瞬間はある。例えば、昔の同僚と話した夜。「お前だけじゃないよ、俺もきついよ」と言ってくれた言葉が、心に染みた。自分だけが苦しんでるわけじゃないんだ、そう思えるだけで少し肩の力が抜けた。こういう小さな救いを、私はずっと求めていたのかもしれない。
昔の同僚の一言に救われた夜
久しぶりに会った大学時代の仲間に、「最近どう?」と聞かれ、思わず「事務員が辞めて地獄」と答えた。すると彼が笑って「うちなんか営業全員辞めたぞ」と言い、酒を飲みながら仕事の愚痴をぶちまけ合った。その時間が、本当に救いだった。「ああ、自分だけじゃないんだな」と思えるだけで、人はちょっとだけ前に進める気がする。悩みを分かち合える相手がいることのありがたさを、改めて実感した夜だった。
野球部時代を思い出して踏ん張ってみる
つらい練習の中でも、最後までやり切れた高校時代の野球部のことを、最近よく思い出す。監督に怒鳴られながらも、泥だらけで走り続けた日々。あの頃も、泣きたかったし、やめたかった。でも結局、踏ん張った。今の自分も、あの頃と同じように踏ん張るしかないのかもしれない。誰かに頼れなくても、弱音を吐けなくても、自分の足で立ち続ける。そう思えるようになったのは、少し成長した証なのかもしれない。