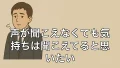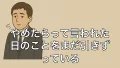先生と呼ばれるようになった日
司法書士として開業して十数年。事務所を構えて「先生」と呼ばれるようになったのは、ある意味で一つの到達点だったのかもしれない。依頼者や関係者、時には近所の人からもそう呼ばれるたびに、肩書きに見合う人間でいなければという気持ちが湧いてくる。最初は照れもあったが、今ではその言葉が心にずしりと響くようになった。あの日、自分が何かを背負った瞬間だったのかもしれない。
司法書士という肩書きがもたらす距離感
「先生」と呼ばれるとき、相手との距離を感じるようになった。依頼者にとって私は専門職のプロであり、ある種の威厳を求められているのだろう。だが、人間としての自分は、ただの45歳の独身男で、書類に追われ、ミスを恐れて神経をすり減らしている。かつて野球部でキャプテンをしていた頃のように、期待に応えることが当たり前のような空気が、少しずつ自分を締めつけていく。
最初は誇らしかった呼ばれ方が今は重たい
開業当初は「先生」と呼ばれるたびに、親に胸を張って報告したものだ。田舎の親はそれを喜んでくれたし、自分自身もようやく一人前になれた気がしていた。でも今、その言葉に疲れを感じるようになった。尊敬よりも、立派に振る舞わなければいけないというプレッシャーばかりが大きくなっていくのを感じる。誇りが重荷に変わる瞬間は、ある日突然訪れるものなのだ。
先生と呼ばれることのしんどさ
「先生」と呼ばれることには、責任と信用が伴う。それは間違いなくありがたいことだ。でもその分、完璧であることが暗黙の前提になってしまうような空気もある。ときには失敗することもあるし、体調がすぐれない日だってある。けれど「先生」がそんな姿を見せてしまったら、信頼を失うのではないかという不安が常につきまとう。人間らしさを隠してまで先生でいることに、時折しんどさを感じてしまう。
完璧を求められている気がして息が詰まる
登記ミスをすれば「先生なのに」と思われる。言葉を選び損ねれば「そんなこと言うんですね」と失望される。人前に出るたび、ミスの許されない存在としての自分を演じなければならない。特に新人司法書士や事務員の前では、弱さを見せることができないと思ってしまう。完璧であることを求められる役割に、自分が自分でいられないような息苦しさを感じてしまうのだ。
人前では弱音を吐けないという思い込み
かつての自分がそうだった。実務経験も浅く、頼れる先輩も少ない中で、司法書士の「先生」は絶対的な存在に見えていた。だからこそ今、自分がその立場にいるとき、無意識に「自分も弱音は吐けない」と思い込んでしまう。けれど本音を言えば、相談できる人が欲しいし、誰かに「しんどいよな」と共感してもらいたい時だってある。
「間違えられない人」になってしまった
たとえ些細な事務ミスでも、「先生でもこういうことあるんですね」と皮肉交じりに言われたことがある。何でもかんでも完璧を求められるのは、正直しんどい。人間なのだから間違えることもある。でも、「先生」という肩書きがそれを許さない空気を作ってしまう。気づけば、自分で自分を縛ってしまっていることに、ふとしたときに気がつく。
人間関係の中で役割に縛られる
仕事を通じて関わる人たちにとって、私は「先生」であることが前提になっている。それがどこか、対等な人間関係を築くことを難しくしているように思う。相談ごと一つ取っても、プライベートな話を交えると「そんな一面もあるんですね」と妙に驚かれる。まるで自分が常に仮面をかぶっているような気持ちになるのだ。
依頼者も事務員も先生として見てくる
事務員にとって私は「社長」であり「先生」だ。何気ない雑談すら、どうしても構えてしまう。「先生はどう思いますか?」と聞かれると、つい正解っぽいことを返してしまう。気を許した会話すらできないのは、自分のせいなのか、それとも相手が私をそう見ているせいなのか。とにかく「普通の人間」として過ごす時間が減ってきている。
ただの一人の人間として話せない日常
飲みの席でも「先生」と呼ばれ続けると、正直疲れる。「もう仕事のことは忘れたいんですけど」と心の中で思いながら、無理に笑ってしまう自分がいる。プライベートでまで気を張り続けるのは、精神的に消耗する。休日にふと鏡を見て「こんな顔してたっけ?」と思うような朝もある。
自分で自分を先生にしていることもある
ふと思う。周りが勝手に「先生」として見てくるだけじゃなく、自分自身もまた、そう振る舞わなければと思い込んでいるのではないかと。誰かが望む「先生らしさ」を自分で演じてしまっている。その仮面を脱ぐことに罪悪感を覚えるくらいに、肩書きに縛られてしまっているのだ。
「らしさ」に囚われる自分との戦い
司法書士たるもの、立ち居振る舞いも言葉遣いもきちんとしていなければならない。そんな「らしさ」に、自分で自分を押し込めてきた。でも本当は、疲れてるときは疲れてるって言いたいし、理不尽には腹も立つし、情けない日もある。それでも「先生」だからと押し殺してしまう。いつの間にか、自分が何者だったか見失いそうになる。
若い頃の理想の自分が今も呪縛してくる
駆け出しの頃に憧れた「理想の司法書士像」。誠実で信頼され、完璧に仕事をこなす姿に、自分もなりたいと思っていた。だが今、その理想に届いていないと感じるたび、自分にがっかりしてしまう。理想を掲げた過去の自分が、今の自分を縛ってくるという矛盾に、苦笑いしか出てこない。
相談されると嬉しいけど逃げたくもなる
「先生、ちょっと聞きたいんですけど」と言われるたび、信頼されてるのはわかる。けれどその反面、「またか…」と心の奥でため息が出ることもある。相談を断るわけにもいかず、でも自分の心がすり減っているときには、逃げ出したくなるのが本音だ。
これからの「先生」としての在り方
「先生」であることは、自分の一部であることは間違いない。けれど、それだけが自分ではないということを、もっと認めていきたい。弱さを見せることも、頼ることも、恥ずかしいことではないと、心から思えるようになるために。完璧じゃない「先生」もまた、信頼される存在になれるはずだと信じて。
「しんどいです」と言える強さを持ちたい
「しんどい」と言える勇気を持つこと。それが今の目標だ。仕事に追われ、人に囲まれていても、心は孤独だったりする。だからこそ、自分の弱さも含めて、人と関わっていけるようになりたい。完璧じゃなくてもいい。むしろそのほうが、共感してもらえることもある。
背伸びしないことで信頼されることもある
肩肘張っていた頃より、素直に「それはちょっと苦手かも」と言えるようになってから、依頼者との距離が縮まった気がする。「あ、先生でもそういうことあるんですね」と笑われたとき、ようやく人間らしくいられた気がした。背伸びをやめることで、信頼が深まることもあるのだ。
独身司法書士としての肩の力を抜く工夫
仕事終わりに缶ビールを飲む時間が、少しだけ肩の力を抜く時間になっている。結婚もしてないし、モテもしないけど、そんな自分でも今日一日頑張ったと褒めてやりたい。誰かの先生であり続けながら、自分の機嫌もとってやれるように、もう少し力を抜いて生きていこうと思う。