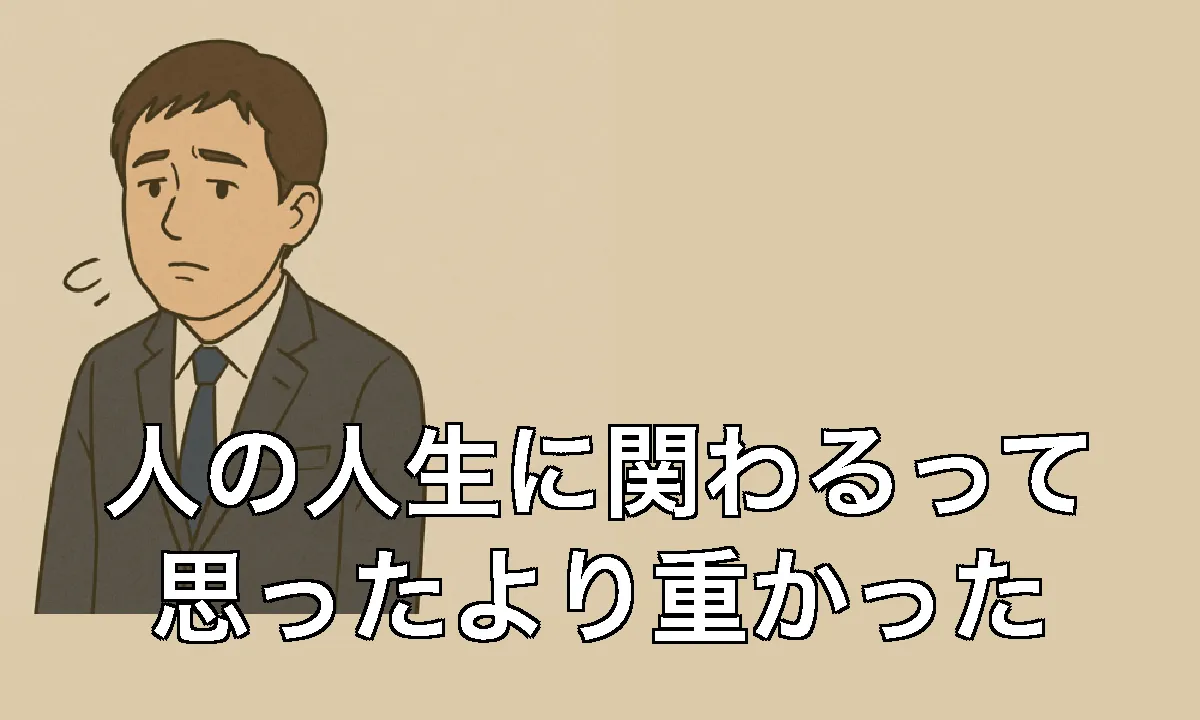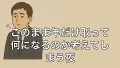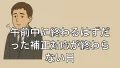人の人生に関わるって思ったより重かった
ただの書類仕事だと思っていたあの頃の自分に言いたいこと
司法書士を目指していた頃、正直言えば「なんか手堅そうな仕事」という程度のイメージだった。法律の知識が活かせて、そこそこ社会に貢献できる。でも今、実際に地方で事務所を開き、一人の事務員さんとともに毎日書類とにらめっこしている自分は、当時の甘さに呆れてしまう。司法書士の仕事は、人の人生にどっぷりと関わる。「手続き」だけで済まされない現実が、山のように押し寄せてくる。
「ミスできない」重圧が地味に肩に乗っかる
司法書士の仕事において、「うっかり」は許されない。たった一文字の記載ミスが、登記のやり直しや契約破棄、信頼の失墜につながる。普段は淡々と処理しているように見えるかもしれないが、内心は常にヒリヒリしている。確認に確認を重ねても、「絶対」はないのが現場の怖さだ。
午前中の確認ミスが一日中尾を引くこともある
ある日、地番の表記に誤りがあったまま登記を進めてしまい、午後になってから気づいた。すぐに法務局に連絡し、修正申請で対応できたが、それまでの数時間は、吐き気がするほど不安で落ち着かなかった。その日一日、集中力が戻ることはなかった。
訂正印のひとつで信頼を失う現場のリアル
訂正印が必要になった時点で、依頼人からの「なんで?」という視線が突き刺さる。説明しても納得はされない。結局、こちらの落ち度。どれだけ丁寧に仕事をしていても、一発で信頼が崩れるこの業界、しんどいと思わない日はない。
依頼人の「人生の節目」に無言で立ち会うつらさ
相続、離婚、借金整理――司法書士が関わる場面は、たいてい人生の大きな転機だ。でもこちらは、その感情の波に飲み込まれてはいけない。とはいえ、他人事のように割り切れるほど、人間は冷たくなれない。
相続の現場は、いつも誰かが泣いている
兄弟で遺産分割を巡って争っている場に立ち会ったことがある。兄が怒鳴り、弟が黙り込む。母の遺影が見守る中で、「遺産」という言葉がこれほど重く響くとは思っていなかった。終わった後、帰りの車でしばらく動けなかった。
離婚届の前で黙って立つことしかできない自分
とある女性が離婚に必要な手続きの中で、「これは最後のハンコになります」と言った瞬間、声を詰まらせた。何か言おうとしたけれど、言葉が出なかった。僕はただ、静かにうなずいた。それが正しかったのかどうかは、今でもわからない。
missing valueと向き合うのが僕の仕事
missing value――それは、記載されないこと、書かれなかった背景、声にならなかった思い。司法書士が扱う書類には、そんな「空欄」が無数に存在する。だが、その空欄にこそ、物語が隠れていることもあるのだ。
空欄に込められた“なかったこと”にしない責任
戸籍の除籍、登記簿の空欄、契約書の「該当なし」。それらが意味するのは、本当に「無」なのだろうか。実際には、語られなかった過去や、避けられた選択が詰まっている。だからこそ、僕は空欄を軽視できない。
登記簿の「記載なし」に漂う人間ドラマ
ある案件で、相続人の欄が一人しか記載されていなかった。普通ならスムーズな手続きだが、よく調べると、もう一人兄弟がいた。しかし絶縁状態で、連絡も取れないという。そこには「存在しなかったこと」にされた家族の物語があった。
見なかったふりができないから、疲れるんです
「自分に関係ないことだから」と割り切ってしまえば、楽にはなる。でも、それができない。missing valueにこそ目を向けることで、依頼人に寄り添える。それがこの仕事の本質だと信じている。でも正直、心がすり減るのも事実だ。
誰にも相談できないことだらけの現実
この仕事をしていると、誰にも話せない悩みが増える。ミスも、不安も、将来への不透明さも、飲み込んでしまうことが多い。話せる相手がいないことも、地方の一人事務所のつらさだ。
職場に同業者もいないし、飲みにも行かない
昔は事務所の近くに数人の司法書士仲間がいたが、みんな引退したり、他県に移ったり。今じゃ気軽に愚痴れる相手がいない。居酒屋に行くことも減った。誰かに話すより、静かに寝てしまったほうが楽だと感じるようになった。
事務員さんに愚痴るわけにもいかない
唯一のスタッフである事務員さんは、とてもよく働いてくれる。でも、経営のことや心のしんどさまで共有するのは違う気がして、つい強がってしまう。たまに「疲れてますね」と言われて、「まあね」と笑ってごまかすのがやっとだ。
モテないし、誰かに甘えることもないから
婚活アプリも試したけど、結局「忙しい人ですね」で終わる。誰かに「今日もがんばったね」と言われることもない。そういう日々に慣れてはいるけれど、慣れただけで、好きにはなれていない。
独りでやっていると、自分の存在意義が問われる
このまま何年続けるんだろう。自分のやっていることに意味はあるんだろうか。ふとした瞬間に、そんな問いが胸に浮かぶ。でも、やっぱりやめることはできない。理由はちゃんとある。
依頼人の言葉に救われたあの瞬間
「先生にお願いしてよかったです」。ある高齢の依頼人が言ったその一言に、何度も救われている。それは社交辞令だったかもしれない。でも、少なくともあの瞬間、自分の存在が誰かの助けになったんだと思えた。
「あなたに頼んでよかった」でようやく呼吸できた
忙しさで息苦しくなっていた毎日が、その一言で一気に晴れた。報酬じゃない、成功報酬でもない。ただ「頼ってもらえたこと」が、自分のアイデンティティをつなぎとめてくれた。司法書士って、たぶんそういう職業なんだと思う。
元野球部の自分が“背負う”のは書類よりも感情だった
高校時代、エースだった。マウンドに立ち、背番号1を背負っていた。あの頃はボールだけを投げていればよかった。今は、もっと重たいものを抱えている。ボールじゃなくて、人の人生を受け止める仕事。肩は痛くないけど、心は時々、痛い。