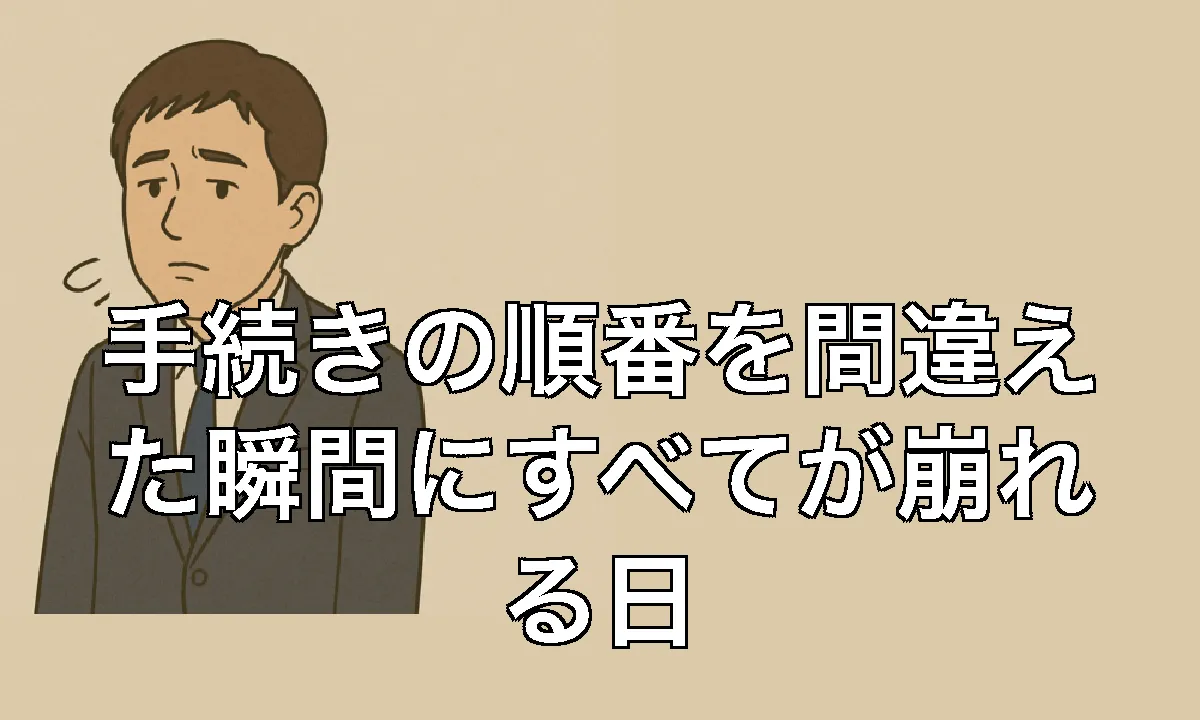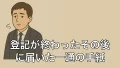手続きの順番に潜む落とし穴
司法書士の仕事には「順番」がつきまとう。登記でも相続でも、ただ書類を作ればいいというわけじゃない。順序を間違えると、あとで取り返しのつかないことになる。まるでドミノ倒しのように、一枚倒れたら全部倒れる。私は何度かそれを経験してきた。特に繁忙期や人間関係に気を取られていると、順序を誤るリスクが高まる。何気ない一歩が、大きなトラブルの入り口になってしまうのだ。
最初の一手が全体を決めてしまう
ある不動産売買の登記で、私は「所有権移転登記」を先に申請してしまった。本来なら抵当権設定登記が先だった。なぜか?それは融資実行のタイミングと深く関係していたからだ。銀行との約束では、抵当権設定の完了が融資の条件。その順序を間違えたことで、融資がストップし、売主も買主も銀行も怒り心頭。私のもとに電話が鳴りやまず、胃がキリキリと痛んだ。
登記申請でやりがちな順序ミス
登記にはいくつもの種類があるが、実務上の「順序」は決して軽視できない。相続登記にしても、遺産分割協議書の有無や戸籍の収集順によって進行が左右される。あるとき、相続人の一人が海外在住で、先に協議書を回したら内容を勝手に書き換えられ、全体が無効に。最初に戸籍を確認し、全員の所在を把握してから着手すべきだったのだ。
依頼人の都合と現実のギャップ
依頼人は「とにかく急いで」と言ってくることが多い。特に売買案件は日程がタイトで、関係者が多い分調整が大変だ。だが、その「急ぎたい」という思いに流されると、順番を無視して処理してしまいがちになる。現実には、順序を守らなければ結局すべてが止まり、余計に時間がかかる。依頼人の言葉に優しさで応えた結果、信頼を失うという皮肉な結末になることもある。
一つ間違えば全体がやり直しになる現場
司法書士の仕事は「一発勝負」が多い。書類を出してしまえば、訂正できることもあるが、多くは「補正通知」や「却下」になり、手戻りに膨大な時間を要する。法務局の窓口で冷や汗をかいた経験は、一度や二度ではない。書類は完璧でも、順序を間違えれば意味がないのだ。まるで野球の守備で一瞬の判断ミスが大量失点に繋がるように、小さな判断が大事故につながる。
補正じゃ済まない事態もある
補正通知ならまだ救われる。問題は「却下」だ。あるとき私は、登記原因証明情報に記載する日付を、誤って1日早くしてしまった。それが原因で申請自体が無効に。しかもその登記は第三者の権利が絡んでいたため、再申請時には状況が変わってしまい、内容が書き換えられた。関係者から「なんでこんなことに?」と問い詰められ、事務所の空気も重くなった。
書類を出す順番を間違えたあの日
あの日、私は疲れていた。前日ほとんど寝ておらず、朝から事務員と小さな言い合い。そんな中、登記書類をまとめて法務局へ。帰ってきてから気づいた。「あれ、添付すべき書類が…後から必要だったやつが先に行ってる」その瞬間、頭が真っ白になった。戻れるわけでもないし、言い訳もできない。ただ、ただ、自分の浅はかさに嫌気がさした。
後戻りできないスケジュールとの戦い
こうしたミスが一番痛いのは「時間がないとき」だ。売買契約日が迫り、金融機関も融資実行のタイミングを待っている。その中で一つの順序ミスが命取りになる。何とか再提出して補正に持ち込んだが、すでに信頼関係は揺らいでいた。書類のやり直しと同時に、自分の精神もすり減っていく。締切は待ってくれないし、誰も「大変ですね」なんて言ってくれない。
事務員さんとの連携ミスが招く混乱
私は事務員を一人雇っている。彼女は真面目で丁寧だが、人間だからミスもある。私もミスをする。そのミスが重なったとき、爆発的な混乱になる。順番を守る意識が甘いと、二人で自爆する。情報共有が足りなかったり、確認作業が雑だったりすると、どちらかが「やったと思っていた」状態になってしまうのだ。結果として、クライアントに謝罪しなければならない羽目になる。
優秀な事務員がいても油断は禁物
「彼女に任せておけば安心」という慢心が、逆に問題を招くこともある。彼女もまた私に対して「先生ならチェックしてくれるだろう」と思っていたかもしれない。ある日の相続登記で、委任状の署名欄が未記入のまま提出され、法務局から連絡が入った。お互い「確認したつもり」で、実際には誰も確認していなかった。優秀さに頼りすぎると、ミスは静かに忍び寄ってくる。
ダブルチェックが機能しなかった理由
ダブルチェックの制度を作っていても、気持ちが入っていないと意味がない。形式だけの確認では、ミスは見逃される。私も「見た」というだけで、じっくり読み込んでいなかった。どこかで「今回は大丈夫だろう」と思ってしまっていた。その油断が現実の損害になった。チェックリストを使っていても、それが形骸化していたら意味がない。機能させるには心が必要だ。
結局最後は自分の責任になる現実
事務所で起こるすべてのことは、結局私の責任だ。事務員のミスも、手続きの順番の間違いも、依頼人には関係がない。私が代表で、私の名前で業務が動いている。だからこそ、どんなに忙しくても「確認」と「順序」の意識だけは緩めてはいけない。誰のせいにしても意味がない。自分の責任として背負っていくしかないのだ。
心が折れそうになる瞬間をどう乗り越えるか
手続きの順番を一つ間違えただけで、すべてが崩れる。そんな日が何度かある。悔しさ、情けなさ、恥ずかしさ。全部まとめて、誰にも言えずに飲み込んで、それでも次の日も仕事はある。どうしてこんなにしんどいのかと思うこともあるけど、それでもやり直して、もう一度やるしかない。失敗はなくならない。でも、次は少しでも減らせるように。
やり直しの電話をかけるときの気まずさ
一番つらいのは、依頼人に「実は…」と連絡するときだ。声が震える。心臓がバクバクする。頭では「仕方ないミスだ」とわかっていても、感情はごまかせない。怒られないか、信頼を失わないか。そんなことを考えながら電話をかける。でも、多くの場合、相手は意外と冷静だったりする。むしろ自分が一番落ち込んでいる。そのギャップに、なんとも言えない寂しさを感じる。
失敗から学んだ段取りの重要性
私は元野球部だ。試合で勝つには段取りがすべてだった。ウォーミングアップ、守備位置の確認、サインプレー。ミスが出るときは、たいてい準備不足だった。今の仕事も同じ。段取り、つまり順番を軽視したら、負ける。準備を怠らず、先を読む。その癖を日々の業務にも活かすようにしている。プレッシャーはあるけど、だからこそ真剣に向き合える。
それでも今日も手続きを進める理由
どれだけ失敗しても、朝になればまた案件が来る。依頼人が待っている。自分が必要とされている。だから、辞めるわけにはいかない。順番を間違えたとしても、また正しい順序でやり直せばいい。完璧じゃなくてもいい。少しでも丁寧に、正確に、次につなげる。そうして今日も机に向かっている。それが司法書士という仕事だと、最近ようやく思えるようになってきた。