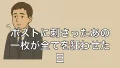朝のルーティンが崩れるなんて思いもしなかった
いつも通りの朝。事務所に向かう道も、コンビニのコーヒーも、事務員との「おはようございます」も、全部が何の変哲もない日常のはずだった。司法書士として働くようになって20年以上、そうそう想定外のことなんて起こらない――と思い込んでいた。だが、それはただの幻想だった。あの日、一本の電話が、その日常をまるごとひっくり返してしまったのだ。
いつもと変わらない朝に潜んでいた違和感
電話が鳴ったのは、午前9時20分。ちょうどメールチェックを終えて、書類を出そうとしていたときだった。最初はよくある問い合わせだろうと気にも留めなかった。でも、受話器から聞こえた声は、どこか緊迫感があった。「急ぎでお話があります」と、食い気味に切り出される。妙に胸がざわつく。私はそのとき、なにかが普通じゃないと察していた。
たった一件の留守電がすべての始まりだった
実は前日の夕方、一本の留守電が入っていたのを思い出した。「明日、折り返しください」とだけ言われていた、無機質なメッセージ。そのときは疲れていて、翌朝に回してしまったのだ。それが今回のトラブルの火種だったと後で気づいた。あと10分でも早く気づいていれば――何度もそう考えた。
コーヒーの味すら思い出せない午前中
電話を切った後、頭の中は真っ白になった。急ぎで対応しなければならない案件が、思わぬ方向でこじれていた。書類の誤記、相手方の怒り、役所との調整ミス。次々に降りかかる問題に、ただ立ち尽くすしかなかった。朝飲んだはずのコーヒーの味なんて、もう思い出せる余裕もなかった。
電話の主はまさかの相手だった
誰からの電話か、という話だ。それは以前から付き合いのある依頼者で、信頼関係も築けていると思っていた相手だった。まさか、その人からクレームが来るなんて夢にも思っていなかった。裏切られたような気持ちと、自分がなにか間違えたのではという不安が押し寄せてくる。
思い当たるフシはあるようでないのが怖い
具体的にどこでボタンをかけ違えたのか、自分でもすぐにはわからなかった。ただ、少し強引に進めた部分があったのは確かだ。忙しさにかまけて、確認を後回しにしたせいかもしれない。そういう“かもしれない”が積み重なると、どんな自信も崩れていく。
声色で察するプロとしての嫌な予感
相手の第一声で、空気の重さはすぐに伝わってきた。司法書士をやっていれば、そういう「ただごとではない雰囲気」に敏感になる。あの独特の沈黙混じりの口調、「すみませんけどね…」という言い出し方。電話越しの声色一つで、こっちの胃がキリキリと痛みだす。
「急ぎで」って言われたら逃げ道はない
一番つらいのは、「急ぎで対応してください」と言われること。相手にとっては当然の要求でも、こちらの手が回っていない現状を無視されているようで、苦しくなる。「今すぐ動いてくれませんか?」なんて簡単に言うけど、こちらにもタイミングや段取りがある。けれど、それを言えば言い訳になる。逃げ場はない。
事務所が戦場になる日
そこからはもう、嵐のような一日だった。電話を受けて、メールを飛ばして、書類を修正して、役所に駆け込んで…。事務員も察してくれてはいるけど、手一杯で助けを求めるのも気が引ける。気づけば昼ご飯すら食べずに走り回っていた。
怒涛の電話ラッシュと押し寄せる書類
一件の電話が引き金になって、他の案件にも連鎖的に影響が出始めた。対応が遅れたことで他の顧客からも確認が入り、それぞれに謝罪と調整。電話の受話器を置く暇もなく、プリンターから吐き出される書類を片手でつかみ、目を通す余裕すらない。こうなるともう、「こなす」しかない。
事務員も無言になる修羅場モード
事務所の空気が変わったのを感じた。事務員も何かを感じ取ったのか、無言で書類整理に集中している。こちらがピリピリしているのを感じさせないように、そっとサポートしてくれているのがわかる。こういうとき、言葉がない方がありがたかったりする。
自分で自分の段取りを壊していく感覚
皮肉なことに、一番迷惑をかけているのは自分自身かもしれない。焦れば焦るほど、段取りが崩れていく。優先順位が見えなくなり、処理が雑になる。まるで自分で自分の足を引っ張っているような感覚だった。
一通の電話が心に与えるダメージ
あの一本の電話で、私は一気に自己否定に陥った。「自分のやり方は間違っていたのか」「あのときの対応がまずかったのか」と、過去の出来事が脳内で何度も再生される。心のなかで繰り返す反省と後悔のループが止まらない。
「何をミスったんだっけ」がずっと頭を回る
書類の確認を怠ったのか、相手への連絡が不十分だったのか、それとも言葉選びが悪かったのか。ミスをしたのは確かだろう。でも、はっきりしないからこそ、余計に精神を削られる。「なんであんなこと言ったんだろう」「あの時やり直せたら」――後悔ばかりが溢れてくる。
根拠のない自信は秒で崩れる
正直、長年やってきているという自負はあった。「これぐらいなら大丈夫」という判断が、今回に限っては裏目に出た。仕事に慣れたぶん、どこかで手を抜いていたのかもしれない。そういう慢心に、今回のような出来事は容赦なく襲いかかる。
過去の仕事が走馬灯のように頭をよぎる
ひとつの失敗があると、なぜか過去の事例まで思い出されてくる。「あの時の依頼者も、ちょっと不満そうだったな」「あの登記、実はギリギリだったよな」と、今さら思い出してもどうにもならない記憶が押し寄せる。これはもう一種の職業病かもしれない。