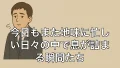心配してくれてたんですねと言われて
司法書士という仕事をしていると、依頼人との距離感に悩むことが多い。とくに自分のように、人との距離を詰めるのが苦手で、感情を表に出すのもあまり得意ではないタイプにとって、どこまで親身になればいいのか、どこからは踏み込みすぎになるのか、その境目がわからなくなる。そんなある日、ふとしたやりとりの中で、依頼人の方から「心配してくれてたんですね」と言われた。驚いた。そんなつもりはなかった。というより、そう見えていたことに気づいていなかった。そのひとことが、不器用に生きてきた自分の胸を、なぜだか少しだけあたためてくれた。
予想外のひとことに戸惑った昼下がり
その日は、登記手続きが少し遅れていた案件の対応で、バタバタしていた。依頼人には経過を報告しつつも、正直なところ、これ以上遅れると厄介になるなという焦りもあった。電話をかけたとき、いつものように淡々と報告をしていたつもりだったが、電話の最後にふと、「心配してくれてたんですね」と静かに言われた。その瞬間、一瞬、何も言葉が出なかった。「あ、そんなふうに聞こえてたのか」と思ったと同時に、何か恥ずかしいような、救われたような気持ちになった。
依頼人との距離感に悩んでいた日々
司法書士という立場上、依頼人とは一定の距離を保ちつつ、冷静に業務を進めなければいけない。感情に流されるのはプロじゃない、そんな風に思ってやってきた。でも、依頼人も人間、自分も人間。言葉ひとつ、態度ひとつで、不安にもなるし、安心もする。最近は特に高齢の依頼人が多く、「先生に頼んでよかった」と言われることもあるけれど、どう接すれば信頼してもらえるのか、まだ正解がわからないままだ。
どこまで踏み込んでいいのか分からない
若い頃、仕事に慣れていなかった頃は、失礼がないようにと距離をとることばかり考えていた。でも今は逆に、「この人は本当に大丈夫かな」と心配になることも多い。それでも、必要以上に詮索するのは失礼かもしれないと思い、言葉を飲み込むことが増えた。そんな日々の中での「心配してくれてたんですね」のひとことは、自分が踏み込みすぎたのではないかという不安をやわらげてくれる、思いがけないご褒美のようだった。
意識してなかったつもりの気遣い
「気遣ったつもりはないけど、気遣ってたんだな」と気づく瞬間がある。誰かに対して、特別な感情があるわけでもない。ただ、目の前の人が困っていそうで、自分にできることがあれば、少しだけでもと思った。だけど、そういう“ちょっとした行動”こそが、人の心に届くことがあるのかもしれない。その日は、たまたま電話口で、少しだけ声のトーンが柔らかくなっていたのかもしれない。無意識のうちに。
忙しさの中で出た無意識の行動
正直、日々の業務に追われていて、自分の言動にそこまで気を配ってはいられないことが多い。登記簿のチェック、役所とのやりとり、事務員への指示、郵送の確認……常に何かに追われている。けれど、そうした中でも、何気ない電話や書類の説明の中で、「この人、不安かもしれないな」とどこかで感じていたのだろう。自分で自覚していなかった“気づかい”が、言葉や声の温度ににじみ出ていたのだと思う。
事務員さんのひとことが背中を押した
電話を切ったあと、事務員さんが「先生、ちょっと声やさしかったですね」とぽつりと言った。普段、ぼそぼそと事務的に話すだけの自分にしては珍しかったのだろう。「そんなつもりなかったけどな」と言いながらも、心の中で「そうだったかもしれない」と思った。事務員さんの目はごまかせない。こういうふうに、人は誰かのフィードバックで、自分の輪郭を知るのかもしれない。
誰にも見られていないと思ってた
独身の自分は、仕事以外に人と接することがほとんどない。休日もたいていコンビニとコインランドリーの往復。だから、誰かに気づかれるとか、感謝されるとか、そんな機会は滅多にない。たぶん、誰にも見られてないと思っていた。だけど、その一言で、少しだけ気持ちが変わった。「ちゃんと伝わってたんだな」と思えたことは、不思議な励みになった。
独りよがりな仕事が思わぬかたちで届いていた
仕事は、どうしてもルーティン化していく。でもその中にも、「この人のために」「少しでも不安を減らせたら」と思ってやっていたことが、ちゃんと誰かに届いていたのかもしれない。普段はなかなか気づかないけれど、たった一言のフィードバックで、自分のやっていることに意味があると再確認できる瞬間がある。そんなとき、自分の存在が少しだけ報われたような気になる。
昔の野球部時代を思い出した瞬間
そういえば、高校時代の野球部でも、同じような気持ちになったことがある。ずっと補欠だったけれど、誰よりも声を出して応援していたら、試合後に監督から「お前の声が一番聞こえた」と言われた。報われた気がした。あの時と、今がちょっと似ている。評価されることじゃなくても、誰かに届いていたなら、それだけで十分なのかもしれない。
ベンチから聞こえたあの声援のように
あのとき、自分は選手としてグラウンドに立ってはいなかった。でも、声でチームに貢献していたと思う。今もたぶん、同じだ。司法書士として、表に出る仕事ではないけれど、誰かの生活の裏側で、少しだけでも支えになっていたなら、それが自分の役割なのだろう。誰にも届いてないと思っていた声援が、実はちゃんと届いていたように。
伝えるよりにじみ出るが効くこともある
無理に良いことを言おうとしたり、感動的な言葉を選ぼうとしても、たいてい空回りする。でも、不器用でも誠実に仕事をしていると、時にはそれがにじみ出て、相手に伝わることがある。今回のように「心配してくれてたんですね」と言われるのは、自分にとっては奇跡に近い。だけど、それが起きるなら、もう少しだけ頑張ってみようかと思えてくる。
人に伝えるのが苦手な司法書士のひとりごと
文章を書くのも、話すのも、決して得意ではない。それでも、こうして少しずつ言葉にしてみると、自分が何を感じていたのか、ようやく整理がついてくる。依頼人からの一言がなければ、たぶん気づくこともなかった感情だ。司法書士は、裏方のような仕事かもしれない。でも、その裏方が、誰かの心にちゃんと残っていることもあると知った。
それでも誰かはちゃんと見てくれている
事務所にこもって書類と向き合い、電話とメールに追われる毎日。モテもしないし、特に楽しいことがあるわけでもない。でも、誰かがちゃんと見てくれているなら、それで少し報われる。依頼人のひとこと、事務員の視線、昔の監督の言葉――どれも、自分という存在が無駄じゃなかったと思わせてくれる記憶だ。
モテなくても少しは役に立ってるのかもしれない
恋愛とは縁遠い。人付き合いもあまり得意じゃない。でも、「先生がいてくれてよかった」と言われる瞬間がある限り、モテる必要はないのかもしれない。役に立てること、それだけでもう、十分な存在理由になる。気づいてくれてありがとう、と思う。そして、少しだけ、また頑張ろうと思える。