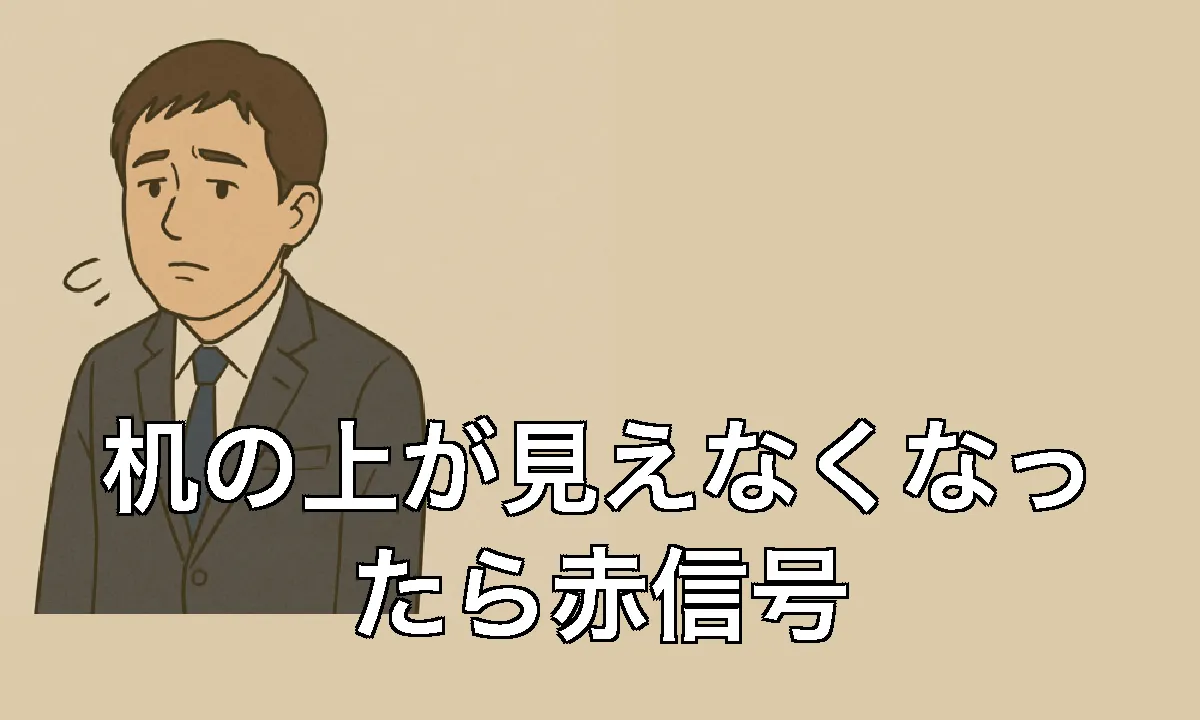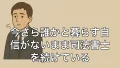机の上が見えなくなったら赤信号
気づけば紙の山に囲まれていた
気づいたときには、もう手遅れだった。パソコンの横に積んだつもりの申請書の控えが、いつのまにか高くなりすぎて斜めに傾いている。ファイルしようと思っていた書類が、付箋付きのまま机の奥でホコリをかぶっている。片付ける時間がないと言い訳していたけど、もしかしたら「片付けないことで、自分の忙しさを証明したかった」のかもしれない。けれど、その山は“頑張ってる証”ではなく、むしろ“崩壊の前兆”だった。
なぜこうなったのか整理する暇もない日々
毎日、登記の期日に追われて気づいたら夕方。午前中に「後で目を通そう」と思って積んだ書類はそのまま忘れ去られ、さらに新しい依頼が重なっていく。相談予約の電話が鳴って、FAXが届いて、印鑑証明が足りないことに気づいて、気がつけば昼食をとる暇もなかった日もある。そうしてどんどん“今度やろう”が山積みになっていった。忙しいのはありがたいことなのに、それを言い訳に、頭の中の整理も追いつかなくなっていた。
朝出した書類が夜には行方不明
たとえば、朝イチで確認した抵当権抹消の書類。どこかに置いたはずなのに、午後の打ち合わせ直前に見当たらない。焦って事務員さんにも手伝ってもらって探し回る。結果、プリンターの裏に落ちていた。笑えない。こういうことが増えてきた頃から、仕事の“質”に疑問を感じ始めた。効率とか段取り以前に、「基本的な管理ができていない」ことが、一番恥ずかしかった。
「あとで処理しよう」が積もる恐ろしさ
“あとで処理する”という選択肢が、実は一番危険だと気づいたのは最近のこと。後回しにしたものほど記憶から抜け落ち、気づいたときには依頼者に催促される。処理ミスではなく、“意識の抜け落ち”が一番怖い。人からの信頼は一瞬で崩れる。たかが紙一枚、されど一枚。その積み重ねに自分自身が押し潰されそうになるのだ。
片付けられない自分への自己嫌悪
机の上を片付けようとしても、どこから手をつけたらいいか分からない。どれも大事なものに見えるし、処分すべきか迷う。書類に囲まれていると安心するという人もいるけれど、僕の場合は単なる“逃げ”だった。目を背けたいタスクを紙の下に埋めていたに過ぎない。そして気づけば、「片付けられない自分」への苛立ちと情けなさに変わっていた。
「できる人」は机がきれいだというプレッシャー
ネットで見かける“デキるビジネスマン”は、机の上が整っていて、無駄な紙が一枚もない。そんな姿を見るたび、自分とのギャップに落ち込む。整っていないからダメなのか?いや、それだけではないけれど、少なくとも“見通しの悪さ”は仕事の判断にも影を落とす。シンプルに「どこに何があるか分かる状態」にすれば、精神的にもずいぶんと楽になるのに、それが難しいのだ。
見栄を張るより現実と向き合う
書類の山を“忙しい証”として誇っていた時期もあった。「俺、こんなにやってるんだぞ」と。けれどそれは、自分に対しての見栄であり、虚勢だった。結局、自分の弱さを紙の山で隠していただけ。整理ができていないことで誰かに迷惑がかかるのなら、それはもう“言い訳”では済まされない。現実と向き合うこと、それこそが自分を救う第一歩だった。
仕事が回らなくなってきたサイン
ある日ふと、「最近、うまくいかないな」と思った。申請書の誤記、提出忘れ、印鑑の押し間違い。以前はなかったようなミスが増えていた。それが「机の乱れ」とリンクしていることに気づいたとき、ようやく事の重大さを実感した。これは“時間がない”のではなく、“管理が崩れている”のだと。
書類の山は心の乱れの鏡
人間の心理は、環境に映し出されるという。机の上が乱れているとき、自分の心もどこかバラバラで、集中できていなかった。案件に対しても「流れ作業」的になってしまい、一件一件に向き合えていない。事務所に入った瞬間に感じる“圧迫感”も、書類の山のせいだった。片付けられないということは、心に余裕がないという証拠だったのだ。
依頼主の名前すら見落としそうになる
信じがたいことだけど、ある日、依頼主の名前を一瞬ど忘れした。ファイルの山をめくりながら、「えっと、この人…誰だっけ?」と。本当にまずいと思った。顔と名前が一致しないなんて、信頼関係以前の問題だ。書類が整理されていれば、見落とすことはなかったはず。仕事が立て込みすぎて、頭の中まで散らかっていた。
優先順位の迷子になる毎日
何から手をつけるべきか分からなくなる。すべてが“急ぎ”に見えて、結果、何も手につかない。やるべきことのリストアップすら追いつかず、目の前の山に途方に暮れる日もある。そんなとき、ふと「これはもう自分一人の力じゃどうにもならないかもしれない」と弱気になる。でも弱音を吐ける相手もいない。そうやって、さらに溜め込んでしまうのだ。
「整理」は仕事の一部だと痛感
ある日、先輩司法書士に言われた。「整理整頓ができていないなら、それはプロじゃない」と。耳が痛かったけれど、その通りだと思った。僕たちの仕事は“正確さ”が命。ミスを防ぐには、まず環境を整える必要がある。整理とは、決して“暇なときにやること”じゃない。日々の業務の中に組み込むべき、大切な工程なのだ。
片付けを後回しにするリスク
片付けを“後で”にすると、後のリカバリーに倍の時間がかかる。探し物に20分、ミスの修正に30分。結局、何も得していない。むしろ信用を失うリスクの方が大きい。片付けは面倒だけど、未来の自分を助ける行動でもある。それに気づいてからは、少しずつでも毎日手を動かすようになった。
自分だけのルールは限界がある
“自分だけが分かるルール”に頼るのは限界がある。もし体調を崩したら?事務員さんに引き継げる状態にしておかないと、事務所が止まってしまう。誰が見ても分かるような整理法にする。そう決めてから、ファイルの色分けや、案件別トレイなどを取り入れた。完璧じゃなくても、共有できる形にすることが、大事なのだと思う。