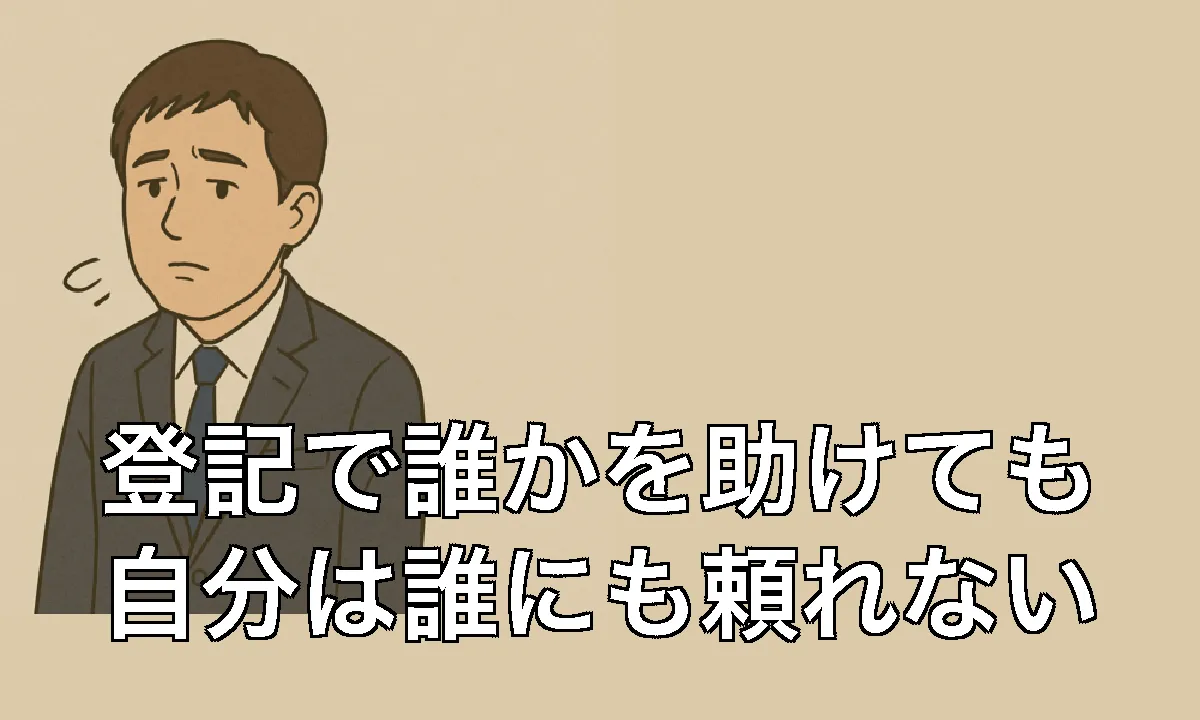人のために働くことがやりがいになっていた
司法書士という職業に就いた当初、自分の力で誰かの役に立てることがただただ嬉しかった。相続や売買など、登記を通じて手続きに困っていた方が安心した顔を見せてくれる瞬間。それが、自分の存在意義のように思えていた。特に、年配の方から「ありがとう、あなたがいてくれて助かった」と言われたときは、不思議と胸がじんと熱くなった。人の人生の節目に立ち会えること、それが自分の役割だと信じていた。
ありがとうの言葉が唯一の報酬だと思っていた頃
開業して間もない頃、報酬額も大したことはなかった。事務員を雇う余裕もなく、ひとり黙々と登記申請書を作り、法務局に通った。書類を提出する帰り道、ふと手帳を見て、次の依頼がない日には不安にもなった。でも、手続きが終わったあとにかけられる「ほんとに助かりました」という一言に支えられていた。金銭以上にその一言が自分の価値を証明してくれる気がして、それだけを頼りにやってこれた。
登記を通じて感じた人のつながり
とある依頼者の話が今も忘れられない。亡くなった父の名義のままの土地を相続するために訪れた女性。慣れない手続きに戸惑い、何度も「私じゃ無理です」と言っていた。だが、丁寧に説明しながら一緒に書類を整えていくと、次第に不安そうな表情が変わっていった。手続きが完了し、登記完了証を手渡したとき、泣きながら「父のこと、ちゃんと整理できました」とお礼を言われた。自分が役に立てた実感があった。
感謝されるたびに少しだけ報われた気がした
誰かに必要とされること、それが自分の居場所をつくってくれると信じていた。役所や銀行では冷たくあしらわれたという話をよく聞く中で、司法書士として寄り添うことができたとき、報われた気がした。「先生にお願いしてよかった」という言葉は、何度聞いても嬉しい。けれども、その喜びは長く続かない。依頼が終われば、その関係も終わる。誰かの問題は解決しても、自分の孤独は少しも減らなかった。
気づけば自分のことは後回し
誰かの書類を整えることには全力を尽くすのに、自分の通院や手続きはつい後回しにしてしまう。昼も夜も仕事が続くと、ふと「俺って何のためにやってるんだろう」と思うことがある。独身で子どももいないから、別に頑張らなくても誰かに迷惑がかかるわけじゃない。だけど、止まれないのだ。止まったら、どこかで何かが壊れてしまいそうで怖い。
誰にも頼らず相談もできず
事務所には一人の事務員がいる。彼女は真面目で気が利くが、愚痴を聞いてもらう相手ではない。気軽に飲みに行って相談できる友人も少ない。学生時代の野球部の仲間とはだんだん疎遠になった。連絡を取っても「忙しいだろうからまたな」と軽く流されて終わる。そうして誰にも話せないまま、心の中だけに疲れが溜まっていく。専門家なのに、自分の心の整え方はまるでわからない。
愚痴を言う相手がいない日々
週末にコンビニ弁当を買って帰る途中、思わず「はぁ…」とため息が出る。職場でのトラブルやクレーム対応も、誰かに話すことなく飲み込んでしまう。SNSで「仕事つらい」と書くことすらできない。見られたら仕事に支障が出るかもしれないから。かといって、話を聞いてくれる人もいない。独り言が増えた自分に気づいて、情けなくなる。
事務所を出た後の静けさがつらい
事務所の鍵を閉めたあとの無音の空気が苦手だ。仕事中は電話や人の声があるから気が紛れるが、帰宅するとその反動がくる。テレビをつけても、YouTubeを流しても、寂しさが紛れない夜がある。夕飯をつくる元気もなく、袋ラーメンで済ませたあと、食器を洗わず寝てしまう。朝起きてシンクを見て、ため息。また今日も誰にも頼れないまま一日が始まる。
事務員の前では弱音を吐けない
小さな事務所だからこそ、雰囲気は大事にしたいと思っている。雇っている事務員の前で「もう疲れた」なんて言えない。経営者としての自分と、弱音を吐きたい自分が頭の中でぶつかり合う。たった一人しかいないスタッフを不安にさせたくないから、つい無理をしてしまう。笑顔を作ることが仕事の一部になってしまった。
経営者としての顔と人間としての顔
事務員のミスにも、なるべく穏やかに対応するようにしている。怒ったところでお互いの関係が悪くなるだけだし、自分にとって彼女は唯一の戦力だ。だけど本音では、「もう少し気を利かせてくれたら」と思うこともある。言えないけれど。でもそんな自分を責める。なんだかんだで、人に甘えられない性格なんだと思う。
孤独と責任の狭間で揺れる
仕事が増えるたびに「ありがたい」と思う一方で、誰かと分かち合いたい気持ちが強くなる。売上が伸びた日も、トラブルが起きた日も、ひとりで抱えて処理するのが当たり前になっている。責任感が強い性格が仇になって、気がつけば「一人でやるしかない」と思い込んでいた。だけど本当は、誰かに「大変だったね」と言ってもらいたかった。
忙しさの裏で置き去りにされた自分の人生
気づけば、自分の人生がどこかで立ち止まっていることにすら、気づけなくなっていた。まるで、他人の人生の手続きを一生懸命進める代わりに、自分の人生の申請は棚の奥にしまってしまったような感覚。ふと気づくと、友人は結婚し、子育てをし、家を買っていた。自分はというと、誰とも住まず、将来のこともぼんやりしたまま、今日も登記に追われている。