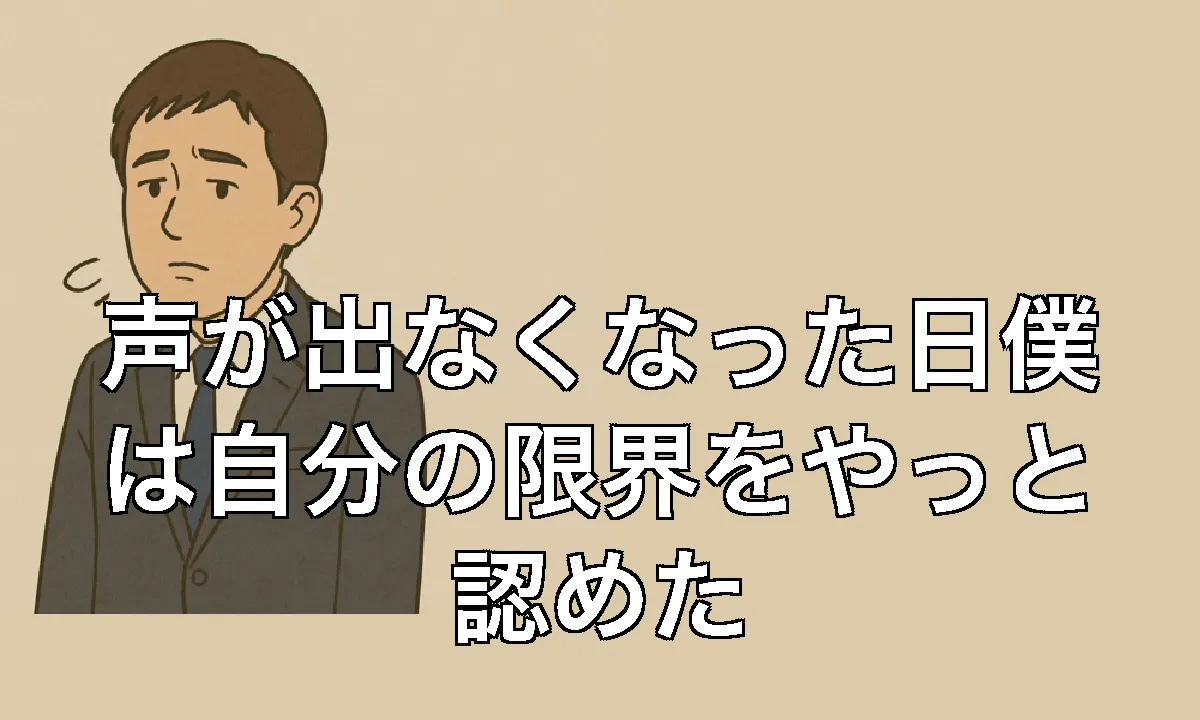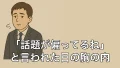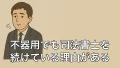あの日突然声が出なくなった
朝からびっしり面談の予定が詰まっていた。相続の相談、会社設立の相談、離婚後の名義変更の相談……。次から次へと相談者が訪れ、昼休憩も取れずに話し続けた。最初は喉が乾く程度だったが、午後3時を過ぎたあたりで声がかすれ始め、夕方には完全に出なくなった。文字通り「声を失った」。その時初めて、これはただの疲れじゃないと気づいた。自分が思っている以上に、心も体も限界だったのだ。
午前から詰まりっぱなしの面談地獄
地方の司法書士事務所は、都市部と違って“ついでに寄る”相談が多い。午前中の一人目が予定時間を30分オーバーし、そこからどんどんズレ込み、午後には2人ほどドタキャンが出るも、それすらありがたいと思ってしまうほどの詰まり具合だった。話を聞くのが仕事とはいえ、限度はある。途中で「あとどれくらい喋るんだろうな」と自分の喉を気にしながらも、顔には出せなかった。
「ちょっとだけいいですか」が何時間も続く
「10分だけ相談したいんですが…」という依頼者に限って、1時間は帰らない。しかもこちらが遮ることはなかなか難しい。優しそうに見えるのが悪いのか、居心地がいいのか、とにかく話し込まれる。そして「これって無料ですよね?」と確認される。体力も声も削られながら、なぜか罪悪感まで抱いてしまう始末。いやいや、こっちが聞いてほしいくらいだ。
気づいたときには喉がヒリヒリしていた
夕方17時。最後の面談が終わった瞬間、喉が焼けるように痛くなった。声を出そうとしても、空気しか出ない。「あ、やばいなこれ」と直感した。でもそのときに浮かんだのは「明日の予約どうしよう」だった。声を失った司法書士って、どんな存在だよと自嘲しながら、無理をしてでも乗り切るか、休むかの葛藤が始まった。結局、休まなかった。喉にスプレーしてごまかした。
黙ったら黙ったで気まずいのが司法書士
司法書士という職業は、書類仕事が中心と思われがちだが、実は“話す仕事”でもある。相談、説明、交渉、説得。全部言葉で成立する。だから声が出なくなると、実務はできても業務が止まる。まるでギターの弦が切れた音楽家みたいなものだ。黙っていると「体調悪いのかな?」「怒ってるのかな?」と相手が気を使う。だから無理してでも話してしまう。それが、また悪循環になる。
話せないだけで信用を失いそうな恐怖
特に初対面の相談者は、こちらの第一印象がすべてだ。「声が小さい=頼りない」「説明が淡々=冷たい」と受け取られがち。声が出ない日、説明が不十分だったのか、依頼を断られたことがあった。そのとき、ものすごく凹んだ。「なんでこんな仕事選んだんだろう」と。でも、また翌日は普通に事務所を開ける。根が真面目すぎるのか、自分に厳しすぎるのか。
声を失っても依頼は止まらない現実
休んだとしても、仕事が消えるわけじゃない。書類もメールも山積みで、事務員ひとりでは到底回らない。体調が悪いからといって、優先順位を下げてもらえる職業ではないのがつらいところ。むしろ「早くしてもらえますか?」とプレッシャーが増す。声が出ないときに限って、電話がよく鳴るのはなぜなのか。神様の悪戯にしては、だいぶ性格が悪い。
結局書類は山積み誰も手伝ってはくれない
「忙しそうですね」と言われることはあっても、「手伝いましょうか」と言われることはない。声が出なくなったからといって、誰かが助けてくれるわけでもない。そんな幻想は捨てるべきだと、身をもって痛感した日だった。司法書士って、ある意味“孤独な職人”だ。音がなくても、書類は待っている。気づけば一人で黙々とハンコを押していた。
無理が当たり前になっていた日常
声が出なくなるまで気づかなかったけれど、無理していたのは喉だけじゃなかった。肩も腰も、頭も心も、すべてが限界寸前だった。だけど、地方の小さな事務所では代わりがいない。元野球部で「喉が潰れるまで声を出せ」と言われて育ったせいか、どこかで“頑張って当然”という思考になっていた。でもこの仕事においては、それが自分を壊す原因になっていた。
喉だけじゃない体のあちこちが悲鳴をあげていた
寝ても疲れが取れない。腰が痛くて朝起きられない。目の奥がズーンと重い。そんな状態が続いていたのに、「まぁこんなもんだろう」と流していた。司法書士は健康診断にも行く余裕がない。いや、行こうと思えば行ける。でもその間に溜まる仕事を考えると足が重くなる。気づいたときには、声だけじゃなく、自分全体が“限界”を越えていたのだ。
元野球部だからって根性で乗り切れるわけじゃない
部活時代、「喉が潰れるまで声出せ」と言われていたのを今でも思い出す。あの頃は若さでなんとかなった。でも45歳、無理がきく年齢じゃない。無理して乗り切った先にあるのは、自己犠牲だけだ。仕事を続けるためには、まず自分を大切にするべきだった。根性論で片付ける時代じゃない。もっと早く、それを認めるべきだった。
優しさが裏目に出るこの仕事の理不尽さ
つい相談者に合わせすぎてしまう。少しでも安心して帰ってもらいたい。その気持ちが強すぎて、自分の声も心も後回しにしてきた。けれど、優しさが必ずしも感謝されるとは限らない。むしろ「もっとやって当然」と思われることすらある。そうなると、どこかで“搾取されてる”感覚になってしまう。それでも、自分を責めてしまうのが、やっぱり優しさの裏返しなんだと思う。
声を失って初めて聞こえてきた自分の声
声が出ない時間、電話を事務員に任せ、ただ黙って机に向かっていた。その静けさの中で、ようやく聞こえてきた。「もう限界です」という自分の声。普段、他人の声ばかりに耳を傾け、自分の心の声にはまったく向き合っていなかった。皮肉なことに、声を失って初めて、ちゃんと自分と対話できたのだった。
「もう限界です」と自分自身が言っていた
「疲れている」ではなく「壊れかけている」。その違いに気づくのは簡単じゃない。でも、体はちゃんと信号を送ってくれていた。声が出なくなったのは、ただの炎症じゃない。無理しすぎるなという最終警告だった。あのとき、自分で自分を無理やり黙らせてしまったんだなと、今なら思える。
忙しさにかまけて置き去りにしていた本音
「これが俺のやりたい仕事なのか?」「このまま続けていいのか?」そんな問いを心の奥にしまい込み、日々の業務に埋もれていた。だけど、それに向き合うのは怖かった。なぜなら、本音に気づいてしまったら、止まらなくなりそうだったから。でも、あの日声を失って、ようやく「立ち止まること」の大切さを受け入れられた。
少しの休みすら罪悪感に変わっていた日々
休んだら負け。そんな感覚が染みついていた。でも今は思う。声が出ない日くらい、堂々と休んでもよかったんじゃないか。誰も助けてくれない世界だからこそ、自分くらいは自分を守るべきだった。少しの休みが罪悪感に変わるような働き方、それ自体がすでに“異常”だったんだ。
今だから伝えたいこれから司法書士を目指す人へ
司法書士という仕事は、やりがいがある。でも同時に、自分をすり減らしやすい仕事でもある。無理をしないと回らないと思ってしまいがちだが、それは違う。長く続けるには「自分の声」に敏感であることが大事。声を失う前に、心の声を大切にしてほしい。それが、誰かを支える力にもなる。
がむしゃらだけじゃもたない世界です
最初はがむしゃらに走っていい。でも、それをずっと続けるのは無理だ。休む勇気も、立ち止まる力も、大事なスキルの一つ。がむしゃらの先には、燃え尽きるしか残っていないこともある。だからこそ、ちゃんと「休む練習」をしておいてほしい。
自分を守ることが依頼者を守ることにつながる
司法書士が倒れたら、依頼者も困る。だから、自分を守ることは、仕事を全うするための責任でもある。体も心も、声も。どれも大切な“資本”だ。それを削り続けた先には、何も残らない。だからこそ、ちゃんと守ってほしい。自分自身を。
声を失う前に気づいてほしい大事なこと
「声を失う前に、声を聞いてほしい」。それが今の自分からのメッセージだ。もし同じように、無理をしすぎている司法書士がいるなら、立ち止まってほしい。声が出なくなる前に、体が動かなくなる前に、自分を振り返ってほしい。それが、長く仕事を続ける唯一の方法かもしれない。