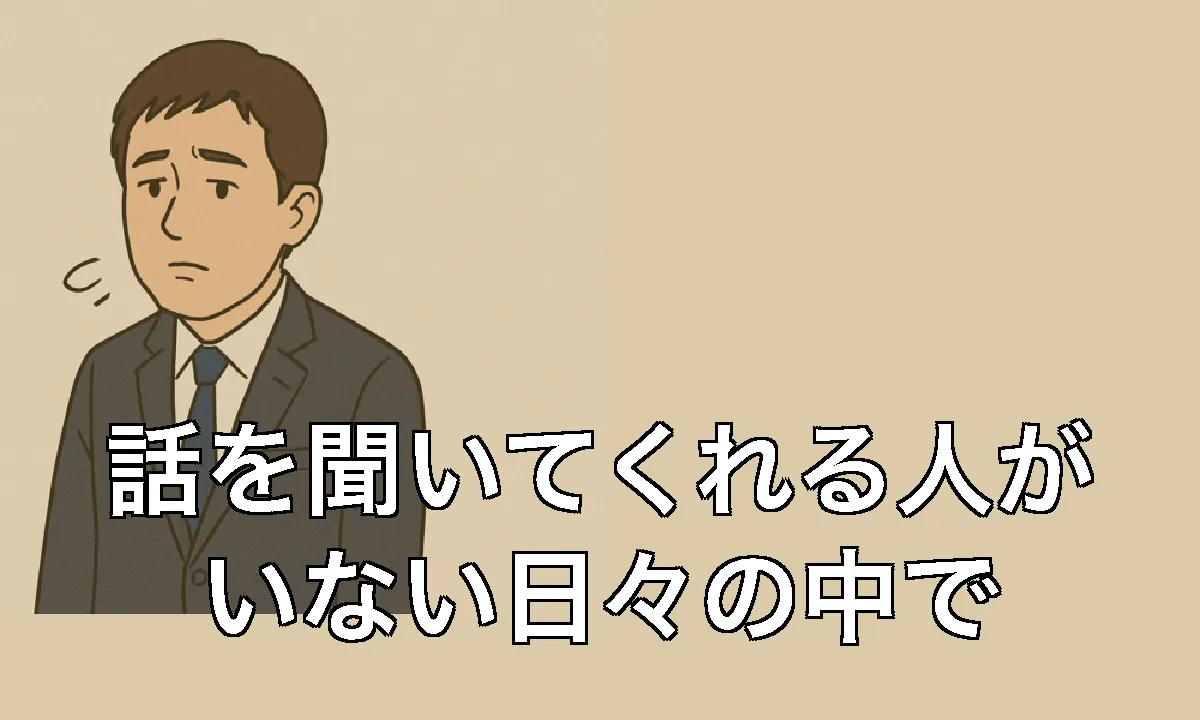朝のコーヒーがいつもより苦かった理由
朝、事務所の鍵を開けて、コーヒーメーカーをセットするのが日課だ。誰に言うでもないが「さて今日もか」と小さくつぶやく。たぶん、心のどこかで「誰か聞いててくれたらな」なんて思っている。事務員さんは朝一で届く郵便物の仕分けを黙々と始めていて、こちらも気軽に話しかけるような空気ではない。そんな中でひとり飲むコーヒーは、どんな銘柄でも、どこか味気ない。仕事の前に、誰かと「おはよう」以上の会話ができたなら、違う一日になったんじゃないかと思ってしまうのだ。
一日の始まりに誰とも会話がない
事務所を構えたばかりの頃は「静かな朝もいいもんだ」と思っていた。ところが、年を重ねるごとにその「静けさ」が、妙に心に堪えるようになってくる。朝のルーチンは確かに整っているし、仕事は順調といえば順調。けれど、ふとしたときに「これ、誰かに話したいな」と思っても、それを話す相手がいないことに気づく。会話って、仕事のためじゃなく、自分の気持ちを整えるためにも必要なんだなと痛感する。誰かと朝から雑談できるって、それだけでちょっと元気が出るのに。
事務員さんとの距離感は保ちたい
もちろん事務員さんはいる。でも、彼女にプライベートな話をするのは違うと思っている。年齢差もあるし、雇っている側としての立場もある。「昨日、実家から野菜届いたんですよ」みたいな雑談すら、踏み込みすぎかなと考えてしまう。そうなると、どうしても本音の会話は自分の中にとどまり、外には出せない。仕事が忙しいときはそれでも気が紛れるが、ふとしたタイミングで「誰にも話してないな、最近」と気づくと、思っていた以上に心がしんとしているのに気づく。
愚痴をこぼす場所がない現実
以前、同業の先輩が「たまに喫茶店のマスターに全部話してる」と笑っていた。うらやましいと思った。僕にはそんな場所すらない。居酒屋に行っても、常連になるには気力がいるし、誰かに「最近さ、ほんとつらいんだよね」と言えるほど、自分をさらけ出せない。結果、愚痴はすべて自分の中で完結する。でも、愚痴って誰かに話してこそ、半分くらい軽くなるものだと思う。ひとりで抱え続けると、仕事に影響は出ないけど、笑顔が薄くなっていく。
電話のベルが鳴るたびに感じる緊張と孤独
電話が鳴ると、事務所に響く音がどこか冷たく感じる時がある。仕事の電話にしては、妙に神経がピンと張ってしまう。用件を淡々と聞いて、処理して、切る。それで終わり。でも、電話越しの声に「あ、今日もお疲れさまです」とか「大変ですよね」なんて一言があると、やけに胸に沁みたりする。逆に、無機質な対応に心がすり減るときもある。電話という「話す」手段が、心を通わせるものではなくなったと感じるのは、自分の感情を置く場所がないからかもしれない。
誰かと話すのが仕事でも、自分の話はできない
司法書士という仕事は、人の悩みや不安、手続きを受け止める仕事でもある。話を聞くことには慣れているし、丁寧に対応しているつもりだ。けれど、だからこそ「自分が話す側になること」がない。何かを話したとしても、仕事絡みの話で終わってしまう。事務所の外に出て、他士業との打合せなどで話す機会があっても、それはあくまで業務の延長線。気を張ったまま帰ってくることの繰り返しで、「今日は自分の話ができたな」と感じる日は、まずない。
相談を受ける側の孤独
お客さんから信頼されるのは嬉しい。でも「先生にだけは相談できます」と言われるたびに、ふと自分の孤独が強調される気がする。こちらは誰にも相談していない。いや、できない。プロとしての自分が当たり前になりすぎていて、「自分も誰かに頼りたい」「誰かに聞いてもらいたい」なんて思っても、それを口にすること自体が難しい。相談を受ける側が、誰にも頼れずに沈んでいく。それがこの仕事の見えにくい落とし穴なのかもしれない。
会話しているようで心は閉じている
会話の回数は多い。でも、心を開いた会話はどれだけあっただろう。言葉のキャッチボールをしているようで、実際は形式的なやり取りに終始してしまう。「書類は〇日までです」「こちらでお預かりします」…そんな言葉の中に、自分の気持ちは一切入っていない。人と接しているのに孤独を感じるのは、相手の言葉より、自分の沈黙の方が強く心に残るからだ。誰にも言えない本音が心の奥にたまっていく。そういう沈黙が、少しずつ自分を蝕んでいる。
夜のコンビニでふと立ち止まった理由
仕事帰りに寄ったコンビニで、ふとレジ横のカウンターに目がとまった。カップ麺と缶ビールを買うサラリーマン。誰かと笑って話している学生。ふと、「自分は何を買いに来たんだっけ」と我に返る。家に帰っても、話す相手がいるわけじゃない。ついで買いしたスイーツを袋に詰めながら、「誰かに“これ一緒に食べようよ”って言える日、くるのかな」とぼんやり考えてしまった。仕事で疲れた頭のまま、夜の街にぽつんと立つ瞬間が、一番「話したい」と思う時かもしれない。