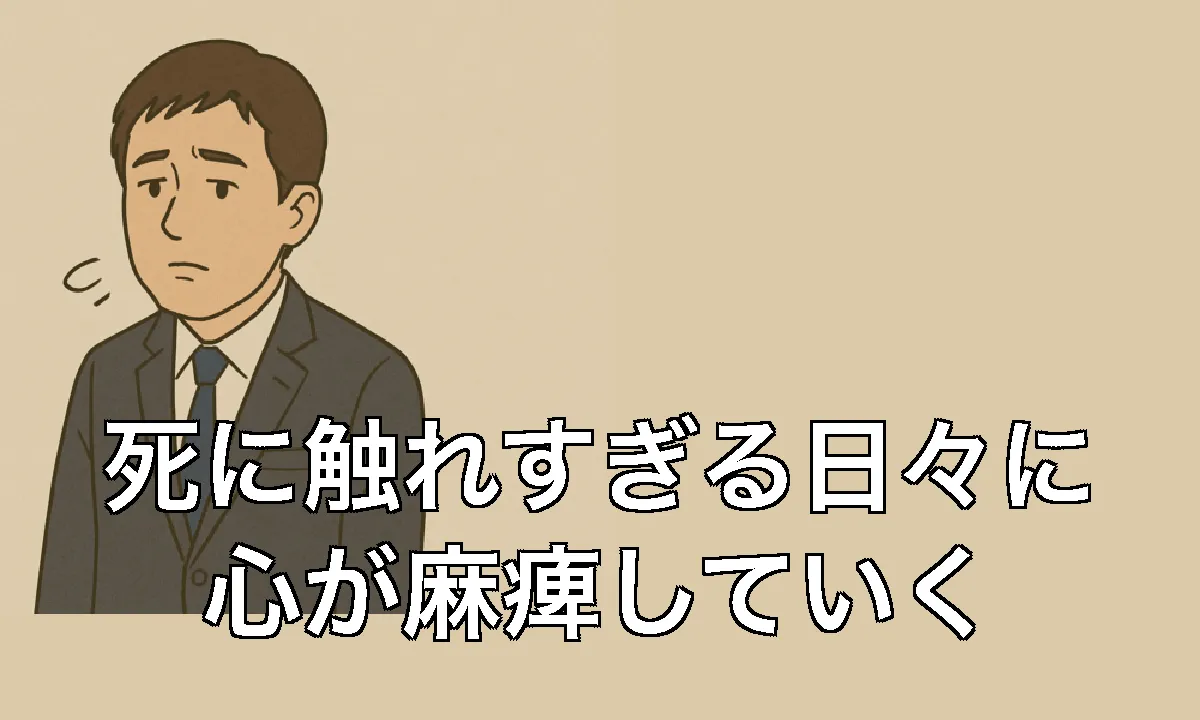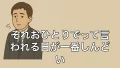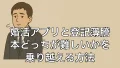ふと気づけば死ばかり見つめていた
司法書士の仕事を長年やっていると、ある日ふと「最近、笑顔を見たことがあったか?」と自問する瞬間がある。相続、遺産分割、後見、そして死後事務。どれも「死」という現実が前提になっている。朝から晩まで、亡くなった方の名前を何人も書類に記入しているうちに、感情が摩耗していくのを感じる。そんな日々がもう何年も続いている。気づけば、私は日常の中で無意識に「誰が死んだのか」にばかり意識を向けている。人の生きた証に触れているはずなのに、それを感じる余裕すらなくなっているのかもしれない。
登記簿の向こうにある現実
相続登記の依頼を受けるとき、相談者の目には疲れが見える。愛する人を亡くし、まだ気持ちの整理もつかぬまま手続きに追われる姿には、いつも胸が痛む。だが、こちらは「被相続人」「相続人」「登記原因」といった無機質な言葉を機械的に処理する役割を担っている。丁寧に説明し、気遣いも忘れないようにしているが、心のどこかでは「またこのパターンか」と思ってしまうこともある。登記簿の記載事項に過ぎないと自分に言い聞かせながら、亡くなった人の人生に線を引いていく仕事。その冷たさに、時折自分自身が怖くなる。
相続の手続きが日常になるという異常
たとえば、月に20件以上の相続関連案件を扱うと、死は日常の風景の一部になる。初めてこの仕事に就いた頃は、1件ごとに胸が締め付けられるような思いをしていた。だが今では「いつ誰が死んでもおかしくない」と無感情に受け止めている自分がいる。これが普通なのだろうか。感情を失わなければこの仕事は続けられない。だがそれが「異常」であるという感覚だけは、どこかに残しておきたいとも思う。私たち司法書士は、死の後片付けを担う役目をしているという意味で、ある種の死の番人なのかもしれない。
顔も知らない人の死を数える日々
一度だけ、亡くなった方の顔写真を持ってきた依頼者がいた。「こんな人だったんですよ」と言われて見せられた笑顔に、思わず涙が出そうになった。その瞬間、自分が“誰のために何をしているのか”を思い出した気がした。けれど、ほとんどの案件では、亡くなった方の顔も声も知らないまま、ただ書類上の処理をして終わる。その人がどう生き、何を大切にしていたのかなど知る由もない。何人もの死を扱いながらも、記憶に残るのは一握りだけ。そうして自分もまた、無感動な処理者になっていく。
死が身近すぎて何も感じなくなる
「また相続の案件か」そう思ってしまう自分に、嫌気が差すことがある。死は本来、重く尊いものであり、誰にとっても一度きりの大切な節目のはずだ。しかし私の職業柄、それが“案件”として処理される数の一つになってしまっている。感情が追いつかないほど多くの死に触れてきた結果、心が鈍くなっているのだ。冷たい人間になったのではないかと自分を責める夜もある。だけどそれを口に出せる相手もいない。誰もが強くあれと望むからだ。
「亡くなった方は…」の一言で始まる会話
「亡くなった方は…」と切り出すとき、相手の表情が一瞬曇るのがわかる。けれどその言葉を言わなければ、業務は進まない。「死」を前提にした会話が当たり前になると、それに伴う配慮や思いやりが後回しになってしまう。まるで定型文のように語られる死は、人のぬくもりを失い、冷たい言葉だけが部屋に残る。相談者の中には、そんな事務的なやり取りに涙を流す方もいる。「あの人は物じゃない」と言われたこともあった。そのとき、私は胸が苦しくなり、ただ黙って頭を下げることしかできなかった。
涙も出なくなるのは冷たいせいか
昔は葬儀の話を聞いただけで涙がこぼれた。だが今は、どんなに悲しい話を聞いても、心が動かなくなっている自分がいる。それが「慣れ」なのか「冷たさ」なのか、自分ではわからない。涙を流すことが優しさだとは思わないが、感情が動かなくなるのはどこか壊れているようで怖い。そんな自分を他人に見せるのが怖くて、余計に無表情になっていく。人としての機微を失わずに、士業としての冷静さを保つ。そのバランスが取れないまま、今日も机に向かっている。
それでもやめない理由がある
こんなに心を削られる仕事を、なぜ続けているのかと聞かれれば、即答はできない。でも、やめようとは思わない。不思議なことに、どこかで「自分がやらねば」という意識があるのだ。遺された人たちの不安を少しでも和らげることができるなら、それだけでいい。そんな小さな使命感だけが、続けている理由なのかもしれない。元野球部で「最後までやり切ること」の大切さを叩き込まれたせいかもしれない。
遺された人の笑顔が唯一の救い
ある依頼者が手続き完了後にこう言った。「あなたに頼んでよかったです。ホッとしました」。その瞬間、胸の奥に温かいものが広がった。死を扱う日々の中でも、こうした瞬間があるから救われる。たとえ涙が出なくても、たとえ感情が麻痺していても、誰かが安心できるなら、この仕事には意味がある。人の死を、遺された者の未来に変える手助け。それが司法書士としての役割なのだと、自分に言い聞かせている。
「助かりました」のひとことがすべて
書類の山と格闘したあと、ポツリとこぼれる「助かりました」のひとこと。その言葉を聞くたびに、「自分のしていることには意味がある」と思える。報酬よりも、効率よりも、その一言が一番の報酬だ。死という重たい現実を前にして、ほんのわずかでも支えになれたのなら、それで充分だと、自分を納得させる。心がすり減っても、そう思える瞬間がある限り、この仕事はやめられない。
自分にしかできない仕事だと信じたい
時代が変わっても、どれだけAIが進化しても、人の死を「扱う」仕事には人の心が必要だと思う。冷たく見えるかもしれないけれど、手続きを正確に、そして丁寧にやり切ることが、残された人たちの支えになる。それは、マニュアル通りにはいかない。「人の死に慣れてしまった自分」を責める日もあるけれど、だからこそ、人に寄り添える力も少しだけあると信じたい。誰かがやらなきゃいけないなら、俺がやる。それくらいの覚悟で、今日も事務所に向かっている。