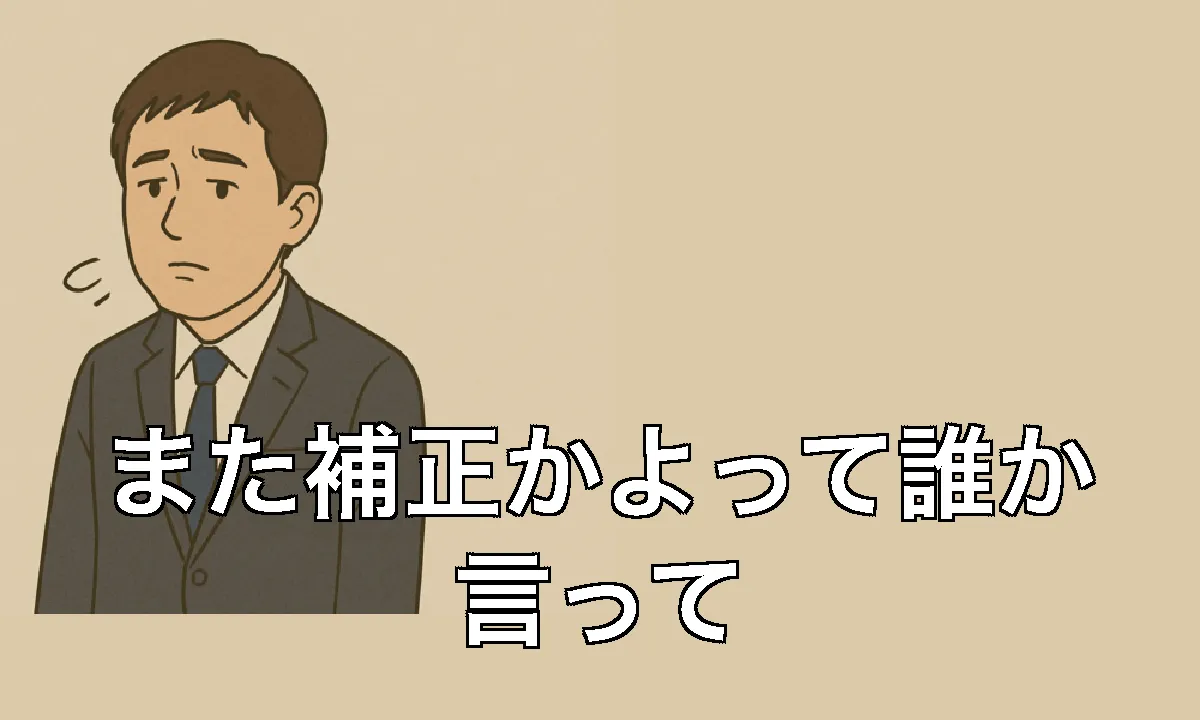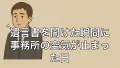補正通知が来るたびに心が折れる
「またか…」という気持ち、司法書士なら一度や二度じゃないはず。僕の事務所にも、週に何度かのペースで補正通知が届く。そのたびに、胸の奥にずしんと重いものが落ちるような感覚になる。自分の不注意か、それとも法務局側の読み違いか。理由はどうであれ、事務所としては「ミス」として扱われる。地方でひとり事務所を切り盛りしていると、この一枚の紙が一日の空気を決めてしまうのだ。
「またか…」と声に出してしまう瞬間
封筒を開けた瞬間、思わず「また補正かよ…」と声に出してしまったことがある。事務員さんの前だったのに、感情が抑えきれなかった。補正通知の見慣れたフォーマット、赤ペンで引かれた訂正箇所。書類を見返すと、確かに自分の確認不足だった。だから余計に情けない。心の中では「一度で通して当然だろ」と思われているような気がして、どんどん沈んでいく。
午前中の仕事のリズムが崩れる
補正通知が届くのはたいてい朝の郵便。だから、朝一番で気持ちが落ち込む。これから始まる一日の予定が、補正対応に食われていく。書類を修正して、再提出して、電話で確認して、依頼人にも連絡して…。本来なら他の業務に集中できるはずの時間が、たった一枚の通知でかき乱される。いつも思う、「この補正がなければ、もっと建設的な一日になったのに」と。
たった1文字のミスでも容赦ない補正
先日は、住所の番地に「-(ハイフン)」を入れ忘れたというだけで補正通知が来た。確かに正式表記ではあるが、それで?と思わずにはいられなかった。依頼人にとってはどうでもいいような細部でも、法務局は見逃さない。こっちは人間なんだから、1ミスくらい大目に見てよ…そんな言い訳すら、無力に感じる毎日だ。
補正がもたらす自信喪失の連鎖
補正通知を受け取るたびに、自信が少しずつ削れていく。最初のうちは「まあ仕方ない」と思えても、連続で来ると「自分は司法書士に向いてないのかも」と思い始める。依頼人の信頼も裏切っているようで、申し訳なさが積もっていく。特に小さな事務所では、自分のミスがダイレクトに事務員にも影響する。それがまたプレッシャーになる。
「あのとき確認したのに」と自分を責める
記憶をたどると、確かに確認した気がする。でも、見逃している。これは単なる見落としなのか、それとも慢心なのか。チェックリストは毎回使っているし、手順も変えていない。けれど、なぜかすり抜けるミスがある。ミスをするたびに、自分のやり方全部を否定されているような気になる。「自分はやっぱりダメだなあ」と、ため息が止まらない。
事務員さんの視線も気になる日
事務員さんは何も言わない。でも、補正通知を机の上に置いたときの沈黙が重い。あの空気が辛い。こちらの不備で二度手間をかけさせていることが、申し訳なくてしょうがない。別に怒っていないとわかっていても、「またですか…」という無言の圧を勝手に感じてしまう。たぶん、全部自分で勝手に背負い込んでいるだけなんだけど、それが現場だ。
補正との付き合い方を見直す
補正通知をゼロにすることはたぶんできない。人間だから。だから、どう付き合うかを考えるようになった。僕にできるのは、減らす工夫と、受け止め方を変えること。補正が来たときの落ち込みを少しでも軽くする方法を、自分なりに模索している。気分転換のタイミングを決めたり、ミスを共有して再発防止につなげたり。些細なことでも、自分のためになる。
チェックリストは増えていく一方
補正が来るたびに、チェックリストは1行ずつ長くなる。初期の頃は5項目だったのに、いまや20を超えた。「そこまでしないと通らないのか…」と思うこともあるけれど、現実は甘くない。ひとつひとつを丁寧に確認することで、補正の数は確かに減ってきた。でも、全部防げるわけじゃない。だから、「漏れたらすぐ直せばいい」くらいの気持ちも大切にしている。
それでも見逃す人間の限界
どれだけ注意していても、見落とすものは見落とす。自分がいかに不完全であるかを突きつけられるたびに、情けなさと悔しさが入り混じる。でも逆に言えば、不完全さを受け入れて工夫できることが、人間の強さでもある。何度失敗しても、少しずつ精度を上げていく。その繰り返しが、自分を支えている。
AIに任せられたらいいのにと思う日もある
「この部分だけAIがチェックしてくれればなあ」と、補正通知を前に思うことがある。時代が進めば、登記の一部は自動でミス検知されるようになるかもしれない。でも、それでも最終責任は人間。依頼人の人生の一部を扱う仕事だからこそ、機械任せにはできない部分もある。結局、自分の手で守らないといけない世界がある。
「完璧」は幻想と割り切れるか
完璧を目指して、ボロボロになっていた時期がある。自分に厳しくしすぎて、胃を壊しかけたこともある。だけど今は、少し力を抜いている。完璧なんてありえない。だからこそ、やり直しが許される司法書士の制度には救われている。ミスをしても、修正すればいい。そのくらいの気持ちでいるほうが、仕事はうまく回る。
元野球部でもエラーはする
高校時代、ショートを守っていた。エラーしたときの空気は最悪だった。でも、次のプレーで挽回するしかない。いま思えば、それが今の仕事に活きている気がする。補正通知は、仕事上のエラーだ。でも、修正して、前に進めばいい。アウト一つ取るために必死だったあの頃の自分を思い出して、今日も補正と向き合っている。
プロでも補正はゼロにならない
ベテランの司法書士仲間も、たまに「補正くらった」とこぼす。どれだけ経験を積んでも、ゼロにはならない。それを聞いて、少し救われた。「自分だけじゃないんだ」と思えるだけで、気持ちは楽になる。完璧な人なんていない。むしろ、ミスから学ぶ姿勢がプロの条件かもしれない。
補正の先に見える本質
補正という現実は苦しい。でも、それを通じて自分の仕事を見直せる。依頼人のために、正確で丁寧な仕事をするという初心を忘れないためのブレーキにもなる。書類1枚で人生が左右されるような世界だからこそ、恐怖と隣り合わせのプレッシャーがある。その中でも、誠実さを貫くことが何より大切だ。
依頼人のために丁寧さを保つ意味
自分が書類に向き合う姿勢が、そのまま依頼人の安心感につながる。補正を減らすことは、信頼を積み重ねることでもある。時には「早くしてくれ」と言われることもあるけれど、慎重さを優先することで、結果的に依頼人の利益になる。補正対応も、その一部だと捉えれば、少しは心が軽くなる。
スピードと精度のバランス
登記はスピードが命。でも、スピードだけ追い求めて精度を落とせば、本末転倒だ。そのせめぎ合いの中で、補正通知は「まだ甘い」と教えてくれる存在でもある。いや、ありがたくはないけど。でも、無視できない現実。適度なスピード、確実な精度、そのバランスをどう取るかは永遠の課題だ。
それでも信頼をつなぐために
ミスをしたって、補正を受けたって、信頼はそこで終わりじゃない。どれだけ丁寧にリカバリーするかが大事。「あ、ちゃんと直してくれたんだ」と思ってもらえるかどうか。結局、司法書士の評価は仕事の積み重ね。補正のたびに凹んでるけど、それでも前に進む。信頼は、へこたれない日々の中にある。