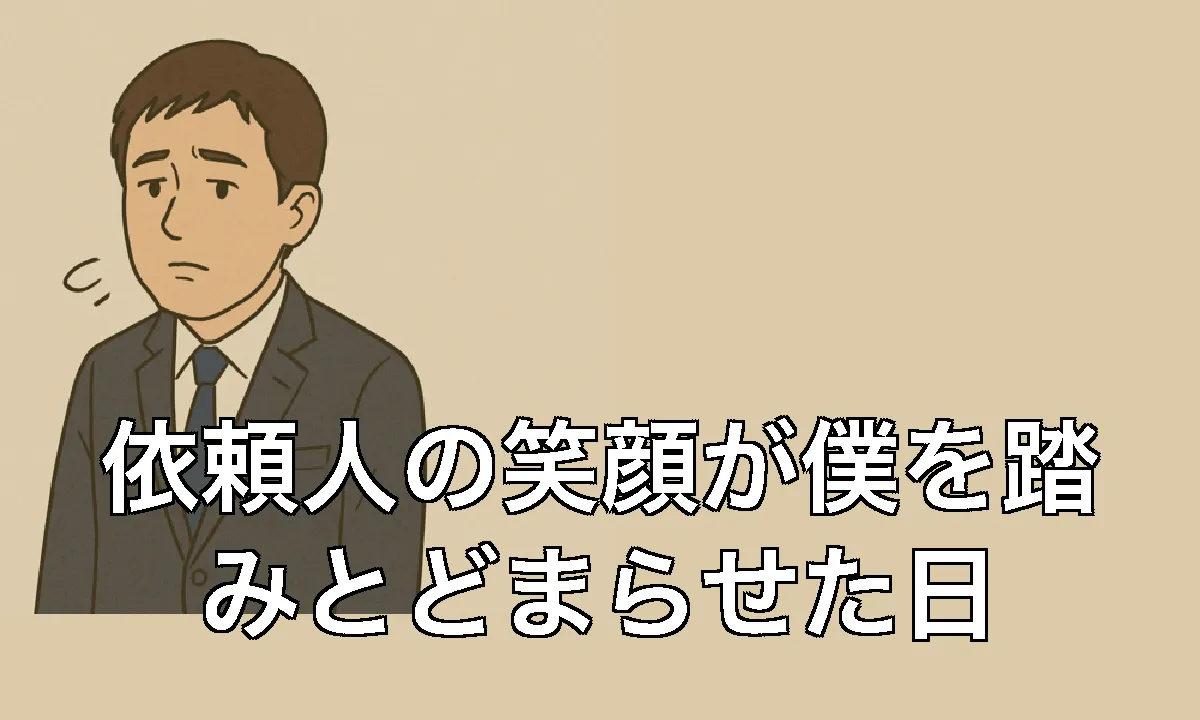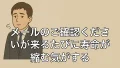もう辞めようかと本気で思った朝
司法書士として独立して十数年。地方の片隅で小さな事務所を営んでいるが、朝目覚めて「今日こそ辞めよう」と思ったのは、正直一度や二度じゃない。その日は特にひどくて、目覚ましが鳴った瞬間から心が重かった。机の上には未処理の登記申請の山、電話の履歴には折り返し忘れた番号、事務員からは「お客様からまだ返答ありません」とのメモ。毎日が詰将棋みたいで、もう自分の存在意義さえわからなくなっていた。
毎日こなすだけの登記と終わらない電話
仕事はまさにルーティン。相談を受け、書類を作り、法務局へ申請。電話が鳴り止むことはなく、午前中はほぼ潰れる。かかってくるのはクレームや確認ばかりで、ほっとする時間なんてどこにもない。野球部時代、どんなに練習がきつくても終われば仲間と笑い合えた。でも今は、一人きりのグラウンドで永遠にノックを受けてるような気分だ。息をつく暇もなく、ただ淡々と「こなす」だけの日々が続く。
効率化の限界と孤独な判断
効率化は限界にきていた。Gmailのテンプレートやスプレッドシートの自動計算を駆使しているが、それでも「人の話を聞く」「書類を読む」「判断を下す」のはAIには任せられない。ひとつ判断を誤れば、依頼人の人生に関わるミスになる。孤独な決断の連続に、肩がどんどん重くなる。事務員は最低限の仕事はしてくれるが、相談相手という感じではない。結局、全てを自分で抱えるしかなかった。
事務員との会話すら業務連絡だけになっていた
人と接する仕事のはずなのに、気づけば誰とも本音で話していなかった。事務員とは「この書類確認しました」「印紙貼っておきます」程度の会話だけ。雑談なんてもう何ヶ月していないだろう。彼女は悪くない、むしろ丁寧な仕事ぶりだ。ただ、事務所の空気が冷えきっていたのは確かだ。気遣ってくれているのはわかるが、それが余計に辛かった。自分が「しんどい」と言えば、迷惑になると思ってしまっていた。
心が擦り切れていくのを感じながら
業務をこなす手は止まらないのに、心だけがどんどん削られていく。数字にも言葉にも感情が入らなくなり、依頼人の声すら上の空で聞いていた。気づけば笑うことを忘れていた。どんなに感謝されても、内心では「また次があるから」と無感動になっていた。自分が人間であることを思い出せなくなるくらい、感情が麻痺していた。
笑顔を作る余裕もなくなっていた
コンビニのレジで「温めますか?」と聞かれても無言でうなずくだけ。ありがとうの一言さえ出ない日があった。鏡に映る自分は、いつも眉間にしわを寄せたまま。依頼人の前では笑顔を作っていたつもりだったが、きっとバレていたんだろう。愛想笑いはできても、心からの笑顔は消えていた。書類が整っていればOK、それで十分。それが自分の限界ラインになっていた。
コンビニの店員の「ありがとうございます」が刺さる
ある日、夕方に立ち寄ったコンビニで、若い店員さんが満面の笑みで「ありがとうございます」と言ってくれた。それだけのことなのに、胸が締め付けられた。あぁ、自分は最近この「ありがとう」を誰かに言ってもらえてなかったな、と気づいた。誰かの笑顔を見ることも、自分が笑顔を返すことも、どこか遠い過去の出来事のように感じていた。ほんの一瞬、涙が出そうになった。
元野球部の気力はとっくに底をついていた
かつては粘り強さが取り柄だった。雨の日も雪の日も、最後までノックを受け続けた。でも今は、心のバットすら持てていない。クライアントの打球に対応する余力なんて残っていないのに、それでも立ち続けるのが仕事。もう引退してもいいんじゃないかと、自分を甘やかしたくなっていた。だけど――そんなときだった。
その日届いた一通の手紙
まさかの出来事だった。古い依頼人からの封書。手続きが終わって半年以上たっていたはずだ。開けてみると、便箋3枚にびっしりと手書きの文字。「あのときは本当にお世話になりました」「あなたが一緒に考えてくれたおかげで、不安が消えました」「こんなに丁寧に向き合ってくれる人はいません」。読みながら、思わず背筋が伸びた。
依頼人からの丁寧すぎる感謝状
その依頼人は、相続登記で悩んでいた女性だった。兄弟と揉めていたようで、複雑な背景があった。僕は何度も彼女の話を聞いて、細かく書類を整えた。でも正直、あの件も「こなした」つもりだった。特別な対応をしたつもりはなかった。ところが手紙には、僕の対応にどれだけ救われたか、どれだけ安心したかが丁寧に綴られていた。まるで自分の存在が肯定されたような気持ちになった。
「あなたにお願いしてよかった」という言葉
その一文が心に深く刺さった。「あなたにお願いしてよかった」。言葉は短い。でも、それだけで報われた気がした。数字でも報酬でもない、人からの本音の言葉。それが自分にとってどれだけ価値があるか、忘れていた。機械のように処理していた日々の中で、人としての感情が蘇るような瞬間だった。
便箋の文字が滲んで見えなかったのは目のせいか涙か
文字を追っていた目が、途中でぼやけてしまった。年齢のせいか、と思ったけど、指先で拭ってみたら涙だった。誰にも見られてない事務所の中で、静かに泣いた。誰かの笑顔のために、自分はまだ頑張れるかもしれない。そう思えたのは、本当に久しぶりだった。
忘れていた大事なことを思い出す
その日から少しだけ、自分の仕事を見る目が変わった。業務は変わらない。でも、書類の先に「人」がいることを思い出した。誰かが不安で、悩んで、その末に「頼る」ことを決めている。そのことに応えるのが司法書士の仕事だ。そう、かつて資格を取ったときの初心が、少しずつ戻ってきた。
なぜ司法書士になったのか
思えば、実家の相続で困っていた母を助けたいというのが出発点だった。専門知識があれば、身近な人を守れる。そう思って選んだ道だった。なのに、いつの間にか「手続き屋」になっていた。あの手紙は、初心を思い出させてくれた。人と向き合う覚悟を、もう一度持とうと思った。
書類の先にある「人」の存在
画面の向こうにある「名前」は、ただの記号ではない。家族を抱え、悩みを抱え、人生を背負った「誰か」だ。自分が処理しているのは、登記ではなく「人生の一部」なんだと、改めて思うようになった。そう考えると、手の動きが少し優しくなった気がした。
僕がやるしかないという気持ちがよみがえる
頼れる人がいないからこそ、僕がやる。それは重荷でもあり、誇りでもある。誰かが「この人にお願いしたい」と思ってくれる限り、もう少し踏ん張ってみよう。完璧じゃなくていい。不器用でも、丁寧に、まっすぐに。
笑顔一つで持ち直せるときがある
心が限界だったとき、救ってくれたのは誰かの「笑顔」だった。それを思い出せたことで、日々のしんどさも、ほんの少し和らいだ。依頼人が見せてくれる笑顔が、自分にとってどれだけのモチベーションになるか。あの日の涙が教えてくれた。