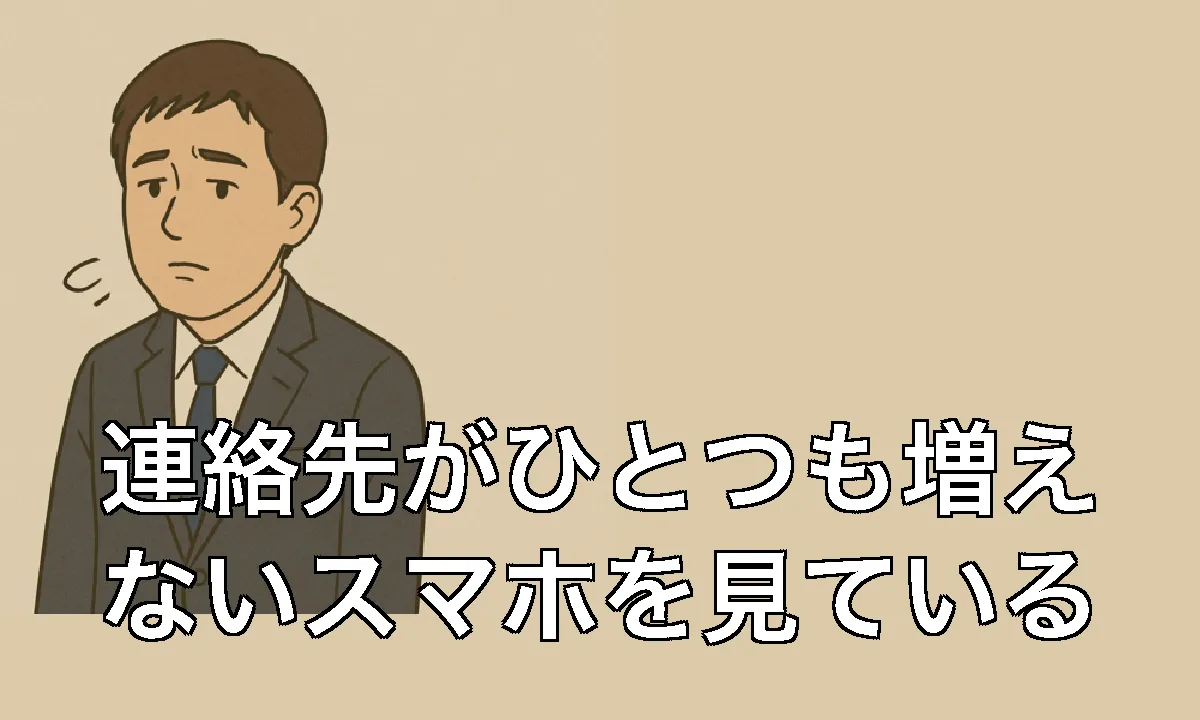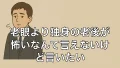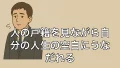人とつながらないままの日々
気づけば、スマホのアドレス帳はずっとそのままだ。新しい出会いがあっても、仕事が増えても、登録する連絡先が増えることはほとんどない。むしろ、昔の誰かの名前を削除しようか悩んで終わることの方が多い。画面を眺めながら、自分の人間関係が静かに、確実に、縮小しているのを感じる瞬間がある。地方の司法書士という仕事柄、多くの人と会ってはいるけれど、心のどこかでは「それは仕事での話」と割り切ってしまっている。深くつながるような関係が、いつの間にか築けなくなってしまった気がするのだ。
新しい出会いがない理由を考える
出会いがないわけではない。ただ、その場限りで終わってしまうことがほとんどだ。仕事柄、相談者や依頼者とはそれなりに丁寧に会話をするけれど、それ以上踏み込むことはない。飲み会も減り、休日も疲れて寝て終わるようになった今、「人とつながる」という行為が、ひどく面倒で、時には怖くすら感じるようになった。年齢のせいだろうか、あるいは、過去に何かを期待して傷ついた経験が尾を引いているのかもしれない。新しい連絡先が増えないスマホは、そんな自分の臆病さを静かに映しているようだ。
仕事で人と会っているのに心は遠い
毎日誰かと会っているはずなのに、なぜこうも孤独なのか。不思議な感覚だ。登記や相続の相談に来る方たちと、時には笑いながら話すこともある。けれどそれは、あくまで“業務”であり、“対応”であり、そこに本音や感情を持ち込むことは滅多にない。表面上は丁寧に、親身になって接するが、心のどこかでは「この人とは今日限り」と割り切っている。元野球部の頃は、毎日顔を合わせて、同じ飯を食って、バカな話をしていた。あのときのような関係は、もう二度と築けない気がする。
「先生」と呼ばれることで距離が生まれる
「先生」と呼ばれることに、最初は誇らしさを感じていた。けれど今は、それが壁になっている気がしてならない。相手は「先生」に気を遣い、自分は「先生」としての役割を演じる。結果、どこまでいっても距離が縮まらない。たとえば飲み会で少し砕けた話をしても、相手はどこか遠慮して笑っているだけ。そんな場面が続くうちに、自分からも距離を置くようになってしまったのかもしれない。名前ではなく、ただの一人の人間として呼んでもらえる関係が、今はとても恋しい。
スマホの中にあるのは変わらない名前だけ
スマホを開いても、新しい名前は増えていない。昔からの友人、仕事関係者、家族。登録されている名前は、もう見慣れすぎている。更新されるのは機種だけで、アドレス帳の中身は時間に取り残されたままだ。何度か、ふとした拍子に「この人って今、何してるんだろう」と思うことがあるけれど、連絡する理由が見つからず、ただ指を止めて画面を閉じる。それが、ここ数年の“再会”のすべてだ。
アドレス帳の中身が5年前と同じ
5年前のスマホと比べて、中身が何も変わっていないことに気づいたとき、正直ぞっとした。あれだけの時間が経っているのに、新しい名前がない。むしろ、削除した人の方が多いかもしれない。結婚して連絡が途絶えた友人、職を変えて関わらなくなった同業者、音信不通になった昔の知人。気がつけば“縁”という糸が切れていく音に、耳が慣れてしまっていた。
削除することも追加することもない寂しさ
名前を追加することも削除することもない日々は、静かな寂しさを運んでくる。たまに連絡先を整理しようと画面を開くが、削除してしまったら完全に縁が切れる気がして、結局そのまま閉じる。そして、誰か新しい人と出会っても、アドレス帳を開く気力が湧かない。どうせまた続かないだろう、そんな予感が先に立ってしまう。自分の中にある“期待しない癖”が、今のスマホの静けさを作っているのだと思う。
司法書士という仕事と孤独
この仕事は「人の人生の節目に立ち会う仕事」だと言われる。でも、他人の人生に寄り添いながら、自分の人生には誰も寄り添っていない、そんな矛盾をよく感じる。特に独身のまま年齢を重ねると、仕事以外の時間が真っ白になっていく。忙しさにかまけて誤魔化しているけれど、正直、夜に静まり返った事務所に一人でいると、自分が社会から少しずつ離れていっているような気すらする。
「先生」という肩書に隠された孤独
肩書があることで、守られていると同時に、孤独にもなる。周囲は「先生」として扱い、こちらもその期待に応えようと無理をする。それが、どんどん自然な感情を削いでいく。疲れていても「疲れてる」と言えない、つらくても「大丈夫」と笑ってしまう。ふと、自分が本音で話せる相手が誰もいないことに気づいて、愕然とすることがある。司法書士という仕事に誇りはある。でも、それが自分を縛る“枷”になっている瞬間も確かにある。
頼られることはあっても寄り添われない
「頼られている」のと「寄り添われている」のは、全く違う。仕事では多くの人に頼られるけれど、それは感情ではなく“役割”としての信頼だ。どれだけ感謝されても、事務所を出た瞬間にその関係は終わる。それが当然なのだけれど、続く日々の中で「じゃあ、自分は誰に頼ればいいんだ」と思うようになる。依頼者の話は聞く。でも、自分の話を聞いてくれる人はいない。そんな風に感じる夜が、最近とても多い。
距離感があるからこそ成立する仕事の難しさ
仕事だからこそ“距離感”は大切だ。依頼者に踏み込みすぎれば、逆に信頼を損なうこともある。冷静で客観的であることが、司法書士には求められる。だが、その姿勢が日常にも染みついてしまい、プライベートでも感情を出すことが難しくなっていく。人としての自分と、職業としての自分の境目があいまいになる。本音を見せることが“仕事に支障をきたす”と無意識に思い込んでいるのかもしれない。
愚痴をこぼす相手がいない
どんなに忙しくても、どんなにストレスが溜まっても、それを吐き出す場所がない。ただただ、机に向かって書類をこなし、電話に対応し、事務員に「おつかれさま」と言って一日が終わる。たった一言でも「しんどいよなあ」と共感してくれる人がいれば、それだけで救われるのに。だけど、そんな相手はもう身近にいない。気軽に「飲みに行こう」と言える友人も減ってしまった。
事務所に戻れば一人きりの空間
夕方、事務員が帰ったあと、事務所に残るのは自分だけ。外は暗くなってきて、蛍光灯の白い光がやけに冷たい。静かな事務所に響くのは、キーボードの音と時折なるFAXの受信音だけ。仕事が終わっても、なんとなく帰る気になれず、つい机に座ったままスマホをぼんやり眺めてしまう。その画面に、新しい通知はない。連絡を取りたい人もいない。そんな夜が、もう何度あったかわからない。
元野球部だった頃の仲間たちはどこへ行ったのか
高校時代、野球部で汗を流したあの頃。仲間たちと一緒にバカ騒ぎしていた時間が、今では遠い過去になってしまった。連絡を取っているメンバーは、もうほとんどいない。それぞれ家庭を持ち、忙しく生きているのだろう。たまにSNSで見かけるけれど、「元気?」とメッセージを送る勇気が出ない。自分だけが立ち止まっているようで、情けなくなるからだ。スマホの連絡先には、そんな過去の名前が、いくつか、静かに残っている。
スマホが映す自分の現在地
連絡先がひとつも増えないスマホ。それは、今の自分の人間関係を象徴している。忙しさにかまけて、誰かとのつながりを後回しにしてきた結果が、画面に現れているように思う。仕事の上ではたくさんの人と関わっていても、個としての自分は、孤立している。そのことを、改めて痛感させられるのだ。
誰かに連絡したい夜にふと感じる虚しさ
夜、ふと寂しさを感じる瞬間がある。テレビをつけてもつまらなくて、なんとなくスマホを開く。でも、誰に連絡をしていいのか、わからない。電話をかけたい相手がいないという事実が、胸にずしんと響く。誰かとつながっていたいという気持ちはあるのに、行動には移せない。自分で壁を作ってしまっていることにも、気づいてはいるのだ。
履歴に残るのは仕事の電話ばかり
発信履歴も着信履歴も、ほとんどが「○○法務事務所」「登記の件で」「相続について」。休日ですら、仕事関係の電話が数件入る。それ以外の名前が並ぶことはほとんどない。昔はよく電話していた友人の名前が、今は履歴にないことに気づくと、なんとも言えない感情がこみ上げてくる。「これでいいのか?」と、自分に問いかけることもある。
LINEの通知が鳴らない日常
スマホの通知音が鳴るたびに、少し期待してしまう自分がいる。でも、それは大抵クーポンか、仕事関連のメッセージだ。LINEは既読のまま止まっていて、新しい通知は来ない。スタンプひとつ、送る相手すらいない夜がある。そんなとき、自分が本当に孤独なんだと実感する。スマホが、寂しさを映す鏡になっているようで、時々目をそらしたくなるのだ。