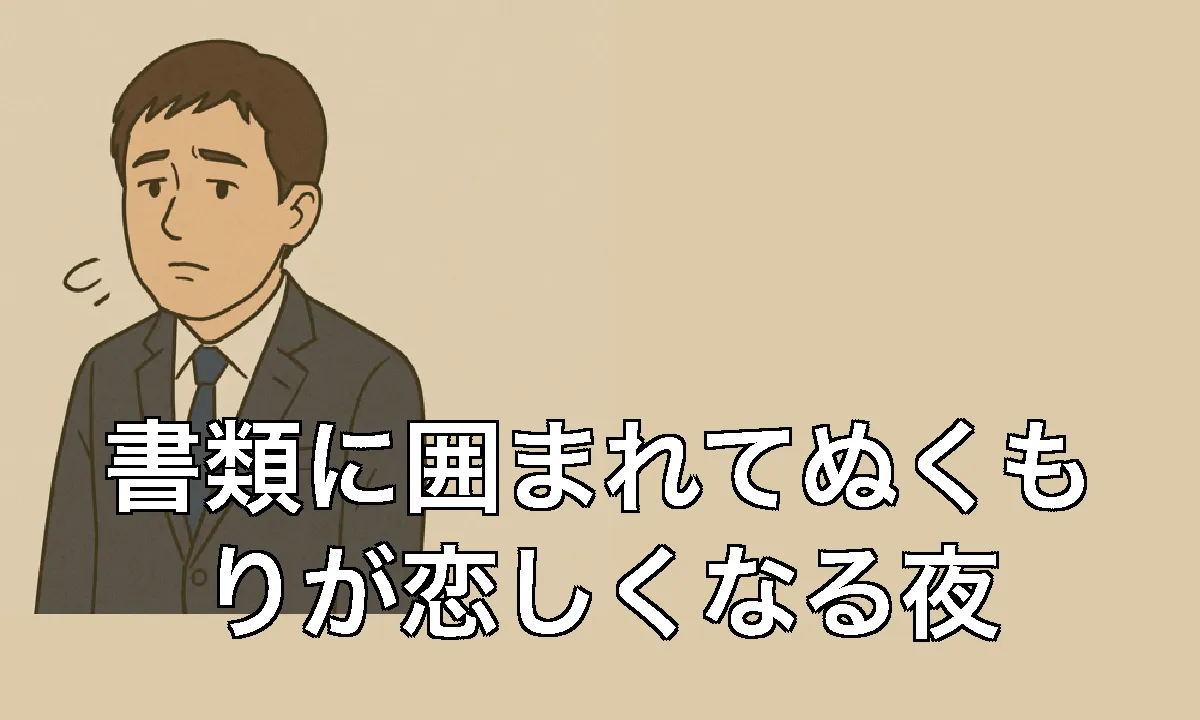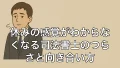ひとりの事務所に響く紙の音
朝、事務所に入るとまず聞こえるのは、自分でめくる書類の音だけだ。事務員は10時に来る。それまでの静けさは、耳が痛くなるほど無音で、かすかな紙のこすれる音さえもやけに大きく感じられる。都会の喧騒とは無縁のこの地方都市で、僕は今日も司法書士としての一日を始める。何かが足りない。けれどそれが何か、すぐには思い出せない。
朝の始まりは静かすぎて
一人でパソコンを立ち上げ、昨日の申請状況をチェックする。それが日課であり、ルーティンであり、孤独のはじまりでもある。隣の椅子は空っぽで、温もりの痕跡もない。昔、営業マン時代には朝の雑談や「おはようございます」の声が飛び交っていた。今は誰も話しかけてこないし、自分から話す相手もいない。静寂は時に心を蝕む。
音がなさすぎることがこんなに寂しいとは
「静かな環境で働きたい」なんて昔は思っていたけれど、実際にそれが手に入ると、むしろ辛くなるという矛盾。自分のタイピング音とプリンターの駆動音だけが事務所を満たす。外の通行人の話し声が聞こえると、つい窓の外を見てしまう。羨ましいわけじゃない。ただ、そこに人の気配があることが、なんとなく羨ましくなる。
昔はにぎやかな職場に憧れていた
学生時代、居酒屋のバイトや野球部のミーティングでワイワイしていた時間が楽しかった。あの頃は一人になりたくて仕方なかったのに、今は一人がこんなに堪えるとは。仕事の忙しさと、誰とも分かち合えないという現実が、想像以上に心をすり減らす。たまには誰かと「今日しんどかったな」と言い合いたい、それだけなんだ。
書類の束と無言のプレッシャー
目の前に積み上がる登記書類。業務量としては確かにありがたい。だが、それは同時に孤独な作業の連続を意味する。誰かが気を利かせて手伝ってくれるわけでもないし、「頑張ってますね」と言ってくれるわけでもない。黙って、黙って、片付けていくしかない。プレッシャーは外からではなく、自分の内側からやってくる。
机の上の山は誰も減らしてくれない
書類というのは、誰かが黙って処理してくれている時こそ美しく回っている。逆に、誰かが抱え込めば、その山は誰にも気づかれないまま積み上がっていく。僕の机の上のその山を、誰も知らない。事務員が気づくことはあっても、「無理しないでくださいね」と言ってくれるだけ。結局、やるのは自分しかいないという現実がある。
頑張っても誰も気づかないという現実
たとえば申請の不備を一つも出さずに終えた日。自分では「今日はいい仕事をした」と思う。でも誰もそれを知らないし、評価する人もいない。組織の中にいれば、成果として残るかもしれない。でも一人事務所では、何も残らない。そんな虚しさが、夜遅くの帰り道にじわじわ効いてくるのだ。
ふとした瞬間に湧き上がる空しさ
忙しさの中に没頭していれば平気だと思っていた。でも、ふと時計を見る瞬間や、昼食のカップ麺にお湯を注ぐとき、胸の奥から何かがじわっと湧いてくる。これが「空しさ」というものか、と最近ようやくわかった気がする。書類では埋まらない心の隙間。お金でも解決できない感情がある。
お客様との会話もどこか形式的で
登記の相談に来るお客様とは、確かに会話はある。でもそれは「職務上の対話」にすぎない。こちらは正確な説明と、丁寧な対応を心がけている。でもそれ以上踏み込むことはなく、逆に向こうもあくまで「業務依頼者」という枠を越えては来ない。人と接しているのに、どこかで孤独なのだ。
優しさを返してくれる相手がいない
例えば体調が悪い日でも、仕事の手は止められない。そんなとき、たった一言でも「大丈夫?」と言ってくれる人がいたら、少しは楽になるのかもしれない。今は誰にも弱音を吐けないし、そもそも聞いてくれる相手もいない。事務員は優しいけれど、あくまで業務の距離感がある。それ以上は、こちらから踏み込むわけにはいかない。
ただ依頼をこなすだけの毎日
感情を入れすぎると仕事が乱れる。だから、できるだけ淡々と処理するよう心がけている。でも気づけば、感情そのものが枯れてきたような気もする。笑うことも減り、誰かを想うことすら少なくなってきた。これで本当に「人として」いいのだろうかと思うと、少し怖くなる。
人肌が恋しくなる夜の帰り道
書類を提出し終えた帰り道。ふと見上げた空には星が見えていた。地方の夜は空気が澄んでいて、よく星が見える。でも、その美しさに誰かと感動を分かち合うことはない。事務所の灯りを消して鍵を閉めるとき、「今日もひとりか」と心の中でつぶやく自分がいる。
灯りのついた家々に胸が締めつけられる
帰り道、住宅街を通ると、どの家にもあたたかい灯りがともっている。カーテンの隙間から、団らんの影が見えることもある。決して覗くわけじゃないけれど、目に入ってしまう。そういうとき、自分の部屋がいかに無音で、無表情で、温もりのない空間かを突きつけられるような気がしてくる。
独り身の寂しさは冬にこたえる
寒い季節になると、余計にこの寂しさが増してくる。湯たんぽや電気毛布じゃどうにもならない種類の寒さ。誰かと肩を並べて歩いた記憶も、もうずいぶん昔のことだ。そういえば、最後に手をつないだのはいつだったろう。思い出そうとしても、もう輪郭がぼやけてしまっている。
元野球部だった頃の熱気が懐かしい
汗をかいて、声を出して、仲間と勝利を目指していた日々。野球部だったあの頃は、孤独なんて無縁だった。今でも夢で見るのは、満員のスタンドとチームメイトの笑顔。でも目覚めると、隣には誰もいない。枕元には書類のファイルが積まれているだけだ。
それでもやめられない仕事の理由
それでも、この仕事を嫌いにはなれない。しんどくても、寂しくても、やっぱり自分にしかできないことがあると信じている。人の人生の一場面に関われるというのは、ある意味でとてもありがたいことだ。誰かの助けになれている、そう実感できる瞬間が、かすかな光になる。
依頼者のありがとうだけが救いになる
たまに、面倒な登記がうまく終わったとき、依頼者が深々と頭を下げてくれる。その「ありがとうございました」の一言だけで、数日分の疲れが取れる気がする。不思議なことに、そういう時ほど仕事に対する情熱が戻ってくるのだ。だから、もう少しだけ頑張ってみようと思える。
時々届く手紙に涙がにじむ
先日、昔の依頼者から絵葉書が届いた。「先生のおかげで助かりました」とだけ書かれていた。たった一行、されど一行。何も言えなくなって、じっと葉書を見つめながら、ただただ静かに涙が出た。こういうことがあるから、やめられないのだ。
ほんの一言が明日をつなげる
この仕事には、大きな報酬もなければ、華やかさもない。けれど、人の人生の節目に寄り添うことができる。それは、きっと誰にでもできることじゃない。だからこそ、明日もまた、机の前に座ろうと思う。書類の山の中に、微かなぬくもりを探しながら。