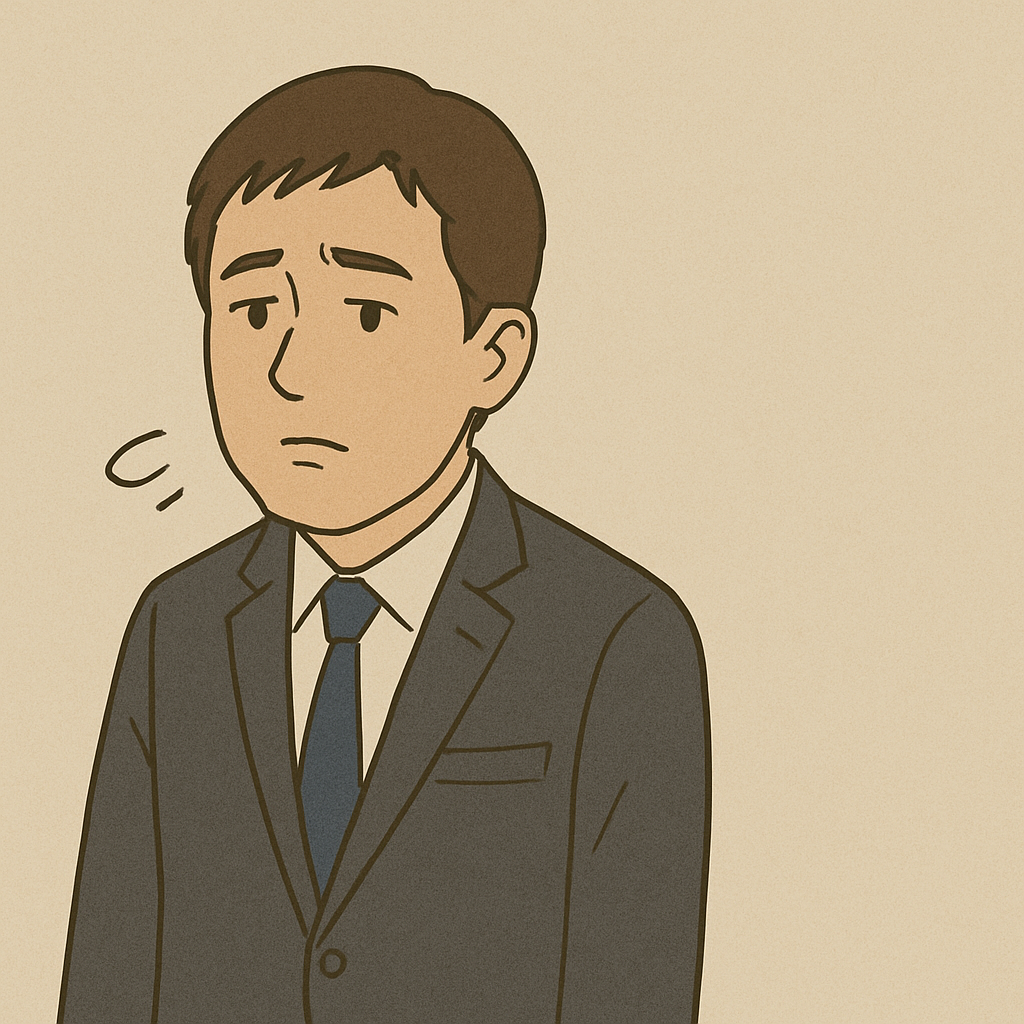不自然な署名から始まった依頼
「これ、先生……なんか、変じゃないですか?」とサトウさんが眉をひそめながら差し出したのは、遺言書だった。公正証書ではなく、自筆証書遺言。書式に不備はなさそうだが、何かが引っかかる。
依頼者は、父を亡くしたばかりの妹。兄が提出した遺言書に違和感があるという。字が変だと。だがそんなの、気のせいじゃないか? と思った自分が甘かった。
「ま、見てやるよ」と言いつつ、すでに胃が痛くなってきたのは、夏バテのせいだろうか。それとも、また何かに巻き込まれる予感のせいか。
遺言書の検認とひとつの違和感
家庭裁判所での検認手続きは、事務的に進んでいった。だが、妹の視線はずっと兄の手元を見つめていた。提出された遺言書の筆跡は、たしかにクセのあるものだ。
「父はもっと、こう……きれいな字でした」そう呟く彼女の声には、疑念というより、確信に近い響きがあった。
遺言の内容は、全財産を兄に譲るというもの。妹に一切触れていない。その一点もまた、彼女の心に重くのしかかっていた。
筆跡が微妙に異なるという指摘
「この“譲る”の字、バランスが不自然です」サトウさんは、赤ペンを取り出して丸をつけた。字が不自然? 筆跡鑑定なんて高いし、裁判沙汰にするのも気が進まない。
けれどサトウさんは、うんざりした顔で続けた。「それよりこれ、去年の住民票にあるご本人の署名と比べてみてください」
やれやれ、、、こういうのは警察がやってくれればいいのに。だが、この事務所ではサザエさんのように日常の中に波乱が訪れるのが常だった。
事務所に持ち込まれた疑惑の遺言書
「そもそもこの紙、百均で買える便箋ですよ」サトウさんの指摘は止まらない。そこまで疑うなら鑑定士にでもなればいいのに、と思いつつも、少しずつ自分も違和感を覚えていた。
提出された遺言書の日付は三ヶ月前。だが、父の通院記録では、その頃にはすでに字を書くどころか、会話もおぼつかなかったはずだ。
妹の話によれば、遺言書の存在は父の死後、兄によって突然提示されたものだったという。におう。これはにおうぞ。
兄妹の間に走る不和
「父の面倒はずっと私が見てました。兄は何年も会いにも来なかったくせに……」妹の声は震えていた。怒りとも悲しみともつかぬ感情が混ざっていた。
「それで全部兄のものにされるなんて、おかしいです」その訴えを聞いて、少しだけ眠気が吹き飛んだ。
単なる争族(そうぞく)トラブルだと片付けるには、あまりにも不自然な点が多すぎた。
手続きより先に疑問が湧いた
司法書士として手続きをこなすのが本分だが、今回はそうもいかなかった。だって、あの“譲る”の字が、どうにも気になるのだ。
書き慣れた人間なら、もっと自然に流れる筆致になるはず。あれは何かを真似た字、つまり……偽造?
ならばこれは、ただの相続ではなく、れっきとした犯罪の可能性もある。
サトウさんの鋭い観察眼
「これ、兄が書いたって証拠にはなりませんよ。でもね、ここの“譲”のはね、左払いが完全に女性の癖です」サトウさんはさらりと言ってのけた。
「女性?」思わず聞き返す。「はい、たぶん母親か、あるいは……誰かに代筆させた」
なるほど。たしかに、まるでルパン三世に出てくる峰不二子みたいに、背後で誰かが動いている可能性があるということか。
筆跡鑑定などいらないと言い切る彼女
「筆跡鑑定は高いし時間もかかる。けどね、郵便物やメモ帳があれば、家庭でも筆跡の一致は見つけられます」
サトウさんはさっさと兄の職場を調べ、本人の書類コピーを依頼していた。おそらく向こうの女性事務員の協力を得ていたのだろう。
彼女の行動力には舌を巻くが、なぜか僕の評価にはまったくつながらない。不思議だ。
赤ペン一本で論破する助手
「はい、これ見てください。ここの“譲る”と、兄の契約書にある“譲渡”の“譲”。違いますよね?」
たしかに、兄の筆跡は丸っこく、遺言書のそれとはまるで別物だ。これで兄本人が書いた可能性は消えた。
つまり、第三者による偽造。公文書偽造ならぬ、私文書偽造。そしてその動機は、金。
過去の署名と比較してみた
僕は役所に依頼して、故人が過去に提出した住民票や固定資産税申告書の署名欄を調べた。
そしてそれらと遺言書の署名を並べてみると、一目瞭然。筆圧、字の傾き、バランス、すべてが違っていた。
「やれやれ、、、もっと早く見ていれば、無駄な検認をしなくて済んだかもな」ため息とともに、ようやく事件の核心に近づいた気がした。
住民票の署名欄と相違があった
「これを見せれば十分です」妹にそう伝えると、彼女は泣き崩れた。「父は、私を忘れたわけじゃなかったんですね……」
その涙は、何かから解放されたような安堵の涙だった。筆跡が語るのは、技術ではなく、心だったのだ。
そしてその心をねじまげようとした者が、法の裁きを受けるのは当然だった。
不自然に震える文字の理由
後に判明したのは、兄が恋人に頼んで書かせたという事実。恋人は元書道講師で、筆跡を真似るのが得意だったという。
だが、死を目前にした者の字には、迷いや恐れがにじむ。それを真似るのは不可能だった。
完璧に見えた偽造も、真実の前にはほころびだらけだった。
やれやれ、、、な展開と墓前の対決
後日、妹は父の墓前で、すべてを報告したという。墓石の前で長く頭を下げていたそうだ。
兄は遺言偽造の疑いで警察に呼ばれ、恋人も共犯として書類送検された。僕の出る幕は、ほとんどなかった。
でも、まあ……そういう役回りも悪くない。「やれやれ、、、これでまた少しだけ、仕事が増えるな」
真実を知った妹の涙
「ありがとうございました」最後に妹が深く頭を下げてくれた。誰かに感謝されるのは久しぶりだ。
だけど、サトウさんはそれを横目に「別に私、感謝されたいわけじゃないので」と素っ気ない。
そんな彼女の横顔を見ながら、僕はちょっとだけ、自分が名探偵みたいに思えてしまった。
司法書士の意地と矜持
司法書士は事務屋だ。警察じゃないし、探偵でもない。けれど、紙に書かれた言葉の裏を読むのもまた、仕事のうちだ。
今回もまた、地味な手続きを超えたところで、ひとつの真実にたどりついた。
それでもまだ僕の評価は「うっかり者」なんだろうけどね。
公正証書を超える証拠とは
公正証書には勝てない。でも、筆跡は証拠になる。感情と技術が交差する、その一点が、真実への鍵だった。
「紙は嘘をつかないって、よく言いますけど」サトウさんがぼそりと呟いた。「書いた人間は、わりと嘘つきますよね」
苦笑しながら、僕はまた新しい依頼の書類を開いた。
筆跡が語る動機と執念
人は文字に心を乗せる。その心が嘘をつけば、文字も歪む。今回の事件は、それを証明するものだった。
兄の執念、妹の疑念、父の沈黙。それらすべてをつなぐ一本の筆跡が、すべてを語っていた。
それに気づいたのは、僕ではなく――たぶん、サトウさんだった。
一件落着の後のほろ苦さ
事務所に戻ると、いつものようにサトウさんが冷たい紅茶を淹れてくれた。「少しは役に立てました?」
「十分すぎるくらいだよ」そう答えたが、彼女は相変わらず無表情だった。
外は夕立。夏はまだ終わらないようだ。
相続とは信頼の証なのか
紙に残された言葉だけでは、人の信頼は計れない。相続とは、信頼の結果でもあり、崩壊の証明でもある。
司法書士として関わるたびに、その重さに背筋が伸びる。
次の依頼者もまた、誰かを信じたいと願ってくるだろう。そのとき僕にできるのは、事実だけを伝えることだ。
サトウさんの冷たい紅茶
「明日は朝から相談二件です」冷たい声が、静かに事務所に響いた。
やれやれ、、、紅茶の味もわからなくなるくらい、現実はまたすぐに僕を引き戻す。
だけどこの冷たさも、悪くない。少しだけ、そう思えた。