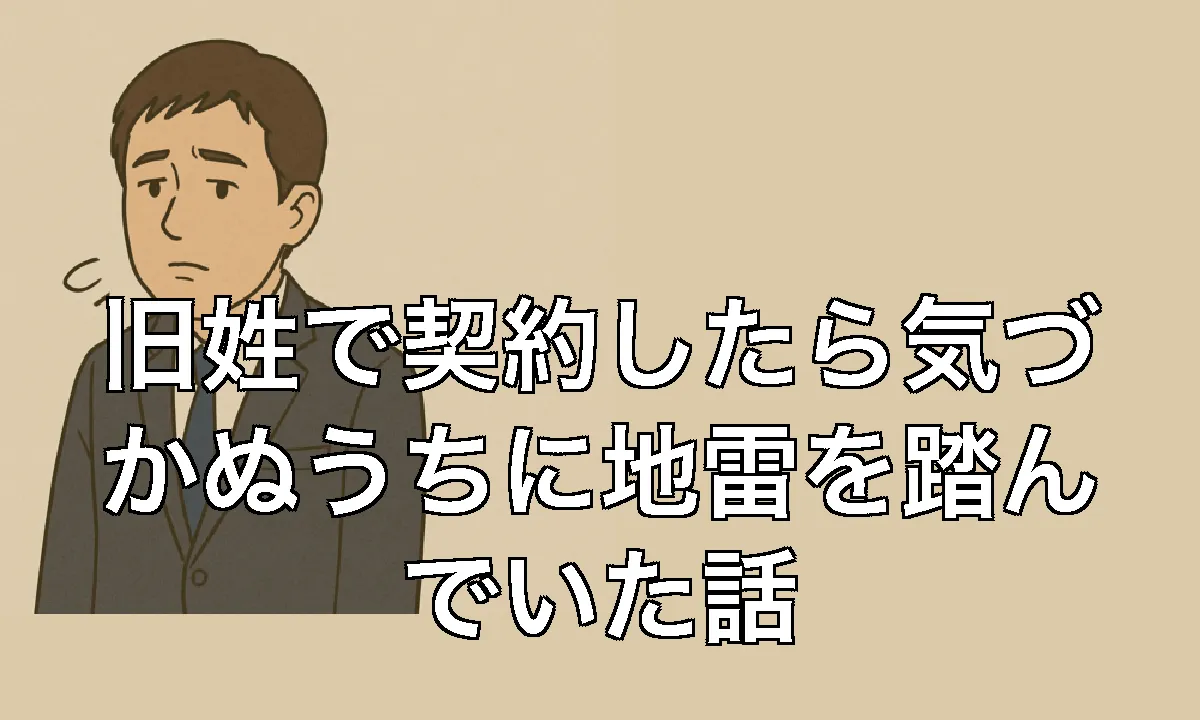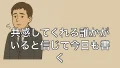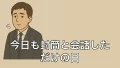忙しさの中で見落とす小さな違和感
毎日のように書類が届き、目を通し、署名捺印し、登記を申請する。そんな慌ただしい日々の中で、小さな違和感なんて気づかない。というより、気づこうとする余裕がない。あの日もそうだった。依頼人が持参した契約書に目を通し、問題なしと判断して処理を進めた。そのとき、まさか記載された名前が旧姓のままだったとは夢にも思わなかった。いくら仕事が立て込んでいたとはいえ、名前くらい確認できただろう、と後から自分にツッコむ羽目になる。
旧姓のままの契約書に気づいたのはいつだったか
すべてが発覚したのは、登記申請が終わった一週間後。依頼人からの電話だった。「あの……契約書に旧姓が書かれていたみたいで……」と、おそるおそる切り出され、最初は何のことか分からなかった。「え?旧姓って、どういうことですか?」と聞き返すと、「実は結婚して名字が変わったのに、前のままの名前で契約書に署名してしまってて」とのこと。もうその時点で、顔から血の気が引いた。何度も確認してきたつもりでも、こういう落とし穴があるのだ。
顧客からの一報がすべての始まりだった
その電話の後、事務所は一気にざわついた。私も事務員も、一気に不安の渦に巻き込まれたような気持ちになった。「どうしよう、訂正効くかな?」「登記終わっちゃったけど、名義どうなるの?」と、頭の中はぐるぐる。今になって思えば、依頼人のほうが冷静だったかもしれない。こちらの慌てようが逆に不安を煽ったかもしれないと思うと、ますます反省ばかりが募る。日常の中の一本の電話が、こんなにも重たくのしかかるとは。
言われてみれば確かにというあの瞬間のヒヤリ
改めてコピーを見返してみると、確かに旧姓だった。「あちゃー」と口に出したが、事務員は苦笑い。私も「気づけよ」と自分にツッコんだが、後の祭りだった。たった一文字違うだけで、ここまで面倒な事態になるとは。まさに、気づかぬうちに地雷を踏んでいたという表現がしっくりくる。見落としは誰にでもある――そう思いたい気持ちはあるが、司法書士として、それを言い訳にしてはいけないのだろう。
なぜそんな初歩的なミスを見逃したのか
これだけ書類を扱っていると、「見るべきところ」が体に染みついてくるはずなのだが、今回は完全に思い込みが勝ってしまった。「依頼人が自分で書いたものだし、大丈夫だろう」という油断。確認は形式的に済ませてしまい、重要な部分を素通りしてしまった。忙しさにかまけて、チェックリストの存在すら頭から飛んでいた。こういうミスは、一度でもやらかすと一気に信頼を失いかねない。実に恐ろしいことだ。
署名欄にある名前の重みを軽く見ていた
名前はその人の「存在証明」だ。特に契約書においては、書かれている名前一つで法的な効果が変わってしまう。にもかかわらず、私はその「一文字」に鈍感だった。自分の名前に置き換えればわかる話なのに。「稲垣」であるべきところが「田中」になっていたら、そりゃ違和感しかないだろう。それなのに、相手の旧姓がそのまま書かれていてもスルーしたのは、自分の怠慢としか言いようがない。反省しかない。
事務作業に追われて余裕がないという現実
もちろん言い訳になるが、実際のところ業務量が尋常じゃなかったのも事実だ。朝から晩まで走り回り、書類は山のように積まれ、合間に電話も鳴りやまない。昼飯もコンビニおにぎりで済ませる日々が続いていた。そんな状態で、細かいチェックに神経を使うのはなかなか難しい。でも、それが仕事だと言われれば何も返せない。ミスを防ぐには、結局「時間のゆとり」が必要なのだと思い知らされた。
チェック体制が整っていない小規模事務所の弱点
うちは私と事務員の二人きり。大手のようにダブルチェック体制があるわけでもなく、ミスのリスクは常に隣り合わせだ。事務員に任せっぱなしにするわけにもいかず、自分もすべて目を通しているつもりだったが、やっぱり見落とすときは見落とす。これが「小規模あるある」なのだろう。自動化ツールも導入していないし、紙ベースでの管理が中心。改めて体制の見直しが必要かもしれない。だがそれも、時間とお金の余裕があってこそだ。
訂正の手続きは思ったよりも骨が折れる
旧姓で契約した契約書、どうするか。訂正契約書を作り直して、双方の署名押印をもらい直す必要がある。その説明にも神経を使う。相手に「手間をかけてしまって申し訳ない」という気持ちと、「こちらの責任ではあるが、手続きを円滑に進めるためにも協力をお願いしたい」というスタンスをどう両立させるか。そのバランスが非常に難しい。ひとつのミスで、ここまで時間と労力が奪われるとは、本当に身に染みる。
本人確認と再押印の面倒なやりとり
まずは新しい契約書を用意して、旧姓と新姓の違いを説明し、どちらが有効であるかを明確にしなければならない。そして再度署名押印をお願いする。中には「またハンコいるんですか?」と不満を口にする人もいる。そりゃそうだ、二度手間だもの。しかも、郵送対応にするのか、直接来てもらうのか、そもそも時間調整ができるのかと、考えることは山ほどある。ほんのちょっとの確認不足が、あとで何倍にも膨らんで自分に返ってくる。
依頼者の心証を悪くしない説明の工夫
この手のミスで一番大事なのは、謝罪だけではなく、相手の不安をいかに早く和らげるか。たとえば「こちらの確認不足でご迷惑をおかけしましたが、登記の効力には影響しないよう手配しております」と伝えるだけで、相手の反応は変わる。言い方一つで「信頼できる対応」に見えるか、「信用できないミス」に見えるかが分かれる。だからこそ、こういうときほど落ち着いて、言葉を丁寧に選ぶことが求められるのだ。
信頼を取り戻すためのひと手間ふた手間
再発防止策を共有したり、チェック体制を強化したことを報告するなど、「次は大丈夫ですよ」と安心してもらう努力が不可欠だ。正直、そういうことを説明するのは面倒だし、やっても意味あるのかと思うときもある。でも、それをやらなければ信頼は回復しない。むしろ、ミスの後の対応こそが「その事務所の本質」を見られていると痛感する。信頼は築くのに時間がかかるが、崩れるのは一瞬。肝に銘じたい。
誰が悪いのかという終わらない自問自答
時間が経つと、なぜあの時ああしておかなかったのか、と自分を責める気持ちが湧いてくる。事務員を責める気にはならない。だって、私が最終チェックを怠ったのだから。最終的にすべての責任は自分にある。でもだからこそ、心の中で「誰かのせいにできたら楽なのにな」と思ってしまう弱さもある。そうやって、何度も頭の中で「自問自答のループ」にハマってしまう。きっとこれは、どの士業でも共通の感覚なんじゃないかと思う。
責任の所在と事務員への申し訳なさ
ミスが起きると、どうしても事務員も気まずくなる。彼女だって一生懸命やってくれているのは分かっている。でも、こちらの態度が少しでも険しくなれば、それがプレッシャーになってしまう。だから「気にしなくていいよ」と言いたいけど、言いながら自分の苛立ちも隠せないときがある。本当の意味での「職場の信頼関係」ってこういう時に試されるのかもしれない。独立して長くやってきたが、そういう人間関係の難しさは今でも課題だ。
結局は自分の監督不行き届き
監督責任。士業の世界ではこの言葉が本当に重く響く。書類一つとっても、「誰がやったか」ではなく「誰が見落としたか」が問われる。だからこそ、どれだけ忙しくても最終確認は手を抜いてはいけない。頭では分かっていても、気持ちが追いつかないときはある。それでも、これがプロとしての責任なのだと改めて思う。どんなに小さな事務所でも、信用だけは守らなければならないのだから。
たった一文字の重さに打ちのめされる
今回の件で、本当に思い知ったのは「たった一文字」が引き起こす影響の大きさだ。旧姓と新姓、その違いは「たった数文字」にすぎない。でも、それが信用を揺るがし、関係性を曇らせ、仕事の根本にまで響いてくる。士業にとっては、文字通り「一文字が命」なのだと思い知らされた。忙しいときほど、初心を忘れてはいけない。文字を扱う者としての覚悟を、もう一度胸に刻みたい。
それでも仕事は続くし反省も繰り返す
今回の失敗は、きっとこれから先も何度も思い出すことになると思う。眠れない夜にふと頭をよぎるかもしれない。でも、それでいいのだ。思い出すたびに、自分の弱さと向き合えるなら、それは成長の糧になる。ミスは誰にでもある。でも、それをどう受け止め、どう乗り越えていくかが問われている。私は今日も、契約書と向き合う。前より少し丁寧に、名前をなぞりながら。