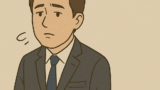不審な相続依頼が届いた日
午後三時、郵便受けに突っ込まれた茶封筒が、俺の運命をまた少しだけ面倒にした。封筒の中には、相続に関する相談依頼と、古びた家屋の登記簿謄本の写しが入っていた。表面上はただの相続登記だが、俺のうっかりアンテナが微かに反応した。
依頼人の名前に、どこか引っかかる違和感があった。だがその違和感の正体を掴めぬまま、俺は書類をサトウさんの机に置いた。
サトウさんの冷静な一言
「これ、死亡年月日と委任日が不自然です」
サトウさんは、俺がただの事務処理だと思っていた依頼を、いとも簡単に切り裂いた。彼女の指摘で気づいたのは、委任状の日付が被相続人の死亡日より後だったことだ。
やれやれ、、、俺はまたしても、サザエさんの波平のように頭を抱えた。
書類の違和感が導く始まり
登記簿に記された過去の名義変更履歴を見て、俺は確信した。これは偶然ではない。意図的に何かが改ざんされている可能性がある。俺の中で、司法書士としての本能が騒ぎ出す。
そうして気づけば、いつものように調査という名の迷路に足を踏み入れていた。
旧家に眠る謎の名義変更
物件は郊外にある、どこか『笑ゥせぇるすまん』に出てきそうな古びた一軒家だった。近所の住民によれば、そこには五年前まで老夫婦が住んでいたというが、今は空き家だという。
俺はその家の玄関前に立ち、空っぽのポストと色あせた表札を見ていた。まるで時が止まったような静けさの中に、嘘の影が潜んでいるような気がした。
登記簿に刻まれた別の名前
現在の登記簿の所有者欄には、依頼人の名前が記載されていた。だがその直前に、一度だけ不自然な名義変更が記録されている。しかも、その変更理由が「遺贈」となっていた。
遺贈には公正証書が必要なはずだが、その写しは送られてきていない。俺はサトウさんに、元の公証役場の所在地を調べてもらうことにした。
三年前に死亡しているはずの人物
調査の結果、奇妙な事実が浮かび上がった。遺贈を受けたとされる人物は、実は三年前に死亡していた。つまり、登記簿上では死人が贈与を受けていたことになる。
まるでブラックジャックのような、死者が動く世界。いや、これは完全に犯罪の匂いがする。
記録と記憶の食い違い
かつてその家の隣に住んでいたという老婦人から話を聞いた。彼女は「そんな贈与を受けた人物なんて知らない」と言った。どうやらこの遺贈は作られたものらしい。
記録は語っている。だが、それを支える現実の記憶がない。そこにこそ真実への入口があると、俺の中で推理の糸が結ばれ始めていた。
隣人の証言が語る真実
老婦人は言った。「あの夫婦、最後は家のことでずっと揉めてたわよ。親族が誰も来なくなってね」
つまり、遺贈が成立するような関係性はなかったということだ。やはり、贈与証書は偽造された可能性が高い。
記憶にない委任状
依頼人に会った俺は、「この委任状、いつ書いたか覚えてますか?」と尋ねた。すると彼は、にやけた顔で「叔父から受け取った」と言った。
だがその叔父は、すでに亡くなっている。死人が書いた委任状なんて、ルパン三世でも使わないトリックだ。
司法書士会での過去の事件調査
俺は過去の不正登記事例を司法書士会の資料室で洗い直した。思いのほか、似たような手口がいくつも出てきた。
そしてある案件に目が止まる。俺の同期で今は独立している同業者の名前が、過去の疑惑案件に何度も登場していた。
類似する名義不正の手口
書類の筆跡、委任状の日付、すべてが似通っていた。もはやこれは一人の犯行ではなく、組織的な登記簿の乗っ取り行為なのではないか。
俺は、かつての同期に接触する決意をした。
旧知の同業者の怪しい動き
彼の事務所を訪れると、応対に出たのは無関係を装う事務員だった。だがその視線の揺れと、書類の受け取りに関しての曖昧な回答がすべてを物語っていた。
やれやれ、、、また面倒なことに首を突っ込んじまったかもしれない。
決定的な証拠が見つかった瞬間
自宅に戻り、再度登記簿と委任状を見比べた俺は、ある特徴的な筆跡の癖に気づいた。それは同期が学生時代から書いていた文字のクセそのものだった。
「こいつ、まだやってやがったか……」俺は静かに呟いた。
サトウさんの仮説が現実に
「これ、別の件でも同じような書類がありましたよ」
サトウさんが机の上に置いたのは、二年前に俺が断った依頼の控えだった。そこにも、同じ筆跡の委任状があった。
ひとつの筆跡がすべてをつなぐ
その筆跡はすべての偽造委任状に共通していた。つまり、同期は依頼者に偽装を持ちかけ、不動産を奪い取っていた。
俺たちは警察に証拠一式を提出した。事件は、ようやく司法の場へと移された。
真犯人は身近な人物だった
依頼人は、同期にそそのかされて書類を用意していた。自分の取り分さえ手に入ればいいという、浅ましい動機だった。
俺はその顔を思い出しながら、心の中でひとつの感情を噛み締めた。怒りでも哀しみでもなく、ただの虚しさだった。
嘘の連鎖が生んだ悲劇
本来の相続人は、音信不通だった娘だった。だが、今さらこの家を受け取っても、喜ぶかどうかも分からない。
登記簿が告げた嘘は、あまりにも多くの人間の心を蝕んでいた。
登記簿が暴いた人間の業
紙の上に書かれた真実と、現実に存在する感情。その乖離こそが、最も深い闇なのかもしれない。
俺はその登記簿を閉じ、しばらくじっと目を閉じた。
解決のあとに残るもの
事件は解決し、相続人の娘とも連絡がついた。だが、彼女の第一声は「もう関わりたくない」だった。
それもまた、ひとつの現実。誰かの正義が、必ずしも誰かを救うわけではない。
依頼者の涙と真実
逮捕された依頼人は、俺に「やり直したい」と言った。その言葉をどう受け止めていいのか、俺には分からなかった。
ただ、再びこんな依頼が来ないようにと、心から願った。
やれやれ一件落着だが
事務所に戻ると、サトウさんが静かにコーヒーを出してくれた。「今回も、無事片付きましたね」
俺は小さくため息をついて言った。「やれやれ、、、こんなに疲れる相続は久しぶりだよ」
そして、また次の一件が来る音が、ポストから聞こえた気がした。