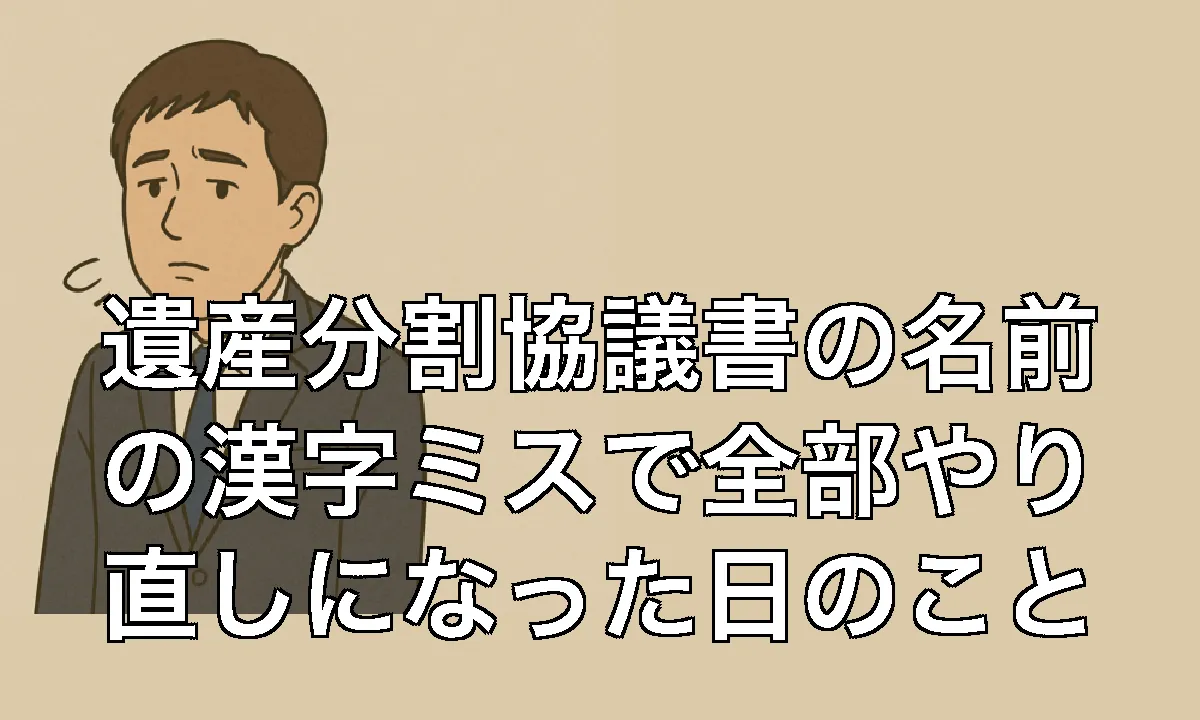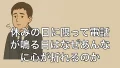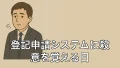たかが一文字されど一文字
司法書士をしていると、「そこ!?」と叫びたくなるようなミスで全てが台無しになることがある。先日あったのは、遺産分割協議書に記載された相続人の名前の漢字が間違っていたという事案。たった一文字。ほんのわずかな違い。でも、それがすべてを振り出しに戻す引き金になるとは、そのときは誰も想像していなかった。正直、「もう許してくれ」と叫びたくなるような案件だった。
地味だけど地雷な名前の誤字
今回の件、原因は「渡辺」さんの「辺」が「邊」になっていたことだった。旧字体か新字体か、本人にとってはどうでもいいと思っていたのかもしれないが、法務局も銀行もそこは容赦してくれなかった。本人確認資料と一致しない名前は、無効とされる。「そこを突くか」と思ったが、ルールはルール。私の目も事務員の目もすり抜けてしまった一文字が、数週間の作業を無にした。
「渡辺」と「渡邊」で修羅場になる
依頼者からの第一声は「こんな字、どっちでもいいじゃないですか」だった。気持ちは痛いほど分かる。しかし、法務局は機械的に書類を見る。印鑑証明書の氏名と協議書が完全一致しなければNG。しかも今回は、相続人が5人いた。5人全員の署名と実印が必要な書類を、また一から集め直し。本人は他の相続人にも説明と再捺印のお願い。もう、胃がキリキリ痛くなった。
相続人全員の署名捺印が水の泡
集め直すと言っても、全員が協力的とは限らない。「なんでまた?」と怒る人もいる。「自分は悪くない」と不満を漏らす人もいる。誰か一人でも「もうやらない」と言えば、調停行きも見えてくる。司法書士は書類を整えるだけとよく言われるけど、その過程にある人間関係の修復まで請け負わされるときがある。今回は、電話とLINEと手紙でひたすら謝り倒す日々だった。
訂正印では済まされない世界
「訂正印でいいでしょ?」と軽く言う人がいるが、こと相続登記においては話が別。訂正印が許されるのは、せいぜい数字の間違いや住所の軽微な誤記程度。名前の漢字の違いは、別人とみなされることがある。こちらも何度もダメ元で役所に食い下がるけれど、最終的には「やり直してください」の一点張り。結局、全部作り直す羽目になる。
役所や銀行の無慈悲な判断
「あんたの仕事が甘い」と怒鳴られたこともある。確かに、見逃したこちらにも落ち度はある。ただ、こうした名前の旧字体ミスは本人の戸籍にも旧字体で残っていることがあるため、非常にややこしい。銀行の窓口では、「免許証と一致しないので受け付けられません」と機械的に言われ、相談しても進展なし。誰も悪くないのに、全員が疲弊する構図ができあがる。
当事者の怒りが全部こっちにくる
最終的に、怒りの矛先は我々司法書士に向く。調整役なのに、調停員のような扱いを受ける。そして一番厄介なのは、感情をこらえきれない相続人がこちらを責め出す瞬間。「先生の確認不足ですよね?」と。グサッとくる。正論だ。でも、どこかで「そんな細かいとこまで…」という思いも正直あった。ダブルチェック体制があっても、こういう地雷は踏んでしまうときがある。
誰も得しないやり直し地獄
やり直しと一言で言っても、その負担は計り知れない。まず、物理的な書類作成だけで半日以上のロス。次に、相続人一人ひとりへの連絡と説明。電話がつながらない、日中は連絡できない、そんな人も多い。そしてやっと揃ったと思ったら、また誰かの捺印がにじんでいてやり直し…という無限ループ。正直、心が折れそうになる。
結局また一から説明しなおし
一度説明して納得してもらったことを、また説明するのは精神的にかなりキツい。「さっきも聞いたよ」と言われることもあるが、こちらとしては確認の意味も含めて話さなければならない。再び手続きをお願いする以上、納得してもらわなければ書類は戻ってこない。説明すればするほど、自分の非を認めているようで苦しい。
「もう一回出すだけでしょ?」の無理解
一般の方にとっては、「紙をもう一枚出せば終わるんでしょ?」という感覚だろう。けれども、実際はその裏に何十通のメール、何時間もの電話、そして何人もの説得と謝罪がある。事務所の仕事はその間すべてストップ。心のどこかで「たった一文字のために…」という無念さが残る。何より辛いのは、それを分かってもらえないことだ。
うちの事務所にも限界はある
たった一人の事務員と二人三脚でやっている事務所にとって、こういうミスは致命的だ。チェック体制はあるつもりだったけど、人間は完璧じゃない。今回は私の確認不足もあったし、事務員の作業が立て込んでいた時期でもあった。忙しさに追われて、大事な確認が疎かになっていた。どんなに誠実にやっていても、限界はある。
事務員一人じゃ捌ききれない
事務員が一人というのは、コスト的にはありがたいがリスクも大きい。たまたまその子が休みの日に問い合わせが殺到したり、複数の案件が同時進行したりすると、現場はすぐパンクする。今回の件も、複数の案件を同時に抱えていた中での見落としだった。小さな事務所の現実は、いつも綱渡りだ。
ダブルチェックしてても起きるときは起きる
私は元野球部で、試合前は必ず基本の反復練習をしていた。でも、どんなに素振りを繰り返してもエラーは起きる。書類の確認も同じだ。ダブルチェック、トリプルチェックをしても、人の目には限界がある。特に名前の漢字というのは、見慣れているぶん見落としやすい。まさか「邊」が落とし穴になるなんて思わなかった。
それでもやっていくしかない
正直、何度も「もう辞めたい」と思った。でも、依頼者の「ありがとう」で踏みとどまるのがこの仕事だ。今回も最後には「先生のおかげで助かりました」と言ってもらえた。その一言に救われる。そしてまた今日も、山のような書類に向き合っている自分がいる。愚痴を言いながらでも、少しずつでも、前に進むしかないのだ。
小さな見直しが未来を救う
今回の件を教訓に、書類の最終チェックには「声出し確認」を取り入れた。昭和の工場じゃないけど、「ワタナベサンノワタナベノヘンヲカクニン」と声に出すだけで、ミスはかなり減った。形式的でも、そういう地味な手間が後のトラブルを防いでくれる。アナログな手法も、捨てたもんじゃない。
同じように悩む誰かへ
今これを読んでいる司法書士の先生、もしくは目指している方、もしかしたら同じようなミスで落ち込んでいるかもしれません。でも、大丈夫。みんな一度はやってます。やり直す勇気があるなら、何度でも立て直せます。独り身で、モテなくて、愚痴ばかりでも、まだこの仕事を辞めてません。なんとか、やっていきましょう。