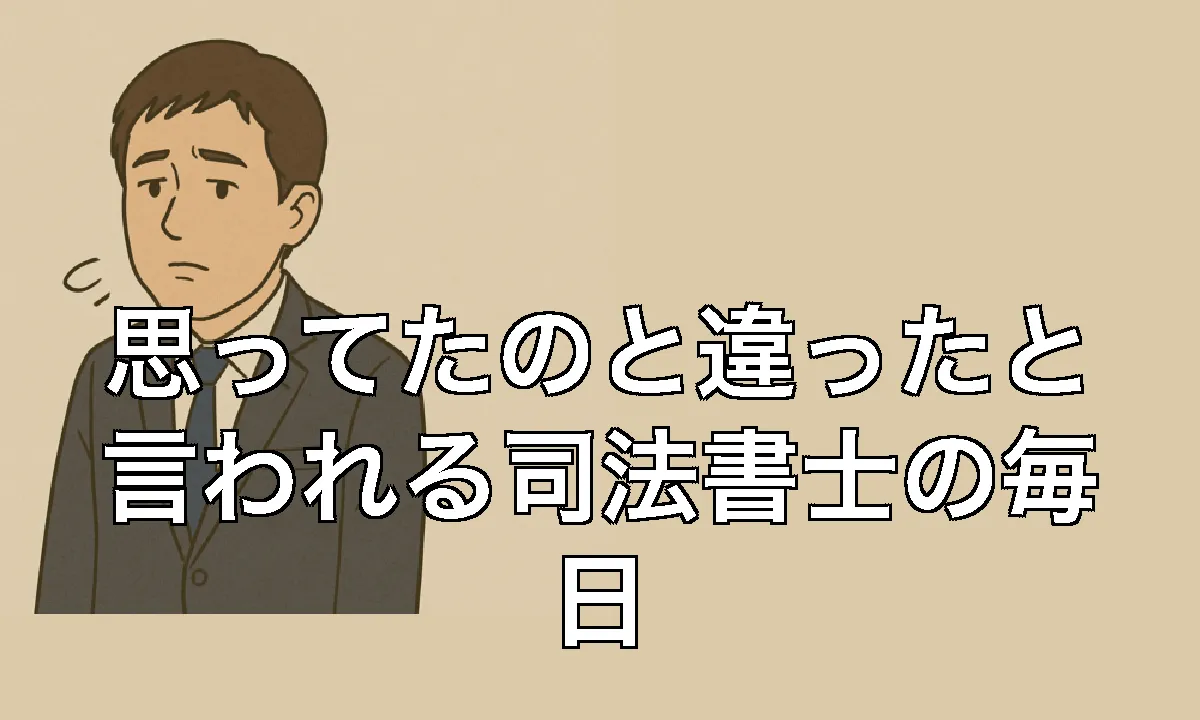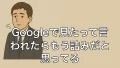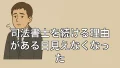忙しさの正体はどこにあるのか
司法書士といえば、「座って書類を作っているだけの人」と思われがちだが、実際はまるで違う。特に地方で一人事務所を運営していると、雑務から来客対応、時には草むしりまでやる羽目になる。忙しさの正体は、仕事内容そのものよりも、「こまごまとした隙間に無数の用事が挟まってくること」だ。全体のスケジュールは埋まっていないように見えて、なぜか一日が終わる頃にはクタクタ。これを毎日繰り返していると、仕事の内容よりも「何をやったか覚えていない自分」に呆れる瞬間がくる。
一人事務所の現実と限界
たとえばある日、午前中に相続登記の依頼が入り、午後には抵当権抹消の申請準備、合間に銀行からの電話、そして郵便局への外出。この時点でもう事務所にいられる時間はほぼ残っていない。誰かに頼もうにも、事務員はその日子どもの急病で休み。こういうとき、「やっぱり人を増やすべきか…」と頭をよぎるが、田舎でフルタイム雇用する余裕はない。現実と理想の間で、ただただ一人で右往左往しているのが本音だ。
電話と来客と提出書類の波
電話は鳴る。来客は来る。書類は終わらない。この3点セットがそろうと、脳がショートしそうになる。たとえば相談者が来ているのに役所から「至急の照会」の電話、そこへ別件の来客が現れる。何から処理するべきか、優先順位をつける暇もなく、全部が緊急に思えてきてパニックになる。書類に向かいたいのに時間が削られ、締切ギリギリに手をつけてまた残業。こういう日が週に何度かあると、「この仕事、思ってたのと違うよね」と本気で感じてしまう。
書類の山に隠れる人間関係のしんどさ
書類と向き合うだけならまだ楽だ。しかし、そこに「人」が関わると難易度が跳ね上がる。相続人同士が揉めていたり、依頼者が話を聞かず自己流で動いたり、感情の処理が必要になる場面も多い。僕は元野球部でそこそこ我慢強いつもりだが、感情的なやり取りが続くとさすがにきつい。相談者との関係に気を遣いながら、ミスのない書類を用意する。まるで綱渡りのようだ。書類の山の向こうに、人間関係のしんどさがひっそりと隠れている。
頼れる人がいない日常
昔、法務局の帰りに急にお腹を壊して、事務所に戻れず車内でうずくまったことがあった。その時、誰かに電話して「今日はお願い」と言えたらどれだけ気が楽だったろう。でも、現実は一人。体調が悪かろうと誰も代わってくれない。事務員もいない日なら、すべて自分で対応するしかない。孤独というより「誰にも頼れない構造」の中で働いている実感がある。頼ることができない環境は、じわじわと心を削っていく。
事務員も人間 こちらの都合通りにはいかない
うちの事務員はとてもまじめで助かっている。でも、彼女にも生活がある。子どもの行事、体調不良、急用。すべて「今日しかダメなんです」と言われれば、「いいよ」としか言えない。すると残る業務は僕がやる。これが積もると、「自分だけが働いている気がしてきて」疲れてしまう瞬間がある。理屈じゃない。感情だ。「このやるせなさ、誰に言えばいいんだろう」とコーヒーを片手にため息をつくのが、最近のルーティンになりつつある。
何でも自分でやるのが当たり前になっていた
開業当初は、「一人で全部こなすのが理想」と思っていた。でも今は、「全部一人でやらないと回らない」が現実になっている。郵送、PDF化、封筒印刷、押印、記帳、請求書…それ全部、僕がやっている。司法書士の仕事ってこんなに雑用多かったっけ?と、ふと疑問に思うけれど、誰かに投げられるような環境じゃない。手伝ってほしいと言えばいいのに、それも言えない自分がいる。この「自分で全部背負う癖」が、ますます孤立を深めている気がする。
思ってた司法書士像とのギャップ
司法書士になる前、もっと堂々としていて、静かな仕事を想像していた。事務所で穏やかに書類を見ながら、お茶でも飲みつつ対応する…そんなイメージ。でも実際は、時間に追われ、対応に追われ、ミスに怯えている。現実は予想の斜め上をいく。「思ってたのと違った」と思うのは僕自身なのかもしれない。
ドラマに出てくるような活躍はない
たまにドラマや映画で司法書士が出てくると、スマートで知的な人物として描かれている。現実の僕とはまるで別人。書類に囲まれて、プリンターと格闘して、外出中に電話が鳴り止まず、クレーム対応までこなす。そんな日々に「かっこよさ」はどこにもない。スーツを着ていても中身はヘロヘロ。元野球部だという過去だけが、かろうじて自尊心を支えている。実務は派手さのかけらもない。
地味で地道で単調な作業の連続
業務の大半は、調査・確認・チェック・記録。この4つの繰り返し。ミスは許されないからこそ、毎回同じ確認作業を延々と繰り返す。まるでグラウンドのノック練習みたいだ。ミスなくやって当たり前、できて当然。それが司法書士の基本姿勢。だけど、評価されることはない。「何も言われないこと」が合格点。そうやって誰にも気づかれないまま、1日が過ぎていく。
正義感よりも締切との戦いの日々
司法書士を目指していた頃は「困っている人を助けたい」と思っていた。確かに、今もその気持ちはある。でも実際には、毎日の締切やスケジュールとの戦いに追われ、「人を助けている」という実感が薄れていく。書類の提出期限、法務局の受付時間、郵便の投函時間。時間に縛られることのほうが圧倒的に多くて、理想はどんどん遠のいていく。それでもやめられないのは、たまに「ありがとう」と言ってもらえる瞬間があるからなのかもしれない。
周囲の期待と現実の温度差
地元では「先生」と呼ばれたりもするが、それがむしろ重荷になることもある。周りは「すごいね」「安定してるね」と言うけれど、実態を知ったらたぶん驚くだろう。仕事の内容も、収入の上下も、精神的な負担も、「想像以上」なんじゃないかと思う。期待されればされるほど、「そんな立派なもんじゃないです」と言いたくなる。このギャップがまた、自己肯定感を削ってくる。
親戚からは先生と言われるけど
盆や正月に親戚が集まると、「司法書士さん」と呼ばれてちょっとした空気が変わる。「立派な職業だね」と言われるけれど、僕は内心で「いやいや」と思っている。年末に休みなく働いていることも、月末に預金残高を見てため息ついたことも知らない彼らに、何をどう伝えればいいのか。口に出せば愚痴になりそうで、結局「そうですね」と曖昧に笑っている自分が情けなくなる。
モテるとかいう幻想は早く捨てたほうがいい
これは若い頃の話だが、「士業ってモテるらしい」と思っていた。実際はどうかというと、まったくそんなことはない。むしろ仕事が忙しすぎて、出会いすらない。休日も平日も仕事が頭から離れず、LINEの返信も遅れがち。そんな状態で恋愛なんて無理だ。モテるどころか、「また連絡が遅い」と言われてフェードアウトされた経験が何度もある。だから今は「モテよう」という気持ちは捨てている。せめて仕事だけでも…と思うけれど、それも報われない日があるから困る。