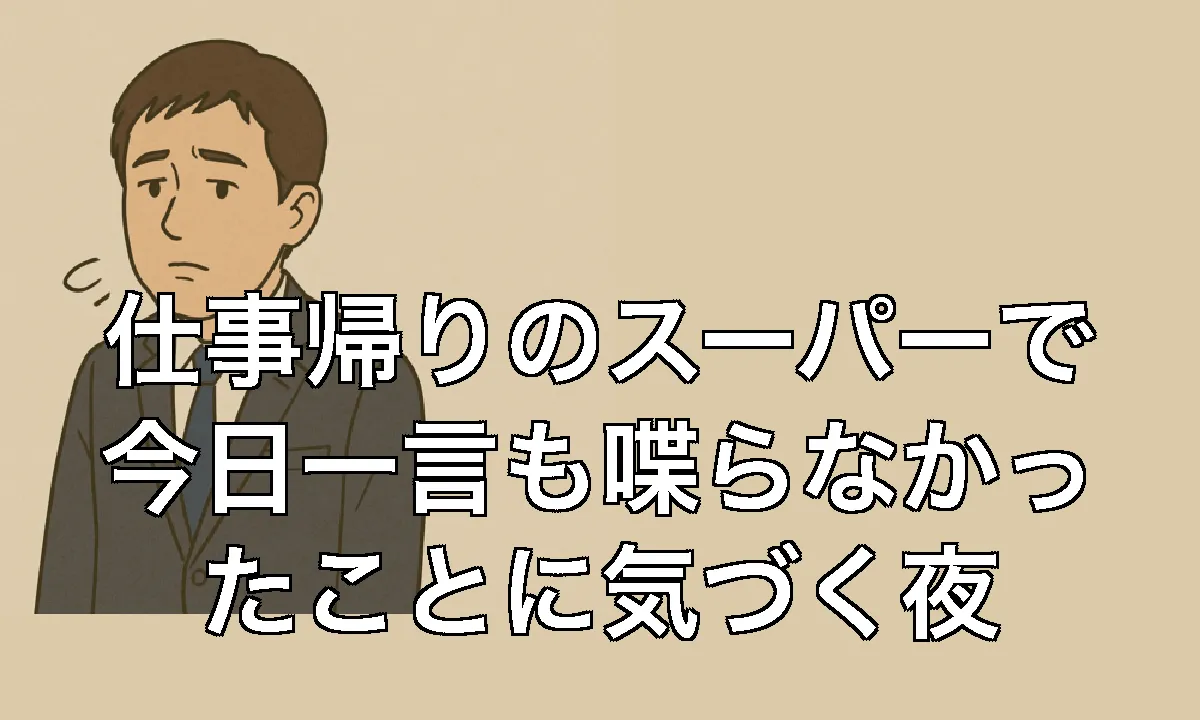ふと気づく静かな一日の終わり
レジ袋の音だけが静かに響く帰り道。仕事を終えて寄ったスーパーで、ふと「今日、一言も誰かと喋ってない」と気づいた。事務所では電話対応もあったし、事務員とも必要最低限のやりとりはあった。でも、声に温度がなかった。帰りに寄ったスーパーで、誰かと会話したわけでもなく、レジで「袋いりますか?」と聞かれたのが唯一のやりとりだった気がする。それすら、こちらはただ頷いただけだった。
話す相手がいないという現実
この年齢になって、誰とも話さず一日が終わるなんて、想像していなかった。若いころは常に誰かと関わっていたし、元野球部というのもあって、仲間との掛け合いが日常だった。でも、今は一人で事務所を切り盛りし、事務員ともあまり雑談がない。仕事は忙しく、集中していると時間は過ぎるが、ふとした瞬間に襲ってくる「自分、誰にも必要とされていないんじゃないか」という感覚が、息をするように日常に溶けている。
レジの「ありがとうございました」だけが残る
レジの店員さんは、丁寧に「ありがとうございました」と言ってくれる。それは仕事だからだし、向こうも義務感だろう。でも、その一言が、今日一日の中で一番“まともな人との関わり”だったと思うと、胸がすこしきゅっとなった。人と話すことがこんなにも貴重に思えるのは、逆に普段からそれが欠けている証拠かもしれない。自分の生活の中で、誰かの声がこんなにも温かく感じられるとは思っていなかった。
司法書士という仕事の孤独さ
司法書士という仕事は、人と関わるようでいて、意外と孤独な職業だ。依頼者と顔を合わせる時間は限られていて、あとは書類作成と手続きの連続。集中している時間が多く、それが日常になると、「誰かと一緒にいる」という感覚そのものが薄れていく。周囲からは「専門職で安定していて羨ましい」と言われることもあるが、正直、安定と孤独は紙一重だ。
会話のほとんどが電話と書面
事務所にいて誰かと話すと言っても、それは電話でのやりとりがほとんど。しかも内容はトラブル、確認、催促、手続き……。雑談ではない。メールやFAXで済むやりとりも多く、直接会話を交わす機会が減っている。書類には無数の言葉が並んでいるのに、声がない。私は毎日文章を扱っているのに、そこに“会話”はない。だからこそ、スーパーの「ありがとうございました」が妙に染みるのだ。
依頼者との距離感は縮まらない
感謝されることもある。丁寧にお礼を言われると「この仕事をしててよかったな」と思う。でも、それは一瞬で、また黙々と登記申請や書類整理に戻る。相手に寄り添いたいと思っても、立場上はっきり距離を保たなければいけないし、無用な親しさはかえってトラブルを招くこともある。信頼は築くが、心を通わせる場面は少ないのが現実だ。
事務員とのやりとりも必要最低限
事務員とは仲が悪いわけではない。むしろ良くやってくれている。でも、年齢も性格も違えば、自然と会話も業務に限られる。愚痴を言いたいときも、相手に気を遣って言えないし、こっちも疲れているから雑談する余裕もない。たまにふざけた話を振ってみるけど、笑いのタイミングがずれて、余計に寂しくなることもある。
忙しさに飲まれて気づかない心のすき間
スケジュールが詰まっている日は、むしろありがたい。考える余裕がないからだ。だが、ほんの少し手が空いたときに訪れる「虚無」。そのとき気づくのだ。誰とも目を合わせていないことに。誰かに「お疲れさま」と言いたいのに、言う相手がいない。だからこそ、スーパーの買い物が“人の中に入る唯一の時間”になることもある。
「今日、誰かと笑ったっけ」
ふと湯船に浸かりながら思う。「今日、声出して笑ったか?」と。思い返しても、笑った記憶がない。テレビを観て薄く口角が上がったかどうか。それくらいだ。誰かと顔を見合わせて、しょうもないことで笑う。それだけで人は生き返る気がする。けれど今の生活には、その“笑う瞬間”が極端に少ない。
業務に追われると感情を置いてきぼりにする
司法書士の仕事は正確性が命。感情に流されてはならない。だから、日々冷静さを装い、感情を封印するのが癖になっている。でも、感情のない状態が続くと、人間として何かを失っている気がする。感情は迷惑でもあり、でも必要でもある。封じたまま生きると、心がどこかで錆びる。
繁忙期の方が孤独が際立つ皮肉
皮肉なことに、忙しいときほど、孤独感は増す。周囲とすれ違う速度が早くなり、誰の顔も見ずに仕事を終える。帰宅して気づく「今日一日、誰と目を合わせた?」という問い。それに答えられない日は、すこしだけ自分が透明人間になった気分になる。
それでもこの仕事を続ける理由
こんなにも孤独で、こんなにも喋らない日々でも、それでもこの仕事をやめようと思わないのは、やはり“誰かの役に立っている”という感覚があるからだ。直接は届かなくても、自分が処理した書類の先に、誰かの安心や、誰かの新しい生活があると信じている。声に出さない声を、仕事を通して聞いている気がする。
誰かの役に立てる喜びはちゃんとある
「先生のおかげで助かりました」そう言われるときだけは、報われる。人と会話することよりも、その一言のほうが何倍も心に響くことがある。少しの関わりでも、確かな手応えがある。喋らない日々でも、それはきっと、声以上に深く人とつながっている証なのかもしれない。
感謝の言葉が染みるのは、静かな日が多いから
毎日喋っている人にとっては、感謝の言葉も流れていくのだろう。でも私のように静かな日々が続くと、その一言がずっと残る。だから今日もまた、誰とも話さなかったことに気づいた夜に、「また頑張ろう」と思える。声はなくても、自分の仕事が、誰かの暮らしの中でちゃんと役に立っていることを信じて。