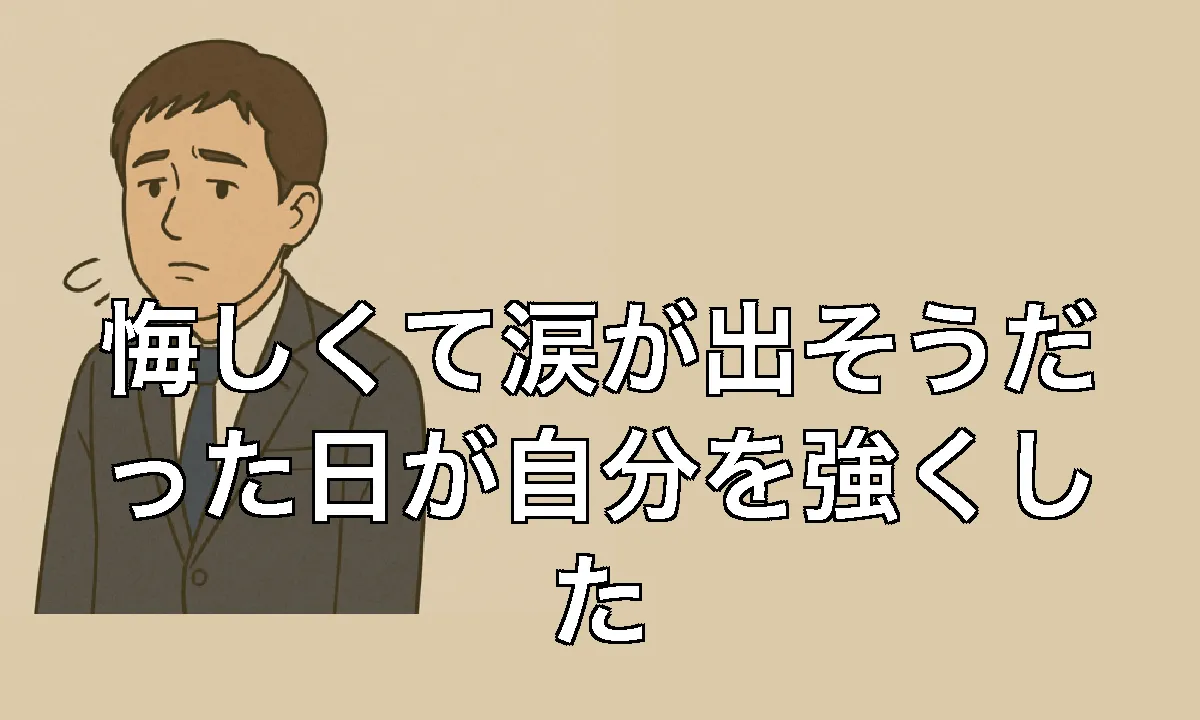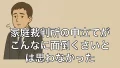朝から嫌な予感がしていた
月曜の朝、なんとなく胸騒ぎがしていた。書類の山、鳴り続ける電話、そして来所予定のお客様の名前を見ただけで、体のどこかが冷える感じがした。予感というのは得てして当たるもので、案の定、その日は散々だった。まだ経験が浅かった頃、司法書士としての自信もなかった。ちょっとしたミスが、取り返しのつかないトラブルに発展する可能性があるこの仕事。だからこそ、緊張感と不安を抱えて始まる一日だった。
月曜の朝イチで叱られると1週間が終わった気分になる
その日は朝から先輩に叱られた。書類のチェックミスがあったのだ。言い訳のしようもなかった。けれど、月曜の朝一番で怒られるというのは、かなりこたえる。週の始まりから心が折れてしまうと、立て直すのが難しい。野球部時代、試合の初回にエラーをしたときの、あの「やっちまった感」に似ている。まだまだ先は長いのに、気持ちはすでに負けていた。
電話が鳴るたびに心臓がキュッとなる
それ以来、その日の電話の音がトラウマのようになった。事務員が席を外していたため、すべての電話に私が出ることになったのも悪循環だった。電話が鳴るたびに、また何か指摘されるのではとビクビクしながら受話器を取っていた。声のトーンもぎこちなく、相手に不安を与えていたかもしれない。自分が壊れてしまいそうな感じだった。
先輩のあの一言が今も耳に残ってる
「こんなことも分からないのか」。先輩のその言葉が、胸に突き刺さった。頭では分かっている。怒っているのは仕事に対してであって、私自身を否定しているわけではないと。でも、心がついてこなかった。言葉ひとつでこんなにも人は落ち込むのかと、自分の繊細さを恨んだ。けれど、不思議とその言葉が、今も私の背中を押している。
仕事ができない自分に落ち込む
事務所に戻ってから、なんとも言えない虚無感に包まれた。誰も何も言っていないのに、自分の存在が場違いのように感じてしまうあの感覚。向いてないんじゃないか、辞めたほうがいいんじゃないかと、頭の中をぐるぐるとネガティブな言葉が巡る。何も手につかず、ただデスクに座っているだけの時間が流れた。
分かってるのに体が動かないあの感じ
やらなければならないことは分かっている。書類を直さなければいけないし、午後にはお客様との面談もある。でも、体が動かない。腕が重く、指先が動かない。まるで誰かが自分を止めているようだった。それでも、机の上のタスクは待ってはくれない。誰か助けてくれ、と心の中で叫びながら、ただ黙って座っていた。
指摘されることが怖くてたまらなかった
その日以降、誰かに何か言われるのがとにかく怖かった。特に、先輩の足音が近づいてくるだけで緊張した。心の中では「落ち着け、冷静に」と自分に言い聞かせているのに、手元のペンは震えていた。まるで試合でエラーした直後、次のプレーが回ってくるのが怖くて仕方がなかったあの感覚だった。
でも、投げ出す勇気すらなかった
本当に辞めたいと思った。けれど、その一歩が踏み出せなかった。実家に帰って「やっぱり無理でした」と言う自分を想像するだけで、情けなくなった。逃げることは簡単だけど、やりきることの方が難しい。でも、せめて今日だけは乗り切ろう。そう自分に言い聞かせながら、手を動かし始めた。
悔しくて泣きそうになりながらも机に戻った
しばらくして、ようやく机に戻った。涙が出るのをこらえながら、パソコンを開いた。事務員が戻ってきて声をかけてくれたのが救いだった。「大丈夫ですか?」の一言に、心が少しだけ軽くなった気がした。叱られたこと、落ち込んだこと、すべてを飲み込んで、少しずつ仕事に戻っていった。
泣いたら負けだと思ったけど涙は出そうだった
「泣いたら負けだ」。そう思いながらも、目の奥がジワっと熱くなるのを止められなかった。机の上に落ちた一滴が、なんとも情けなかった。だけど、それが自分の全力の証だったようにも思える。やれるだけのことはやった。そう思いたかった。悔しいという気持ちは、まだ踏ん張れる証拠なのかもしれない。
「自分には向いてない」と思ったあの日
正直、「司法書士に向いてない」と思った。人とのやりとりも、法律の知識も、すべてがプレッシャーだった。こんな小さな事務所でさえ、こなせない自分が、今後やっていけるのか。資格は取ったけど、それだけでやっていける甘い世界ではない。だけど、現実は逃げ場のないフィールドだった。
それでも辞めなかった理由
辞めなかった理由を言葉にするのは難しい。でも、あの日の悔しさと、自分への怒りと、少しのプライドが、踏ん張る力になった気がする。野球で言えば、コールド負けにならないよう、意地で9回まで戦い抜くような気持ちだったのかもしれない。とにかく、「もう一日だけ頑張ってみよう」。それが、その日を越える唯一の方法だった。