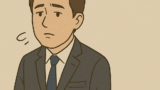雨の朝に届いた封筒
朝から土砂降りだった。気温も低く、まるで誰かの機嫌の悪さが天気に乗り移ったような空模様だった。そんな中、事務所のポストに一通の茶封筒が届いていた。切手の位置がずれており、宛名も妙に震えていた。
「これ、普通の書類じゃないですね」とサトウさんが低い声で言った。封筒には差出人の名前がなかった。なんとなく、ただならぬ雰囲気が漂っていた。
中身は登記簿のコピーと、手書きの短いメモだけだった。そこには、たったひとこと。「この名義人は生きていないはずです」と。
差出人不明の書類
メモの筆跡は震えており、急いで書かれた印象を受けた。だが、内容はあまりに衝撃的だった。登記簿には、確かに“中野文三”という名前が名義人として記されている。
ただし、この人物について私は別件で扱ったことがあり、その時点で彼はすでに他界していたはずなのだ。死亡届も戸籍も確認していた。つまり、この名義は「幽霊名義」というわけだ。
「これは、、、少し厄介ですね」と私は呟いた。サトウさんが無言でホワイトボードを引き寄せた。
開封された封筒の違和感
さらにおかしなことに、封筒の封が完全に開いていた。つまり、誰かが一度開けてからまた投函した可能性がある。宛名の筆跡と中のメモの筆跡が一致していないことにも気づいた。
雨で少しにじんだインク。それでも、薄く残る封緘の痕跡は封筒が一度閉じられたものではなかったことを示していた。差出人は一体、何を伝えたかったのか。
まるで怪盗キッドからの予告状のように、曖昧なヒントだけが残されている。
登記簿の片隅に見えた異変
送られてきた登記簿には確かに“中野文三”の名が記されているが、添付されているはずの遺産分割協議書が存在しない。しかも、住所が異様に古いままになっていた。
「これは、相続登記が途中で止まってるのかもしれませんね」とサトウさんが言う。私はふと、今の時代に合わない紙質の登記簿を撫でながら首を傾げた。
「いや、、、そもそも、これは最新の情報じゃない。手を加えられてる可能性があるな」と私は唸った。
仮登記の主張と実登記の影
しかも、その名義は「仮登記」ではなく、完全な「所有権移転登記」として記載されている。どう考えても不自然だ。仮登記から実登記に移るには、明確な裏付け書類が必要なはず。
その過程が一切ないまま、まるで“ある日突然、土地が死人の名義になった”ようにしか見えなかった。
「やれやれ、、、また面倒なことに巻き込まれたな」と思わず声に出た。
名義人の謎に包まれた足取り
戸籍を調べ直してみると、中野文三の死亡記録は10年前にあった。火葬許可証もきちんと残っている。だが、それ以後に登記が動いているのだ。まるで死人が判子を押したかのように。
「幽霊が実印持って戻ってきたんですかね」とサトウさんが皮肉を言う。まったくその通りだ。
私は頭をかきながら、サザエさんの波平よろしく「バカモーン!」と叫びたい気分だった。
依頼人は無口な老女
午後になって、一人の老女が訪ねてきた。しわがれた声で「相談したいことがある」と言いながら、そっと机に古びた手提げ袋を置いた。中には、色あせた戸籍謄本と一冊の古いノートが入っていた。
「文三は、もう、、、死んでるんです。でも、登記は戻らなかった」と彼女はぽつりと呟いた。
私は静かに頷いた。この人が、差出人なのかもしれない。
過去に縛られた言葉
ノートには、昭和の終わり頃の記録が丁寧な文字で綴られていた。農地転用、売買契約、仮契約、そして転売。それらが手書きで追いかけられていた。
ただ、あるページだけが破かれていた。そこに、重要な何かが記されていた気がしてならなかった。
「これは、、、掘れば掘るほどドロが出ますね」と私はつぶやいた。
サトウさんの冷静な指摘
ホワイトボードに付箋が増えていく中、サトウさんが一つの資料を差し出してきた。「先生、この筆跡、微妙に違いませんか?」
それは所有権移転登記の申請書類だった。確かに、印鑑は同じでも、署名の“文三”の文字の崩し方が微妙に異なる。別人が書いたとしか思えなかった。
「筆跡鑑定は司法書士の仕事じゃないけど、、、これは警察が絡む案件かもしれないな」と私の顔も引き締まった。
真犯人は机の向こう側にいた
一週間後、調査に協力してくれた元銀行員の情報で、驚くべき事実が明らかになった。なんと、登記申請に関与したとされる司法書士の印鑑が盗用されていた。
つまり、偽装登記だったのだ。そして、その登記の申請書を提出した者の名前は、、、先日訪れた老女の甥だった。
「家族って、時々一番ややこしいですね」とサトウさんが呟いた。私は深くため息をついた。「やれやれ、、、もう誰も信じられん」。
事件の終わりと事務所の日常
登記は無効として抹消され、正しい相続が行われた。老女は、深々と頭を下げて事務所を後にした。笑顔というには少し苦い、そんな表情をしていた。
私はぐったりとソファに腰を下ろし、ため息をついた。「また一つ、心のシミが増えたな」。サトウさんは無言で、コーヒーを私の机に置いた。
ふと目をやると、ホワイトボードに残された最後の一言。「名義は、心を映す鏡かもしれませんね」、、、あいつ、やっぱり只者じゃない。