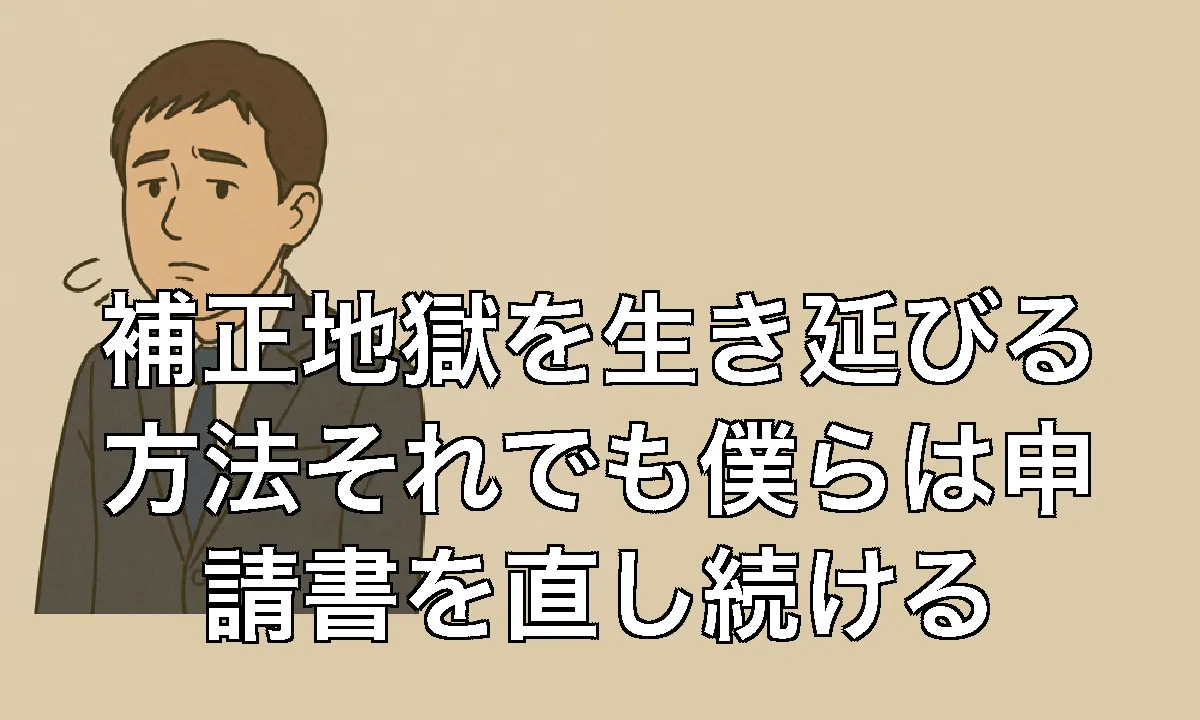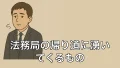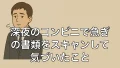そもそも補正って何なのか
補正とは、司法書士が法務局に提出した申請書類の内容に不備や誤記があった場合に、法務局からの指摘に基づいて修正を求められるものだ。字面で見るとただの「直し」に思えるが、現場にいるとこれがなかなかの地獄。補正通知が届いた瞬間、胃がキュッとするような感覚になる。「またか…」と思わず口に出てしまうのは、僕だけではないはずだ。
補正通知が届くたびに思うこと
封筒を開ける手が、どうにも重い。「何がいけなかったんだ」と自問自答しながら、まず見るのは受付印の日付。申請から数日経って届く補正通知は、まるで過去の自分からの反省文のようなもの。開封して一文目に「登記原因証明情報の記載が不十分です」なんて書いてあると、心が折れる。わかってる、ミスしたのは自分。でも、もう少し優しく言ってくれてもいいじゃないか。
「またか…」の溜息が出る瞬間
補正通知を見るたびに、「この案件、早く終わらせたかったのに」とつぶやいてしまう。しかも多くの場合、その修正には1ミリも報酬が上乗せされない。事務員と二人で黙々と訂正作業を始めるが、空気は重い。せっかく片付いたと思った案件が再び蘇る。自分の未熟さを突きつけられたようで、ただただ気が滅入る。
内容確認より先に確認するのは受付印
受付印の位置や日付が真っ先に目に入るのは、納期との闘いをしているせいかもしれない。「この日付でこのタイミングということは、まだ間に合うか…」と、反射的に判断してしまう。補正内容より先にタイムリミットの確認。それが習慣になってしまった自分に、時々嫌気が差す。
補正地獄に陥るまでの道のり
補正はある日突然始まるわけではない。ちょっとした見落としや、慣れによる油断が重なることで、いつの間にか「補正の常連」になってしまう。特に注意力が下がっている繁忙期には、普段ならしないような初歩的ミスを繰り返す。気づけば、補正通知の束が机の端に積み重なっていた。
一件の誤字から崩れていく連鎖
僕の場合、一番最初のつまずきは登記義務者の住所の番地の誤記だった。それも、見た目には気づかないような「丁目」と「番」の打ち間違い。そこからずるずると、印鑑証明の有効期限を見落としたり、添付書類を間違えたり…。一件一件のミスは小さいのに、なぜか連鎖していくのが補正の怖さだ。
見落としが見落としを呼ぶ地獄
見落としたまま提出してしまうと、補正通知が来るまでミスに気づかない。そして補正に気を取られることで、次の案件でもまたうっかりが増える。この悪循環に陥ると、気持ちの余裕が完全に失われる。気をつけているつもりでも、焦って確認をおろそかにしてしまい、さらに補正を呼び込む。
事務員に責任を押しつけたくなる夜
「あのとき確認してくれれば…」と、事務員に思わずあたりたくなる瞬間もある。もちろんそれは筋違いだとわかっている。責任は最終的に僕にある。でも、夜遅くまで事務所に一人残って補正作業をしていると、そんな感情が胸に湧いてしまうのだ。
誰のための申請書か分からなくなる
補正が続くと、だんだんと自分が誰のために仕事をしているのか分からなくなる瞬間がある。依頼者のため、という建前は崩れ、法務局のために書類を整えているだけのような気がしてくる。そんなとき、ふと「俺、何やってるんだろうな…」と声に出してしまうことがある。
依頼者と法務局と自分の三すくみ
依頼者は当然、正確かつ迅速な登記を望む。法務局は形式に厳しく、少しでもずれていれば補正通知。間に挟まれた僕はというと、どちらにも頭を下げながら、自分の落ち度と向き合う日々。まるで、どこにも逃げ場のない三すくみのようだ。しかも、その中で一番報われないのが自分のような気がしてならない。
どこに正解があるのか分からない
補正指示に沿って書類を直しても、再補正になることがある。理由を聞こうにも電話はなかなかつながらず、窓口に足を運べば「こちらの見解としては…」と曖昧な説明。正解があいまいなまま試行錯誤を強いられる作業は、精神的にかなりくる。
経験があるほど迷走するのはなぜか
不思議なことに、司法書士としての年数が増えても補正がゼロになるわけじゃない。むしろ、「これでいいはず」と思い込んでしまうことで、細かい部分の確認を怠るようになる。経験者ゆえの慢心。それが補正地獄の引き金になることもある。