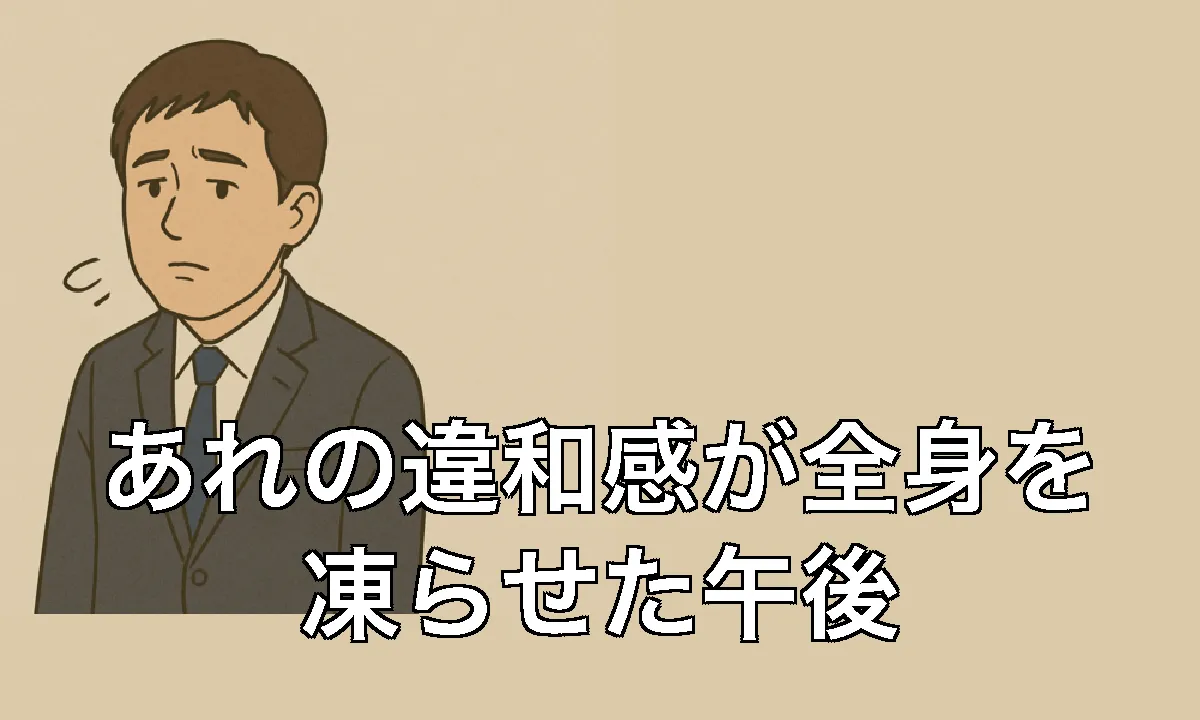あの日の午後 突然訪れた背筋の冷たさ
なんでもないような日だった。朝から予定通りに進んでいた登記の処理。急ぎの案件もない。事務員も落ち着いてデータ入力をしていて、僕はというと、郵便で届いた書類を一通一通確認しながら、ゆるやかな午後を過ごしていた。そんな時、ふと一枚の書類に視線を落とした瞬間、背筋に走る冷たいものを感じた。頭が真っ白になるような違和感。その正体が何かも分からないうちに、体が勝手に固まってしまった。
何気なく見返した書類の一行
それは、すでにチェック済みのはずだった委任状。控えもちゃんと取ってあるし、捺印もある。問題ないはずの書類に、なぜか目が止まった。「これ、前にも見たよな…」と一度は通り過ぎたつもりだった。でも、その“はず”がどこか引っかかって離れない。何度か目をこすって見直すうちに、一文字だけ、いや一箇所だけ、日付のズレに気づいた。依頼人の署名日が、実際の申請日より未来になっていたのだ。なんで今まで見逃していたんだろう。
確認作業は終わったはずだったのに
自分でも信じられなかった。あれほど慎重にやったつもりだった確認作業。それでも、最後の最後にこうしてミスを見つけてしまうと、「じゃあ今までは何だったんだ」と落ち込む。書類の束を見返しては、頭の中で手順を巻き戻す。「あの時、事務員さんが電話対応してたし、自分が焦ってたし」などと言い訳が頭をめぐる。でも結局、目の前の現実は変わらない。出していたらアウトだった。単純だけど、恐ろしいミス。
それでも消えなかった違和感の正体
たぶん、どこかで心のセンサーが働いていたんだと思う。目では見逃していたけど、無意識の中で違和感を覚えていたから、また手に取った。あの「なんとなく」って感覚、僕らの仕事では本当に大事だと思う。でも、裏を返せば、「完璧な確認なんて存在しない」ってことでもある。いつもどこかに、見落としの可能性があるという前提で動く。その前提が、いつも自分を疲れさせる。全身が冷えるのは、寒さじゃなくて、気づかなかった自分への恐怖だ。
冷や汗とともに蘇る過去のミス
この瞬間が初めてじゃない。過去にも、登記申請の提出ボタンを押す直前で「添付書類が足りない」と気づいたことがある。あのときも冷や汗が止まらなかった。司法書士という職業は、失敗がすぐには表に出ないぶん、後から大きく響く。だからこそ、冷や汗をかく瞬間に、いつも過去の自分がよみがえる。「またやってしまったかもしれない」と、胃がキリキリ痛むのだ。
「またやったかもしれない」という予感
この仕事をしていると、「これは大丈夫だろう」という楽観が、一番の敵になる。自信が油断に変わる瞬間が、いちばん怖い。今回もそうだった。一度確認していたという記憶が、見直しを甘くしていた。でもそれは記憶であって、証明ではない。どれだけ経験を積んでも、予感に頼る瞬間がある。「なんか変だ」という直感が働いたら、素直に見返す勇気が必要だ。
小さなミスが呼び起こす大きな不安
この「日付のズレ」も、冷静に見れば小さなミスかもしれない。でも、出していたら法務局から補正指示が来て、依頼者に謝罪して、関係者に連絡して…と、一気に地獄のような展開になる。司法書士の仕事は、結果的に「何も起きなかった」が最良で、「何か起きた」時点で全てがマイナス。だから、小さなミスでも過剰なほど自分を責めてしまう。そしてまた、不安に取り憑かれる。
たった一字に翻弄される仕事の現実
一文字、一日、一筆。そのどれかがズレるだけで、仕事が崩れる世界。言葉にすればシンプルだけど、現場ではそんな軽さじゃ済まない。特に地方で一人事務所を運営していると、確認作業も、提出作業も、説明も、すべて自分が最終責任者。精神的にも体力的にも、気を抜ける時間がない。地味な職業だとよく言われるけれど、その裏には「見落としたら終わり」というプレッシャーが常にある。
「間違えてないはず」の思い込みの危うさ
一度提出してしまえば、もう後戻りできない。その恐ろしさがあるからこそ、「間違えてないはず」と思ってしまった瞬間に負けが決まる。自信と慢心は紙一重。この仕事で長くやっていると、確認作業を省略したくなる誘惑と常に戦わないといけない。時間が足りない、疲れている、今日はもう帰りたい…そんな気持ちと戦いながら、毎回同じ書類を何度も何度も見直す。
確認のフリをしていた自分への怒り
正直に言えば、僕はときどき確認の“フリ”をしていたことがある。「一応見ておこう」という表面上のチェックで、本当は見ていなかった。見た気になっていただけ。今回の一件で、それがいかに危険かを思い知った。怒りというより、情けなさの方が強い。司法書士の肩書きがある自分が、確認作業を疎かにしていたなんて。本来なら依頼人を守る立場なのに、自分の油断でそれを脅かしていた。
それでも最後に救われた紙一重の偶然
ミスに気づいたのは偶然だったかもしれない。でも、その偶然に救われた事実が、また皮肉でもある。「ギリギリで気づいたから良かったね」と思われるかもしれないが、僕からすれば、それは敗北に近い。ちゃんと最初に見抜けていれば、こんな冷や汗をかかずに済んだ。それでも、ギリギリで踏みとどまれたことを感謝しなければとも思う。その一歩手前で止まれたことで、信頼を守ることができたのだから。
こんな日々を重ねながら僕らは仕事を続けている
誰にも褒められない日々。誰にも気づかれない確認作業。毎日地味で、正直やってられないと思うこともある。でも、今日もこうして仕事をしている。書類の山に囲まれて、事務員さんの溜息を背中で聞きながら、それでも依頼者の安心のために、なんとかやっている。完璧ではないけれど、誠実ではありたい。その思いだけで、冷や汗を拭きながらまたペンを取る。
独身司法書士の独り言に見えて実は多くの共感
ひとり事務所、独身、元野球部、そしてミスに怯える日常。特別なことじゃないけれど、似たような思いを抱えてる人、きっと多いと思う。だから、こうして文章に残しておきたい。司法書士でなくても、何かを背負っている人なら、この「冷える瞬間」の怖さがわかるはず。誰にも見せない裏側に、共感があるなら、少しは意味があるのかもしれない。
事務員さんに頭が上がらない日々
ちなみに、今回も事務員さんが「これ、念のためもう一度見ておきましょうか?」と声をかけてくれたのがきっかけだった。僕のプライドは傷ついたが、彼女の冷静さに救われたのは間違いない。こういう時、つくづく思う。「一人じゃ無理だな」って。肩書きじゃなく、人の目と気配りが仕事を支えている。感謝しないといけない。でも、つい「俺がなんとかした」って言いたくなるんだよな。
それでも辞められない理由がある
大変だし、報われないし、誰かに感謝されることなんて少ない。それでも、司法書士という仕事を辞めずにいるのは、やっぱり「責任」があるからなんだと思う。誰かの大切な手続きに関わっているという緊張感と誇り。それがなければ、とうの昔に投げ出していたかもしれない。今日もまた冷や汗をかくかもしれないけれど、それでもまた、書類を手に取ってしまう。きっと、それが僕の選んだ道なんだ。