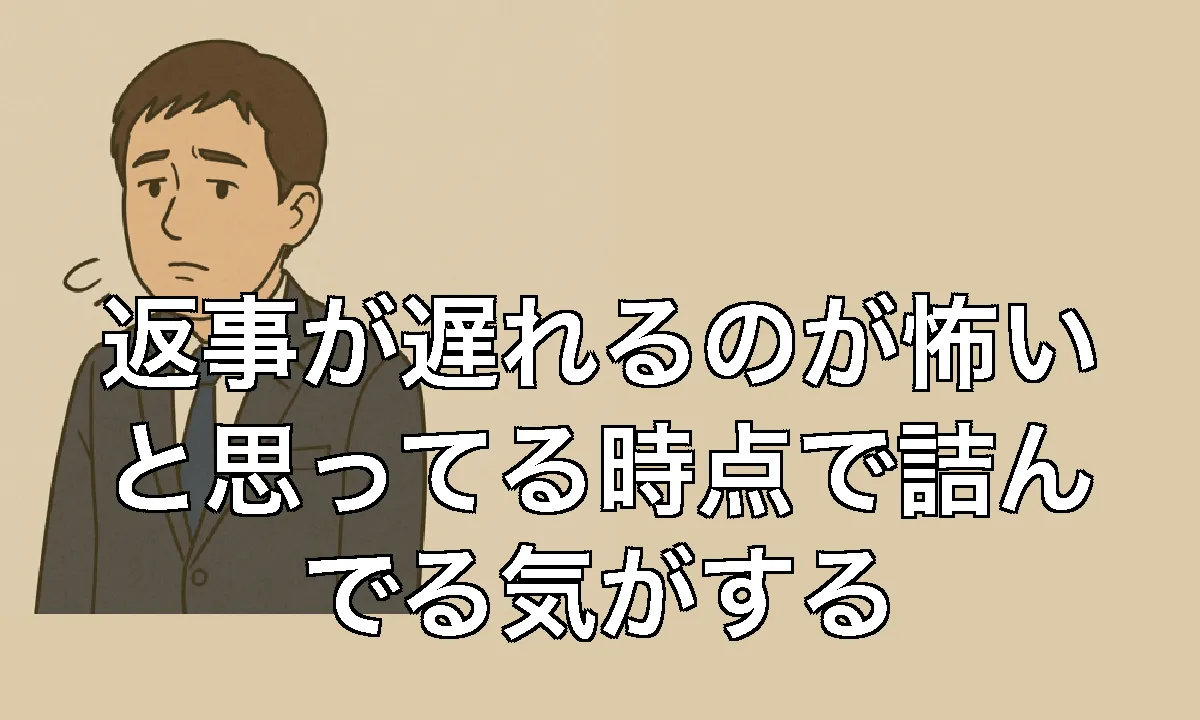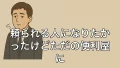返事ひとつで関係が壊れる気がしている
「返信が遅れてしまう」それだけのことが、なぜこんなにも重くのしかかるのか。特に司法書士という職業柄、依頼者や関係者からの連絡には迅速に対応しなければと常に思っている。でも現実は、すぐに返せない日もある。たった数時間の沈黙が相手の信頼を裏切るんじゃないかと、不安がつのる。以前、ある依頼者に2日返事をしなかっただけで「不安になりました」と言われて以来、ますます怖くなった。「返事が遅れる=信用を失う」という呪縛が、日々のプレッシャーとして積み重なっている。
LINEの通知を見るたびに胸がざわつく
スマホに通知が来るたび、ドキッとする。特に夜、自宅でやっと一息つこうとしているときにLINEが鳴ると、まるで急患が来たかのように心が騒ぐ。見るのが怖い。開いてしまえば、何かしら対応を求められていることがほとんどで、読むだけで疲れる。事務員がいるとはいえ、最終判断は自分。結局、返信を後回しにしてしまい、翌朝になってさらに罪悪感が膨らむ。まるで返信という名の借金を背負っているような感覚になる。返せば減るけど、放置すれば利子が増える。
返す内容は決まっているのに手が止まる理由
内容が複雑ならまだしも、よくある「了解です」だけで済むようなメッセージでも、なぜか手が止まってしまうことがある。たぶん心のどこかで、「何をどう返したら相手にとって最も適切か」を考えすぎてしまうんだと思う。昔、少し軽い返信をしたら「軽く見られているようで残念です」と言われたことがある。それ以来、毎回「言葉の重さ」を測るクセがついてしまった。たった数文字に、こちらの人格が詰まっているような気がしてしまうのだ。
相手の顔が浮かぶほど手が重くなる
「この人、こういう言い回し嫌がるかな」とか、「以前こう言ったら引かれたな」とか、相手の反応を想像すればするほど、どんどん返信ボタンが遠くなる。人付き合いが苦手なわけじゃないけど、気を遣いすぎるタイプなのかもしれない。特に長く付き合いのある関係者ほど、ミスしたときの影響が大きいと考えてしまう。返事が遅いことで不信感を持たれるくらいなら、いっそ最初から無言の方がマシなんじゃないかと、極端なことを考える自分もいる。
なぜこんなに早く返さなきゃと焦るのか
現代社会において、即レスが“マナー”のように語られている。そんな風潮の中で、ちょっと返信が遅れるだけで「感じが悪い」「忙しそう」「こっちに興味ない」と思われるのではないかと恐れる。でも、よく考えたら、みんなそんなに暇じゃない。自分だって、すぐに返事が来ないからといって相手を責めたことはほとんどない。なのに、自分に対してだけは厳しくなる。それは、司法書士という「信頼されてなんぼ」の職業的な性質も関係している気がしている。
昔は返信なんてファックスで数日後だったのに
自分が新人だった頃は、まだファックスが当たり前だった。返信が翌日でも、誰も気にしなかった時代。今思えば、あの頃はよかった。少なくとも“即レス”なんて言葉はなかった。時代は変わり、便利になったけれど、心はどこか不自由になった。ファックスの時代なら「すぐに送れなかったんで…」で済んだことも、今では「なぜすぐ返信しないのか」と詰められる。進化した通信手段が、逆に人を縛っている皮肉な現実がある。
スマホが便利になった分だけ心は不自由になった
スマホは確かに便利だ。でも、それによって“いつでも連絡がつくはず”という期待が生まれてしまった。依頼者からのLINE、友人からのメッセージ、家族からの連絡…すべてが“すぐ返さなきゃ”という義務のようにのしかかってくる。中には、5分返事をしなかっただけで電話をかけてくる人もいる。「すぐに返せない=嫌われた」と感じる人が増えているようで、ますます息が詰まる。便利の代償は、心の休む時間の喪失かもしれない。
即レス文化の裏で崩れていく余裕
司法書士という職業は、正確性と誠実さが命。その分、即時の対応も求められやすい。でも、だからこそ一呼吸置く余裕が必要なはずなのに、即レス文化の圧力で、それが難しくなってきている。「すぐ返せない=やる気がない」と受け取られるのではないかとびくびくしながら、夜中に慌てて返信を書く。そんな生活が続くと、心も身体もすり減っていく。余裕がないと、ミスも増える。余裕のなさが、結局信頼を壊す要因になりかねない。
怖いのは返事じゃなくて人間関係そのものかもしれない
結局のところ、返事を遅らせること自体が怖いんじゃなくて、それによって生まれる“関係の変化”が怖いんだと思う。相手がどう思うか、自分の立ち位置がどうなるか、そればかり気になってしまう。でも、それって本来、仕事の効率や質とは無関係なはず。必要以上に人の顔色を気にすることで、自分自身のバランスを崩してしまっている。たかが一通の返事にここまで悩む自分に、時折情けなさすら感じる。
忙しさの中で無意識に関係を整理しようとしてる
返信が後回しになる相手って、決まっている気がする。つまり、優先順位をつけてしまっているということだ。「あの人には早く返さなきゃ」「この人は明日でもいいかな」と無意識に分類してる。それは悪いことではないけど、後回しにされた側がどう思うかを考えすぎると、また悩みのループに入る。人間関係はシンプルじゃない。返信ひとつで、その人との関係性を自分の中で測ってしまっている自分に気づいて、ちょっと怖くなる。
距離を取りたいのに嫌われたくないという矛盾
本当はちょっと距離を置きたい。返信を急ぎたくない。だけど嫌われたくない。そういう矛盾が心の中にある。昔、大学時代の友人からしつこく近況報告LINEが来て、疲れて返事をしなかったことがある。すると「もう連絡しない」と言われてしまった。正直ほっとした気持ちと、罪悪感が同時に襲ってきた。「うまく距離を保つ」のが下手くそなのだ。だから、距離を取りたいのに、つながっていたい。その中間地点で、いつも立ち往生している。
結局返事が遅れるのは気を遣っている証拠
返事をすぐにできる人は、ある意味“割り切れる”人だと思う。気遣いすぎる自分は、いつも考えすぎてしまう。相手の受け取り方、タイミング、語尾の柔らかさ…そんなことまで気にして、返信が遅れる。そしてそれが“悪いこと”として自分を責める材料になる。でもよく考えれば、相手を思いやっているからこそ慎重になっているわけで、責められることじゃないはずだ。返事を遅らせることがあっても、それが誠実さの裏返しだと思えるようになりたい。
元野球部としての連絡の早さと今のギャップ
高校時代、野球部では連絡が命だった。「伝令が遅れたら負ける」と叩き込まれたので、当時は即レスどころか“即叫び”が当たり前だった。連絡にタイムラグは許されなかった。でも、今は違う。司法書士としての判断や対応には慎重さが必要で、即レスが裏目に出ることもある。かつての反射神経で生きていた自分と、熟考と慎重を求められる今の自分とのギャップに、よくわからないモヤモヤを感じる。
当時は即返し当たり前だったのに
野球部の頃は、返事が遅れるなんて考えられなかった。監督からの指示は秒で伝える。ミスれば怒鳴られる。だから連絡=瞬発力だった。でも、今はそのスピード感が逆に“軽率”ととられることがある。法律の世界では、即答よりも慎重な判断が求められる。昔は正解だった行動が、今では逆効果。そんな変化に、自分が適応しきれていないのかもしれない。スピードと誠実さのバランスが、今の最大の課題だと思っている。
今は打席に立つのすら怖い感じ
昔はどんどんバットを振った。三振してもいいから、打席に立ち続けた。でも今は違う。返信という打席に立つことすら怖くなる日がある。打てなかったらどうしよう。相手を怒らせたらどうしよう。そう考えているうちに、時間だけが過ぎていく。そして未返信のメッセージがどんどん積み上がる。打席に立たなきゃ何も始まらないのはわかってる。でも、踏み出せない。そんな自分に対して、「また逃げたな」と心の中でつぶやいてしまう。
すみません返事遅れましたしか言ってない気がする
気づけば、ほとんどのメッセージの冒頭が「すみません返事遅れました」になっている。それがもはや定型句。そう言えば許されると思ってる自分もいる。でも、そんな自分に嫌気もさす。本当はもっと軽やかにやりとりしたい。言葉に追われるのではなく、言葉を使って関係を深めたい。だけど現実は、謝ってばかりの日々。自分の言葉が、自分を追い詰めてる。そんなループから抜け出すには、まずは自分をもう少しだけ許してやることなのかもしれない。