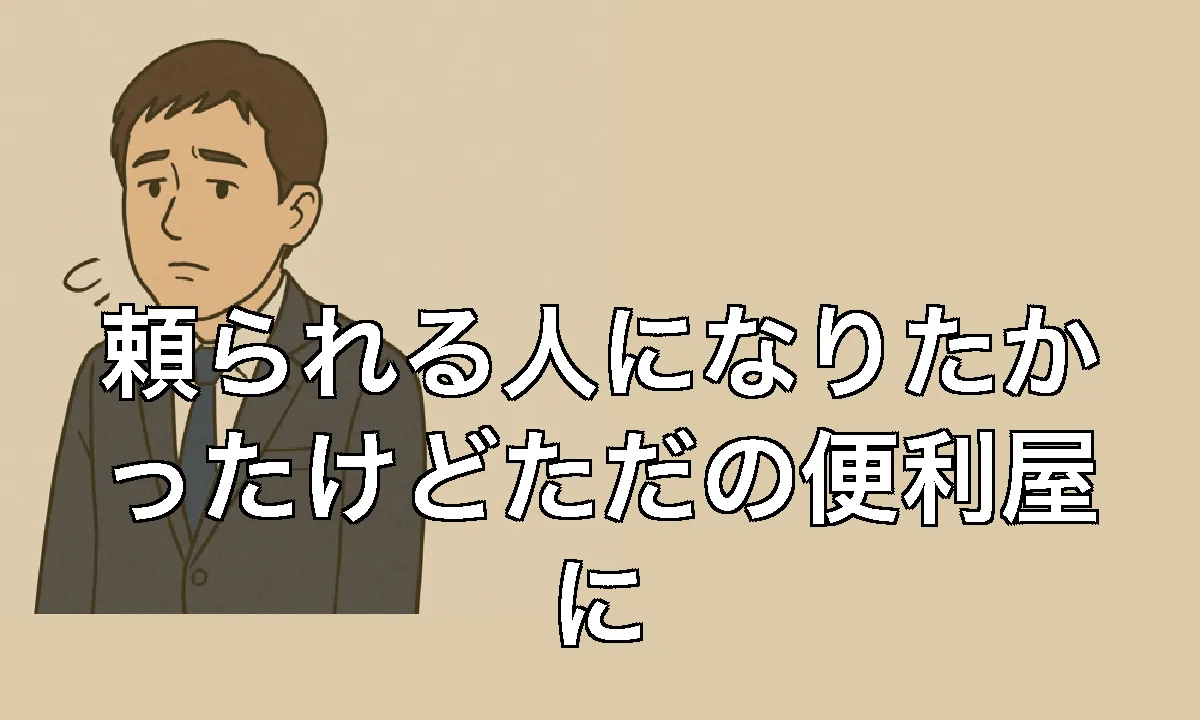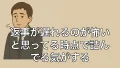頼られることの始まりは悪気のないお願いから
司法書士として独立した当初、頼られる存在になりたいと思っていた。地域の人に必要とされる人間になれたらと、それだけを支えに頑張っていた。最初は少しでも名前を覚えてもらえるのが嬉しくて、書類の作成以外のことでも「分かる範囲ならやりますよ」と安請け合いしていた。だが、その積み重ねが後に大きな代償となるとは思いもしなかった。
最初は感謝されることが嬉しかった
事務所を開いて間もない頃、近所の人に「ちょっとこの書類の見方が分からないんだけど」と声をかけられた。それが始まりだった。公的書類の読み方、ネットの使い方、果ては役所への付き添いまで頼まれるようになった。感謝の言葉に支えられ、自分が役に立っている実感があった。だが、それは「仕事」としてではなく、ただの「親切な人」扱いでしかなかった。
電話番から始まったあの頃
当時、事務員もおらずすべてを一人でこなしていた。外出中でも電話を転送して、着信があれば急いで折り返していた。電話番というと簡単そうに聞こえるが、実際は気を張る作業だ。昼食の時間も落ち着かない。しかも内容の半分は「ちょっと聞きたいだけ」の世間話混じりの相談だった。司法書士というより、町の案内人になっていた。
簡単な相談に乗るのが日常に
「すぐ終わるから」「これって専門の範囲じゃないんだけど」——そう言われる相談が、気づけば一日に何件もあった。住宅ローンの見積書の見方、相続じゃなくても保険の話。これって士業の仕事なのか?と思いながらも「断ると悪い気がする」と思って応じていた。その頃の私は、誰にでもいい顔をしようとしていた。
気づけばスケジュールは他人の都合で埋まっていた
予定表を見れば、自分が主導する案件よりも、人の都合に合わせた予定ばかりが並ぶようになっていた。午前中は役所の付き添い、午後は近所のお年寄りのスマホの設定。気づけば、本来の業務である登記や契約書の確認は夜遅く、事務員が帰った後にようやく取り掛かるという始末だった。
断れなかったのは誰のせいでもない
「そんなのやらなくていいじゃない」と言われても、その時は断れなかった。相手が悪いわけでもない。自分が勝手に「頼られる=価値がある」と思い込んでいただけ。野球部時代の癖で、人に喜ばれるのが自分の存在意義だと思っていたのかもしれない。だが士業はチームプレイじゃない、全部自分の責任で回す世界だ。
時間を使えば使うほど報われなさを感じる
たくさん時間を使ったからといって、見返りがあるわけではない。むしろ「これもお願いできる?」とハードルが下がっていく。報酬の出ない時間外労働が積もり積もって、自分の業績には何も残らない。休日にも「急ぎじゃないけど相談があって」と電話がくるようになり、プライベートと仕事の境が曖昧になっていった。
本当に頼られているのか自問する日々
ある日ふと、「これは信頼されているのか?」と考え込んだ。便利な存在ではあるけど、それはプロとしての評価とは違う。自分の専門性を認めてもらいたくて司法書士になったのに、今の自分はなんでも屋。このままでは、自分の価値を自分で下げ続けることになると思った。
それって信頼じゃなくて依存では
「何でもやってくれる人」と思われるようになると、相手は考えずに依頼してくるようになる。それは信頼というより、ただの依存だ。「この人に聞けば何とかなる」「断られないだろう」という前提があるから、こちらの都合や負担には配慮されない。相手の依存は、自分の疲弊につながる。
自分の存在価値が分からなくなる
毎日が人のための時間で、自分の仕事や生活は後回し。気づけば、自分が何のためにこの仕事をしているのかすら曖昧になっていた。お客さんからも「先生」とは呼ばれず、ただの「◯◯さん」。便利な相談相手として消費される自分に、どこか虚しさと怒りが湧いてきた。
便利屋扱いは信頼ではないと気づいた瞬間
あるとき、業務時間外に「スマホの充電ができなくなった」という相談をされたとき、ハッとした。「これは俺の仕事じゃない」と。その瞬間、自分が便利屋として利用されているだけだと気づいた。本当に信頼されていたら、専門外のことを当然のように頼んでくるはずがない。
役に立っているのに虚しさが残る理由
ありがとうと言われても、心から喜べない。なぜなら、報われていないと自分が感じているから。人の役に立つってこんなにも疲れるのか?と疑問に思うようになった。それは、自分の価値を他人の評価に依存していたからかもしれない。自分が何をしたいのかより、他人の期待に応えることを優先していた。
ありがとうが減っていく日常
最初は感謝されていた依頼も、慣れてくると当たり前になっていく。「ありがとう」の代わりに「もう終わった?」と聞かれるようになり、やって当たり前の空気になる。人は慣れる生き物だ。でも、こちらも人間。感謝の言葉一つで頑張れるのに、それすらなくなれば、ただの労働だ。
自分の仕事はどこにいったのか
登記や契約書作成といった本来の業務に集中したいのに、雑務が積み重なっていく。いつの間にか、司法書士の「顔」を保つだけの存在になっていた。本来の自分の仕事はどこへいったのか。本来やりたかった「専門職としての誇り」はどこで見失ってしまったのか。
便利屋から抜け出すために必要だった視点
このままでは潰れると思い、ようやく「NO」と言う練習を始めた。依頼を断るのは勇気がいった。でも、一度境界線を引いてみると、意外と相手は理解してくれた。むしろ、「専門じゃないんだからそこまではやらなくていい」と言われて拍子抜けした。自分が勝手に背負い込みすぎていただけだった。
線引きは自分でしかできない
便利屋にされるかどうかは、自分がどう対応するか次第だった。他人に線を引いてもらうことはできない。どこまでやるのか、どこからはやらないのか。自分の価値と時間を守るためには、自分でルールを決めるしかない。そうしなければ、仕事はどこまでも膨張し、自分の人生を圧迫し続ける。
断ることも優しさの一つ
今思えば、何でも引き受けていた頃の私は「優しさ」のつもりだったが、実際は相手の自立を妨げていたのかもしれない。きっぱり断ることで、相手に考えさせる機会を与えることができる。「それは自分でやってみてください」と伝えるのも、ある意味で本当の優しさだ。
本当の意味で頼られる存在になるには
ただ便利なだけでは、人の信頼は得られない。本当に頼られる人とは、「この人に相談すれば、本質的なアドバイスがもらえる」と思ってもらえる存在だ。専門性を磨き、時間を守り、自分の価値をしっかり伝えること。それが、司法書士として、そして一人の人間として信頼されるために必要なことだった。